
【歴史総合】知識構成型ジグソー法の授業づくり① / 私の授業の作り方
「知識構成型ジグソー法とはなんぞや?」については、既に様々なところで話されていますから、ここでは、私自身の授業づくりの手順をお話しします。
具体的な知識構成型ジグソー法の授業例
1つ実践例を挙げておきます。
以下は歴史総合の単元「フランス革命の影響と国民意識の芽生え」の授業「「国民意識(ナショナリズム)」の芽生えと広がりは、どのような成果と課題を生んだだろうか?」です。有料サービスの山川二宮ICTライブラリ、高大連携歴史教育研究会の教材共有サイトに掲載されている教材を一部引用して作っているので、大部分が隠してありますが、大まかなイメージは可能だと思います。

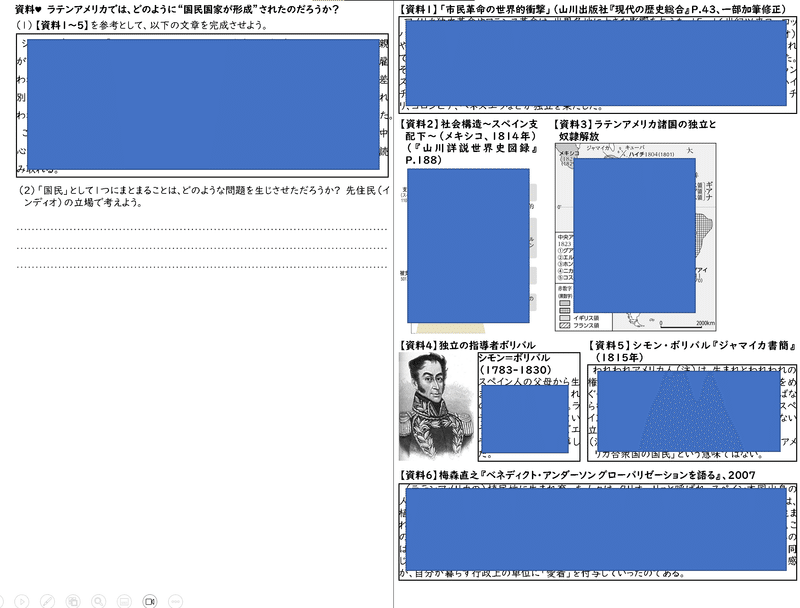

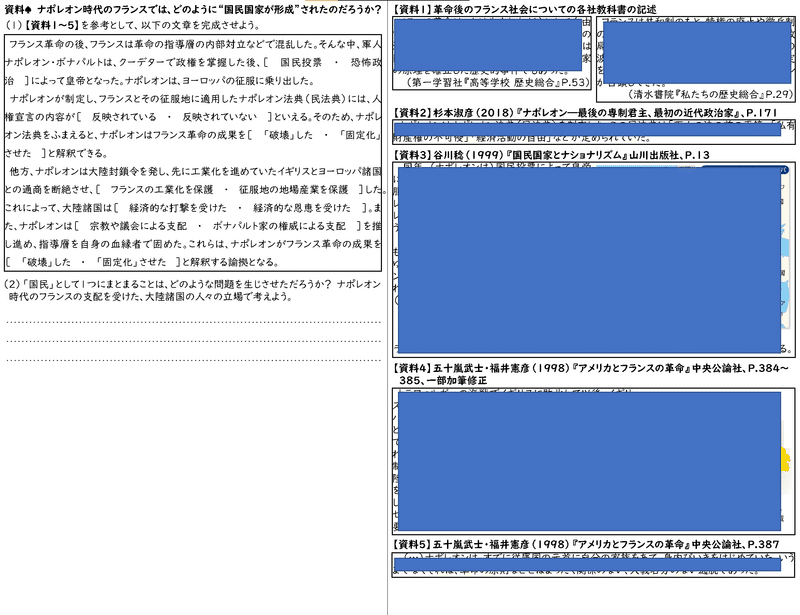
私の授業づくりの手順
①採択教科書の1単元分を基準に、学習内容の範囲を決める
指導書には、Excelの年間指導計画作成資料がついてきます。それを基本として、1回でどこまで進むか?を決めます。歴史総合では、帝国書院や第一学習社など、見開きページで1単元と割り振っている教科書会社があり、分かりやすいです。場合によっては、教科書の既定の単元計画とは関係なく、自分で1回あたりの進度を決めてもよいですが、進度が遅くなると、終わりきならなくなるので避けましょう。
②山川二宮ICTライブラリ、高大連携歴史教育研究会の教材共有サイトでキーワードを検索し、参考になる教材を探す
この2つのサイトはそれぞれ有料ですが、オススメです。どちらもKCJの教材がたくさん共有されています。私の教材もアップロードされています。(今年度の分は、学期ごとに生徒のアンケートの記述なども合わせて、投稿予定です。)
③B4の裏紙に大きくYの字を書いて、設計図の土台を作る
殴り書きで、アイデアを書き込んでいきます。KCJの授業で生徒がやっているのと同じです。1人でジグソー活動をしているイメージです。
④単元を3つに分解して、それぞれの問いを暫定的に決める(これがKCJの各エキスパート資料になる)
例えば、単元「イタリア・ドイツの統一とロシアの近代化」の場合、ちょうど対象の国がイタリア、ドイツ、ロシアの3つなので、国ごとに分けるのも手です。
一方で、単元「アメリカの拡大と第2次産業革命」の場合、南北戦争前後のアメリカ合衆国と第2次産業革命が扱われます。ちょうど2023年5月27日(土)現在、制作中の授業です。南北戦争について3つの視点から考察する教材も可能ですが、私は今のところ、第2次産業革命のほうを軸として設計しています。以下は、暫定的なメモを文字起こししたものです。
MQ候補:第2次産業革命とは何がどう変わった出来事なのか?
・アメリカ合衆国とドイツの共通性を見出す
Introduction:
・教科書のこの時期の発明家の表、グラフの読み解き
・アメリカ合衆国とドイツの工業化、イギリスとフランスは投資中心に移行
・重工業、石油化学工業
エキスパート資料♥:国家主導、大企業の発生
・南北戦争の結果、北部主導の工業化の進展
・保護貿易、国家予算を産業政策に投入?
・米独ともに大企業が生まれる → なぜ?
エキスパート資料♦:移民労働力
・アメリカ合衆国のアイルランド系、中国系
・ドイツも『世界史研究』を参照
・大陸横断鉄道
エキスパート資料♠:資源の調達、低コスト
・鉄鋼関係の資源
・南北戦争の奴隷解放は一種の方便だった。北部は安い綿花を入手していた点で、奴隷制を間接的に進めているともいえる
・ビスマルクの社会主義者弾圧
分け方は様々ですが、MQで何を考えさせたいか?を踏まえて分けていきます。とはいえ、私はMQを確定させてからエキスパート資料を考えるのではなく、同時進行で考えます。
⑤歴史総合の全ての教科書、山川『新世界史』、山川『詳説世界史研究』の該当箇所を読み、参考になる史資料、記述を確認する
設計図にメモしていきます。ここで問いが深まるので、適宜修正します。
これと並行して、「世界史の窓」等を参考にして面白そうな史料、本を図書館で借りて確認します。 1つのKCJ教材を作るのに、だいたい5~6冊は読みます(部分的なつまみ食いで)。 概ね岩波新書の10講シリーズ、新版 世界各国史シリーズ、山川の世界史リブレットはmust item。他は場合によります。
⑥山川二宮ICTライブラリ、採択教科書のデジタル指導書から、使用できそうな図版を選び、エキスパート資料のテンプレート(B4横)に貼っていく
授業プリントは、PowerPointのB4横置き設定で作成します。図版が動かしやすいためです。
PowerPointは適当なテキストボックスを2つ作り、右クリック→テキストボックスの設定で、位置をそれぞれ「100cm, 100cm」「-100cm, -100cm」に設定しておくと、スライドの外側の部分が無限に広がり、使うかもしれない史資料やテキストボックスをそこに置いておけます。
これをしないと、カーソルをちょっと下げただけで次のスライドに移動してしまいますが、これを防げます。
テキストボックスは10.5pt、余白上下左右全て0の物を作り、既定のテキストボックスに設定しておきます。
B4横のエキスパート資料のテンプレートは中央に縦線を入れ、スライドの周りに、表で作った罫線や、囲みありのテキストボックス等のテンプレートを置いておきます。Ctrl+カーソルで増殖させられるので、効率よく作れます。
左右のうち、印刷時にファイルに綴じる穴が開く側は余白を作っておきます。

⑦必要な文章、図版を【資料○】と番号をつけて、右ページに貼る。左ページに問いを作っていく。
横書きなので、指示がなければ無意識に左ページから目を通す人がほとんどです。左ページに資料を貼ると、全部読もうとして時間が足りなくなる生徒がいるので、左ページには問いを、右ページには資料を配置するようにしました。(今年度の途中から)
⑧同時に、B5縦のワークシート(ホームとなるプリント)のテンプレートにIntroductionの文と図版、問いを書き込む。 これで完成。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
