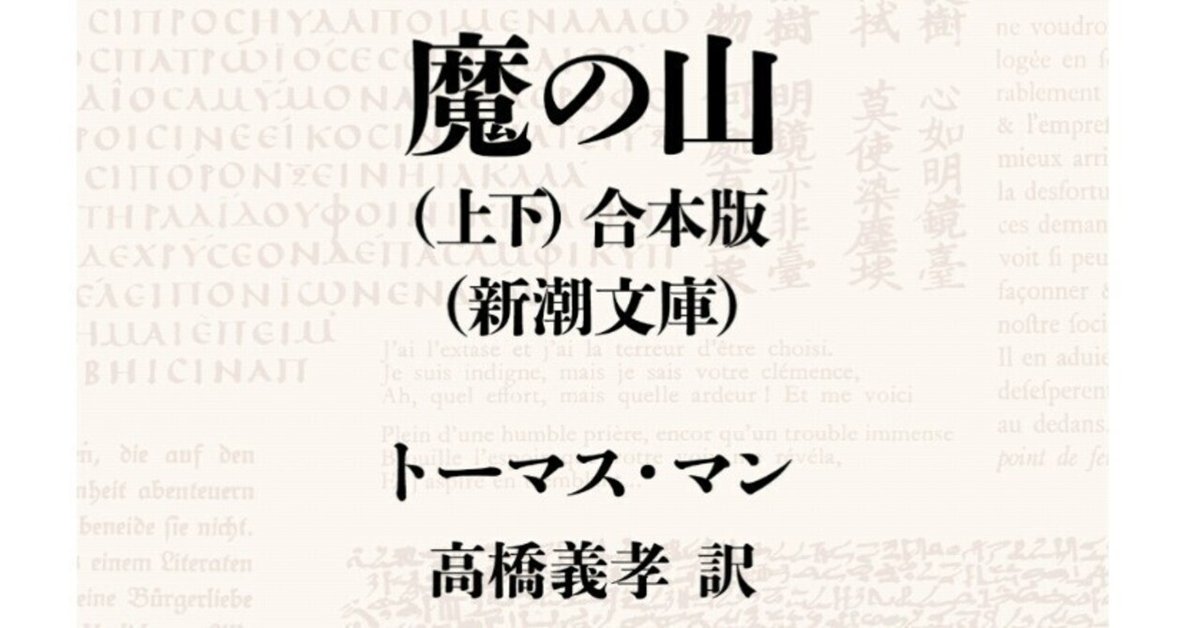
『魔の山』という山
死ぬまでに一度は読まなければと思うが、きっと死ぬまで読まないだろうなと思う本が何冊かある。
ウンベルト・エーコの『薔薇の名前』とか、マルセル・プルーストの『失われた時を求めて』、ジェイムズ・ジョイスの『フィネガンズ・ウェイク』などがそれに当たる。オーク材の大きな本棚に全巻並べてはあるが、誰にも開かれたことのない世界文学全集のような位置付けで、それらの本は意識の片隅に鎮座している。
トーマス・マンの『魔の山』も、そういう文学作品の中のひとつだった。
20世紀ドイツ文学において、最も影響力のある作品のひとつとされている教養小説だ。当然、ものすごく長い。
(以下、少しネタバレあり。未読の方はご注意下さい)
主人公ハンス・カストルプは、ハンブルクの裕福な商家に生まれ育った二十代前半の青年だ。造船会社のエンジニアとして内定が決まっていた彼は、入社前にいとこのヨーアヒム・ツィームセンを見舞うため、3週間の予定で高地のサナトリウムを訪れる。ヨーアヒムは軍人だが、結核を患っているため入隊できず、長くこの高地で療養生活を送っていた。
ヨーアヒムはハンス・カストルプが来たことを喜び、高地での過ごし方やほかの患者たちのことなどを詳細に語る。ハンス・カストルプもサナトリウムを気に入るが、自分はあくまでゲストであり、3週間後にはここを去るのだという心持ちでいる。
だが、医師のベーレンスの見立てとレントゲン写真の裏付けるところにより、ハンス・カストルプ自身にも病巣があることが判明し、ゲストではなく患者としてサナトリウムに留まることになる。
と、この辺りまでが導入部と言っていいかもしれない(ここまでも相当長いが)。正直なところ退屈で、そろそろ何か事件が起こってくれないかと思う頃にハンス・カストルプの病気が発覚するので、おっ来たな、という感じだ。だがここから話が加速するかというとそうではない。
定石ならば主人公の病気の発覚なんて、ストーリー上の大きな転換点になりそうなものだ。しかし病気は軽症で、ただハンス・カストルプがサナトリウムにだらだらと居続けるための口実に過ぎないように思える。
そのこと以外にも、ハンス・カストルプの周りでは様々な出来事が起こり、出会いと別れがある。それこそ人生を変えてしまうに足るような事件もあるのだが、ハンス・カストルプはサナトリウムに留まり続けることを選ぶ。冒頭では自分はゲストに過ぎないと散々言ってたくせに、医者からもう退院してもいいよと言われても、なんだかんだ理由をつけて山を下りないのだ。
さては君、働くの嫌になったな? とさえ思える生活態度はずっと続き、結局ラスト近くでどうにも抗いがたい事態に陥るまで、療養生活は維持される。
とはいえ教養小説であるので、ハンス・カストルプに多大な影響を与える人々は多い。長々とご高説を披露したり、論戦を繰り広げたりする場面が何度となくあり、話としてはこちらの方が肝だ。サナトリウムはこのための舞台装置に過ぎないだろう。
成程若者たちはこの辺りを読んで何事か学ぶのだな、これが教養小説ね、という理解は出来る。だが決して若くはない歳の私としては、率直に『ほんとどうでもいいな』と思ってしまう。
『魔の山』が書かれ、発表された当時のヨーロッパの政治的・宗教的情勢、思想、文学を取り巻く環境などに鑑みると、この小説が若い人たちにどれほどの影響を及ぼしたかは想像に難くない。
しかし21世紀の今、私自身に限って言えば、登場人物の口を借りて語られる主張も思想も、すべてが悉くどうでもよかった。面白くなかったわけではないが、何も心に響かなかったのだ。
生きてる時代が違うからと言えばそれまでだが、それにしたってこんなに感受性が鈍くなっているのかとちょっと驚いたくらいだ。今ではなく高校生の頃、せめて大学生くらいの歳の頃に読んでおけば、全く違う読後感が得られただろう。その頃読了済みだった友達と感想戦が出来たかもしれない。
なぜ読まなかったかといえば、単に学校の図書室になかったからだ(『魔の山』置いてない図書室!)。そして今になってやっと読んだのは、電子書籍になっていることに気付いたから。
そんな理由だから思い入れもなく読み切ってしまったのかなと、本を読むタイミングについては結構考えさせられた。
それでも、いいなと思って心に残った場面はある。
ハンス・カストルプがヨーアヒムのレントゲン撮影を見るとき、『君の心臓を見せてもらうよ』と言ったこと。
謝肉祭の夜、クラウディア・ショーシャが去り際に『私ノ鉛筆、忘レナイデ返シニキテネ』と告げたこと。
ハンス・カストルプを『エンジニア』と呼び、常に正しい方向に導こうとしていたロドヴィコ・セテムブリーニ。
高潔な志を持ち、未来に希望を抱いて、常に周囲に対して優しかったヨーアヒム・ツィームセン。
雪深い山に分け入り、遭難しかけたハンス・カストルプが見た、恐ろしくも美しい景色。
轟然と響めく世界で、最後に彼が歌う『菩提樹』。
そんなエピソードは、昔に読んだ若者たちの心にも、今の私と同じく色鮮やかな印象を残しただろう。
何はともあれ、『死ぬまでに一度は読まなければと思うが、きっと死ぬまで読まないだろうなと思う本』の中から、一冊が除外された。
『魔の山』という山を、生きているうちに越えることが出来たのだ。
そしてこの読書体験を経て、まだまだ高い山は幾座もあると改めて気付いた。登り甲斐はあるが、遭難の危険もまた大きい。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
