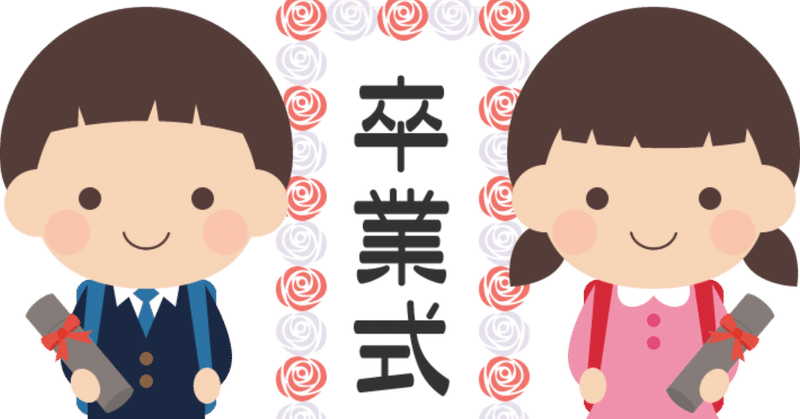
この支配からの(小学校編)
『卒業』に関するエッセイ。
今回は小学校編です。
幼稚園編はこちら。
私の根底にある『根暗気質』は、この頃から形成され始めていたのかもしれない、と今になって思う。
地元の市立小学校に6年間通った。
あの頃は人より勉強ができたし、フィジカルが強かったおかげで休み時間にはドッジボール、放課後にはチャリを乗り回してばかり、という楽しい学校生活を過ごせていたとは思う。
しかし、高学年を迎えるあたりから、自分の中で何かが変わった。
「あの子、うざいよね」
クラスの中心的存在であるませた女の子たちが、自分とタイプの違う同級生を一括りに『うざい』と軽蔑し始めた。そういう子たちの影響力は絶大で、取り巻きの女の子たちをはじめとするクラスの女子は、まるで子羊のように彼女たちに同調して「うざいうざい」と嗤う。こうして、標的となった子は上履きを隠されたり、2人組を作るときに仲間外れにされたりしていた。
人を信じるのが、少し怖くなった。
『うざい』と言われていた子を知っていたが、彼女はまったく悪い子ではなかった。ユーモアと思慮深さを兼ね備えた立派な子だったし、自分の意見というものをちゃんと唱えられる子だった。
きっと、その意見がリーダー格の女の子には自分に楯突く刃のように感じてしまい、それを悪とすることで自分の威厳を保ちたかったのかもしれない。それも今ならわかる。同じ人間だから。
しかし、あの頃は彼女を助けることも、「そういうこと言うの良くないよ」と注意することもできず、ただただどうしていいかわからなくなってしまった。
「もしかしたら私も裏で何か悪口を言われているかもしれない」
憶測でしかないのに、そこはかとない恐怖が幼い子どもの弱い精神を襲った。
それから、何を言うにも何をするにもその恐怖に脅かされるようになり、発言する意欲、楽しそうにはしゃぐ権利、ついには友人を遊びに誘う勇気すらなくなった。
以前は、帰宅するや否やランドセルをぶん投げて自転車で友人たちと待ち合わせをしている公園に出かけに行ってしまったのに、小学6年生の頃には、家にまっすぐ帰ってきては、Eテレとカートゥーンネットワークを交互に観続ける私を、もしかしたら母は心配していたかもしれない。
卒業を目前に控えたある日、普段はあまり会話を交わさないリーダー格の女の子が
「もちこちゃんは受験して私立行くんでしょ?」
と断定的な質問を投げかけてきたことがあった。受験なんてしていないし、する気もさらさらなかったので、そういった話はクラスの誰にもしたことがなかった。
「ううん、みんなと同じ地元の中学校だよ」
と答えると、
「えー!そうなんだ!頭いいから受験したかと思ってた!」
とだけ言って私の机から去って行った。
私の考えすぎかもしれないが、あのとき、彼女たちは一瞬顔を歪めたような気がした。まるで、私が同じ進学先なのが気にくわないかのように。
そのせいだろうか。卒業式ではまったく涙が出なかった。
というか、泣く方が馬鹿馬鹿しいとすら思っていた。だって、ほとんどが同じ中学校に進むのだ、何も変わらないに等しいじゃないか。私は、早くこのくだらないいがみ合いの存在する地獄から脱したいのに。
そんなことをぼんやり考えながら、抱き合って泣くクラスの中心女子たちを教室の隅から眺めていた。
この子たちと違う世界に早く行きたいと願った根暗の卵の女の子が、立派な根暗人間に成長するまであと11年。
物書き志願者です! 貴方のサポートが自信と希望につながります!
