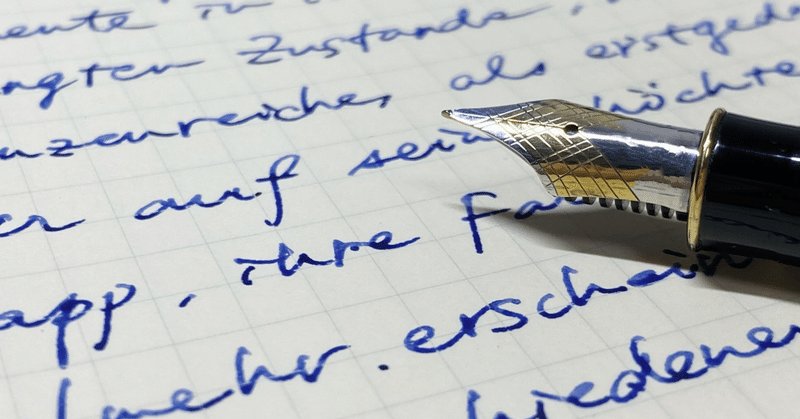
キャッチコピー毎日100本書けるか?
「夏はハタチで止まっている。」という名コピーを書いたのは秋山晶である。翻ってぼくのハタチは春で止まりそうだった。ハタチの春、ぼくは目黒にある総合広告代理店に潜り込むことに成功。まんまと新卒入社組の大卒諸君にまぎれて新入社員研修でうたったりおどったりしていたのである。
そんな、いま考えるとお遊戯のような研修は、世間知らずのハタチにはたいそう楽しめた。なにせ部長という人の言う通りにやっていれば褒められるのだ。それまで他人から認められることのなかったぼくはいい気分だった。承認欲求などという言葉のない時代だが、ぼくは調子に乗った。
しかし何事もやりすぎはよくない。血気盛んで生意気盛りのぼくは同期の飲み会で同僚を追い込んでしまったのだ。これは反省している。反省してはいるがその同僚がいまどこで何をしているのかわからないので謝りようがない。ただしひとたび面と向かったならばすかさず詫びる準備はある。
もうひとつやりすぎてしまったのは、研修中の飛び込み営業で初受注してしまったことだ。飯田橋の工場の主はぼくのことを野良犬のようなものだと思い、不憫に感じたのか「お前の言うアルバイト雑誌に載せる金はないが新聞チラシの枠なら買ってやるから上役にいまここで交渉しろ」という。
仕方がないので電話を借りて(携帯電話というものはまだこの世になかったのだ!)部長に事の次第を話すと、偉いぞチラシでもいいから売ってこい口座が開いてるかどうかはしらんが俺の決済で開くという。そこでアイデムだかなんだかの新聞折込チラシに求人広告が載ることになった。社に戻ると営業部の先輩たちが拍手して迎えてくれる。握手まで求められる。
年の近い岡さんという人が「お前すごいなー。研修中に受注するなんて、営業の才能あるよー」といって褒めてくれた。しかし残念ながらぼくは営業になる気などさらさらないのだ。営業の才能などどうでもいいのだ。コピーライターの才能があるかどうかが目下の興味のゆくさきなのだ。
不思議な配属辞令
そうして迎えた研修最終日。配属発表でぼくは制作部に行くことに決まっていたはずである。にも関わらず、なぜか「辞令、早川博通、第一営業本部への配属を命じる」というではないか。あれ?おかしい。なぜ?ぼくはコピーライターになるためにこの会社に潜り込んだはずだ。なぜ営業部に?
ぼくはその場で抵抗した。社長はじめ役員たちがいる前で、挙手をし、なぜ俺が営業部配属なのかわからない俺は制作部希望で入社したはずだし納得がいかないのでこのままだと会社を辞めることになるがだいじょうぶかオーバー、と伝えた。最後のオーバー、というのは無線で使う定型句だ。
オーバーについて詳しく知りたい方は映画「シャイング」を見てほしい。怖くて怖くて「ああ、週末に見ておいてよかった…平日だったら次の日会社にいけないところだ」とおもうだろう。
話を戻そう。
そんなふうにぼくが抵抗したら会社のえらいさんたちはびっくりしていた。特に営業部長は「何をいっとるんだキミは…」という顔でこっちを見た。営業部長は研修中、特にぼくをかわいがってくれていたので申し訳ない気持ちになったが、こんなところで命を削ってる暇はない。早くコピーライターにならないといけない。
会社は「営業は楽しい」「営業こそがビジネスの原点であり頂点であるのだ」「営業ならがっぽり稼げていい生活ができる」「営業ならモテる」「お前は営業に向いている」「お前はすでに死んでいる」などさまざまな変化球で攻めてくる。しかしぼくも重いコンダラで育った男。簡単には引けない。
丁々発止ののち、やや態度を軟化させた会社側は言った。「そんなにコピーが書きたいのなら書かせてやる」と。ぼくは当たり前だ、と言わんばかりの態度で「では制作部配属なのだな」と確認する。すると驚くことに営業部だという。営業しながらコピーを書きなさいと。そんなバカな話はない。
しばらく膠着状態が続き、さすがに疲れてきたのかある営業課長が「お前は一日に何本キャッチが書けるのか」という。ぼくは当然のように「1000本でも2000本でも書ける」と断じる。すると「そんなに書かなくていいから毎日10本、自分のデスクに届けろ。一年間続いたら認めてやっていい」という。
当時何の根拠もなく己の才能を信じ切っていたぼくは快諾した。一日10本など散歩みたいなもんだ。しかしふと不安になって確認した。「それで配属は?」「第一営業本部」謀ったな、とおもった。これだから大人は信用できねえ、とおもった。そのやりとりを眺めていた制作部門の長が「しょうがねえなあ」とため息をついた。
営業はなまはげなのか?
どうやらその年の制作部門の新卒枠は埋まっており、さらに追加で山形の銀行員だった女性を中途採用したところで、ぼくの席は物理的にも予算的にもなかったんだそうだ。しかしそんなことは知ったことではない。当時のぼくはいまの10倍自己中心的でいまの30倍キレやすい子どもであった。
「じゃあいいよ、一応制作で。でもお前適性がなかったらクビか営業配属にするぞ。それから毎日尾崎課長にキャッチ10本出せよ。一日でも未提出だったらその時点で営業にするぞ」まるで営業がなまはげかの如く脅しの材料に使われていて、なんだか気の毒になったが、ぼくは勝った、とおもった。
将来「わが闘争」というような題名の自伝を書くときにはこのくだりだけで100ページほど使おう、ともおもった。以来、30年以上にわたりぼくが営業畑を歩くことは一度もなかった。
あのとき「将来後悔するぞ」「ぜったいに後で役に立つのに…物の道理がわからん馬鹿者め」等々の罵詈雑言を吐かれたが、ハタチの自分に伝えたいことは「そんなことはないから安心しろ」である。
あれからたくさんの川が流れた。
いま、会社に属しながら個人で仕事をいただく機会に恵まれている。本当にありがたいことである。そしてよく言われるのが「ハヤカワさんってすごく営業力ありますよね」である。
しかしそれは違う。営業力?営業を舐めてはいけない。ぼくにそんな特殊能力はない。
なぜならぼくの営業力はハタチで止まっているからだ。「夏はハタチで止まっている。」繰り返すがこれは秋山晶の名コピーである。そして「営業力はハタチで止まっている。」これは紛れもなく、ぼくのことである。
とにもかくにも、こうしてぼくのコピーライター人生は、いささか頼りないにせよ、スタートしたのでありました。
(つづく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
