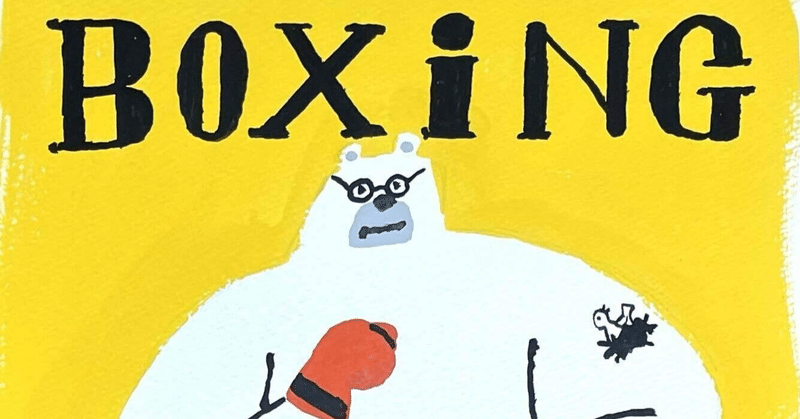
つはさんのこと
むかしむかし。
つとめていた居酒屋でのできごと。
そのお店は池袋にある個人店だった。個人店とはいえオーナー以下、料理人が5人とホールが10名ほど。そこそこの業容といえるだろう。
それなりに人の出入りも激しいらしく、ぼくがアルバイトとして入店したときもつい先日板前が辞めたところだという。開店前の仕込みが人手不足だから、よかったら手伝ってくれと頼まれた。
時給の身としては願ったりかなったりだし、水商売ははじめてだったので後学のためにもぜひお願いします、と13時からお店に入るようになった。
そのお店には妙なしきたりがあって、たとえばホールスタッフは伝票を持ち歩かない。お客からの注文はすべて頭の中に叩き込むやり方だった。さらにホールから厨房にオーダーを通す時にも独特の符牒があり、その通し方じゃないと返事すらされないというテッテぶりであった。
ぼくは最初のうち、メニューを近くのコンビニでコピーしてアパートに持ち帰り、彼女を相手にオーダーの練習をしていた。なにせレギュラーメニューだけで50種類ほど。ここに旬のものが週替り単位で加わるのだから、慣れないうちはなにがなんだかとまどいトワイライトだ。心がゆれる。
そうこうするうちに仕込みのおかげかすべてのメニューが頭に入り、オーダーもスラスラ通せるまでに成長した。なにせ25歳。それまで頭をたいして使ってこなかったのでストレージ容量はたっぷり残っている。
すると途端に余裕がでてきて、仕込み中のおしゃべりにも参加できるようになる。やがて以前働いていたOBOGの話題に興味をそそられるようになる。そのお店は過去、何人もの変わり者を輩出してきたらしいのだが、なかでも特に異彩を放っていたのが、つはさん、という人だ。
つはさんは沖縄出身。ボクサーとして身を立てようとしたらしいのだが、プロになるなら本土だ、東京だということで上京した。そして池袋にあるボクシングジムに通うかたわら、そのお店でアルバイトとして働いていた。
アルバイトとして、と書いたが、つはさん自身は社員になりたかった。なりたかったのだが、なれなかった。その理由はいくつかあるが、いちばん大きな原因はコミュニケーションかなあ…とコンロ前のハットリさんが振り返りながらつぶやく。
うまく打ち解けられなかったんですか?とぼくが聞くと、ハットリさんは「そうだよなあ、悪いヤツじゃなかったんだけどなあ」となんとなく歯切れのよくない言い方でぼかそうとする。
このお店でハットリさんは絶対だ。社歴が長く、オーナーからの信頼も厚い。最初はバイトだったのだがあまりにも水があうことから大学を中退して社員になったぐらいだ。ありあわせの食材でどんな料理でもつくってしまうハットリさんにとって、この仕事は誰から見ても天職だった。
仕込みのあとの休憩中に野菜場のヘイちゃんに聞いたところによると、つはさんは前の職場でも料理人として働いていて、経験者として採用されたそうだ。だけどハットリさんが自分のポジションを奪われたくないあまり、野菜の仕込みや盛り付けしかやらせなかったらしい。それがつはさんのストレスとなり、あるとき爆発したんだって。
どう爆発したかというと、ハットリさんに詰め寄り胸ぐらをつかんだ。そして怒りにまかせてホシザキの業務用冷蔵庫を殴ったんだそうだ。おかげで冷蔵庫にはボッコリ大きな穴が3つもついた。
「みっつも!?」
「そう…みっつも」
「ハットリさん殴られなくて良かったね」
「ライセンス剥奪されちゃうよ」
「あ、そっか…」
ヘイちゃんはあたかも現場を目撃したかのように語ったが、なんのことはない又聞きであった。だから真偽のほどはわからない。ちなみにヘイちゃん曰く「つはさん?ちょっと怖いけどいい人だったよ。俺は好きだったな」。
ぼくは、つはさんに会ってみたくなった。もしかするとぼくはその店で腰を据えて働いてもいいかな、と思いはじめていたのかもしれない。だから、なんだか追い出されたような感じの辞め方をしたらしいつはさんに、本当のことを聞いてみたかったのだ。
つはさんといちばん親しかったというホールのアルバイトに頼んで、つはさんが毎晩通っているという沖縄料理の店に行った。場所は西巣鴨で、池袋から自転車で30分ぐらいだった。
蒸し暑く長い夏の夜である。
仕事が終わってから向かったので、沖縄料理の店には午前0時ごろについた。こじんまりとした家庭的な雰囲気のお店で、つはさんは常連らしく座敷のまんなかにドン!と迫力満点に座って泡盛を呑んでいた。
「つはさん、はじめまして」
「おう、おまえが、ハヤカワか」
「はい、そうです」
「おまえは、おれに会いたいそうだな」
「はい」
「おれは、おまえ、簡単には人に会わない」
「はあ」
「おれは、あの店の人間には、会わない!」
「ええっ!?」
「おまえ、わかっているのか!」
「すませんっ!」
「まあいい、おまえハヤカワ、のめ!」
「はい!」
つはさんはぶっきらぼうに、沖縄の人らしいイントネーションで言葉をぶつけてくる。読点のところ、長めの一拍を置いて読んでください。
目の奥がどろん、としている。体型はさすがボクサー、どちらかというとずんぐりむっくりとしているが、肩のあたりから二の腕までががっちりと太い。筋骨隆々とはこういうことか、とおもった。こんな腕から繰り出されるパンチくらったら死ぬな、ともおもった。
乾杯ののちにぼくは沖縄出身の先輩の話をしたり、沖縄に旅行にいったときの話をした。さかんに沖縄への親愛の情をアピールする作戦だ。しかしそのどれもが華麗にスルーされた。まるで人の話を聞いていないのだ。
なんとなく、ハットリさんがやりにくかった理由が見えてきた。
「おい、おまえ」
「はい」
「おれの名前をおしえてやろう」
「え?知ってますけど」
「うるさい!おれの名前は、つなみのツに、つなみのハで津波、というんだ。わかったか?」
「はあ…」
「おまえは高卒か?おれは中卒だ。おれでもわかるのだからおまえはぜったいにわからなければならない。いいか、もう一度いう、おれの名前はつなみのツにつなみのハで津波だ、わかったか!」
「でも…つはさん、つなみ、の時点ですでに津波ですよね」
「おまえっ!おまえはほんとうにだめなヤツだなあ。おまえはなにもわかっていない。いいか、もう一度だけおしえてやる、おれの名前はつなみのツッ!そしてつなみのハッ!それで津波だッ!わかったかっ!」
「わかりました」
こんなやりとりが朝の4時過ぎまで続いた。しじゅう怒られていたような気がするが、言葉の端々から、つはさんは本当はめったやたらと優しい人なのではないかな、と感じられた。そして、このいかつくも人間くさい兄さんのことがなんとなく好きになっていた。
そして夜が明けるころ。つはさんの目尻と鼻の頭は赤くなっていた。お店を辞めた理由の本当のところを聞いたからだ。
つはさんによると、ハットリさんは最初、俺の言うことを聞けば正社員としてコンロ前に立たせてやると約束したらしい。それを信じてハットリさんの手足となって働いた。でもいつまで経っても場所があく気配がない。一年が過ぎたころ、思い切ってつはさんは社員登用とコンロ前の話はどうなっているのかハットリさんに聞いてみた。
そうしたらハットリさんは「オーナーに聞いてみる」というので、これはいよいよと期待したんだそうだ。翌日、あらためて確認すると、明日からコンロ前は任せるという。つはさんは喜んで新しい雪平鍋をサイズ違いで3つ、買った。以前の店で着ていたコックコートも引っ張り出してきた。
そして翌日、いつもより1時間も早く厨房に行くと、すでにハットリさんは来ていて仕込みを全て終わらせていた。どういうことか尋ねると、残念だがやはりコンロ前は俺がやることになった、オーナーが決めたのだから俺としても従うしかない。いやあ、悪いな、つは。
そこからのつはさんの記憶はぼんやりしている。気がついたらベロベロに酔って、両の拳が血だらけだったそうだ。ホシザキの業務用冷蔵庫以外にも犠牲になった物がいくつかあるんだろう。それが人でないことを願った。
「あいつは嘘つきだ。おれの料理人としての腕を妬んでいたんだ」そこまで話してつはさんは、グラスに残った泡盛を一気に流し込んだ。ぼくは何も言えなかった。
そろそろ帰ろう、6時近いよとホールのアルバイトに促されて、店を出ることにした。
そうして滝野川7丁目の交差点でつはさんと別れた。つはさんはかなり酔っていた。最後はぼくの名前を忘れるどころか「おまえ!おい、おまえは誰だ!」と繰り返し叫んでいた。ぼくはつはさんがパンチドランカーになってしまうことを想像して、怖くなった。
そのままホールのアルバイトとふたり、まっ赤に染まった池袋の街を横切るように自転車を漕いだ。ペダルがやたらと重かった。
つはさんと会ったのはあとにもさきにもその一度きりだった。
それから4年後、ぼくはハットリさんから店を辞めるように言い渡された。事実上のクビである。なるほど、こういうことだったのかとおもったが、それを話す相手はいなかった。つはさんがどこにいるのかもわからなかった。
数週間後、失業保険を給付してもらうために池袋の職安に並んだ。職安に行けばつはさんに会えるかもしれないと思ったが、気のせいだった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
