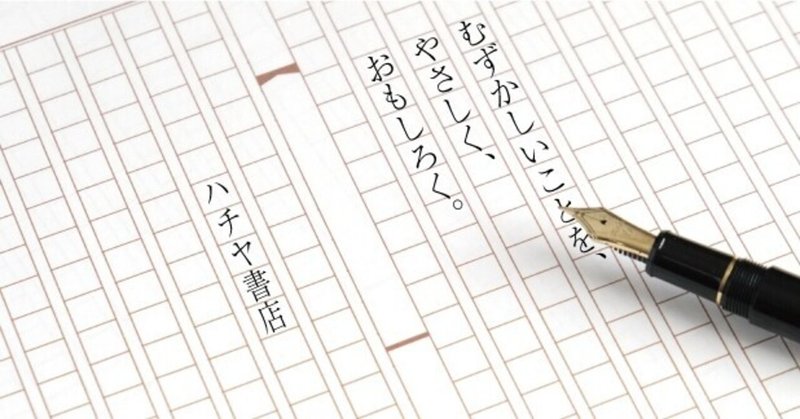
【書店便り2】漱石は「手紙」が一番面白い!
先日つぎのようなジョークを耳にした。
ある男が「君、オウガイはスキ?」と訊いたら、「それ食べられるの?」
と訊きかえした女がいた。
オウガイとは貝のことではない、鴎外のことだ。ダジャレをつかったこのジョーク、かの明治の文豪も遠くになりにけり、ということか。
ところで漱石はどうか。このnote上でハッシュタグ数を調べたら、#鴎外:#漱石=257件:2,004件。約8倍も漱石のほうが多い。この数値を仮に人気度の指標とすれば、漱石の人気は依然として高い、とでもいえようか。いまの超有名作家とも比較したが、なんと遜色ないのである。これには驚いた、漱石はまだ遠くになりにけりではない、死んで100年以上にもなるのに。
その漱石に関する本を文芸にはズブの素人がアマゾンの店頭に出品した。
漱石で一番面白いのは、本の帯にあるように「手紙」、つぎが俳句と日記が面白い。(面白くないのは、修善寺での大患以降のいくつかの小説だ)
さて、拙書では、漱石がまだ無名の英語教師であったころのイギリス留学とその2年半のあいだの正岡子規と寺田寅彦との交友を主題に据えた。かれらが遺した、手紙、日記、小品などをふんだんに引用し繋ぎ合せて辿ったノンフィクションである。プロローグを以下引用しよう。
明治三十三年九月八日午前八時ごろ、横浜{埠頭|ふとう}にて一隻の大型船が錨をあげていた。プロイセン・ブレーメン号、二本マスト、二本煙突、排水量三千トンである。晴れあがった空に汽笛をひびかせ、ラ・マルセイユを{奏|かな}でながらゆっくりと岸を離れて行く。風おだやかにしてこれからの長い航海がはじまろうとしている。
英国留学に向かう夏目金之助こと漱石は、{舷側|げんそく}にもたれたままじっと岸壁を見つめていた。そこではハンカチを目にあてた鏡子夫人とともに帝大生の寺田寅彦が別れを惜しみ、いっぽう根岸の{庵|いおり}では親友の正岡子規が病床に{臥|ふ}せっていた。
--------------
熊本第五高等学校の英語教師であった漱石は、国費留学生として英国の都ロンドンに二年あまり滞在する。そこでさまざまな人々と出会い、異質な文化に触れながら新世紀を迎えた時代を{嗅|か}ぎ取っていく。「西洋」というものに戸惑いながらも{諂|へつら}うことなく真っ正直に向き合い、ときには{毅然|きぜん}と{対峙|たいじ}することもある。また下宿に{籠|こ}もり続けて、英文学を「科学」するためのノート作りに没頭する。その結果、神経をすり減らしてまわりの人たちを心配させてしまう。
いっぽう、帝大を中退し俳句や短歌という短詩形文学の革新をとげつつあった子規は、母・{八|や}{重|え}や妹・{律|りつ}に介護されながら、かろうじてつながった命をまっとうしていく。弟子たちに囲まれて筆を走らせ、ときにはみずから口述して作品を発表していく。
寅彦は物理学科の学生で、妻・夏子と本郷西片町に暮らしていた。バイオリンを弾き絵をかいたりする幸せな日々をおくっていたが、それもつかの間、身ごもった妻の体には病魔が忍び込んでいた。また自らも病をえて休学、郷里の高知で離ればなれではあるが、病妻と幼子に寄り添って生きていく。
漱石、子規、寅彦はそれぞれに日記をつけ、手紙を交わし、また随筆や小品などを遺している。そのような多くの資料に目を通していくと、かれらとまわりの人たちの素顔や生きざまが明治という時代の空気とそこをゆったり流れている時間のなかに見えてくる。
わたしは、資料ファイルが入った端末をもって、かれらの{足跡|あしあと}をたどる旅にでかけた。本書はその旅の記録を{紡|つむ}いだノンフィクション・ドラマである。
章立て、目次、あとがき、サンプルページ、文献などは
のハチヤ書店>出版本のページに、本を書いた動機は「あとがき」に記しておいた。
内容は、小説のようなストーリー性は希薄で、どちらかと云うと各章各節がそれぞれ独立した一口はなしになるよう仕立てた。したがって、一日一節、数分から精々10分もあれば読み終えるはなしが、ほぼタイムラインにしたがってつづいて行く。
ご閑暇なおりにでも、あるいは就床まえのほんのひととき、少しづつページをめくってもらえると大変うれしい。俳句も多く引用したのでゆったりと鑑賞してほしいし、ところどころ当時の科学や技術に関する余談なども挟んでおいた。
(おしまい)
