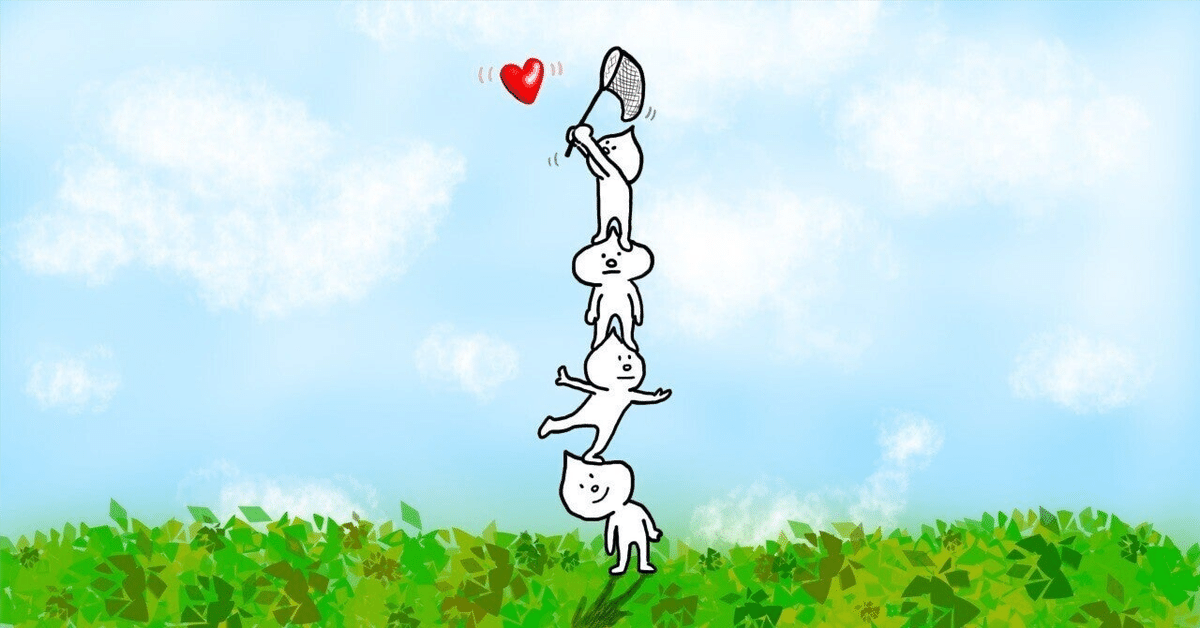
進歩、挑戦、繋がり
ジュニア選手が辞める理由、将来伸び悩む理由に早期からの練習のやりすぎがあると聞いたこともあれば、私自身そう思っている時もありました。しかし、「練習のやり過ぎ」と言っても定義が曖昧で実際にどのくらいがやりすぎで、そのくらいが適切かは目の前の個人を見て考えていくしかありません。
肉体的には耐えれる練習でも精神的に耐えれないケース(練習の習慣がついてないなど)もあれば、逆も同じで意欲はあるが身体が追いついてなく、怪我や疲労に悩まされるケースもあると思います。
心身ともについていけない練習は苦痛でそれにより問題が発生、もしくはその前に辞めるなどにつながります。しかし全然苦しくなく、ただ楽な練習をやっていればいいのかというわけでもありません。ひたすらジョギングを行うだけの練習は返って苦痛になり、特にこの年代にはつまらないものになります。
2年前から中高生の練習を行う機会があり、走力の近い選手が2人います。
1人は年間通して継続して参加してくれ、もう1人は少し続けたと思ったら来なくなって、最近また戻って切れくれました。
前者の場合、大きなモチベーションになっているのは自身の進歩、いろんなレースへの参加です。もう1人はあまり自身の記録には興味がありません。しかし友達と走ることは大きな理由になっていると感じます。あとは最近、負けたくない相手ができたのも影響していると周りから聞きます。
こう考えるとライバルや仲間の存在は競技を続ける上で大きな理由になり、友達がいるから参加するは親やコーチ、先生などが進めるよりも競技を始めたり、続ける上で効果が高いと感じました。
続ける上で大事な要素に、進歩、チャレンジ、繋がりの3つの要素があると感じます。逆にこれらの要素を感じれなくなった時が辞める理由になると思います。
日々の練習、またレースで上記の3つをうまく満たすことができれば走るのが好きでなくても続ける理由にはなるのではないかと考えています。
例えば練習で走るペースが上がった、レースで自己ベストを達成できた、今まで勝てなかった選手に勝った、などは進歩を感じる上で欠かせないものだと思います。
進歩を感じれば新たな課題に挑戦したくなります。今度のレースではこの記録を、今日の練習ではレベルが上の選手についてみよう、など定期的にチャレンジ精神を持って新たなことに挑戦する場があることも続けたくなる理由の一つだと思います。
競技思考ではない人たち向けにインターバル走を行った時も、最初はゆっくりがいい、きついペースは無理と話してた人たちでしたが、結局最後はみんなペースを上げて必死に走っていました。
一つの練習の中でも、「このペースでこの余裕ならもう少し上げれるかもなど」自分で課題を用意してもう少し速いペース挑戦していく姿勢が見受けられます。
最後に競技を通して人との繋がりを感じれるかは一番欠かせない要素です。
練習ではチームメイトと協力して乗り越えること、レースでは他チームの選手と競い合って、新たな出会いに繋がることもあります。そう言った意味で上記でも話したライバル、チームメイトの存在は大きいです。
おそらく競技をやめたくなる大きな理由はこれらのバランスの崩れから生じることが多いのではないでしょうか。
進歩を感じられない、そんな時でもチームのシステムがあり練習のコントロールができず引こうにも引けない、そのため練習やレースがチャレンジではなく脅威に変わる、練習についていけないことから疎外感が生じてしまう。
これらの3つはそれぞれ相互してると思うのでどれかだけというのはないかもしれません。
人と向き合えば予想外の問題はたくさん生じます。現場から離れた位置から「こうすれば解決する、あれをやるから駄目なんだ」と言うことは簡単ですが、おそらく自分が思う以上に見えない問題点が存在します。
これらはレベルや年代に関係なく共通するものです。日々目の前の相手と向き合って問題点の理解に努め、取り組む中で出てくる新しい情報を元に考え直して改善していくしかないと思います。
日常からの学び、ランニング情報を伝えていきたいと思います。次の活動を広げるためにいいなと思った方サポートいただけるとありがたいです。。
