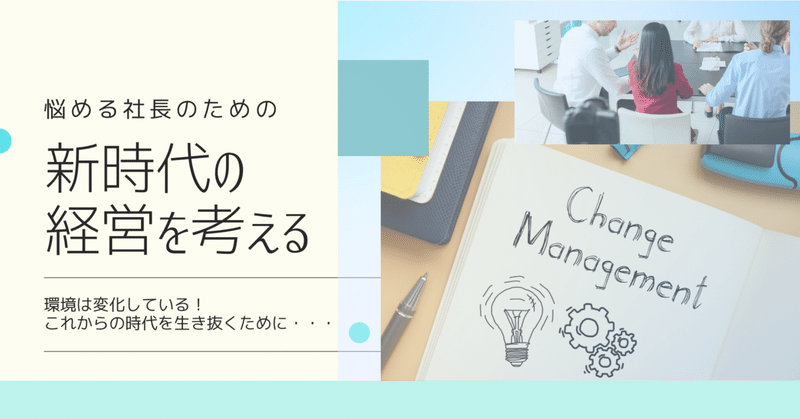
地方創生 <事業承継編>
地方において、事業承継者がいない、という問題は大きい。
そして、それに対する支援策は、行政施策としては、
補助金がいくつかある。
専門家の派遣もあるが、そこは使ってみて、
話がうまく合うか、というところを、吟味しなくてはならない。
どこが主体か、どの省庁の管轄か、という区分けがあって、
見つけにくいと思う。
そして、書類として整えるものも多く、
また、インターネットでの情報公開や、申請と、
中小企業、個人事業、どちらも、譲りたい、と考える側からすれば、
ハードルは高い。
なぜなら、高齢化しているからこそ、その情報にたどりつけないのだ。
孤高の経営者というのも、多いもので、
人にゆずるという考えの前に、廃業を考えることも多い。
昔ながらの経営は、人と人をつなぐ場所であったため、
従業員を家族のように思い、
給与の滞りがないように、少しでも賞与を出せるように、
と起業、経営をしていた期間を何十年、何百年と重ね、
廃業やM&Aへと進めていくとき、
廃業する余力があるうちに、行われる。
余力とは、資金であり、対応する健康と能力があるうちに、
ということだ。
一方、起業したい者にとってのハードルは、
資金やノウハウである。
最近は、小さく始めて大きくする、というよりかは、
小さく始めて小さいままか、
大きくしようとして、組織経営のノウハウはないため、
マネジメントの不足や売り上げの不振に陥り、
経営者が健康を害して、続けられなくなることも多い。
たたき上げの起業家が減り、
様々な困難を前に、精神的にもたなくなる。
相談できる人、場所を持っておく、という準備がないからだ。
事業承継は、会社という器をそのまま引き継ぐことで、
技術や顧客を引き継ぐことができる。
気をつけねばならないのは、
その企業ならではの売り物は、
経営者の力がなくては維持出来ないものではないか、
ということ。
そして、組織を構成する人材と、
価値観、意思の疎通を図れる状態か、
ということ。
企業を支える「人」の力は大きい。
「歴史」の中にある当たり前を、
紐解いて、強みの根幹を、理解しておかなければならない。
大企業と違うのは、
中小企業には、ネームバリューも、組織の設計も、
ほとんどないのが普通だということ。
企業経営は、人に求められる仕事を事業化し、
継続してゆくことが出来るように仕組みをつくり、
それを動かす人を育てること、引き継いでゆくこと、
新しい技術を取り入れることで、
未来へと進んでいくことが出来る。
新しい世界に触れること。
これは、若い人ほど、躊躇が小さい。
まずは、自分が引き継ぎたい、と思う事業を行っている企業を
探してみる、話を聞きに行ってみる、ということも、
必要だろう。
教えてもらえる人がいるうちに、
その事業を引き継げると、
スムーズになることは確かである。
どちらにしても、簡単に起業できるとか、
簡単に経営できるとか、
そんなことはない、ということだ。
事業承継も、儲かるから、というだけで考えるのではなく、
その事業を引き継ぎたい、と思えるかどうかが重要である。
その思いが、困難を乗り越える原動力となる。
地方では、人の要素が強く出る。
だからこそ、思いをもとに、
しっかりと企業の整備を行うと決めて、
買い取る必要がある。
中小企業生産性革命推進事業「事業承継・引継ぎ補助金」(九次公募)の公募要領を公表します | 中小企業庁 (meti.go.jp)
あなたの応援がある、とっても喜びます♡ あなたを笑顔にするために、少しでも役立てればうれしいです!
