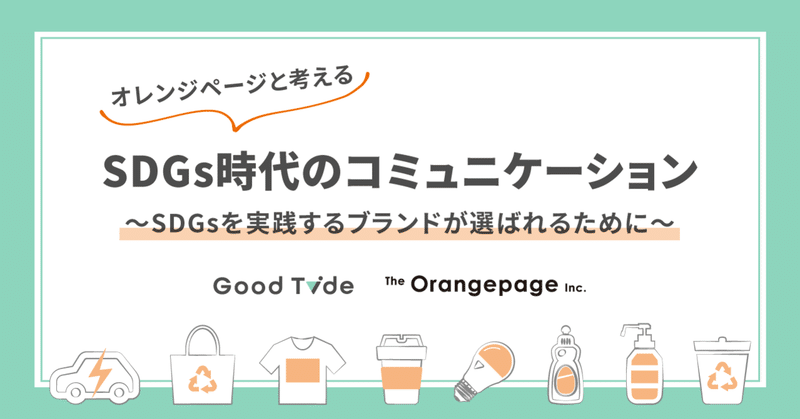
【Webセミナー】オレンジページと考える SDGs時代のコミュニケーション ~SDGsを実践するブランドが選ばれるために~<前編>
この記事は、2021年7月15日(木)に開催したトライバルメディアハウス主催のWebセミナー「オレンジページと考える SDGs時代のコミュニケーション ~SDGsを実践するブランドが選ばれるために~」の一部を書き起こしたものです。
本セミナーはGood Tideチームが株式会社オレンジページ くらしデザイン部の「SDGsコミュニケーション戦略」の策定を支援したことをきっかけに開催いたしました。
セミナーアジェンダ
第1部:「なぜ生活実装がポイントになるのか」
株式会社トライバルメディアハウス
マーケティングデザイン事業部 副部長
Good Tideチームリーダー
太田 裕美子
第2部:「オレンジページが考えるSDGsの生活実装について」
株式会社オレンジページ
くらしデザイン部 部長
高谷 朋子 様
くらしデザイン部
チーフプランナー
吉岡 華子 様
【第1部】「なぜ生活実装がポイントになるのか」
オレンジページ社にてキーワードとして使用されている「生活実装」という言葉は、生活者の“ライフスタイルに落とし込んでいく”ことを意味しています。SDGsというのは、長く取り組まれてこそインパクトを生むものなので、生活に落とし込まれ長く続くことがとても重要になります。
生活実装のためには、企業の皆さんは商品・サービスを提供するだけではなくて、それが実装されていくプロセスを共創することが重要であると考えています。そうした皆さんの共創力とオレンジページさんが得意としている「生活する上で、こういったことが将来あり得る」といった兆しを見つける暮らしのデザイン力、そして「こういう姿であるべき」というあるべき姿のハードルを下げ誰でも取り組めるような生活実装力、これらを掛け合わせてSDGsの達成に向けて共に歩んでいこうと考えています。
1.女性誌の特集から見る30-40代女性を取り巻く「SDGs事情」
詳しい話に入る前に、オレンジページさんの読者層の中心である30~40代の女性を取り巻くSDGs事情を振り返ってみます。
まず、SDGsへの関心度です。皆さんも感じていらっしゃるように、いま世の中のSDGsへの関心はすごく高くなっており、下記の株式会社電通が行った調査における回答者の約半数が「SDGsという言葉を聞いたことがある」と回答している状態です。
この調査は、2020年1月に第3回、21年4月に第4回を実施しているのですが、「聞いたことがある」と答えた人が一年間で約2倍になっています。しかし回答者の多くが、SDGsを知っているからといって何かしらアクションをしているわけではありません。
ただ、その中でも実際にエシカルな商品・サービスを購入している人たちがどういった人かといいますと、20~40代、そしてその中でも女性が中心になっています。特に下記のトレンダーズ株式会社が行った調査からは、ちょうどオレンジページ読者層である30~40代は、(エシカルな商品・サービスの)購入に至っている方が半数以上という結果が出ています。
こうした関心というのは、女性誌の紙面にも表れています。この女性誌のコンテンツを見ながら、30~40代女性のSDGsに関する傾向を深堀っていきます。
まず、SDGsに対して関心が高いと言われている若年層と比較してみます。若年層向けの雑誌(講談社「With」、小学館「CanCam」)、こちらは大学生から20代前半向けの雑誌ですが、こういった雑誌では、SDGsを取り上げる際に、教育や啓蒙というものがテーマとしたものが多いです。
いずれも、SDGsに関する連載になるんですが、タレントがメインとなって一緒にSDGsについて学んでいく、といったコンテンツです。続いて、こちらは主婦向け雑誌(オレンジページ社「オレンジページ」、光文社「VERY」)です。これはオレンジページさんの事例なんですが、フードロスの減らし方であったりとかすぐ痛んでダメになってしまう夏野菜をどのように使うか紹介したページです。

SDGsをどう生活に取り入れるか、という実用的なアクションを伝えるものが多いですね。こういった生活に近い雑誌だけでなく、ファッション誌の「VERY」は「誰の中にもサステママがある」という特集ページを組んでいて、サステナブルのアクションとして、例えば自分でセルフ古着という形でお母様からいただいたものを自分で作ってみるとか、そういったことをテーマとしています。同じような傾向は、商品・サービスの提供方法にも表れています。
2. SDGsのプロモーション事例から見る若年層と30-40代女性のSDGs意識の違い
ここからは、事例をいくつかご紹介します。まずは若年層向けのプロモーションです。
ネスレのキットカットは、タレントの長谷川ミラさんを擁してSDGsに貢献する日本各地を取材していくような動画シリーズをやっています。
こちらは昨年ルミネ新宿で行われていた「エシカル コンビニエンスストア」ですが、エシカルなアクションを商品化してそれを陳列するといったことをしていました。
Schickは「毛について話そう(#BodyHairPositive)」というメッセージで、体毛を必ずしも全部ムダ毛として剃る必要がないということを提案しています。
パンテーンでは、「#令和の就活ヘアをもっと自由に」ということで黒髪で髪の毛をまとめるだけが就活時のスタイルではないよね、という訴求をしています。
ピーチ・ジョンは、リアルサイズモデルとしてスタイルが整ったモデルさん以外のリアルな体型の方をモデルとして商品を見せています。
商品ですと、素材自体をヴィーガンなものやサステナブルな素材に変えていく動きをしている企業が多くなっています。アディダスはヴィーガンレザーを使っていたり、アダストリアの新しいブランド「O0u(オー・ゼロ・ユー)」ではリサイクル繊維を使っていたりしますね。
スタートアップ企業でも、多くの事例が見られます。アディダスとコラボレーションしているallbirds(オールバーズ)ですと、ウールやツリー(ユーカリ)、サトウキビの素材を使ったり、サンダルは廃タイヤを再利用していたりします。
次に、30~40代の主婦層あるいはファミリー層向けのプロモーションと商品を見てみましょう。ポーラは「国際女性デー」に女性の社会進出に関するメッセージを発信しています。
パナソニックは「#しない家事 を話そう。」として“家事は女性がやる仕事”という潜在意識からの解放を訴求していますね。
Oisixはヴィーガンミールキットの提供を開始しています。
ハウス食品はCO2排出削減に貢献するレンジ加熱対応のパウチカレーを提案しています。
キットカットは大袋タイプの商品パッケージを紙に変えたり、イオンは水産資源に配慮した水産物にのみ表示できるMSC・ASC認証「海のエコラベル」を自社の商品につけて販売しています。
スタートアップだと、Stasher(スタッシャー)というプラスチックフリーの密閉保存シリコーンバッグやこのあとオレンジページさんに話していただく事例にも出てきますが、毎日出る生ゴミを堆肥に変える「コンポストバッグ」などがあります。
こうした事例を見てみると、若年層向け商品は“商品自体がすごく変わった”というよりは、素材を変えて既存商品をリニューアルする、あるいは商品は変えないけれどSchickのようにメッセージを変える、といったケースが多いです。一方で、主婦やファミリー層向け商品は、生活スタイルは変えずに使っている商品をサステナブルなものに置き換えるケースが多く見られます。
なぜこのような違いが出るのかというと(これはオレンジページさんの調査結果でもわかっていることなんですが)、SDGsという言葉が使われる前から主婦層は「食品の無駄をなくそう」とか「電気代をどうやったら節約できるかな」といったことを日ごろから考え、自然と環境負荷の少ない選択をしてきたからなんです。
もともとSDGsに対する意識が高い状態なので、若年層向け商品のように「SDGsとはどのようなものか」といった“意識を変える”ところからスタートせずとも、商品・サービスの提案をすることが可能なんですね。
企業は、主婦・ファミリー層に対して“普段の生活で使うモノを、サステナブルなモノに代替する”という提案をすることで、生活者とともにSDGsに貢献することができるわけです。
ただ、意識が高いからといって何でも刺さるわけではないので注意が必要になります。
3. SDGsコミュニケーションの課題
最後に、オレンジページさんが実施したSDGsに関する調査をもとにSDGsコミュニケーションの課題についてお話しします。
各質問に対して、どういった回答がされているか見てみましょう。

(上2つの)マイバッグ持参や詰め替え商品というのは、すでにアクションをしている方が多いです。それに対して、(下2つの)環境に配慮した製品やメーカーを選ぶようにしている、エコ認証マーク付きの商品を買っている、という項目になるとかなり黄色の割合が増えます。
定性的な項目も見てみます。これはオレンジページさんの誌面で連載されている、編集の皆さんのSDGsアクションです。

例えば、急な雨が降ってもビニール傘を買うのではなくてシェアリングサービスを使う、余ってしまった食材はフードバンクに持っていく、短くなってしまった鉛筆を新しい鉛筆と繋げて最後まで使い切る、といった取り組みが紹介されています。家計にとってプラスになる・気分が上がるといったことが、アクションとして続けられる理由であることがわかります。
すでに生活に落とし込まれ継続されているSDGsアクションは、値段が安くなるとか今の生活の延長線上にあって取り組みやすいとか、取り組むべき納得感がある、取り組むことで自分の気持ちや生活が豊かになる、といったものです。続けられているもの=生活実装されているもの、と言えます。このように生活実装されるために必要なのは、商品・サービスを提供するときに丁寧な導入を行うこと、そして“継続してもらうためのモチベーションはメリットである”という点を共創していくことです。
以上、SDGsにとって重要な生活実装についてお話しさせていただきました。この後、オレンジページさんから詳しい内容を紹介いただきます。ありがとうございます。
オレンジページ様のお取り組みを紹介した「後編」はこちらから
====
☆SDGsマーケティングのご相談は随時受付中!
Good TideのTwitterアカウントのDMやトライバルのお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。
☆Twitterアカウントでは、最新SDGsマーケティング情報を更新中!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
