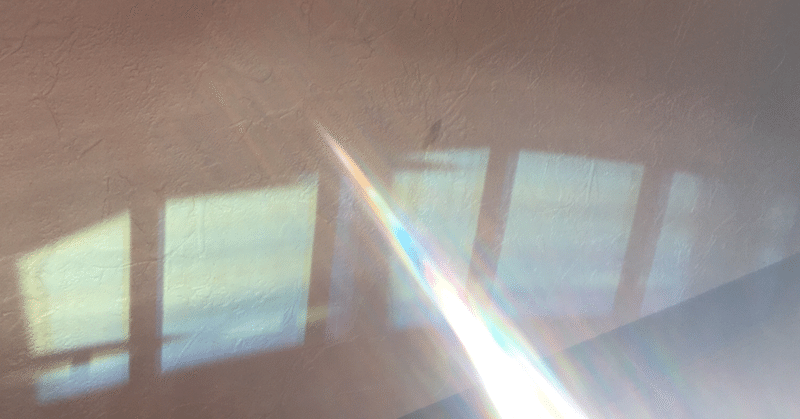
プリズム
野中柊著。
本とは関係ないけど、元々は本の備忘録と自分自身の思ったこと言いたいことの書き殴りは違うnoteに書いてたのよね。
でも、書いていくうちになんだかんだ本の備忘録を書いていても結局は自分の思考に収束するし、だったら統一してしまえとこの場所に一本化した訳。
その化学反応でか、自分の思考を書き連ねるnoteのタイトルを考えるのが楽しくなってしまった。小さい頃から作文やら図画工作やら何かしら「タイトル」が必要なものには何故かタイトルだけやけに気合いを入れていた記憶がある。変わらんな。結局タイトルは何においても「顔」で、所詮その先に進むか掘るかは顔にかかっていたりする。男は第一印象の顔審査で8割落としているなんて言ったり言わなかったりするけどまあ同じようなもんよね。違うか。
大脱線事故を起こしてしまったので漸く本に触れようと思う。
野中さんは多分初めましての方だった。大体本のカバーデザインを見て、中の登場人物の名前を見て、その後に著者のプロフィール、主に過去作のタイトルを確認するのは常なんだけど、さっとタイトルの文字列を流し見した限りではなんとなくティーンズ向けの青春小説に強いタイプかな、と思った。そういう青臭い話は嫌いじゃないので是非読ませていただこう、と手に取って今ここに至る。
しかし家に帰って落ち着いて開いてみたらどうやら青春小説ではなさそうだということが分かる。寧ろ対極。何かというと、単刀直入に言うなら不倫小説。
結構私の好きな文体で、細かく情景が描写されているけれどやりすぎでもない、くどくなく想像ができるタイプの著者さん。
不倫に触れる前に、この小説はやや複雑な家庭環境に生きている「波子」が主人公。両親は離婚し、出ていった母親の方の家族と、血の繋がっていない母親のいる家族。どちらもそれぞれにストーリーがあって、主人公はその間でゆらゆらと生きる。印象的なのは始終どちらが悪いとも言わず、そしてどちらもそれぞれの形できちんと「家族」ができていること。形は違えど、それぞれの家族が主人公に要所要所で影響を与えていく。
冒頭、いきなり誰かの葬式のシーンから始まる。どうやら母親のようだけれども、読んでみると母親の葬式ではない。なぜか自分には母親がいない、という事実だけ知らされていた主人公が幼い頃に作り上げた想像の世界の風景らしい。いつしかそれは死んだのではなくよそに男を作って出ていったのだと知ることになる。そしてその実の母と漸く再会した頃に実の父親は13歳年下の女と結婚する、といった感じで二つの家族が出来上がった。そこにそれぞれ妹と弟が生まれ、現在。
結局親の子なのだろうか。皮肉にも母親がよそで男を作って出ていったその娘が、夫の親友のことを好きになるという話。人によっては胸糞が悪いかもしれないけれど、個人的にはその堕ちていく様子がリアルで、寧ろ怖かった。確かに人を好きになる、という行為はごく自然に行われているもので、止めようと思って止まるものなのかということは私には分からない。何十年とたった一人に愛されてたった一人を愛してたった一人に抱かれる人生は、一体どんな世界なんだろうか。
よく目にする不倫ドラマは毎日に退屈して、とか、刺激が欲しくて、とか、そういう描かれ方をしていることが多いように思うけれど、この本はとても静かで、繊細で、どちらかというと始終悲しい雰囲気が漂っている。
波子の夫、幸正さんはそれこそ静かで、落ち着いた所謂「良い夫」な男。不満は何もない。日々穏やかに過ごしている。それなのに、いや、でも、完全な個人の見解として言うのなら、根本は男が悪いと思う。幸正さんの親友、高槻は、紀代美さんという妻のいる男。よく四人で食事をして、バーで飲んだりする仲だったのに、ある日酔った高槻が波子にキスをしたところから全ての歯車が狂い出す。
「私は怯えていたのだろう。いや、今だって怯えている。恋というものが本来持つ破壊力、獰猛さ、しぶとさを、私はたくみに手なずける自信がない。いつか、自分が自分でなくなりそうな気がして、こわい。でも、その一方で、意思など持ちえなくなる瞬間の、あの甘美さを知ることができる自分は幸福だとも思う。」
例えば出会うタイミングが幸正さんよりも早かったら、幸正さんとの結婚生活が上手くいっていなくて離婚を考えていた時だったら、幸正さんの友達じゃなかったら、考えればいくらでもタラレバは出てくる。でも、タラレバとして存在している架空の世界はあくまでも過去の話で実現する可能性なんてなくて、結局存在するのはただ結婚している私と結婚している高槻、そしてその間で静かに罪を犯す二人だけ。確かに自分を保てなくなるほどの恋愛を知ることができる女はこの世界にどれだけいるんだろうと思うと、それを身を以て知れただけで幸せかもしれない。けれども何よりこの本を読んで分かったのは何か大きく大切なものを失う覚悟をする間もなく坂道を転がるように堕ちていく恐怖が如何ほどかということ。
大切なものがあってもなお、大切だと思ってもなお、失いたくなくてもなお、それでも止まらなくなってしまうそれは一体なんなのか。今まではただ背徳感に酔っているだけでしょうと思っていたけれど、そうでもないのかもしれないと思ったら悪寒がした。うーん、ずっと同じことを書いている気がするな。上手く言葉にできない。
「このひとは何者だろう。ふと、そんなふうに思った。もちろん、私の夫だ。六年以上も生活を共にした。でも、彼は私について、なにを知っているだろう。なにを知って、なにを知らずにいるだろう。私自身も、彼について、なにを知って、なにを知らずにいるのだろう。知らないからこそーあえて互いに鈍感であったからこそ、私たちはこれまで一緒にいられたのかもしれない。」
恋人と夫婦という存在は勿論違う。友達と夫婦も違う。でも、個人的な思いからするとどちらかというと夫婦という存在は友達の方が恋人よりも近いんじゃないかと思うことがある。友達というのは不思議なもので、何もかもを話している訳ではなくてもきっと何かあった時は真っ先に駆けつけて、自分の味方になってくれると信じている。逆に恋人は、ある程度「話すべきこと」「隠すべきではないこと」の領域が存在するよね。確かに夫婦もその領域が存在する上に成り立っている関係だって分かってはいるんだけど、何も説明しなくても私の傍にいてくれる、言葉がなくても信じてくれる存在という意味で、個人個人の足し算で出来上がっている恋人よりも友達寄りな気がしてしまう。そういう意味で言うと夫婦でも一定の距離感はあるし、親しき仲にもなんとやらと言うし、そこに割って入ってぬるっとパーソナルスペースに別の男が入ってきてしまうことは無理な話じゃないんだろうな。結局不倫も知らぬが仏で、寄り道しても必ず自分の元へ帰って来てくれると思っていればいいだけなのかもしれない。そんな心穏やかな訳ないんだけどね。
この本の行く先はあまり明確に書かれてはないけれど、波子は高槻にもしっかり鍵を返した上で自分は自由の身なんだと実感するシーンで終わる。それは結婚という言葉に支配されてしがらみのように感じていたけれど実は自分の進み方次第でどうにでもなるんだという暗示なのか、自分には一人が性に合っているんだと幸正さんまで離れる選択をするのかはよく分からない。でも前者であってほしいし、そう信じたい自分がいる。
そして高槻のような男には思い通りにならない女を好きになって今までの過去の自分を是非恥じてほしいね。それに振り回される女も女だと確かに思うけれど。
.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
