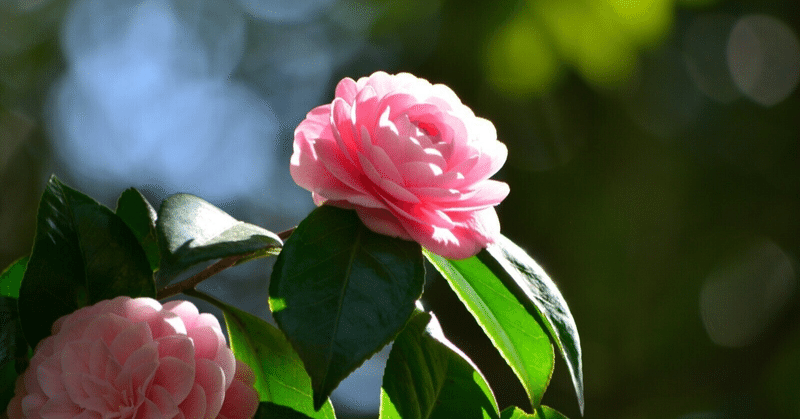
『暇と退屈の倫理学』感想文
人からもらった本が、今年読んでよかった本の暫定1位になるなんて思ってなかった。
この本は2020年以降を生きる我々、すなわちステイホームとSNSが切り離せない人間に必要な本ではないだろうか。
ステイホーム万歳
人間の不幸などというものは、どれも人間が部屋にじっとしていられないがために起こる。部屋でじっとしていればいいのに、そうできない。そのためにわざわざ自分で不幸を招いている。(p.36引用)
※孫引きで申し訳ありません。
おろかなる人間は、退屈にたえられないから気晴らしをもとめているのにすぎないというのに、自分が追いもとめるもののなかに本当に幸福があると思い込んでいる、とパスカルは言うのである。(p.37引用)
※傍点は太字にて表現してあります。
引用部分がめちゃくちゃ刺さった。メディアがこぞって「ステイホーム=我慢=苦痛」という刷り込みをこの1年強ずっとしてるのにもやもやしていたから、救いの言葉がやってきた!って興奮した。
自分から離れたところに幸せがあるかもしれないって思うのは、不幸の中で自分はどうせ…ってやってるのでなければ、いわゆる青い鳥症候群なんだと思う。
人と同じ空間をシェアすること、屋外レジャーや2019年以前と同じ暮らしを求めること、これらを否定はしないけど、今惰性でやること?1年も順応期間あったのに?って感じるのは、ひきこもり好きな人間の傲慢なのだろうか。
ネットワーク環境がないせいでなし上がれなかったガリーラッパーのことを思うと申し訳ないけれど、少なくともnoteを定期閲覧・更新できる人間にとって、肉体を動かさずとも広い世界にでれるから全然閉塞感も退屈もない気がしている。
それにしても、帯文のモリス然り、この章のパスカル然り、既に知っていたはずのものをこの本がなかったら思い出せていなかったのは不覚。思い出させてくれたこの本ありがとう。
SNS非経由で出会った「好きなもの」が思い出せない
高度消費社会ー彼の言う「ゆたかな社会」ーにおいては、供給が需要に先行している。いや、それどころか、供給側が需要を操作している。つまり、生産者が消費者に「あなたが欲しいのはこれなんですよ」と語りかけ、それを買わせるようにしている、と。(p.24引用)
※彼=ジョン・ガルブレイス(経済学者)
フィジカルな買い物をほとんどできていないってのはあるけど、私がSNSを経由せずに買った「好きなもの」ってあっただろうか。
参考文献や推しの作品を買うことを除くと、SNSでレビューが流れてきたものをポチり、フォローしてる有名人がおすすめしているものばかり買っている。
決済ボタンを押しているのは自分だけど、他人のお墨付きがないものを最後に買ったのがいつだか思い出せない。この本だって人に選んでもらったものをたまたま読んだだけだし。
この本で私の「好きなもの」や欲しいものって他人に作られたプレイリストにすぎないのだと気づかされてしまった。与えられた好きと自発の好きの区別が知らない間に溶けていたなんて、我ながら恐ろしい。
絶えざるモデルチェンジを行わねば消費者は買わず、生産者も生き残れない、そのような生産体制がいま決死の努力で維持されている。(中略)なぜモデルチェンジしなければ買わないし、モデルチェンジすれば買うのか?「モデル」そのものを見ていないからである。モデルチェンジによって退屈しのぎ、気晴らしを与えられることに慣れきっているからである。(p.142引用)
※傍点は太字にて表現
さらに追い打ちをかけてきたのがこの部分。大量生産・大量消費社会による労働弊害=途上国の低賃金問題って思ってたけど、所得に関係なく全労働者がお互いの首絞めあってないか…?という気づきを得た。
他者の労働によって生まれたものを惰性で消費するのと同じように、他者も私の労働によって生まれたものを惰性で消費している。それって結局他者を苦しめてるから自分も苦しんでるってことじゃん。
自分が怒るべき労働のあれこれって実はここがもともとあって、残業や低賃金はこの問題の副産物というか付随バグなのかもしれない。
この循環思想ってこれを書いている人も私も日本人で、東洋思想の影響下にいるからそう結論づけちゃうのかもしれないけど、少なくともこの考え方するだけでちょっと労働に対する見え方が変わった気がした。
暇≠退屈
暇だけど退屈じゃない、暇じゃないけど退屈、確かにそんな時あるなぁ。って思いつつ本書のハイデッガーとか環世界のとこまとめられんわ…とか思ってたらご本人インタビューでいい感じに出てたのでそっちを貼る。
本から離れちゃうけど、このインタビューされてる孔さんの読解力と質問力すごいので全3部見てほしい。
結論は各自で出してほしい
以下、これまでに得られた成果をまとめ直し、〈暇と退屈の倫理学〉が向かう二つの方向性を結論として提示する。ただし、それら二つの結論は、本書を通読するという過程を経てはじめて意味をもつ。
論述を追っていく、つまり本を読むとは、その論述との付き合い方をそれぞれの読者が発見していく過程である。本書は暇と退屈について述べてきた。しかし、同じことを同じように説明しても、だれもが同じことを同じように理解するわけではない。(p.353引用)
※傍点は太字にて表現してあります。
前項でもそうだったけど、このnoteは感想文だから結論だったり論旨だったりを要約するつもりはない。私は私の人生の過程で本書に出会って本書に心動かされたのであり、違う過程で出会った人にとったら私に響いた部分は読み飛ばした箇所なのかもしれない。
だからもし暇とうまく付き合いきれてない人がいたら、ぜひこの本を読んでほしい。そして、あなたなりに理解し、あなたなりの結論を出してほしい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
