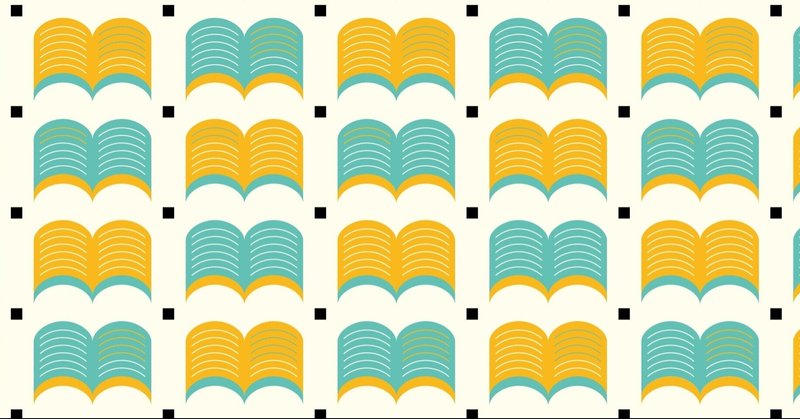
『翻訳 訳すことのストラテジー』読書感想文
最近雑に扱っていた言葉の力について見直そうと思った。
大学受験での英単語丸暗記や物事のカテゴライズ化は、導入や基礎理解には役に立つ。例えば高校生の頃、英単語帳をぼろぼろになるほど読み込んで、「この単語の類義語は〇〇と△△だ!」って頭に叩き込んだものだ。
感情を伴わない簡易文書確認くらいならそれで事足りたのだけど、政治や歴史の記録、文学の翻訳になるとそうもいかない。その実例や「翻訳」について書かれているのが本書だった。
この本を読んで、「参考文献は必ず原著にあたること。ウィキペディアは論外。」って大学の研究室で叩き込まれたのを思い出した。仕事疲れとか文書が電子化されてない(外出自粛で外に探しに行きづらい)を言い訳に、海外文学や理論書を日本語でしか読んでない最近の自分の行いを反省した。
言葉の力というか、言葉の可変性。忘れがちだけど気をつけなきゃいけないことだ。こたつライターの仕事ぶりのように、日本語だって日本語話者に伝わらない。アンジャッシュのコントがノンフィクションで発生すると笑えない事案に発展するし、夏目漱石の文章ですら引っかかりを感じる時がある。
だからといって「翻訳」された語学書が現代のネイティブスピーカーにとって「正しい」かも学習者にはわからないし、それを怖がって何もしないのは違う気もするし、結局のところ「理論・解釈には多様性があるけど、私はこれを信頼する。」って思って取捨選択するしかないのだろう。
読了、めちゃくちゃいい本だった。「翻訳」についての本だが扱っているのはコミュニケーション論であり表現論でもある。読んでいる間中ずっと手触りがいい。オックスフォード大学出版会の超ベストセラー。知性のかたまり pic.twitter.com/CMCYPUKSgz
— 病理医ヤンデル (@Dr_yandel) December 22, 2020
知らず知らずのうちに言葉を軽視してたタイミングで、この本に出会えてよかった。Twitterでこの本紹介してくれたヤンデル先生ありがとう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
