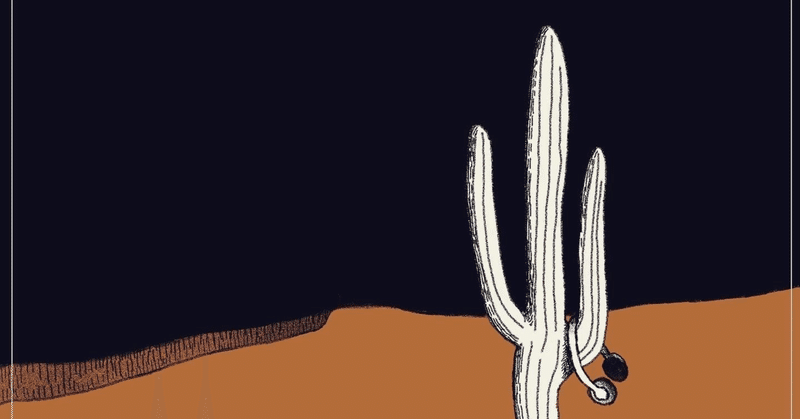
賢く生きるより、辛抱強いバカになれ/著者:稲盛和夫、山中伸弥
【3Point】
①捉え方次第で変わる
倒産寸前の会社という事実に対して、それを解釈するのは人間です。解釈は、その人の過去の経験や教育、知識といったもので作り上げられていた心の中のレンズ、もしくはフィルターによって行われます。それが歪んでいると、良いものも悪く見えるし、悪いものもよく見えてしまいます。ですから、後継者は、レンズやフィルターをクリアにしていくことが必要で、そのためには、正しいものの見方、考え方の基礎となる哲学が必要になってくるのです。
②自分なりの仮説を立てて情報に接する
仮説を立てたら、必ず検証する癖をつけましょう。他人の仮説も、自分の仮説も、時を経てから、正しかったのか、間違っているのか、間違っていたとしたら何が間違いの原因だったのか、きちんと検証することが大事なのです。こうしたことを地道に繰り返していれば、3~5年もすれば、精度の高い仮説を立てられる未来予測の達人なのか、そうでない偽物なのかが自ずと分かってきます。
新聞の小さな記事であっても、それが気になるようになり、見逃さなくなります。小さな記事であっても、それが重要であることが分かるようになるのです。
すべての物事は、初めに微細な変化があり、それはあるとき急激に大きくなるという法則があります。経営者は、この微細な変化に気づく必要があります。
物事の解釈を否定的に見るか、肯定的に見るかで、結果は100%違ってきます。だからこそ、心の傾向性が大事なのではないでしょうか。
③リーダーはそもそも「世のため人のために生きる」という役割を担っている
社業が順調になればなるほど、人間は「これは俺の力だ」と過信しますし、増長します。そのような人に部下はついていくでしょうか。「ついていけない」と思った雲は一つ抜け、二つ抜けしていきます。そして、推進力である雲が無くなったとき、龍は落ちてこざるを得ないのです。
【1Action】
[発見]
精神的な備えをしておくことが大変重要。
世界中で目まぐるしい変化が起き、過去の強みや過去の栄光がいつまで続くか分からない時代です。一挙に強みが消え去ってしまう可能性すらあります。
そのような変化にも対応できる、変化に動じないメンタルを持っておくために精神的な備えが必要になってくるのです。
[行動]
『真実を見るためにはまず、それに対して私たちが持っている視点を捨てなけらばならない』-テック・ナット・ハン‐
本書にも「物事の解釈を否定的に見るか、肯定的に見るかで、結果は100%違ってきます」と記述されていたように私たちは、自分を通して判断していることが分かります。自身の経験によって得た視点から物事を捉えるのは、とても自然なことなのです。
しかし、真実は時折、思いもよらぬ方向に存在していることがあります。それを見ようとしたときに役立つのは、今までと少し、違う角度から物事を見る必要があるのです。
【Task】
経営者に必要な哲学とは何か?
最初に哲学を論じる前になぜ、経営者(ビジネスパーソン)が「哲学」を学ぶべきなのかを『武器になる哲学』(筆者:山口周 KADOKAWA出版)を参考に述べたいと思います。
①状況を正確に洞察する
哲学を学ぶことの最大の効用は、「いま、目の前で何が起きているのか」を深く洞察するためのヒントを数多く手に入れることができるということです。
過去の哲学者が提案した様々な思考の枠組みやコンセプトが、その一助になります。このように重要な問いについて考察する際の、強力なツールやコンセプトの数々を与えてくれるのが哲学だということになります。
②批判的思考のツボを学ぶ
ビジネスでは批判的思考が求められます。変化する現実に対して、現在の考え方や取り組みを批判的に見直して、自分たちの構えを変化させていく。かつてはうまくいっていた仕組みを、現実の変化に適応する形で変更していくのです。
このように「自分たちの行動や判断を無意識にのうちに規定している暗黙の前提」に対して、意識的に批判・考察してみる知的態度や切り口を得ることができるというのも哲学を学ぶメリットの1つなのです。
③アジェンダを定める
なぜ「課題を定める」ことが重要かというと、これがイノベーションの起点となるからです。そこで課題設定の能力が重要になってくるのです。
では、どうすれば「課題設定能力」を高めることができるのか?
鍵は「教養」ということになります。
なぜかというと、目の前の慣れ親しんだ現実から「課題」を汲み取るためには、「常識を相対化する」ことが不可欠だからです。目の前の世界を、「そいうものだ」と受け止めて、あきらめるのではなく、比較相対化してみる。そうすることで浮かび上がってくる「普遍性のなさ」にこそ疑うべき常識があり、教養はそれを映し出すレンズとして働いてくれるということです。
④二度と悲劇を起こさないため
過去の多くの哲学者は、同時代の悲劇を目にするたびに、私たち人間の愚かさを告発し、そのような悲劇が二度と繰り返されないために、どのように私たちの愚かさを克服するべきかを考え、話し、書いてきました。
過去の哲学者がどのような問い向き合い、どのように考えたかを知ることは、愚かな過ちを再び繰り返すことのないよう、高い費用を払って得た教訓を学ばせてもらうという側面があります。
哲学を学ぶメリットについて述べたということで、本題である『経営者に必要な哲学』について論じたいと思います。
結論から述べると、『自分の考えをアクションに転換できる』ことが肝要だと考えました。
なぜかというと、人それぞれ言葉に対する重みが違うからです。重みについてはワンピースで例えることができます。ワンピースの主人公のルフィーは「海賊王になる」という目的・ゴールを持っています。もし、海賊王に興味ない人が「海賊王になる」という目的・ゴールを決めたとしてもそれをアクションに転換することはできないと私は考えています。その違いこそ、言葉に対する重みが人それぞれ違うということなのです。
もし、経営者が必要な哲学を持つとしたら『自分の考えをアクションに転換できる』ものである必要があるということです。
人は論理=ロジックやデータだけでは動かないものです。むしろ感情で動くことの方が多いです。
自分の感情が高鳴るような哲学こそ、経営者持つべき哲学だと私は思います。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ぼくに寄付するとよいことがあります。 サポートして下さった方、本当にありがとうございます。
