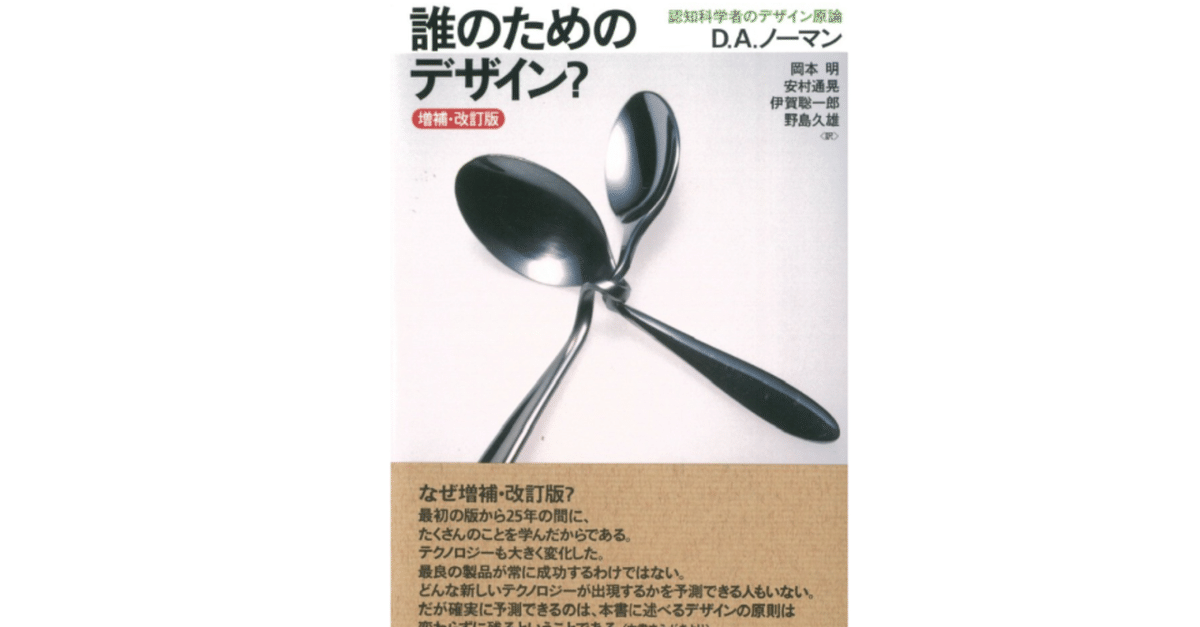
【読書記録】デザインの7つの基礎的原理
おはようございます。
Xデザイン学校主催のとある交流会に参加した際、「使いやすさ」を学問的に追求している例はないのか?と質問したところ、山﨑和彦先生から「認知心理学を知っているか?『誰のためのデザイン』を読んでみなさい。」と言われ、読んでみました。
自分が求めていた、論理的に「良いデザイン」について解説された盛りだくさんの内容になっていたので、復習も兼ねてnoteに記録を残すことにしました。
第2回は、「デザインの7つの基礎的原理」です。
1.デザインの7つの基礎的原理
前回の記事で、「行為の7段階理論」について学びました。

この行為の7段階理論に基づくと、デザインの7つの基礎的な原理が導かれるというのです。
1.発見可能性
2.フィードバック
3.概念モデル
4.アフォーダンス
5.シグニファイア
6.対応づけ
7.制約
この7つの原則は全てが並列の関係絵あるかのようにも取れるが、因果関係があり、発見可能性は、他の6つの原則によって向上されるものであると第1章に記載されていました。
その中でも、概念モデルは最も重要な概念であるとも書かれています。
これらの原則について、1つずつ振り返ってみようと思います。
アフォーダンス
アフォーダンスとは、物理的なモノと人との関係を指している。
自分的に解釈すると、モノを見たときに、それを使ってできると考えられる行為との対応づけだと考えています。
例えば、ダイニングチェアを見た時に、「座る」「運ぶ」「引きずる」ことができると考えます。これらの行為は、ダイニングチェアによって、アフォードされた行為であると言えます。
面白いのが、同じモノであっても、人によってアフォードされる行為が真逆になることがある点だと思いました。
例えば、2Lペットボトル6本入りの段ボール箱を見た時、私は「運ぶ」という行為をアフォードされますが、子供や女性が見た時、「運べない」がアフォードされるでしょう。
モノをデザインすることによって、人の行為をアフォードしたい時、「人」そのものをはっきりと定義しないとブレが出るなと感じました。
この「アフォーダンス」のシグナル的要素を「シグニファイア」と言います。
シグニファイア
シグニファイアとは、人々に適切な行動を伝える、マークや音、近く可能な標識全てを示すものである。
行為の7段階理論の図で言う、フィードバックもフィードフォワードも与えるのはシグニファイアであると言えます。
このフィードバックとフィードフォワードが繰り返し人と外界の間で行われ、コミュニケーションが多くなればなるほど、人がゴールに辿り着きやすくなると考えています。
そのための手段であるシグニファイアがとても重要と言うことです。「言葉」「アイコン」「音」「形状」など、様々な種類のシグニファイアがありますが、これらを人が理解しやすい適切な形で示すのが、デザイナーの腕の見せ所なのではないかと思いました。
また、多くの人が使い慣れているモノに使われているシグニファイアであればあるほど、適切に理解できるのではと思います。「←」アイコンはUndoを連想させます。「🏠」アイコンはHomeを連想させます。これらのアイコンは、世の中のGUIで一般的に使われているアイコンであるからこそ、様々なGUIで使用され、人も簡単に理解することができるのです。
何かをアフォードするためのシグニファイアをデザインする時、同じような役割を持たせているシグニファイアが世の中にあるかどうかを探すところから始めるのが重要だと感じました。
対応づけ
対応づけは、2つの集合の中の要素同士の関係を意味している。
車のタイヤとハンドル、電灯とスイッチ、ガスコンロとスイッチのような、連動する2つの要素の対応づけのことだと考えれば、イメージしやすいです。
人が行為をインプットする対象と、アウトプットされる対象が異なる場合に対応づけが起こるのだと考えられます。
何かしらの制約があって、このようなインプットの対象とアウトプットされる対象が異なるモノにならないといけない時、人は頭の中でそれらの要素を対応づけしないといけないのです。
そもそも、アウトプットが起こる対象と、インプットを行う対象が同じものであることがわかりやすいデザインの原則(「オブジェクト指向UI」とはこのこと)だとして、やむ負えない場合は、この対応づけを上手く人に理解させることが重要だと言うことですね。
対応づけが「自然だ」と感じられるかどうかが重要とのことです。
フィードバック
フィードバックは、要求したことに対してシステムが働いていることを知らせる手段である。
フィードバックはすばやく、理解しやすい形で発生させることで、人が行った行為によって外界に起こったことを理解できる。
フィードバックは強弱が重要であると書かれていて、貧弱なフィードバックは気を散らすし、情報を理解できないので、フィードバックがないよりも悪い。フィードバックが強すぎても、人はそれを全部無視したり、無効にしたりして重要なフィードバックを見逃すことにつながってしまうと言うのです。
難しい。。適切なフィードバックを適度に行うこと。いい匙加減を見つけていかないといけないです。
概念モデル
概念モデルとは、通常は極めて簡素化された、あるモノがどう動くかについての説明である。
デザイナーが持つ概念モデルとユーザーが持つ概念モデルをつなげるのが製品のデザインであり、製品デザインから概念モデルを正しく生成させなければならないと言うのです。
おそらく、デザイナーや開発者が持っている全ての概念モデルを正確に理解してもらうまでは必要なく、デザイナーが期待する使い方をしてもらうために最低限必要な概念モデルは理解できるようにしなければならないのですね。
また、概念モデルはシグニファイア、アフォーダンス、対応づけ、制約から生成される。デザインしたモノからこれらの原則を通じて期待する概念モデルが出来上がるのか、これは開発者やデザイナーとは異なる、開発に関わっていない第3者に協力してもらうことによって確認しなければならないのかもしれないです。
制約
制約については、第4章でとても詳細に説明されています。適度な制約を行うことによって、ユーザーをデザイナーが期待する行為へ誘導するのです。
これについては、また別途取り上げようと思います。
2.重要ポイントリスト
上記のような形で、本書について私が重要だと感じたポイントごとに記録を残しています。
毎回のnoteの最後に、これまでの重要ポイントリストを記載して、備忘録のような形にしています。
1. 良いデザインの重要な特性 (2022/3/13)
2. 行為の7段階理論(2022/3/15)
3. デザインの7つの基礎的原理(2022/3/21)
それでは。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
