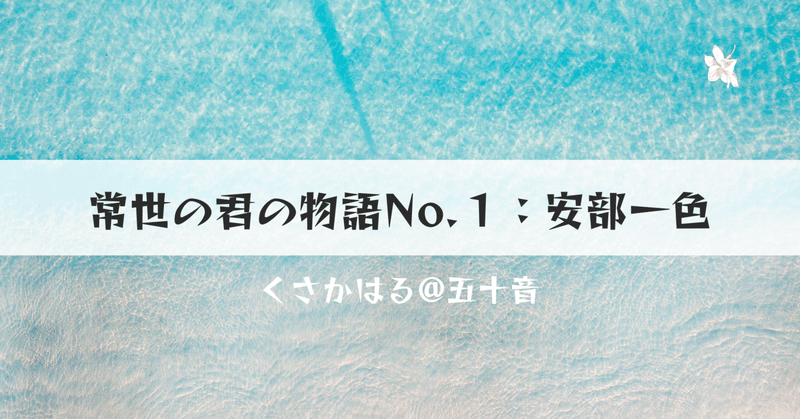
第六章 お香
翌朝は、鍋を金物で叩くけたたましい音で起こされた。
言われるがまま顔を洗い、食事の支度をし、全員分の椀が各々に手渡され、朝餉となった。
汁物を椀に注がれながら、早速、貞盛が口を開いた。
「今日は、この寺に眠る古文書の解読をしてもらおう。」
「解読?」
すぐさま一色が問う。
「そう、この土地についての記録があるはずであるから、それをまとめて報告してもらう。
我らはほぼ半数が文字が読めぬでな。
面倒ごとを頼むという訳だ。」
なるほど、「人の事は人に――」という狐の言が去来する。
「あい、分かった。」
無論、一色たちに拒否権などというものはなく、こう答えるしかなかったのだが、かの地を収めたいという気持ちは同じ、ましてや今はそれしか命を延べる手立てが無いのであるから仕方がなかった。
朝餉の片づけを小坊主たちとこなした後、一色たち四名は、寺の書庫へと移っていった。
寺の書庫は雑然としていた。
頭の上まである棚が部屋を間仕切り、その中に無数の巻物が収められているのであった。
「これは、骨ですねぇ。」
目の前の難題に真中がぼやく。
「そうは言っても、この中に、この地の歴史が記されているのだから、手を付けないわけにはいくまい。
何より今は命がかかっている。
励むぞ。」
一色の号令を皮切りに、四名は各々担当する棚から書物を引っ張り出した。
しゅるしゅると巻物を繰る音だけが書庫に響いていた。
四名が書と格闘することどれほどであったか、突然、玄奈が持っていた書物に目をとめて口を開いた。
「どうやら大昔にこの地をおさめていた秦氏というのは、稲荷を祀ることを始めた士族のようですね。」
「ふむ、こちらの所にもそのような記述がある。」
雅之が答える。
「その秦氏を源氏が打倒した、という話でしたよね。」
書から顔を上げて真中が言う。
「祀っていた人間がいなくなり、自然と稲荷は力が落ちる――、か。」
一色が続けた。
「何やら源氏がこの地に悪い種をまいた気がしてならん。」
雅之の言に、四名は顔を見合わせた。
「では、その源氏とやらに会ってみるか?」
そう頭上から声がしたので顔をあげてみると、書棚の間から顔をのぞかせていたのは貞盛であった。
貞盛の話では、ちょうど一月前に源氏と小競り合いがあった際、妙な娘を捕らえたのだという。
昼餉の席でそう聞かされた一色ら四名は、午後になり、早速その娘と相対する機会を持つに至った。
貞盛の命を受け、後ろでに縄で縛られた娘は、一目見て、奇怪であった。
白塗りに、目と口の部分に朱で縁取りをされた珍妙な面をつけて現れたのである。
「この面がな、外そうと思っても誰も外せぬのよ。
大の男、数人がかりでも無理であったわ。」
娘を前に、貞盛が言う。
「失礼。」
言って一色は大衆監視の中、娘につとにじり寄る。
そして面に指先で触れたり、両の手でそれを抱えてみたりする。
面の中の真っ黒な目だけが、一色の挙動を追っている。
「これは呪いですね。それも相当強力な。」
一色はぽつりと言った。
すると次の瞬間、面の内より声がした。
「当然じゃ。我が兄上がこの身を守るためにとつけてくださった面じゃからのう。」
声の主は確かに目の前の少女である。
「そなた、しゃべれるのか。」
一色は面の中の瞳をまじまじと見つめた。
娘は続ける。
「当然じゃ。
そなた、わらわをなんと思うておった。
源義彬の娘、香とは私のことよ。」
ざわり。
この時、この大広間にもとより巣くっていた物の怪の類の気配がいっせいに部屋の隅に後ずさったのを、四名は感じ取った。
娘の名が、ひとつの呪である証拠であった。
一色はひるまずに続ける。
「お香殿、そなたの兄君について、お尋ねしたい。
そなたの兄君はこの地に何をした?」
しばしの沈黙がおりた。
「答える義務は無いのう。」
娘はそう、口にした。
「おのれ、死にたいか。」
貞盛がすごむ。
「わらわを殺せば我が兄への手がかりが無くなるが、よいのか」
娘は声高に言い放った。
「くっ。」
貞盛は悔し気に口を閉じる。
「ふむ――。」
その様子を見やって、一色はひとり心の中で得心を得るのだった。
「どうする。」
貞盛の仲間が宙に声を投げた。
「この娘は源氏の娘だ。殺すわけにもゆくまい。」
貞盛がおもしろくなさそうに答える。
ひとまず娘の件はこれでお開きとなりはしたが、依然として、娘は超然とした態度を崩してはいない。
そのことが一色には不思議でならなかった。
まるで何かを待っておるような――。
一色のこの問には、そう間をおかずして答えが与えられることとなる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
