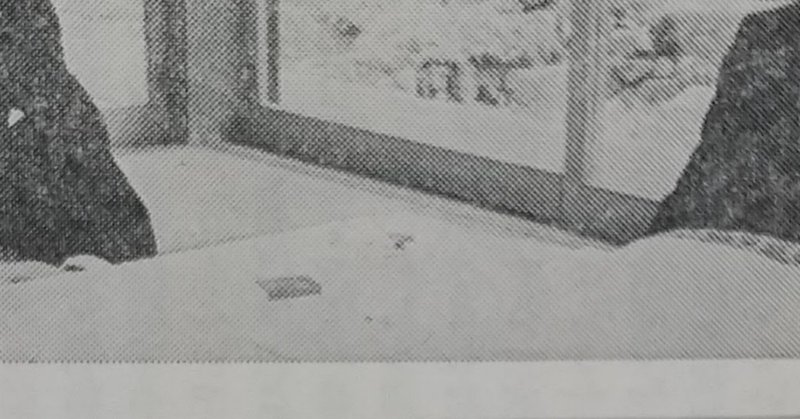
豊饒の海に関するメモ書き
三島由紀夫の没後50年だそうである。
いっとき、ネットのニュースに三島由紀夫のことが溢れた。へんだな、と思ったらそういうことだったのか。当時を知っている人の話は面白い。そして、わたしは当時を知らない。知らないから想像するのであった。
言ってみれば、ヒマなおとなの書く読書感想文みたいなもんである。
問.わたしはこんなことをたらたらと書いて何をしておるのですか。
答.休日をぼさっと過ごしておるのです。
そういうことです。
* * *
豊饒の海 四巻 のハードカバーが家にあって、そこには佐伯彰一と村松剛との対談が付録として付いている。早い段階から物語の構想だけはあって、三島由紀夫は周りにそのことを話していたんだそうである。
最初の二巻は文章としてたしかに
たをやめぶり、ますらをぶり、
という言葉が当てはまるし物語の大きな流れとしても、この先どうなるのだろう、と思わせるものがあったけれど、三巻で、おや?と思わされる。
確かに三巻「暁の寺」は、起承転結の理屈からいえば「転」にあたるもので、世間の評価のとおり物語の視点を、輪廻転生する若者からその若者を見る観察者へ移すための作業のように思う。
対談の中で村松剛は、春の雪、奔馬については安定した二つの小説だと評する一方で、こう言っている。
ところが『暁の寺』から急速に変るでしょう。
佐伯彰一は村松に同意する。
それが非常に問題だ。
(中略)
本多の見ている眼というふうなものが、
ぐうっと中央にせり出してきた感じでね。
さて
三巻「暁の寺」では、三島は本多の姿を借りて話の展開とは関係のない唯識論を延々と展開し、のみならず自分の理解の及ばない対象を前にして「世界は存在しなければならないのだ!」と、珍しくがなり散らすのであった。
なぜわたしが「がなり散らす」という表現を使ったかというと、四巻にわたる長編小説のなかの、たかが二頁の間に、四度も
「世界は存在しなければならないのだ!」
と書いているからである。普通に文章を書いてもくどい三島が、同じことを四度も言うのである。自分に言い聞かせるように。
わたしはここで思うのであった。
「あんた、ほんまは解ってなかったんちゃうのん?」
解ってなかった、という中身は、阿頼耶識という仏教用語の指す対象ではなく、三島が書いている小説の設定そのものである。
三島は論理の作家であった。
平岡公威とは別の人物としてロジックの世界を(世間からみて)綻びなく歩んできた彼であればこそ論理破綻は避けなければならない。しかし、私小説として長編へ挑んだにしては、私小説のもととなる「私」自体が無いではないか、とわたしは考えたのである。三島自身が
本当の自叙伝は長編小説の中にしか書いていない
と自ら著しているにも関わらず。
彼は、青っちょろい平岡公威ではなく、筋肉むきむきの三島由紀夫である。このマッチョで頭脳明晰な作家は、過去からの連続した時間を生きているのではなかった。自らが用意した「三島由紀夫」という偶像を生きていて、その偶像の枠の内側を、行動で埋め尽くすべく生きているのであった。
自らを演出しながらその作家像の枠の中で論理破綻なく生きているのが三島由紀夫であった。しかし、私小説は、過去から現在まで連続する「私」という存在があって初めて成り立つ。人生の途中から自分の演出方法として「作家像」をぶち上げ、それを完璧に演じる三島由紀夫は、平岡公威ではないのだから、告白に値する生身の過去の姿など無いのだ。彼の思い描く作家像があって、現実の彼はその作家像の枠の内側で生きているである。枠の内側はフィクションである。しかし、過去から連綿と続く現実世界は彼の作った枠の外側にある。
本当に私小説を書くのであれば、枠の外側の事実の積み重ねが必要となる。言い換えると、生身の人間が思いついたフィクションの枠の中に棲む作家の源流に遡ろうとしたって「そんなものない」のである。
本当の自叙伝は長編小説の中にしか書いていない
という作家の私小説が破綻を見せるのは、当然やないか。
そうなると読んでいるこちらとしては「輪廻転生」の物語は、松枝清顕が死んで、その続きが曖昧にならざるを得ないと思う。なぜならば私小説であるがゆえに生かさねばならない「私」自体がないからである。ここでの「私」とは、
「輪廻転生」で彼が生かし続けたいと願う、松枝清顕に投影した過去の自分自身
である。
一方で本多の姿をした認識者である三島自身は、唯識論に首を突っ込んで自分の生きている現在(=”世界”)を前提に、阿頼耶識を理解しようとした挙げ句に失敗しただけでなく「世界は存在しなければならないのだ!」と無理やり自分を納得させようとする。
わたしが、阿頼耶識を理解しようとした挙げ句に失敗した、と思ったのは「"世界"という確固たるものがある」という三島の出発点が間違っている、と解釈したからである。平岡公威は、あるべき「三島由紀夫像」を勝手に設定してその一点に自分を収斂させようと行動し続けた。その作家像がいるべき世界もまた彼のなかで「あるべき世界」として一義的に規定されていたのである。
その一義的に規定された世界があるからこそ(それがポーズであっても)楯の会を結成して、あるべき世界のあるべき精神の発露の一つとして会の活動を推し進めたのだと私は理解するのである。
彼はそのように自分を含めた「一義的に存在すべき世界」を想定して、しかしその一方で、時は流れる。時の流れがある以上、世界は一義的には存在しえない。今の世界と1秒後の世界は、認識する主体の捉え方によって全く異なる。全く同じ世界はありえない。あたりまえのことである。
それを理解していながら肉体的な若さに執着する自分の存在を正当化しようとして輪廻転生にヒントを得た、と考えるのはあまりに短絡的なように思えるけれど、その思考実験が失敗に終わった、という告白がこの豊饒の海であるとするならば、実はこれ以上の私小説はないのだ、と言えてしまう。その私小説は、平岡公威の連続的な人生を語ったのではなく、「三島由紀夫像」の造形に失敗した、という書き手の独白である。
そういう解釈を可能にする作家であり、作品であった。
ーーおーーまーーけーー
ここから先は、何やらごたごたと書いておる。なんとなく消すのがもったいないと思ったのであった。先生、そういえば私はもったいない精神と貧乏性の境目がわかってません。
村松と佐伯は、作品後半の出来に関して、安保闘争による影響を挙げている。それも無いとは言えないのかもしれないけれど三島にとってそれは論理を修正させるための隠れ蓑、あるいは破綻している論理を取り繕う言い訳だったのではないか、という気がする。
暁の寺を読んでいると、彼が
「探しものをしていて、でもしっくりくるものがみつからないんだよ」
とおろおろしているようにも見える。阿頼耶識なんて高尚な概念を出してきて、彼ほどの人が小説のなかで引き写しみたいなことをして、いったい何をしようとしていたのか。自分の作った論理の正しさを、参考文献で補強して書き残しておきたかったのではないか。しかしその結論は
「世界は存在しなければならないのだ!」
という一方的な決めつけである。それも、4回も繰り返さないと納得できない程度の。
読んでる方としては
知らんがな
と言いたくなるレベルである。
そんなに力んでるということは、彼の思う「世界の存在」がなにか危うい状態にある、ということであって、だから躍起になって「存在しなければならない!」と言うのである。
こういうのは、自作の論理が破綻してるとき、発言者に見られる態度であって、つまり、阿頼耶識なる思想は彼個人の論理とは相容れず、物語が思った通りの筋書きに進まないことを自覚していたのであろう。輪廻転生の論理はそもそも破綻しておったのだね。
そのうえで「書くと言ったから続き書くけど、ほんとはもうどうでもいいんだよね。まあ、それでも書けちゃうし、最後の場面まで続けないといけないから書くんだけど。」という感じにも見えるのである。
三巻で
「ほら、自分も論理も、無いんだよ。しょうがないんだ。」
と言って認めてしまうと
もう、着地までは惰性で進むだけである。
その尾を引いて、四巻もなんだか醒めてるし、悪い言い方をすると、もう投げやりなのである。そして最後、本多は肉体のみならず、理性からも裏切られるのであった。
これは三島自身の投影だ。自分の組み上げようとした論理を眺めると、明晰なもう一人の自分が「破綻してるよ」と反応する。
四巻について、佐伯は言う。
本当に透明な、抽象的な構造だけの骨組みの小説みたいになっちゃった。
(中略)
どうしてこう抽象的にやせちゃうのか、
一方で
しかしいちばん最後の月修寺の場面の描写、
(中略)
あそこでは小説的時間が流れている。
と評していて、村松もそれに同意している。
村松によれば、三島がいつ切腹をするか決めたのは『天人五衰』の最終章を書き上げた時だったようだ。最後の場面を書ききったら、辻褄を合わせてそこへ進むしか選択肢がないのである。彼は、そう決めて自分で書いて、現実世界の自分までも、作品に歩調を合わせたのであろう。
もはや狂気である。
そもそも輪廻転生は、彼にとって拠って立つに値するものだったのか。「豊饒の海」という言葉の意味。最初から「そんなのない」と知っていて「だから、ないと言ってるじゃないか」というための四巻の冗長。
自分で設定した役柄が最初から無いのを知っていながら、
それを「ある」と言い張って演技する作家。
自分の敷いた作家像の上を歩き、綻びなくそれを体現するための計算。そういう人物の私小説が、豊かなはずがない。繰り返しになるけれども、立ち返る「私」がないのである。文体は彼一流のレトリックで埋められて豪奢だけれども、その中身は何か、と問えば、がらんどうである。
彼はそこまでの論理構築をした上で
豊饒の海
としたのか。
昭和の巨人は、虚構であった。
