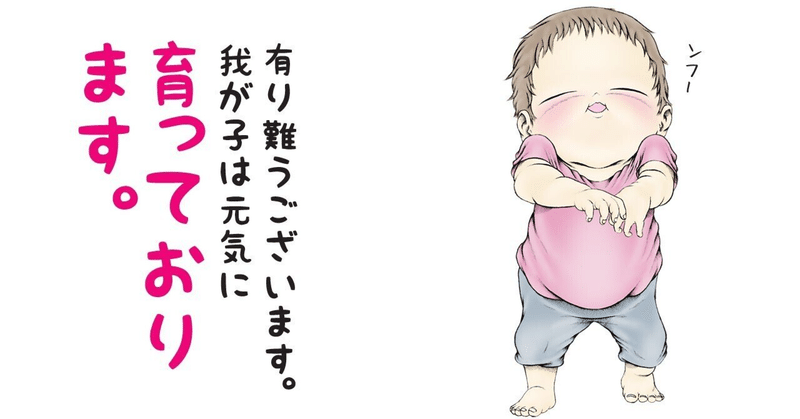
通院多めな子を育てながら働くとどうなるか(育児と共働き【2】)
我が家には子供が3人いるが、入院・通院に関して言えば第三子の長女がダントツである。喘息持ちでかれこれ1週間にわたる入院を4回繰り返している。
初回は夜間救急を受診したらまさかのそのままの入院(この時初めて小児喘息と知る)。2回目以降は、これは入院になるぞと勘が働くようになって荷物を持って行き、そのまま入院して院内からリモートワークもした。
ただ、入院中は検査や回診で忙しく、またトイレのたびに酸素ボンベや点滴と共に移動せねばならず、点滴の管を長女の足にひっかけないようにするのに忙しなかった。
因みに、入院中は点滴の管を手の甲に入れっぱなしで生活するのだが(定期的に薬を流すため)、長女は途中で点滴が上手く通らなくなり、夜中にベテラン先生2人が順番に特殊な赤いライトで血管を浮かび上がらせながら血管を探してくれたことがある。
これぞという血管を見つけるまでに7、8回は刺したと思う。もう慣れっこになっていて、長女は刺される腕をじーっと見つめていた。
話は逸れるが、人生で最初にこの点滴をやった際には、医師から「お母さんは部屋の外で待っていてください。」と言われた。小さい子の場合はタオルで巻いて身動きを制限してから処置をするのだと思う。医療的にこれが安全なわけだが、親には少々ショッキングな光景なのかもしれない。
私はそれよりも、長女の母親を求める泣き声がずっと聞こえてきている方が辛くて、できれば傍に居たいと思ってしまった。
院内からリモートワーク
入院が複数回になるとさすがに職場の同僚にも申し訳ないと、院内から半日単位でリモートワークもしたのだが、その間、長女をテレビ漬けにするしかなく、それはそれで悩ましかった。
もともと業務の堅牢性とメンバーの習熟度に差が出ないようにと交代で業務を回していた部分も多く、急に誰かが抜けても大事にはならない仕組みが出来ていた。だから入院中は完全にメンバーに任せていても支障はなかったかもしれないが、出来ることはやりますというスタンスでやったのだった。
一方で思ったのが、これでは続く人たちが自分も子供が入院したらリモートワークをしないといけないというプレッシャーを感じてしまうのではないかと不安にもなった。自分としては、子供が入院しているのなら、その時は子供に専念したら良いと考えているのだが、明らかに行動は逆になっていて、優柔不断を感じてしまった。
因みにこの交代制は、入院してみると院内でも医師や看護師の方々が実践されていることに気づいた。当然だが、この先生がいないと診察ができませんというのでは患者は困る訳である。ナースステーションでは交代の時間になると、看護師さん達が申し送りを徹底しているため、担当が変わってもこれまでの経緯や薬の把握は大丈夫かなどの心配もなかった。特別な手術等は別として、普段はこういった運営は重要だと思ったのだった。
家庭内の役割分担
入院が何度も繰り返しそうだったため、次に発生した時には夫に付き添い入院してもらう話もしていたのだが、夫の場合は自身がスピーカーとなる会議も多く、それを院内からするのは厳しいし、長女も私の付き添いを求めていることを考えても、対応は私が良さそうだと思っていた。
コロナの関係もあって、一度付き添い入院すると院外には自由に出られないし、付き添いの途中交代も一週間の短期の場合は原則不可だった。
因みに、よく付き添い入院は大変と言われるが、私自身は精神的な負担はほとんどなかった。
強いて言えば、長女が頸部リンパ節炎で入院した時は体力的に大変だったくらいだろうか。首と頭の痛みが強すぎて身体を横たえられず、夜もベッドを90度にしたまま寝ていた(身体を横にする際に、首で頭を支えながら身体を倒していく格好になるが、痛すぎて嫌がった)ため、長女がうとうとして首がガクンと落ちないように支えておくのに一苦労だった。
この時は炎症の数値や白血球の数値が異常に高く、心電図をとったり、血液の培養をしたり、喘息で入院するのとは違った緊迫感もあった。原因は溶連菌で間違いなさそうだったが、川崎病の疑いも払拭できなかった時期は、通常より医師も多めで回診があったように思う。
慌ただしかったのと、ベッドが90度では私自身が寝られず、この時は仕事はさすがに厳しいと判断して休暇で対応した気がする。
子の付き添い入院は必須ではなく看護師さんに任せても問題はないらしいと聞くが、一週間程度の入院で、子供も辛い場合は、個人的には付き添いたいと思った。
もし夫が付き添っていたらというのは想像でしかないが、恐らく思うように仕事がはかどらずストレスになったのではないかと思う。夫の場合は交代ができる仕事ではなく、おそらくジョブ型に該当するのだと思う。
見方を変えると人に迷惑が掛かりづらいとも言えなくはないが、夫には家の方で上の2人の子を見てもらうのがベストだったと思う。長女の退院後の通院や定期通院はできる限りやってくれているため、家庭内でもバランスは取れていると思っている。
仕事との両立
通院関係の家庭内での役割分担はこんな感じだが、夫は長男の中学受験の時期は柔軟に対応してくれ、その時期は休みも私より多く取っていた。上司の計らいで丸々一ヶ月、リモートワークの許可ももらっていた。感染リスクを下げられたりと、とても有り難かった。
そういえば知り合いが、リモートワークがなかった時代は、「保育園と小学校は乗り切れたのに、中学受験は働きながらは無理で退職した人が結構いた。」と言っていた。
私自身は長男の中学受験は仕事との両立に影響しなかったが、夫が対応が難しい状況であれば状況は違ったと思う。そして同時期の同僚の休みの入れ方を見ていると、この時期は毎年、複数人の休みが被るだろうとも思った。
因みに夫は長男の受験当日が平日の時は、会場近くのワーキングスペースを予約して、待ち時間はそこでリモートワークをしていた。これは休みが重なる場合の解決方法にもなるなと思った。
個人的には追い込みの時期が大変だということは知っているため、何らか仕事面で微力ながらも力になれるならそれは厭わない。お互いがお互いのために仕事で返そうという雰囲気があると、職場は働きやすくなると思う。
「子持ち様」が槍玉に挙がっているようだが、子供を産んでからの方が周囲に感謝して働くことが増えた人も決して少なくないのではないだろうか。
次は現在進行形で通院が最も多い次男について書いてみる。
