
魂の犯罪と一人称という窓|杉江松恋・日本の犯罪小説 Persona Non Grata【第6回】
▼前回はこちら
文=杉江松恋
人は心を傷つけられたときにも罪を犯すことがある。
つきつめて言えば結城昌治の犯罪小説は、そういうことを書いているのではないか。
一九二七年生まれの結城は、「エラリー・クイーンズ・ミステリマガジン」誌が開催した第一回短編コンテストに「寒中水泳」(光文社文庫『通り魔』他)が入選したことで作家デビューを果たした。同誌一九五九年七月号の掲載である。一九九五年に最後の短篇「犬も歩けば」(『小説新潮』八月号。『泥棒たちの昼休み』現・講談社文庫所収)を発表するまで三十六年余の執筆生活を送ったが、同一主人公での連作を書くことには熱心ではなかった。短篇連作の紺野弁護士シリーズは例外的な作品で、一九六九年から七九年にかけて十六篇が発表された。『死者たちの夜』(一九七三年)、『犯罪者たちの夜』(一九七九年。ともに現・角川文庫)に全篇が収録されている。この二冊は親本の版元が異なり、また収録も発表順ではない。たとえば発表が最も早い「夜に追われて」は第二短篇集の『犯罪者たちの夜』巻頭に収められている。キャラクターが作品を縛る箍になることを結城は怖れたのだ。
ファーストネームが明かされない紺野は、七人の仲間と一つの事務所を分け合っている、金回りの悪い弁護士である。彼が請け負った依頼は、哀しい結末を見ることが多い。しかもそれらは、わかりやすい暴力の産物ではないのだ。紺野が手がける調査では、犯罪とは無縁である市井の人々が悲劇を引き起こすことが多い。無理解、無関心、そして自己中心的な振る舞い。そうしたものの連鎖によって追い詰められる者が出てくる。常態において人は死からは遠く、生に近い。ところが、異常な心理状態に置かれたとき、人は忌避すべき死を選んでしまうのである。そのような非人間的な事態を描くために紺野という主人公は設定された。純然たる悪意ではなくて、普通の人間の普通の行為が犯罪と呼ぶべき結果を引き起こすこともあるということを徹底して描いたという意味で、この連作は非常に画期的であった。
『死者たちの夜』巻頭に置かれた「暗い海辺で」は、真相を知った紺野が、ある女性の死を引き起こした男と会う場面で終わる。その際に紺野が吐く言葉は「それで責任がとれたと思うのか。きさまにとれるような責任はない。責任なんて言葉は、もう少しまともな奴の言うことだ(後略)」と非常に激烈である。もっとも、ここまで紺野が感情を露わにすることは珍しく、多くの場合は関係者たちに向けられる眼差しは諦念に満ちたものだ。短篇集の題名に「夜」の一字が含まれるのは、人間の持つ暗い一面が描かれた物語という意味だろう。
結城昌治の長篇における代表作の一つが、私立探偵・真木を主人公とする三部作、すなわち『暗い落日』(一九六五年。現・中公文庫)、『公園には誰もいない』(一九六七年。現・小学館P+D BOOKS)、『炎の終り』(一九六九年。現・講談社文庫)である。最も狭義のハードボイルドとは一人称視点の主人公を用いた犯罪小説のことを差すが、真木三部作と紺野弁護士の連作がその日本国内における早期の例であったことは間違いない。
初期の結城は、『ひげのある男たち』(一九五九年。現・創元推理文庫)他の郷原部長刑事シリーズなど、洒脱な謎解き小説を書く作家であった。早川書房の編集者であった小泉太郎に勧められ、一九六二年に『ゴメスの名はゴメス』(現・中公文庫)を書き下ろしたことで路線変更が行われ、犯罪小説的性格の強い作品が増えていく。それが真木三部作につながるのである。ご存じの通り、小泉太郎とは後の生島治郎だ。
結城は海外作品から推理小説のなんたるかを学んだ作家だった。特に強い影響を受けたのはロス・マクドナルドで、リュウ・アーチャーという主人公を起用して完成度の高い推理小説を書いたことを評価していた。結城は、世評の高い『ウィチャリー家の女』(一九六一年)にはトリック上の欠陥と見逃しがたいアンフェアな点があるために評価できないとし、代わりに『縞模様の霊柩車』(一九六二年。ともに現・ハヤカワ・ミステリ文庫)をマクドナルドの最高傑作として推していた。真木ものの第一作『暗い落日』は、『ウィチャリー家の女』の欠陥を補完する意図から生まれたと思しい作品である。
この例からわかるように、結城は謎の提示とその解決を中心とする推理小説の自覚的な書き手だった。創作に関する基本的な考え方を「一視点一人称」というエッセイで表明している。「エラリー・クイーンズ・ミステリマガジン」一九六五年六月号に発表されたもので、第一エッセイ集『昨日の花』(一九七八年。朝日新聞社)に収録された。この文章で結城は、謎解きの意外性を保つために小説的面白さを犠牲にするなど、非文学的技巧が推理小説には必要になる、としている。最たるものが、読者に対して手がかりを与えるために置かれたワトスン役という登場人物だ。この欠陥を克服するために発明されたのが、ハードボイルドで用いられる一視点一人称という技巧なのである。書けることが外面描写に限定される一人称を視点に用いればワトスン役の必要がなくなるからだ。だからハードボイルド派は推理小説の異端児ではない。むしろ忠実に伝統を負っているのだ、と結城は説く。少し長くなるが、エッセイの最終段落を引用する。
――推理小説を読む愉しさは、読者が作中人物といっしょになって犯行現場をあらため、容疑者や証人たちの話を聞き、あるいは珍しい地方の風物に接し新しい知識をあつめ、そしてさまざまの人生に立会いながら事件の真相を推理してゆく愉しさにある。推理小説における作者の視点とはフェアプレイの原則につながる技巧上の問題だが、もちろん多視点三人称によってしかとらえられぬ現実や内容の面白さもあるはずで、私もその立場を捨てたわけではない。しかし目下の私は、一視点一人称という方法に最も正統的な推理小説の技巧をみとめ、その試みの一つとして、私立探偵という職業の存在に小説的リアリティを与えたいと企んでいる。ただしアメリカのハードボイルド作家が創造した私立探偵の肖像画を描こうというのではない。
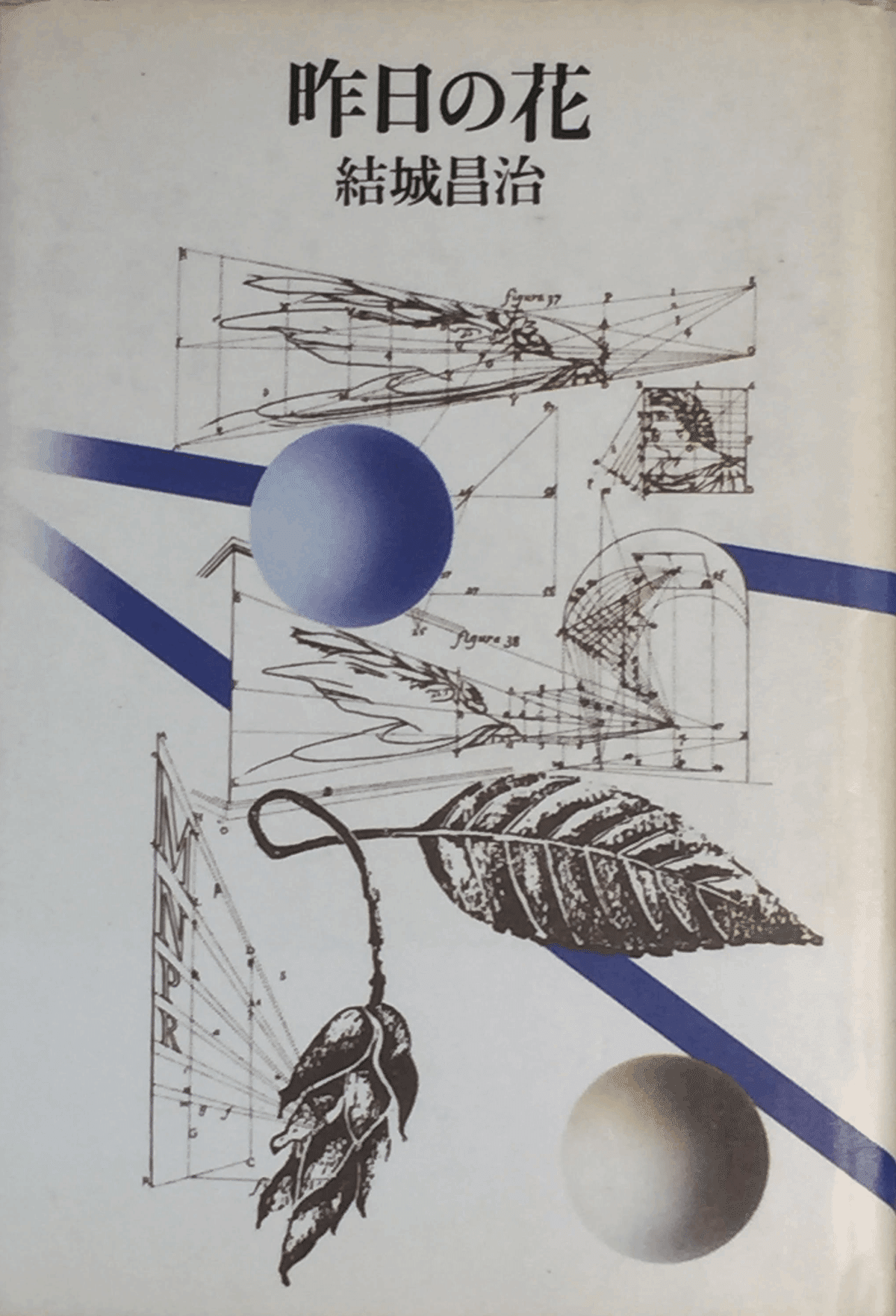
もちろん、ハードボイルドに備わった推理小説的技巧面を評価したのは結城昌治が最初ではない。レイモンド・チャンドラーは一九四四年に発表したエッセイ「簡単な殺人法」(創元推理文庫『チャンドラー短篇全集 事件屋稼業』他所収)で古典的探偵小説への不満と私立探偵小説の可能性に言及しており、結城もこれに影響を受けている。ただし、チャンドラー作品は『長いお別れ』を除いては推理小説としての構造に不満があるとも批判しているのだが。現在ではハードボイルドが雰囲気美人でいいと考えている向きはむしろ少数派で、推理小説としての結構を求める読者のほうが多いのではないか。その意味では非常に現代的なハードボイルド観なのである。「一視点一人称」を書いた時点では、結城にとって最初の私立探偵小説である『暗い落日』は「オール讀物」での連載が始まったばかりだった。『日本ハードボイルド全集5 結城昌治 幻の殺意/夜が暗いように』(創元推理文庫)解説で霜月蒼が指摘しているように、結城が一人称一視点を技巧として発見したのは一九六二年の『ゴメスの名はゴメス』であった。世界を見る目、覗く窓としての一人称が有効であることに、そこで気づいたのである。

創元推理文庫
『ゴメスの名はゴメス』と『暗い落日』の間に長篇が四作ある。『夜の終る時』(一九六三年。現・ちくま文庫『夜の終る時/熱い死角』所収)、『幻の殺意』(一九六四年。前出創元推理文庫所収)、『裏切りの明日』(一九六五年。現・光文社文庫)、『夜は死の匂い』(一九六五年。現・集英社文庫)だ。『夜は死の匂い』のみ「女性セブン」連載で風俗小説の性格が強い。それ以外はいずれも書き下ろしで、重要な意味を持つ作品である。これらを見ていこう。
『夜の終る時』は警察小説で、東京都杉並区付近が舞台となっている。ある日、徳持という実直な刑事が捜査に出たまま消息を絶つ。翌日になって、徳持は絞殺死体として発見されるのである。徳持と面識のある暴力団員・関口隆夫がなんらかの形で事件に関与しているものと考えて、刑事課の面々は捜査を開始する。
この作品は第十七回日本推理作家協会賞に輝いた。河野典生『殺意という名の家畜』(一九六三年。現・双葉文庫)との同時受賞である。選評を見ると『殺意という名の家畜』は日本ではまだ珍しいハードボイルドの実作として評価されたことがわかるが、『夜の終る時』は前年の候補作『ゴメスの名はゴメス』が惜しくも落選したことも考慮に入れ、合わせ技一本のような形で授賞が決まったらしい。ちなみに五回目の最終候補である。各委員の選評では大井広介が、犯人の不憫さが書かれている点を評価したことに注目したい。もともとこの作品は、普通の犯人捜し小説として企図されたものだったが、途中で結城の中に犯人の内面を書き込みたいという思いが強くなってきた。そこで第一部を捜査側、第二部を犯人側の視点で書くという変則的な構成をとったのである。犯人が誰か判明した途端にその〈おれ〉の語りが始まる。それは身勝手で、かつ哀れなものだ。己れの弱さのために許されぬ行為に手を染めた者の、断末魔のような呻きである。いよいよ追い詰められ、最後の瞬間が近くなったとき、犯人は自らの原風景を幻視する。幼少時に見た海の風景だ。
――どこで死んでも同じことだが、おれは急に海が恋しくなった。黒いうねり、一筋の銀色、水平線、そのむこうで、いつも、誰かの呼声がしていた。太陽が燃え落ちる、赤い雲、海が金色にかがやく、そして夜、暗い夜……。
次々に浮かぶ断片的な光景によって犯人の悔恨と絶望が浮かび上がる。不法行為によってこの犯人は僅かな幸せを掴んだが、自らの愚かさによって自滅し、すべてを失う。そうした犯人の卑小さはこの一人称の語りがなければ到底描き出せなかっただろう。
続く『幻の殺意』は、初め『幻影の絆』の題名で発表された。沢島忠監督で一九七一年に映画化された際、それに合わせて改題されたのである。〈わたし〉こと田代圭策は平凡な会社員だ。ある日、高校一年生の息子・稔が逮捕されたとの報せを受ける。藤崎清三という暴力団員を殺害した容疑で、本人は自供しているという。あくまで息子の無実を信じる田代は、知人の弁護士を雇い、自ら事件を調べ始める。
家族が殺人犯として告発され、無実を証明するために主人公が捜査を行うという物語は、スリラーの一類型といってもいいほどに作例が多い。後年に書かれた同型の作品と比べると、『幻の殺意』は構成にひねりがなく、手がかりが与えられるとそこから一気に真相が見えてくる。つまり単純な構造なのだが、だからといって物語に深みがないわけではない。むしろ逆で、その単純さゆえに大きな衝撃がある。本作で一人称が採用された理由は明白で、田代の視界を狭くしたかったからだろう。彼は従軍経験はあるものの平凡な人生を送って来た男で、現在の境遇に何の不満も抱いていない。そんな人物がある日突然、世界を侵食しようとする悪夢の存在に気づくのだ。田代は元の人生を取り戻そうとして奮闘するが、自分の眼が見ないようにしていたものが他にもあることに気づいてしまう。『幻の殺意』のどんでん返しは一度きりである点に意味がある。覆った世界はもう元に戻らないのだ。
偶然だと思われるが、本作も海の情景で物語はしめくくられる。『夜の終る時』のそれは原風景の幻影だったが、こちらはそうではない。現実に描かれるのはごく普通の海の情景だ。ところがそれが田代の眼に入ったとき、彼の胸には絶叫したいほどの思いがこみ上げてくるのである。創元推理文庫解説で霜月蒼は「ハードボイルドを文学的姿勢から定義するならば、それは形而上の心理よりも形而下の行動に叙述の焦点をおく技法を指すだろう」と述べている。田代圭策の見たものに彼の胸中を投影し、直接は語らずにその心理を読者に推測させるという技法が、『幻の殺意』でほぼ完成に至っている。
この次に発表されたのが『裏切りの明日』だ。本作の主人公・沢井は汚職に手を染めている刑事として読者の前に姿を現す。すでに刑事にして犯罪者なのだ。沢井がなぜそのような人物になったのかということは伏せられているが、過去のある蹉跌が原因で、そのために暗い情念を募らせるようになった、ということが語られる。彼の中には何があるのか、ということが本作における最大の関心事である。自分のような汚れた警察官を手先に使って経済犯罪を進めていく企業人たちに、沢井は憎悪を募らせている。不当に自分を貶める社会に対する怒りが沢井を衝き動かしているのである。だが、それは二次的な要因で、もっと深いところに別の動機があるであろうことは初めからほのめかされている。
『夜が終る時』の犯人は自らの弱さゆえに罪を背負いこむことになった。沢井はそうではなく自ら望んだ犯罪者である。この長篇が光文社カッパ・ノベルスで刊行された際の題名は『穽』だった。後半で沢井が自ら語るように、彼の中に「心の底にぽっかりと暗い穴があいたように何物によっても満たされぬ飢え」があることに由来している。沢井は社会を動かしているシステムそのものというべき大企業の犯罪に与して大金を得ようとする。金が欲しいからというよりも、内にある空虚を埋めるために巨大な蓋が必要だからだ。自身が悪であることを承知している犯罪者だが、沢井もやはり心の傷を埋めたい主人公なのである。
一九二七年生まれの結城は十代で不良少年のレッテルを貼られ、それを払拭するために海軍特別幹部練習生を志願する。英雄としての死に場所を探してきたはずなのにただ殴られるだけの日々が続き、そのうちに戦争に負けて再び居場所を失った。戦争で両親を失い、引き取られた伯父の家で孤独な窮乏生活を送ったという沢井の過去には、結城のそれを感じさせるものがある。年齢も異なり、沢井は結城そのものではないが、戦争と共にすべてを失ったという大きな空虚が共通しているのだ。それを埋めきれずにいまだに世界を彷徨っているもう一人の自分を、沢井を描きながら結城は幻視したのではないか。
結城は放浪する若者を主人公とする長篇を他にも書いている。『不良少年』(一九七一年。現・中公文庫)はその一つだ。拳銃を盗んだ澄川隆が暴力の誘惑に駆られていく姿を描いた作品で、内なる怒りをぶつける対象と同時に心から愛せる存在を探し続ける少年像は、若き日の沢井と重なり合うはずである。
もう一作重要な作品が一九七一年の『志ん生一代』(現・小学館P+D BOOKS)だ。五代目古今亭志ん生を主人公とする芸人小説である。一八九〇年生まれの志ん生は一九四五年に慰問のため満州へ渡り、そこで終戦を迎えた。一九四七年に帰国して脚光を浴びるのだが、それまでずっと芸人としては不遇であった。『志ん生一代』はその不遇時代を描くことを主眼とした作品といってよく、印象に残るのは昏い目で周囲を見回しながら彼我の差を嘆く志ん生の姿だ。この不遇時代があったから伝記小説を書くことを発意したのか、もしくは尊敬する芸人について書いているうちに自身との共通点を見つけたのか。それはわからないが、若き日の彷徨を前半部で書くことで結城は自らの志ん生像を掴んだのではないか。
芸人としての開眼によって志ん生は遅咲きの春を迎えた。小説の終盤はやはりその事実に基づいた展開になる。結城の描く晩年の志ん生像は、自身のそうした成功に戸惑っている人に見える。あるいは内なる空虚を埋められずに堕ちていった、無数の同胞の影を背負っているようにも。
《ジャーロ No.85 2022 NOVEMBER 掲載》
■ ■ ■
▼ジャーロ公式noteでは、皆さんの「ミステリーの楽しみ」がさらに深まる記事を配信しています。お気軽にフォローしてみてください。
いいなと思ったら応援しよう!

