
日本ミステリー文学大賞の軌跡・第7回 都筑道夫|横井 司
日本ミステリー文学大賞の第一回の選考は一九九七年十一月五日に行われました。
その後、昨年二〇二一年の第二十五回までに選考された受賞者の一覧は、戦後から現代までの日本ミステリー史をそのまま映し出しているといっても過言ではない、錚々たる顔ぶれです。
本企画では、作風と特徴、作家の横顔、いま読むべき代表作ガイドなど、第一回からの受賞者を一人ずつ特集します。
回を追うとともに、日本ミステリー史を辿っていきましょう。(編集部)
▶日本ミステリー文学大賞《これまでの受賞者》
▼第6回はこちら
文=横井 司(探偵小説研究会)

第六回日本ミステリー文学大賞は都筑道夫が受賞した。選考委員は阿刀田高、権田萬治、佐野洋、皆川博子の四名。《選考経過》では「ミステリーの長・短編、評論、エッセイ各分野において半世紀以上にわたり活躍を続け、後進に指針を与えた都筑道夫氏が受賞と決定」したと報告されている。第一回の大賞受賞者である佐野洋は《選評》において、日本語版『エラリイ・クイーンズ・ミステリ・マガジン』(通称・日本語版EQMM)の匿名コラムを愛読していたといい、その匿名コラムの筆者がのちに都筑であることを知って、「私は都筑さんの導きで作家になったとも言える。結城昌治さんも同様に考えていたようだ」と述べている。《受賞の言葉》で都筑は「選評を拝見し、選考委員の方々が、私の書いたものをなにかしら意識において、推理小説の道に進まれたことを知らされた。長年言いつづけてきたことが、多少なりとも皆さんの頭に残ったとすれば、それがなによりも嬉しい」と述べているのは、右にあげた選考経過と佐野洋の選評に紐づけられるように思われる。
皆川博子は「戦後いち早く海外ミステリーの翻訳紹介にあたられ、創作の面でも、垢抜けた文体で、常に、斬新な手法、凝った構成に挑まれ、本格から怪奇、ショートショート、ホラー、伝奇、と幅広い道を開拓してこられました」と述べ、阿刀田高は自身が「ブラック・ユーモアという用語をたずさえてマスコミにお目見えしたころ」関西のテレビ放送に招かれて出演した際に「後見役として」招かれた都筑が「この新しい概念の説明に当たった」という思い出を語り「星新一さんとともにショートショートの第一人者であり、もちろんミステリーについては長編、短編、評論、エッセイ、なんでもこなし、どれもみな造詣が深く、キラリと光っていた」と述べている。これらを読むと、ちょうどアメリカ探偵作家クラブのグランドマスター賞を授賞するような感じで、選ばれたことをうかがわせる。
都筑道夫はミステリ作家としてデビューした一九六〇年代前半から九〇年代までの間に、長編や短編、長編評論によって日本推理作家協会賞の候補にあげられてきたが、何度も見送られている。二〇〇一年になってようやく自伝的長編エッセイ『推理作家の出来るまで』(二〇〇〇)によって「評論その他の部門」を受賞し、その翌年に日本ミステリー文学大賞を受賞したわけである。権田萬治が選評において「都筑道夫氏は日本のミステリー界のいわば前衛であり、アヴァンギャルドだというのが私の持論であり、氏が長い間賞に恵まれなかったのも、その作風が余りに前衛的で、斬新だったからではないかと思っていた」と述べているのは、右のような事情による。権田は続けて「氏は常に実験に次ぐ実験で日本のミステリー界に刺激を与え続けて来た」と書いているが、そこでいわれている「実験に次ぐ実験」とはどのようなものであったのか。また、《選考経過》でいわれている、後進に与えた指針とはどのようなものであったのか。それぞれについて以下に概説していく次第だが、その前に都筑道夫のプロフィールを簡単に紹介しておくことにしよう。
都筑道夫は一九二九(昭和四)年七月、東京に生まれた。本名松岡巖。早稲田実業学校高等部中退。当初、戯曲家を志し、一九四六年の春ごろ、正岡容の門を叩いた。翌年、正岡の紹介で新月書房に入社して、同社から発行されていた様々な雑誌の編集に携わった。その後、青灯社に移り雑誌『ポケット講談』に講談のリライトを発表するようになる。それまで、様々な筆名を使っていたが、同誌の編集長に中心となる筆名を決めておいた方がいいと言われて「都筑道夫」と命名し、一九五〇年に発表した時代もの「木彫りの鶴」で初めて小説に使用。同じ年、『宝石』に掲載された創作「天狗」(一九四八)を読んで感動して以来、手紙のやり取りを続けていた大坪砂男の許を訪ねる。以後、頻繁に通うようになり、宇野利泰や日影丈吉など、先輩翻訳家・小説家との交流も生まれた。一九五二年には探偵作家クラブ(現・日本推理作家協会)に入会。そのころから、主な収入源だった読物雑誌が軒並み廃刊となったため、口紅会社の広告部に入社し、広告の文案を作るようになる。同時に、海外推理小説のペイパーバックを集め始めていたが、大坪の紹介で松村喜雄と知り合ってからは共同で翻訳を始めるようになる。松村の翻訳した作品を小説らしくリライトするという作業だったが、翻訳が間に合わない時は創作して辻褄を合わせることもあった。創作翻訳を含む読物雑誌時代の作品は『都筑道夫ひとり雑誌』全三巻・別巻一(一九七四)に、当時のペンネームを添えて収録されている。
一九五四年に「十八、九から書きはじめた時代小説に、長篇を一本、書きおろしてピリオドをうつ」というつもりで書いた(引用は中公文庫版「あとがき」から)書き下ろし長編時代小説『魔界風雲録』(別題『かがみ地獄』)を都筑名義で上梓。翌年から翻訳家へと転身するが、一九五六年に日本語版EQMMの編集長として招聘され、早川書房に入社することとなった。同時にハヤカワ・ポケット・ミステリ(通称ポケミス)のセレクトも任されることになり、EQMM編集とポケミスのセレクトおよび解説のかたわら、創作と翻訳を発表するようになる。一九五七年には福島正実と共にハヤカワ・ファンタジイ(後のハヤカワ・SF・シリーズ)を発刊し、初期九冊の解説を担当(『都筑道夫ポケミス全解説』[二〇〇九]に併録)。また一九五九年には、EQMM誌上で初めてショートショートという呼称を紹介している。同年の夏頃、早川書房を退社し、執筆専業となった。一九五八年から五九年にかけて雑誌『マンハント』に翻訳連載していたカート・キャノン(エド・マクベインの別名)の〈酔いどれ探偵〉シリーズ(のちに『酔いどれ探偵街を行く』の邦題でポケミスに収録)が好評で、一九六〇年には原作短編がなくなったために自ら贋作して継続してもいる(のちに『酔いどれひとり街を行く』[一九七五。のちに『酔いどれ探偵』と改題]と題してまとめられ、その際、契約の関係で探偵の名前はクォート・ギャロンと改められている)。贋作シリーズを連載しているころに、書き下ろし長編推理小説の打診を受けて取りかかり、一九六一年に『やぶにらみの時計』と題して上梓され、推理作家としてのデビューを果たした。
以後、『猫の舌に釘をうて』(一九六一)『誘拐作戦』(一九六二)『三重露出』(一九六四)といった作品を刊行し、前衛的といわれる作風を印象づけた。一九六七年になって、日本在住アメリカ人で自称詩人のキリオン・スレイを探偵役とするシリーズの第一作「剣の欛」(のちに「最初の? なぜ自殺に見せかけられる犯罪を他殺にしたのか」と改題)を、翌年には、〈なめくじ長屋捕物さわぎ〉シリーズの第一作「人食い舟」(のちに「よろいの渡し」と改題)を発表。一九七〇年には、日本語版EQMMの後継誌『ミステリマガジン』に長編評論「黄色い部屋はいかに改装されたか?」を連載。連載終了後、自らが理想とする本格推理小説(都筑は「パズラー」と呼んだ)の実作として長編『七十五羽の烏』(一九七二。別題『平将門呪殺事件』)を書き下ろしたほか、一九七三年からは、安楽椅子探偵ものの形式に則った〈退職刑事〉シリーズを開始。その後も推理小説や怪奇小説を主軸に据え、時代伝奇小説、ヒロイック・ファンタジー、SF、ハードボイルドなど、幅広いジャンルの作品を発表し続けた。一九九九年で新作の発表は途絶えたが、二〇〇〇年になって、一九七五年から書き始め、一九八八年に完結した自伝的エッセイ『推理作家の出来るまで』がまとめられ、同書によって翌年、日本推理作家協会賞を受賞。二〇〇二年に日本ミステリー文学大賞受賞後、光文社文庫から全十巻の選集がまとめられた。二〇〇三(平成十五)年三月に東京の自宅から長女の住むハワイに転居したが、同年十一月に心臓発作のため急逝。享年七十四。
都筑道夫の作風は、先に引いた阿刀田高や皆川博子の選評でもいわれている通り、多岐にわたる。光文社文庫でまとめられた〈都筑道夫コレクション〉全十巻は、初期作品集・青春篇・ユーモア篇・パロディ篇・本格推理篇・SF篇・怪談篇・アクション篇・ハードボイルド篇・時代篇というふうに分けられていることも(初期作品集と青春篇はそれぞれ、ジャンルではなく活動歴や主題に即したものだが)作風の多彩さをよく示している。だが、都筑道夫という作家の凄さを知るには、何を措いても初期に書かれた、いわゆる前衛的でアヴァンギャルドとされる八大長編――『やぶにらみの時計』『猫の舌に釘をうて』『なめくじに聞いてみろ』(一九六二。旧題『飢えた遺産』)『誘拐作戦』『紙の罠』(一九六二)『悪意銀行』(一九六三)『三重露出』『暗殺教程』(一九六七)を読むに如くはない。
初期八大長編のうち『やぶにらみの時計』『猫の舌に釘をうて』『誘拐作戦』は、大内茂男によって「超本格」と名付けられた(「前衛作家・都筑道夫」『推理界』一九六八年三月号)。
『やぶにらみの時計』は、「目がさめたら、まったく違った環境に、身をおいていた」という欧米の推理小説にお馴染みのパターンを踏まえたスリラーで、「不可能犯罪のトリックは、できるだけ異常な事柄が、できるだけ単純に解明されること」「たったひとことで、すべての不可能が可能になること」が理想であるとする都筑は、「このパターンの欠点である偶然の入りやすさを避けるために、そのたったひとことを探した」のが本作品の「みそ」だとのちに解説している(三一書房版『やぶにらみの時計/かがみ地獄』あとがき)。「別人にされた男が、自分を探して、東京を歩きまわる」(「秋の雷雨」『推理作家の出来るまで』)というプロットからは本格ミステリという印象を受けないにもかかわらず、「超本格」と目されたのは、右に述べたようなトリックが印象的だったからだろう。本作品の場合、それに加えて、一九六〇年代の東京の風俗を描くために、ミシェル・ビュトールの『心変わり』(一九五七。本邦初訳は一九五九年)に倣って、主人公をできるだけ読者に密着させると同時に主人公の知らないことを書きこむことができる、二人称という「実況放送スタイル」を採用している。今でこそ二人称のミステリは、竹本健治『カケスはカケスの森』や法月綸太郎の『二の悲劇』などが書かれているものの、当時はまったく新しい試みだった。
『猫の舌に釘をうて』は先の三作品の中では最も本格寄りだが、「ひとりの人間が同時に犯人であり、探偵であり、被害者でもある、という小説は書けないだろうか、という考えから、形をとりはじめた」もので(三一書房版『猫の舌に釘をうて/三重露出』あとがき)、同じ設定で有名なフランスのミステリ、セバスチアン・ジャプリゾの『シンデレラの罠』(一九六二。本邦初訳は一九六四年)よりも一年前に書かれている。本作品はそれに加えて、出版前に本の厚さを確認するために作られる束見本に主人公が事件の経緯を書き込むというスタイルがとられており、本そのものにトリックが仕掛けられているという趣向が施されている。途中で、エラリー・クイーンばりに読者への挑戦状が挿入され、その挑戦状にも仕掛けがあるという凝りようで、まさに「超本格」と呼ばれるに相応しい一編だ。
『誘拐作戦』もまた「正体不明のふたりの人物が、一章ごとに交替して、書いた小説、というスタイル」(「わが小説術」)で誘拐事件の顛末を描き「登場人物のだれとだれが執筆者か」というのが謎になっている。また、「パズラーとしてのトリックを、つつみかくす煙幕の要素」(三一書房版『紙の罠/悪意銀行』あとがき)として、当時アメリカで流行していたシック・ジョーク、今日でいうところのブラック・ユーモアの糖衣を意識的にかぶせており、初期長編の中では最も端正な仕上がりを示している。それもあってか第十六回日本推理作家協会賞の候補作となったが、受賞は土屋隆夫の『影の告発』に譲った。松坂健は創元推理文庫版(二〇〇一)の解説で「名探偵役の人物まで、話者の好みで名前が変えられて、ふたつ名前があるなんていうミステリは今もって書かれていないと思う」と述べているが、そうしたジョークをジョークとして受け入れる土壌がまだ整っていなかったということだろう。
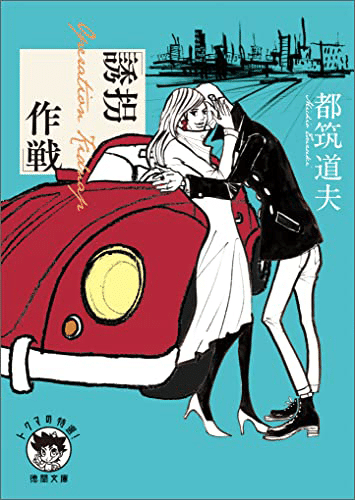
初期八大長編のうち、『誘拐作戦』に続いて刊行された『紙の罠』およびその続編『悪意銀行』は、「ひとの悪事をかぎつけては、わりこんでいって、ひっかきまわす商売。大まわりも小まわりもきく、あたまと手あしだけを資本に、油揚げをさらって儲ける、とんびみたいな男たち」(『悪意銀行』第一章b)近藤庸三と土方利夫を狂言回しとするコミック・スリラーである。『悪意銀行』では冒頭に「落語的なスリラー」を意味するa lack-gothic thrillerという副題が添えられており、作者に推理小説と落語の面白さを教えた次兄・鶯春亭梅橋への献辞が掲げられていた。『紙の罠』の方は近藤が沈思黙考して殺人犯を突き止める場面があり、ユーモア・ミステリとしてまだ推理の要素が残っていたが、『悪意銀行』になると、対抗勢力同士が殺戮しあったり、奇妙な殺し屋が呼ばれたりするなど、アクションものとしての要素が前面に押し出されている。
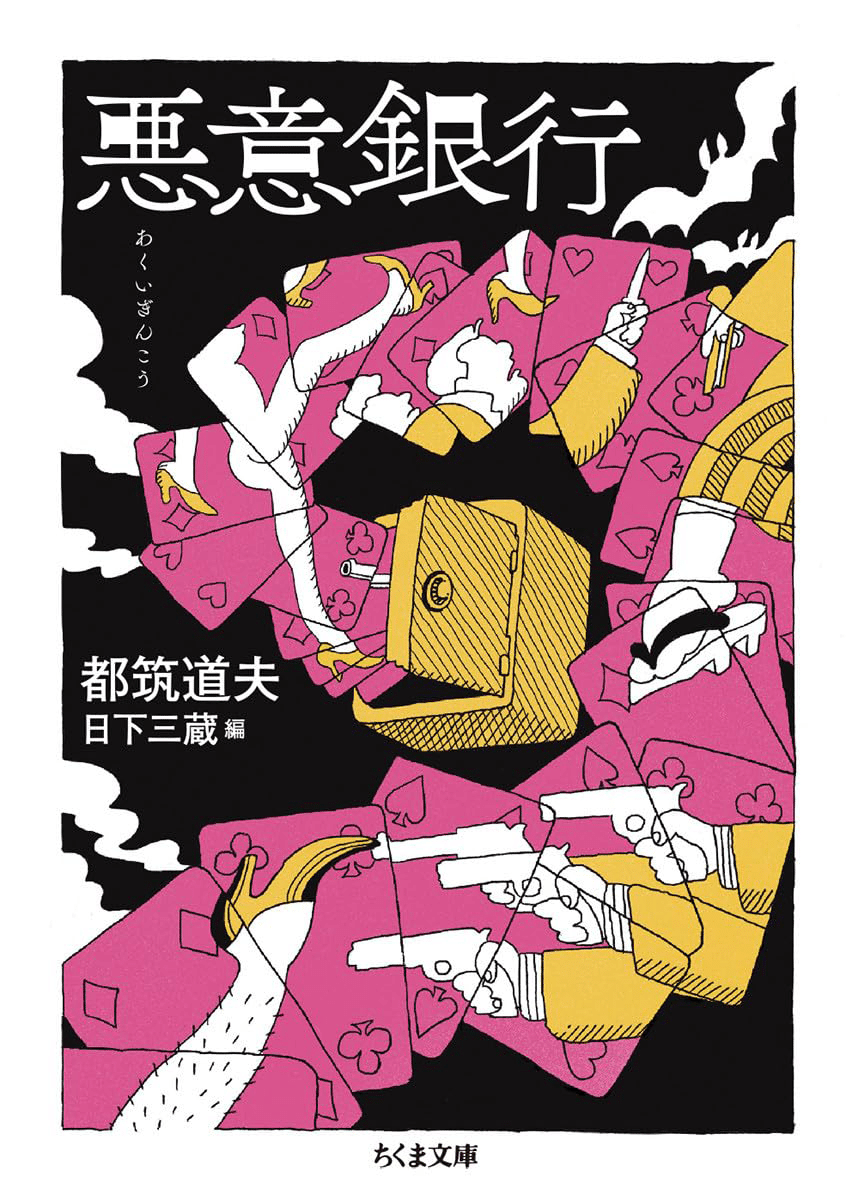
こうしたアクションものとしての性格は、初期長編の中では『なめくじに聞いてみろ』や『暗殺教程』に顕著に見られるものだ。いずれも、イアン・フレミングの007シリーズに惚れ込み、ポケミスによって日本に初紹介した都筑の活劇趣味が全面的に展開された一編といえる。『なめくじに聞いてみろ』が、そのパロディ版ともいえるナンセンス活劇に仕上がっているのは、「007のようなスーパースパイを、当時の日本に設定して、活躍させるのは無理だったし、最初からその気もなかった」(三一書房版『なめくじに聞いてみろ』あとがき)からである。『暗殺教程』にしても、シリアス・スパイものではなく「ストーリイの展開のスピードと、敵味方のあいだにくりひろげられる闘いの変ったアイディアに、作者は主力をそそいで」おり、スパイ小説というよりも冒険小説と呼びたいと、初版本(桃源社版)の「あとがき」で述べている。変わったアイディアという点では『なめくじに聞いてみろ』とも共通しているが、『暗殺教程』の方がまんがチックでありながら、シリアスなのは、当時「日本の冒険小説の伝統は、時代小説のほうに旺盛で、現代小説ではかぼそいから」というのも創作動機になっているからだろう。都筑は冒険小説の魅力について、三一書房版『なめくじに聞いてみろ』の「あとがき」で「Chase and Adventure(追跡と危険な行動)とAttack and Escape(攻撃と脱出)という、ふたつの語句でいいあらわされることが多い」といい、フレミングが重点を置いたのは後者であるとしているわけだが、都筑のあげたふたつの語句は『紙の罠』や『悪意銀行』の内容にもそのまま当てはまるわけだから、この二作と『なめくじに聞いてみろ』および『暗殺教程』は、アクション路線の作品群としてまとめることができるわけである。大内茂男はこれらの作品群を「超アクション」と評した。
右に紹介してきた「超本格」路線と「超アクション」路線との両方の要素をまとめてひとつにしてしまったのが『三重露出』である。アメリカで刊行された、日本を舞台とする忍者アクション・スリラーを翻訳した部分である「超アクション」パートと、それを翻訳する訳者が、作中に登場した日本人女性の名前が、かつて殺害された人物であることを知っていて、その事件を探ると同時に、なぜアメリカの小説にその名前が出てきたのか、という謎を追求する「本格」パートとが、交互に提示されるという構成をとった一編である。翻訳パートが二段組、訳者パートが一段組になっているが、前者には版権取得表示のコピーライトが印刷されており、これは早川書房のポケミスの体裁を踏襲したものだ。「超アクション」パートは山田風太郎の忍法帖のパロディーを意図しているが、実際にアメリカで出版されたアール・ノーマンの日本を舞台にしたシリーズにもインスパイアされている。「本格」パートは作者自身の『猫の舌に釘をうて』を思わせる雰囲気がある。「超アクション」パートに普通の「本格」パートが挟み込まれることで「超本格」になっているという意味で、「超本格」と「超アクション」の両方の要素をまとめる形になっていると見なせるわけで、まさに初期の作風の集大成的な作品といえるわけだ。近年話題となったアンソニー・ホロヴィッツの『カササギ殺人事件』を彷彿させなくもないし、そういえばホロヴィッツはイアン・フレミング財団から依託されて007シリーズのパスティーシュも手がけており、意外と都筑道夫との親近性が高い。イギリス風のひねった作品を好んだ都筑であってみれば、ホロヴィッツとの相似は嬉しいものではなかったかと想像される。
『三重露出』の後、ナンセンス・スリラー路線に倦んでいた都筑は、『暗殺教程』の連載が終わる頃から、G・K・チェスタトンやエラリー・クイーン、ディクスン・カーなどを読み返して、日本のミステリに何が欠けているかを見定めようとしていた(「運動の時期」『推理作家の出来るまで』)。同時に、短編推理小説の執筆に軸足を移していく。一九六七年にキリオン・スレイ・シリーズの第一作「剣の欛」を雑誌『推理界』に発表。翌年にはやはり同誌に〈なめくじ長屋捕物さわぎ〉シリーズの第一作「人食い舟」を発表したのは経歴にも述べた通り。本としてまとまったのは後者のシリーズが先で、一九六九年に『血みどろ砂絵』(のちに『ちみどろ砂絵』と改題)が、一九七〇年に『くらやみ砂絵』という題で刊行され、ともに日本推理作家協会賞の候補となっている。前者のシリーズは少し遅れて一九七二年に『キリオン・スレイの生活と推理』と題した作品集としてまとまり、一九七四年に上梓された二冊目の『情事公開同盟』(のちに『キリオン・スレイの復活と死』と改題)が日本推理作家協会賞の候補となった。

岡本綺堂が基本形を形造り久生十蘭によって受け継がれてきた謎解き小説としての捕物帳の伝統を現代に復活させた〈なめくじ長屋捕物さわぎ〉は長く書き続けられ(最終作は一九九九年発表)、著者を代表するシリーズとなった。現代なら人々が怪奇現象だとは思わないような不可思議な現象や奇妙な謎、要するに不可能犯罪も、江戸時代であれば素直に受け取られるという考え方を背景とする作品――死者が天狗に操られて人を殺した挙句、逃走して死体となって発見されるという「天狗起し」や庭の巨石によって寝たきりの老人が座敷で圧し潰されるという「小梅富士」などは、都筑流の謎解きミステリとして高い完成度を示している。
『くらやみ砂絵』が上梓されたのと同じ年に、『ミステリマガジン』で長編エッセイ「黄色い部屋はいかに改装されたか?」の連載が始まった。日本の本格推理小説に多く見られた特徴であるトリックのためのトリック小説を否定し、なぜそのような状況が生まれたのかという必然性に着目して、論理的に思考することで意外性を導き出すという論理のアクロバットを重視する、トリックよりもロジックを、という姿勢を明確にしたエッセイで、連載の最終回では、論理的に思考するキャラクターとして名探偵の復活を提唱している。連載から五年後にようやく単行本化され、日本推理作家協会賞・評論その他の部門の候補作ともなった本エッセイは、後進に大きな影響を及ぼし、綾辻行人の登場によって始まった〈新本格〉ムーヴメントを起こす起爆剤としての役割を果たした。

「黄色い部屋はいかに改装されたか?」における本格推理小説論の実作編が、長編では「謎と論理のエンタテインメント」と添え書きされた『七十五羽の烏』、短編では安楽椅子探偵ものの〈退職刑事〉シリーズである。前者は、『吸血鬼飼育法』(一九六八。旧題『一匹狼』)に登場したトラブルシューター片岡直次郎が、親が金持ちなので働きたくないという怠け者の青年・物部太郎のために、心霊現象が絡む事件を担当するサイキック・ディテクティヴの事務所を開設するという設定。後者は、引退した刑事(父)が現役刑事(息子)から担当している事件の話を聞いて謎を解き明かすというのが毎回のパターンである。物部太郎シリーズは第二作『最長不倒距離』(一九七三)、第三作『朱漆の壁に血がしたたる』(一九七七)を出して、中断したが、退職刑事シリーズは単行本で六冊分(一九七五~九六)がまとめられるほどの長寿シリーズとなった。
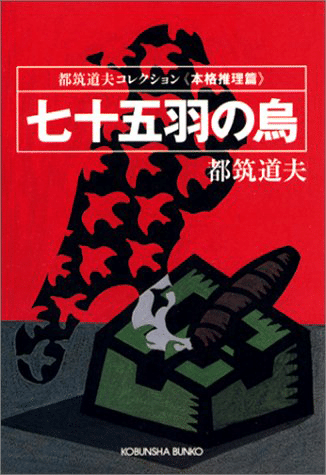

以後、都筑道夫は様々なジャンルへと手を広げていき、多彩なキャラクターを創造した。それらについてはジャンル別に見ていくことにしよう。
●オカルト探偵/ゴースト・ハンターもの
物部太郎シリーズのように合理的に解決するのではなく、怪異現象を怪異現象のまま扱うゴースト・ハンターあるいはサイキック・ディテクティヴものとしては、『雪崩連太郎幻視行』(一九七七)『怨霊紀行』(一九七八。のちに『雪崩連太郎怨霊行』と改題)二冊と、『にぎやかな悪霊たち』(一九七七)一冊がある。前者は、フリーのルポライターを主人公とするシリアスさを基調としたシリーズ。それに対して後者は、似非オカルト評論家をサポートする雑誌記者とその助手を探偵役に据えた、ユーモアに主軸を置いたシリーズだ。他に、念仏の弥八という岡っ引きが稲生外記と霊感を持つ盲目の美女お涙の助けを得て怪事件に対処するという時代捕物スタイルで書かれた連作長編『幽鬼伝』(一九八五)がまとめられている。
●怪奇小説・怪談
怪異現象の謎を解く探偵役が登場しない怪奇小説として、長編に『怪奇小説という題名の怪奇小説』(一九七五)『血のスープ』(一九八八)がある。前者は、道尾秀介が小説家を目指すきっかけになった作品で、都筑道夫の初期長編を思わせるような、メタフィクショナルな構成を持っているが、後半は伝奇的な展開を見せて、不思議な余韻を残す。後者は、ハワイでドラキュラを思わせる存在に籠絡された主人公が、日本に帰国してから操られて生贄を見繕うことになるという物語で、怪しの存在からのメッセージが脳内で再現される場面にはタイポグラフィックな面白さがあるあたり、都筑らしい。
短編は、作者自身も怪談が好きだというだけあって、ショートショートも含めて膨大な数の作品を残している。一九七六年に刊行された『都筑道夫自選傑作短篇集』には「はだか川心中」「ハルピュイア」「風見鶏」「人形の家」「かくれんぼ」「古い映画館」が選ばれており、光文社文庫版『都筑道夫コレクション〈怪談篇〉』には右の六編に、「風見鶏」の原型となるショートショート「夜の声」を加え、その他に「夢見術」「骸骨」が選ばれているから、以上の九編(八編)がとりあえずの代表作といえようか。
●SF/ヒロイック・ファンタジー
長編ヒロイック・ファンタジー『翔び去りしものの伝説』(一九七九)のほか、シリーズものとして『未来警察殺人課』(一九七九、八六)シリーズ全二冊と『銀河盗賊ビリイ・アレグロ』(一九八一)全一冊、ノン・シリーズものを集めた『宇宙大密室』(一九七四)がまとめられている。
雑誌『SFアドベンチャー』に連載された連作長編『暗殺心〈アサッシン〉』(一九八三)は、「あとがき」によれば、日本人作家なのにカタカナ名前のキャラクターを登場させることに違和感を覚えて、「アメリカの作家が東洋ふうの舞台を設定し、日本の忍者を主人公に想定して、ヒロイック・ファンタジイを書いたら、こうもあろうか、という姿勢」で書いたもの。初期長編の『なめくじに聞いてみろ』を連想させるだけでなく、刺客の名前に得意技を隠しておくというミステリ趣向も相俟って、都筑道夫らしい遊び心に溢れた秀作に仕上がっている。

●伝奇小説・時代小説
都筑道夫の第一著書は『魔界風雲録』と題した長編時代伝奇小説で、同作品で時代小説の執筆にピリオドを打つというつもりで書いたものだったことは、経歴でも書いたとおりだが、〈なめくじ長屋捕物さわぎ〉で、捕物帳という形ではあれ、時代小説を再び書くようになってからは、長編では『神州魔法陣』(一九七八)『神変武甲伝奇』(一九八四)が出ており、短編集として『変幻黄金鬼』(一九八二)『女泣川ものがたり』(一九八五。のちに『べらぼう村正』と改題)『風流べらぼう剣』(一九八八)の三冊がまとめられている。後二者は『神変武甲伝奇』で脇役として登場した剣客・左文字小弥太が主役を務める連作短編集。時代小説としては他に、単独で一冊にはまとまっていないが、為永春水を探偵役とした〈春色なぞ暦〉シリーズや、旗本の次男坊で剣の使い手でもある戯作者を主人公とする〈善亭武升なぞ解き控〉シリーズがある。後者は「甲賀の忍びの裔」である娘が加わって、新たな展開を見せ始めたところで中断したのが惜しい。日本推理作家協会賞・短編部門の候補となった「西郷星」(一九八九)は、E・S・モースが探偵役を務め、ダイイング・メッセージの謎を解くこともあって、キリオン・スレイの明治版という印象がなくもない。
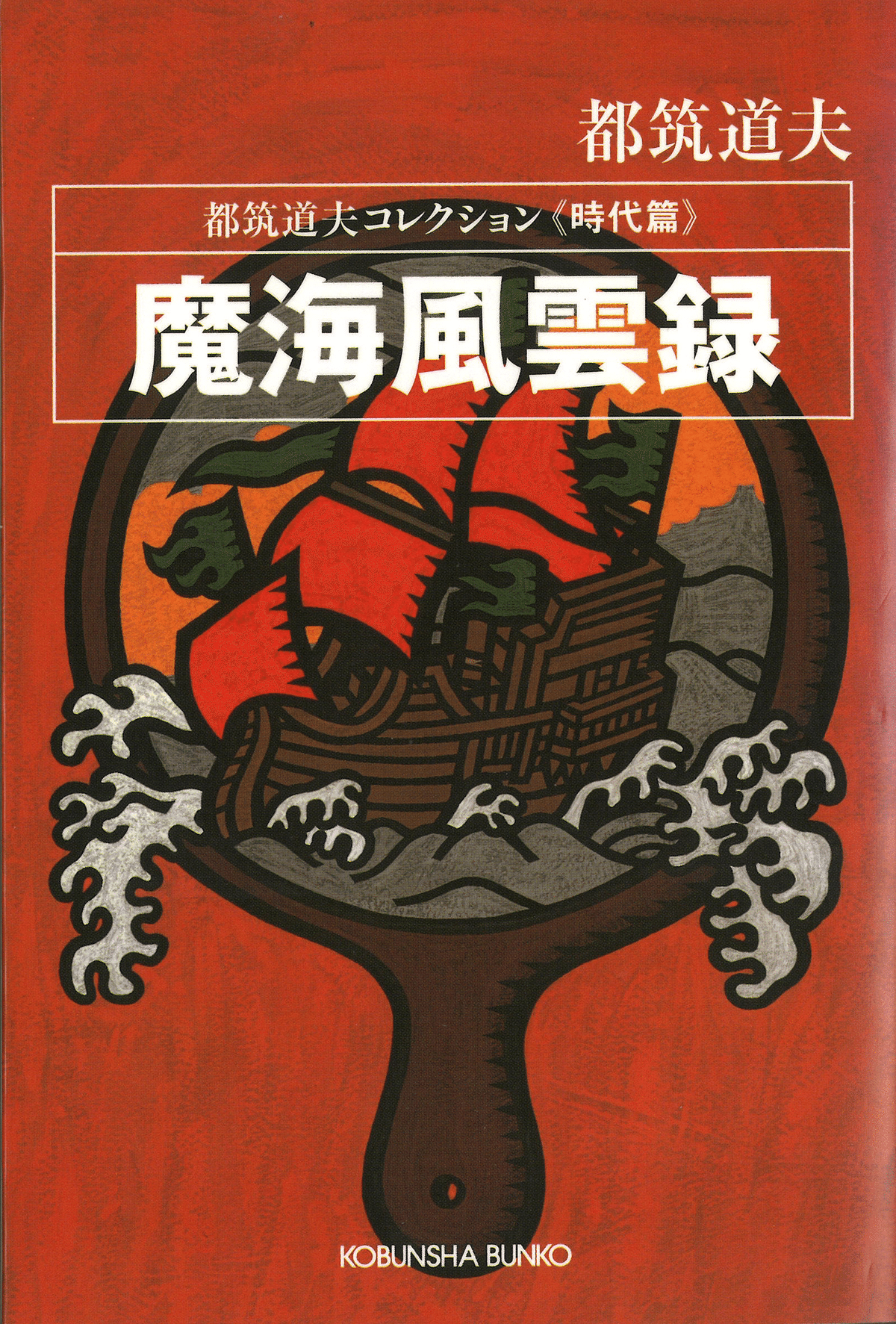
●パロディ・パスティーシュ
都筑道夫が惚れ込んだ作家の一人に久生十蘭がいる。三一書房版『久生十蘭全集』では、第四巻「顎十郎捕物帳」(一九七〇)の校訂を担当し、理想的な形での普及に与ったほどだ。その顎十郎を、十蘭の遺族から承認を得て復活させたパスティーシュのシリーズが『新 顎十郎捕物帳』全二冊(一九八四、八五)である。ジャンルとしては時代小説に入れるべきかもしれないが、〈なめくじ長屋捕物さわぎ〉にも通ずる性格を持つ、本格味の強いシリーズでもあり、あえて別扱いとした。
パスティーシュならぬパロディ時代小説に、『捕物帳もどき』(一九八二。旧題『捕物帖もどき』)『チャンバラもどき』(一九八四)の二冊があるが、これらは現代を舞台とした『名探偵もどき』(一九八〇)と合わせて、パロディ三部作とみなすべきだろう。いずれも当該ジャンルの小説や物語、評判記を読み過ぎた主人公が、そのジャンルの主人公になりきって事件の解決にあたるという趣向の物語。霧舎巧の『新本格もどき』は都筑の本シリーズにインスパイアされたものだ。
〈もどき〉シリーズの前身としては、いつも同じ酒場で腰を据えていながら前歴がはっきりせず、アルジェリアの外人部隊にいる番場の忠太郎というイメージから、ついたあだ名がアルジェの忠太郎という男を謎解き役に据えて、毎回披露される過去の経歴を活かして事件を解決していく作品集『妄想名探偵』(一九七九)がある。ただしこちらは現代物。
●ハードボイルド
都筑道夫といえば本格推理小説が代名詞のようになっているが、作家生活の中盤から後期に力を入れたのはハードボイルドだった。そもそも都筑が最初に発表した評論が「彼らは殴りあうだけではない」(一九五六)というハードボイルド本質論であり、翻訳家として活躍していた時期にカート・キャノンの贋作を物しているから、当該ジャンルとの付き合いは長い。ボクサー崩れの私立探偵・西連寺剛シリーズの第一作「逃げた風船」は一九七七年に発表され、翌年に第一作品集『くわえ煙草で死にたい』が刊行された。その後、十年にわたって五冊の作品集が上梓された。西連寺シリーズと並行して書き始められたのが、妻子を失って酒に溺れていた元刑事・久米五郎が活躍するシリーズだが、作品集は『ハングオーバーTOKYO』(一九七九。のち『二日酔い広場』と改題)一冊にとどまった。もう一人、浅草に新築された高層ホテルの夜間警備責任者で元刑事の田辺素直を主人公とするシリーズがあって、『殺人現場へ二十八歩』(一九八六)『毎日が13日の金曜日』(一九八七。のちに『毎日が十三日の金曜日』と改題)と作品集が二冊刊行された後、長編『ホテル・ディック 探偵は眠らない』(一九九一)が書かれた。
この他に通俗ハードボイルド路線の探偵でアルコール・ポパイの異名を持つ仁礼達也の活躍する短編三話を収めた『殺されたい人この指とまれ』(一九八二)、邪神の呪いを受けて死なない身体を持つことになった名無しの殺し屋「おれ」を主人公とした連作『闇を食う男』(一九八五)などがある。後者は、「連続殺人者を主人公にしながら、読者が感情移入できるようなシリーズを、書こう」として「スーパーナチュラルな味つけをすることになっ」たと、『都筑道夫名探偵全集』全二巻(一九九七)がまとめられた際に書き下ろした「あとがき」で述べているが、内容自体はアメリカ作家が物する殺し屋ものの系譜にあるという位置づけも可能なので、ハードボイルドに加えた次第。『都筑道夫名探偵全集』でも第二巻「ハードボイルド篇」に収録されている。
都筑道夫は、これまで述べてきた以外にも、いくつかシリーズ・キャラクターを創造している。タロット・カード(都筑作品ではタロウ・カード)探偵・鍬形修二が活躍するシリーズ『西洋骨牌探偵術』(一九七五)と、マンション警備員の娘を語り手に宇能鴻一郎風の文体で書いた滝沢紅子シリーズ『全戸冷暖房バス死体つき』(一九七八)が、それぞれ一冊。当初はトルコ嬢、のちに泡姫と呼称されるようになるソープランド嬢探偵シルビアのシリーズは『トルコ嬢シルビアの華麗な推理』(一九八四。のちに『泡姫シルビアの華麗な推理』と改題)、『泡姫シルビアの探偵あそび』(一九八六。のちに『ベッド・ディテクティヴ』と改題)の二冊にまとめられた。このうち、鍬形修二の活躍は五短編にとどまったが、滝沢紅子シリーズは短編集一冊にとどまらず、十年後に文庫書き下ろし長編『髑髏島殺人事件』(一九八七)で再登場し、同作品を含む長編四作で活躍することとなった。短編版では猿紘一が真の探偵として謎解き役を果たしていたが、長編版では猿の存在は排除されてしまった。

これらの他、もちろんノン・シリーズの短編集も多く、単行本化されているジュブナイル・ミステリやドラマ用の脚本も含めると、とても一人の作家が成し遂げたとは思われないほどで、受賞を機に編まれた光文社文庫版〈都筑道夫コレクション〉全十巻でも、その一端に触れられるに過ぎない。
最後に、都筑の創作姿勢が奈辺にあったのかということを述べて、本稿の締めとすることにしたい。
これまでにも紹介してきたように、都筑道夫は多様なキャラクターを創造してきたわけだが、なぜこれほどまでに名探偵が増えることになったのか。為永春水を探偵役にした〈春色なぞ暦〉シリーズを始めることになったきっかけを、都筑は〈なめくじ長屋捕物さわぎ〉を連載中「心理的な密室トリックを思いついたことから、誕生した」と書いている。「そのトリックは、砂絵のセンセーに解決させるには相応しくなかったので、男女の恋愛心理を江戸末期に書いた作家、為永春水を探偵役にすることを思いついて」書いたのだという(「私の推理小説作法」)。
ちなみに『ハングオーバーTOKYO』の「あとがき」でも「おなじハードボイルドといっても、西連寺剛と久米五郎とでは、あつかう事件も、あつかう姿勢も、違っている」と述べられている。
これらの発言を踏まえるなら、都筑は事件の性格によって探偵役を使い分けていることになる。砂絵のセンセーであれば、男女の機微が絡んだ事件も解決できそうな気はするが、マメゾーやユータといった非人たちを駆使して情報を収集し、いっけん不可能・不可解に見える出来事を合理的に解釈するという趣向を凝らした世界と、男女の恋愛心理をベースとする趣向を凝らした世界とは、世界が異なるということなのだろう。ロジック自体は合理機械的に働かせば済むものなので、人情の機微なども合理機械的に解釈して処理することができないわけでもないだろうが、それでは作品世界を統括する論理が乱れてしまう。つまり新しい趣向(トリック)が活きてこないのである。都筑が感じ考えていたのはそういうことではないか。
こうした感じ方考え方の背景には、歌舞伎における「世界」という考え方が胚胎しているように思われる。「世界」とは、江戸時代に至るまでの間に人々に愛され、語り継がれてきた物語群のことで、狂言作者はそれら物語群を人々が知っていることを前提として、新たな「趣向」を組み込むことで新しい台本を作ってきた。都筑が本格推理小説を書こうとしていた時期、本格ものを評価するには本格ものの歴史を知らなければならない、という趣旨のことをしばしば述べたのは、歌舞伎の「世界」と「趣向」という考え方を前提にすれば、腑に落ちる。そして初期長編を書いていた頃も、一般的に書かれる定型を外した変わった作品を書いていたのは、ミステリの伝統を前提として、そのパターンを知り尽くした読者に対して、新しい趣向を提示して見せていたのであり、そう考えると、都筑の創作姿勢は一貫して変わらなかったことが見えてくる。「私の推理小説作法」の最後で、自分のことを「伝統の形式を重んじる保守主義者」だと規定しているのは、右のような補助線を引くと理解できるのであり、決して型を破っていたわけではないことが理解される。したがって「超本格」とか「超アクション」とか評されることは、あるいは前衛とか、アヴァンギャルドだとかいわれることは、都筑にとっては心外であったかもしれない、と考えてみる必要がある。
「気になる言葉」(一九七二)というエッセイの中で都筑は、「作者も読者も、非常に不自由な形式のなかで自由にふるまう魅力にとらわれて、本格推理小説を書いたり、読んだりする」のだと述べている。これは決まった形式のなかで、論理のアクロバットによって意外な解決を提示してみせることを述べているわけだが、「不自由な形式」を歌舞伎でいうところの「世界」に、「自由にふるまう」ことを「趣向」を凝らすことに置き換えてみれば、都筑の言葉が意味するところは明らかではないだろうか。その言葉こそ、都筑が企図するパズラーのみならず、都筑の全作品に通底する要諦なのである。
《ジャーロ No.90 2023 SEPTEMBER 掲載》
■ ■ ■
★ジャーロ編集部noteが、光文社 文芸編集部noteにアップデート!
ミステリーはもちろん、読書の楽しみが深まる記事を配信いたします。
お気軽にフォローしてみてください!
この記事が参加している募集
いただいたサポートは、新しい記事作りのために使用させていただきます!
