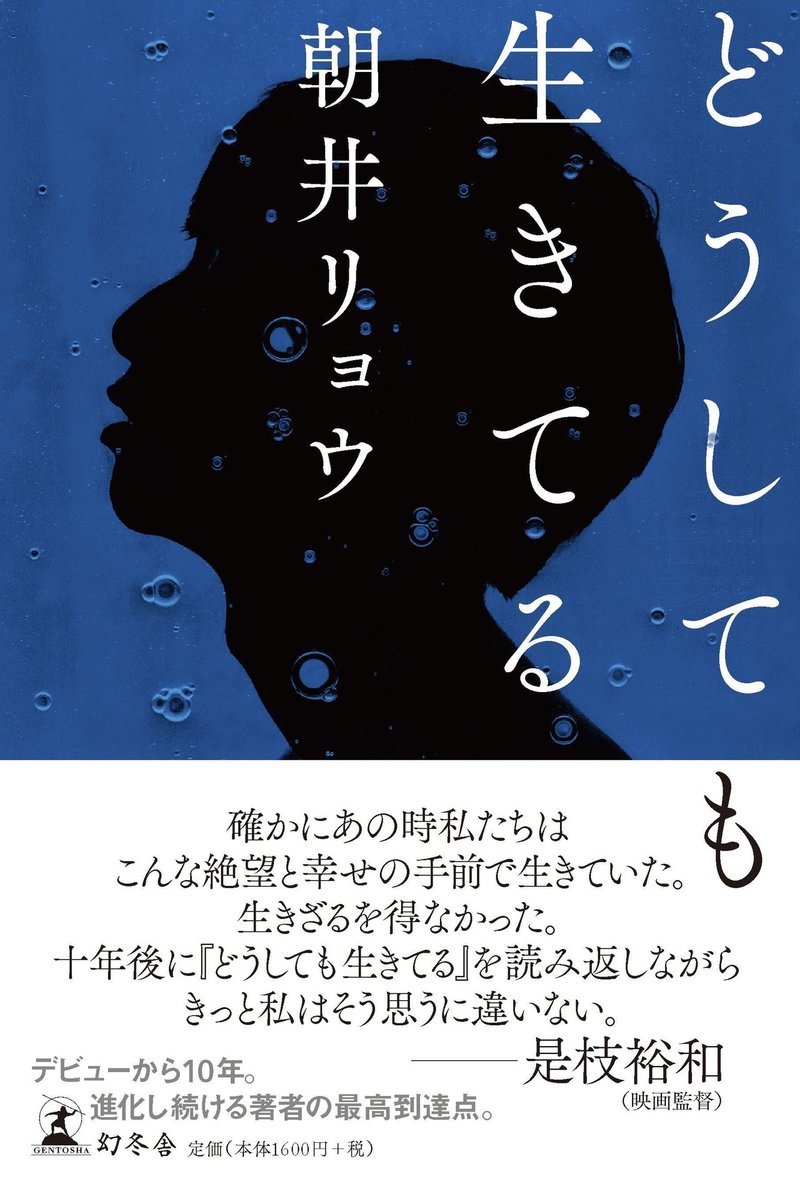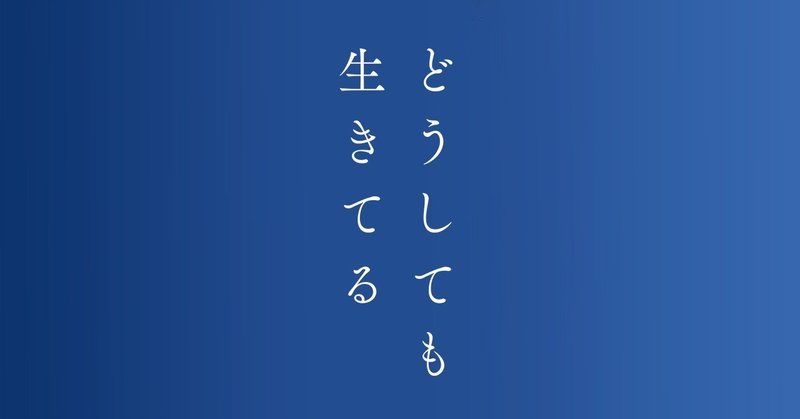
どうしても生きてる|七分二十四秒めへ 2|朝井リョウ
自動車教習の学校に通っていたころ、教官と折り合いが悪く、卒業試験で不合格を言い渡されたことがある。そのときは、町を歩きながら、目に映る人間を自動的に二つのグループに分けていた。
あの人は車を運転しているから免許を持っている、あの人は学生服姿だからきっと免許を持っていない。そんな基準で人を振り分けたことはそれまでなかったので、自分の中の変化に、依里子は当時とても驚いた。
「あの、谷沢さん」
声のするほうに振り返ると、明日美がいた。
「お昼、ご一緒していいですか」
そう言う明日美は、あしたから一人になる人間の顔をしていた。
依里子は立ち止まり、ポケットの中にある携帯電話を一度、強く握る。
観たい。十二時を過ぎたから、新しい動画がアップされているはずだ。
「……最後だし、一緒に食べようか」
依里子が絞り出した声に、明日美はほっとしたように破顔する。「ありがとうございます」明日美が依里子の隣に並ぶ。
四階建てのビルから吐き出された人間たちが、それぞれ食べたいもの目がけて散っていく。何歳くらいか、男か女か、顔が良いか悪いか──若いころはそんなふうに、人間の集団を見分けていた。免許を持っているかどうかで人を振り分けていた時期も、次の試験に合格をしてしまえば、終わりを迎えた。
派遣社員、契約社員、正社員、アルバイト──その人がどんな雇用形態を結んでいるのか。そんな基準で人を振り分けるようになって、もう何年経つだろう。
「すごい匂い」
明日美が、顔の前でぱたぱたと掌を振った。
「男の人って、昼でもラーメンとか気軽に食べられていいですよね」
ラーメンまんぷく堂には連日、多くの男性客が列を作っている。この地域にはラーメン屋が少なく、開店してからその人気は持続している。
「女が一人でこういうところに並んでたら、どうせ色々言われるんですよ。女らしくないとか彼氏できなそうとか。ほんと、生きづらい世の中ですよね」
依里子は、ポケットの中の携帯を握りしめる。「そうだね」と返しながら、早く彼らに会いたい、と思う。
◆
佳恵の最終出勤日は、同じ部署の正社員の女性が出産を機に退職する日と重なっていた。
部署の人たちは、正社員の女性のために送別会を企画した。湯葉が好きなその人のために、会社からアクセスのいいところにある、生湯葉のしゃぶしゃぶがおいしい店を探し出し、ずいぶん前に予約していた。その日はみんな、長時間の残業をしなくていいよう、午前中からいつもより真面目に業務に取り組んでいた。
依里子はその日、久しぶりにお酒を飲み、久しぶりに他人が作った夕食を食べた。洗い物のことを考えずに小さな皿をたくさん使えることが快感で、新しい料理が運ばれてくるたび自分の取り皿をきれいなものと交換した。普段は会話をする機会のない人とも、少し、言葉を交わした。自分も生湯葉のしゃぶしゃぶを食べてみたかったけれど、鍋がある場所からは遠かったので、諦めた。
長いテーブルの端、向かいには、佳恵が座っていた。牛肉を使ったお寿司や鮪まぐろカマトロの生姜煮などはテーブルの真ん中に集まっており、依里子と佳恵の間には余った唐揚げやフライドポテトが流れ着いていた。
佳恵は芋焼酎のお湯割りを飲んでいた。依里子はその日初めて、佳恵が酒に強いことを知った。
「油ものばっかりですね」
私たちの目の前、と話すと、佳恵は少し赤くなった顔で依里子の名を呼んだ。
「谷沢さん」
そして、いつも通りの柔らかい声で、言った。
「がんばってね」
依里子は、突風に吹かれたように、一瞬、泣きそうになった。だけど我慢して、これまでの感謝を伝えた。明日から一人になることへの不安は、かろうじて口の中に閉じ込めた。
会も終盤になると、生湯葉のしゃぶしゃぶの真ん前に座っていた女性社員に、花束と子ども用の靴下がプレゼントされた。他の女性社員でセレクトしたらしい。そして最後に、「みんなから」と、寄せ書きが渡された。みんなで書いたというカラフルな色紙を、依里子と佳恵はそのとき初めて見た。
退職する女性の夫は、同じ会社の別の部署に勤めている。同じ会社内で出会い、二人で稼いだお金で同居し、二人で子どもを作り、女だけが仕事を辞める。
会計を済ませ、店を出ると、もう二十三時近かった。依里子は、二次会の会場へ移動する集団から佳恵がさり気なく離れていく姿を見つけた。
どこに行くんだろう。
気づけば依里子は、佳恵を追っていた。二人でどこかで飲み直しませんか──そう声をかけようかと思ったが、佳恵が自分にさえ何も言わずに集団を離れたということは、と、思いとどまった。そして単純に、一次会で発生した四千円の出費が痛かった。
数メートル先を、佳恵が一人で歩いている。いつもと変わらないカーキのチノパンが、太ももとふくらはぎにびったり貼り付くように張っている。依里子は、明日から、あの後ろ姿はどこへ向かうのだろうと思った。佳恵の契約が更新されないことを知らされてから、その次にどこへ行くのかという話はしていない。できない。
佳恵が、駅とは逆方向へと歩いていく。佳恵を通り過ぎ、依里子を通り過ぎていく人たちのほとんどは、明日も同じところを同じように歩く。そのことをつまらないと嘆きながら。目を瞑って歩けるような毎日があることを当然だと思い、それが物足りないなんて愚痴りながら。
佳恵は、一人で、ラーメン屋に入った。
ラーメンまんぷく堂。店の外壁に貼り付けられている文字を一つずつ追いながら、依里子は不思議に思った。お酒のあとはラーメンが食べたくなるとは聞いたことがあるけれど、佳恵はもう脂っこいものなんて食べられないと言っていたはずだ。さっきだって唐揚げにもフライドポテトにも手をつけていなかった、なのにこんな深夜にどうして──店の外でそんなことを考えていると、若い店員に食券を渡した佳恵が、道路に面したカウンター席に座った。
ガラス窓一枚を隔てて立っている依里子に、佳恵は全く気づかない。化粧っけのない両目は俯(うつむ)いており、両耳からはイヤフォンの白いコードが垂れている。手元に置いた携帯電話で何かの動画を観ているのだ。
佳恵と食事と携帯電話。依里子は、その三点が揃った光景を、これまで何度も見たことがあった。
着任初日に定食をごちそうになって以来、昼食はそれぞれ個別に摂っていたが、たまに、入ろうとした店に先客として佳恵がいることがあった。
佳恵はいつも、十二時になった途端会社を飛び出し、少し離れたところにある店に一人で入る。そして、イヤフォンを両耳に装着し、携帯電話の画面を見ながらご飯を食べているのだ。そんな佳恵の姿を見つけたとき、依里子は声をかけず、その店から立ち去ることにしていた。あまりにも幸せそうな表情をしているので、邪魔をしては悪いと思ったのだ。
ガラス窓越しに、大きなどんぶりが届く。
佳恵は割り箸を取り出すと、動きを止めた。どうしたのだろうと思っていると、ある瞬間にいきなり、どんぶりに勢いよく箸を突っ込んだ。その湯気の量からどんぶりの中身はかなり熱いとわかるが、佳恵はまるで数日ぶりの食事であるかのように、様々な具材をぽんぽんと口の中に放り込んでいく。
依里子はしばらく、店の外に立ったまま、その光景を眺めていた。明日もこの道を歩くだろう人たちが、依里子の背後を通り過ぎていく。依里子はなぜか、佳恵がくれた左利き用のハサミのことを思い出していた。その左手に握る割り箸で、佳恵が卵を丸ごと口に押し込んでいる。
この人は今、何の動画を観ているんだろう。
昼食時に見かける佳恵は、待ち受けにもなっている飼い猫の動画でも観ているのか、いつもとても幸せそうだった。会社用のアドレスが使えなくなれば、佳恵とは連絡が取れなくなる。いつも嬉しそうに何の動画を観ていたのか、知ることができるチャンスは今しかない。
ラーメンが冷めてきたのか、湯気が途絶えてきた。佳恵の表情が、はっきりと見えるようになる。
あ。依里子は唇の間で糸を引く唾の冷たさに触れて、自分が思わず口を開けたことを知った。
泣いてる。
依里子は、店の中に入った。入り口に置いてある券売機を無視して、店内すべてに背を向けている佳恵に少しずつ近づいていく。ボリュームがなくなり始めている頭髪、個性と体形を隠すことに徹底している服装。
やがて依里子は、乱視に対応してくれる眼鏡のレンズを経て、丸い背中の向こう側に置いてある携帯電話の画面には猫なんて映っていないことを確認した。もう一歩、近づく。半分以上残っているラーメンに、もう手をつけなくなっているその人に、もう一歩だけ、近づく。
* * *