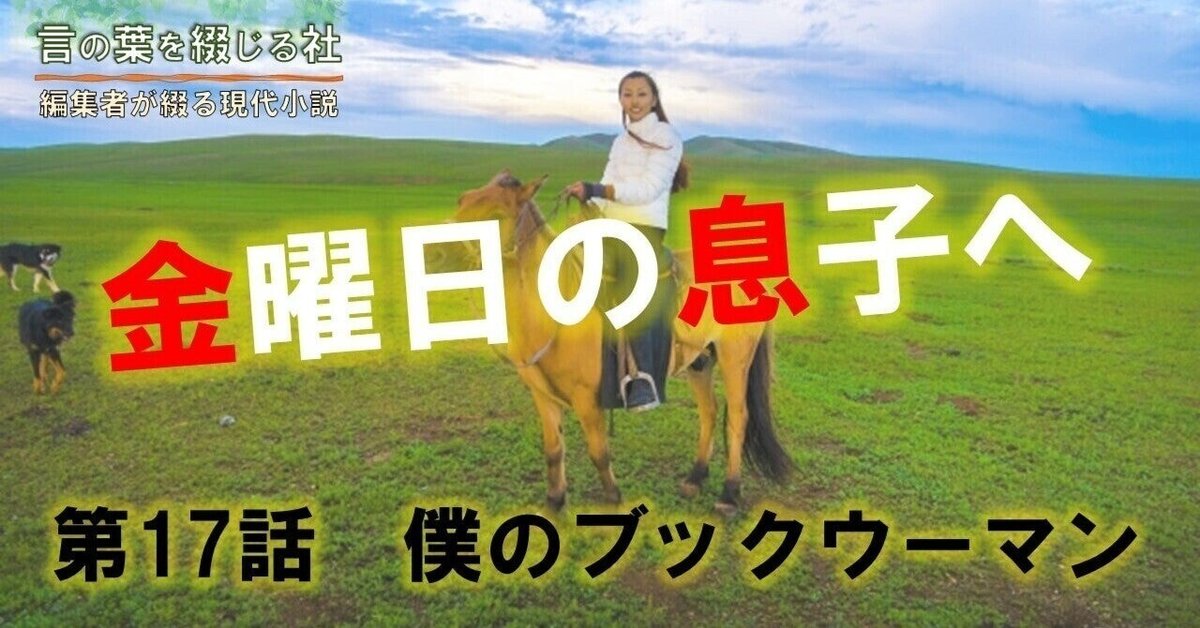
【現代小説】金曜日の息子へ|第一七話 僕のブック・ウーマン
前回の記事はコチラ
その日の深夜、俺は北米のケンタッキー州東部にあるアパラチア山脈のなかで、人里離れた山のずっと高いところに住む一家の読み書きできない少年が主人公の絵本を読んだ。
少年には時間があればいつでも本を読んでいるような本好きな妹がいるんだ。ある日、山の少年の家にアメリカ西部劇に出てくるガンマンのようないで立ちで馬の背中に大きな革のバッグを馬に乗せた女の人がやってくる。
しかし、その女性が持っていたのは銃ではなかった。一日がかりで山の上まであがってきたその女性が携えてきたのは、バックいっぱいに詰め込んだ本だったのだ。
舞台は1930年代のアメリカということで、ルーズベルトが大統領だった時代だ。経済状態は最悪の状態だったろう。そんな大恐慌のさなかに大統領になったルーズベルト大統領は雇用促進事業計画の一環として「荷馬図書館員(パック・ホース・ライブラリアン)」プロジェクトを開始した。
少年の家にバッグいっぱいの本を携えてやってきた女性は、馬に乗って家々に本を配ってまわるパック・ホース・ライブラリアンだったのだ。
当時はアメリカでも女性が働く場所は家のなかでという考えがまだ一般的だった時代に自ら進んでパック・ホース・ライブラリアンの仕事に就いたのは女性たちだったのだ。
ルーズベルト大統領は、1929年のアメリカで起きた大恐慌は、一大悲惨事というだけでなく、「一つの時代の終わり」という象徴的な出来事だった。
そこで政府は困窮のなかにあえぐ国民のため義務と責任をまっとうするがごとく、まったく新しい職業をつくったのだ。
その義務と責任のあらわれの一つとして実行されたのが図書館予算の削減などでなく、パック・ホース・ライブラリー・プロジェクトだったのだ。
このプロジェクトは、歩いていけるような場所に学校がなくて図書館もないような遠隔地に本を届けることを目的として、ブック・ウーマンとよばれるようになった人たちによって支えられていた。
そんな職業があったことを俺はこの本を読んで初めて知ったのだ。報酬はわずかでも、 ブック・ウーマンたちはとても忍耐づよく、その仕事に誇りをもっていた。
少年が暮らすアパラチア山脈に、やがて長く深い雪に閉ざされる冬がやってくる。本を山の上に暮らす少年の家にたっぷりと置いていったブック・ウーマンが、次に馬にまたがって姿を現したのは春だった。
冬のあいだ妹に教わって少年が覚えたのは本を読む喜びだったのだ。君は想像できるかい? 現代は多様性に溢れて選択肢の多い時代だ。本を読む以外にもテレビやゲームなど限られた時間を取り合いをしているのだ。
そんな中で本が唯一の娯楽だとしたら一冊の重みが違うだろうな。
そんなブック・ウーマンは冬の間に成長した少年に言うのだ。「わたしのために本を読んで」と。少年が声にだして読むのを聴いて、ブック・ウーマンは顔いっぱいに笑みを浮かべるんだ。
なんということだろうか。貧しくとも幸せにあふれた日常生活を思い浮かべられる。いまは手を伸ばせば何でも手に入る時代だけど、何にも手にしていないと感じる時代だと思わないか。
本当に貧しいのはどちらなんだろうか。
この時に読んだアパラチア山脈のイメージは、その後、長く俺の中に留まった。降り積もった雪とホワイトアウトする吹雪、その中でポツンと耐え忍ぶ少年が暮らす小さなロッジ。
日本で生まれ育った俺にとって、これほどの孤独を感じるにふさわしい光景はなかったのだ。にもかかわらず、俺はある種憧れにも似た気持ちを抱いたのだ。
そしてただの思いつきに違いないのだけれど、俺はジュリアと一緒にアパラチア山脈のその村へ行ってみたいと思ったのだ。訪ねても実在はしないであろう小さなロッジを探しに行きたいと思ったのだ。
旅の道中、好きな本の話や音楽とか映画、どんなことでもいいから彼女の話を聞いて、その上で彼女が俺の身の上に起きている不条理で退屈な打ち明け話にも耳を傾けてくれたらどんなにいいか。そんなことを妄想していたのだ。
その年の夏、ジュリアにこの絵本の話をすると、彼女も同じ絵本を読んだと言ってくれた。そして、自分はスペインのマドリードから北東197キロの地点にあるモリナ・デ・アラゴンの生まれだと教えてくれた。
彼女が生まれた地域は「スペインのシベリア」といわれているそうなのだ。
「私は雪を見るたびに生まれた街を思い出す」
と、彼女は言った。
この記事が参加している募集
よろしければサポートお願いします! いただいたサポートはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます!
