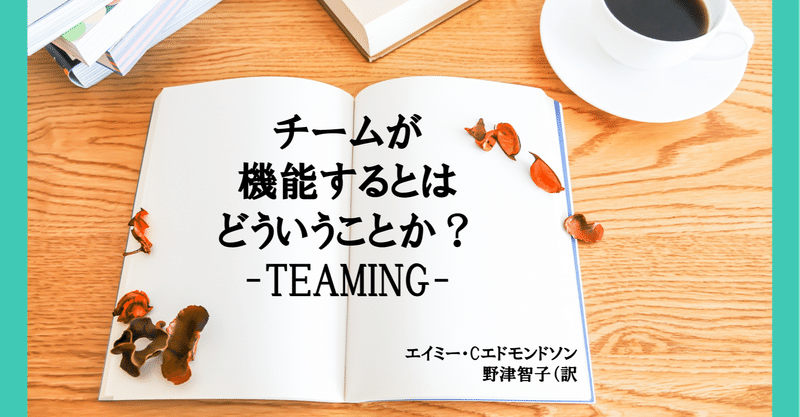
チームを導く、新たなフェーズへ。事例から学ぶ、プロセス知識の本質とは?
おはようございます!
11月の体感気温ということもあり、この冬初のダウンを使用した今日この頃です。
さて、今日も読書メモの回です。
「チームが機能するとはどういうことか-TEAMING- (著:エイミー・C・エドモンドソン/訳:野津智子)」
前回は、自社の立ち位置からのリードの仕方を観てまいりました。リーダーとして必要な条件も立ち並ぶ中、自身の振り返りを行ういい機会でした。
今回からは、これまで出てきたキーワードである、学習ーイノベーションとチーミングがどのような関係性を構築するのかを学びましょう。
―――――――――――――
とある‟病院”の事例から観る
―――――――――――――
医師からの指示により、CTスキャンを取り、病状含む確定のための補助を行うのはよくあることです。そして、この作業にタイムラグがあるのも、よくあることではあります。
ですが、患者視点に立ち、このタイムラグをどう感じるのか…そして、それが緊急性の高い時にも起きてしまったら…
これらの作業は、別個の作業でありながら、共同作業を行うチームであることが必要とされています。
‟チーム”としての認識が低いと、誰も悪くなく、各々が自分の仕事を「こなした」のにもかかわらず、不手際が発生し、患者、ご家族の負担が多くなっていくという現象が起こり易くなります。
そもそもの‟チーム”としての定義が、職種や専門科であれば、この単位での必要性と効率性を追求し、管理を行うことになり、大きな流れの一部である認識は薄れるでしょう。
失敗する可能性や複雑な業務を「こなしていく」には、重要な考えである一方、創意工夫をする、判断する、知的な試みを行う、立ち直るなどのスキルを発揮する機会はなくなります。
共同作業を行う‟チーム”としての価値は、無いに等しくなるのです。
――――――――――――
チーミングの本質から学ぶ
――――――――――――
チーミングは、気付き、コミュニケーション、信頼、協力、積極的な省察が基礎となります。そのプロセスは、本質的に学習プロセスとなります。
話合い
↓
決定
↓
行動
↓
省察
このサイクルを回し続けることにより、前回のサイクルからの性質を引き継ぎつつ、新たな集合知を形成していくのです。
そのためには、大きく2つのことが必要となります。
① 認識する:相互依存の仕事であることを認める
② 省察とフィードバック:貢献を認め、変化を提案する
様々な意見を取りまとめ、コミュニケーションを図ることを促進することから、一番重要なのは、意見の衝突を管理することです。
つまり、学ぶこと=教えることに関連する対人能力の向上にこそ、一番の問題を孕んでいるとも言えます。
次回は、様々なリサーチから導き出された対人能力の問題解決に必要な4つの行動を観ていきましょう。
病院の事例は、努めたことがある人間、そして、患者体験のある人間であれば、良く分かることかもしれません。「あるある」で終わらせているようでは、進歩がなく、早急なTry&Errorを繰り返すことが重要な視点であるのかもしれません。
今日も学んだー!!
ではでは、今日もワクワクするような最高の笑顔で、いってらっしゃい!!
アクティホーム
講内 源太
今年もやります!!お申し込み、お待ちしています!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
