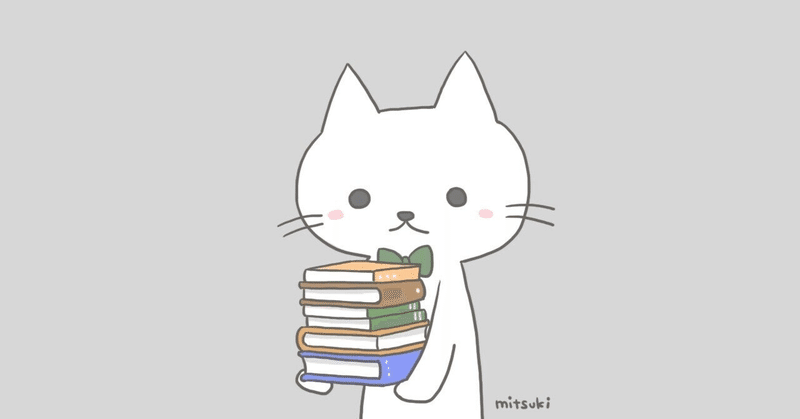
ミツイパブリッシングという出版社が好きだ! 〜新刊『デンマーク式 生涯学習社会の仕組み』の紹介〜
遊びは悟りの境地で
もうだいぶ昔の話になるが、幼稚園のいわゆる体験入園に、子どもと一緒に参加したことがある。体験入園とはいってもほとんどが自由時間で園庭や教室を好きに使わせてもらえたので、砂場遊びが大好きだった我が子は、お山を盛ったり型抜きでカニさんやイカさんを作ったりに没頭していた。パパもやれと言うので、僕もそこらへんに転がっていたコップに砂を詰め、「ほい!」とひっくり返して砂の塔?などを建ててみる。すると我が子はニヤリと悪く笑い、塔を壊す。もちろん、私はまた「ほい!」と建てる。やはり、子が壊す……という、何というか、ギリシャ神話のシーシュポスみたいな無為な作業を繰り返していた。
「パパさん、遊ぶの上手なんですね」
僕たち父子の様子を見ていたらしいどこかの子の母親が、声をかけてきたのだった。あまり元気のある声ではなかった……というより、とても寂しげな口調だったことをはっきり覚えている。その母親のお子さんも、我が子の近くで砂場遊びに興じていたが、母親の方は、何をするでもなく、ただその姿をうつろな目で眺めているだけだった。
「私、子どもとの遊び方がわからなくって」
ポツリとつぶやくように言った。
何だか胸が苦しくなった。
「あ、子どもの真似すればいいんですよ。同じことすれば」
「同じこと……なんかコツとかあります?」
「無心。悟りの境地で。『私、何してんだろ……?』とか考えたら負けです」
母親は、あははと笑ってからすっくと立ち上がり、お子さんの隣にしゃがみ込んだ。そして、僕のアドバイス通り、自分の子の真似をしながらお砂のケーキを作りはじめた。彼女の「楽しいかも」という言葉は、たぶん、演技ではなかったと思う。
『デンマーク式 生涯学習社会の仕組み』
こんな話を思い出したのは、2022年10月にミツイパブリッシングから刊行された『デンマーク式 生涯学習社会の仕組み』に所収されている、和気尚美「デンマークの公共図書館プログラム」を読み、こんな一節に出会ったからだ。
「ベビー・カフェ」の主な目的は、これから子育てし始める、あるいは、育児を始めて間もない親が、安心してスタートを切れるよう必要な情報を提供し、人的ネットワークの形成を支援することにある。

僕はろくな人間ではないし、たくさんの人々を傷つけてきたけれど、ただ、あの時、あの砂場でのやりとりに関しては、今ふりかえっても、良いことができたと思う。あの珍妙なアドバイス?で母親が救われた、とまでは言わないが、きっと、ほんの少しくらいは、彼女の気持ちを軽くすることができたはずだ。
いかに幼稚園の敷地内で子連れとはいえ、僕の見た目は、「この人なら声をかけても大丈夫」と思ってもらえるようなものではない。当時は確か、モヒカン気味の坊主頭だった。ヒゲも生やしていた。若い母親が、自分から声をかけようと思えるような風体ではない。決して。
それを、彼女は話しかけてきた。きっと本当につらかったのだと思う。
ままならぬ子育て。おそらくは、初めての。
その苦しみを和らげることができるのは、やはりまずは、誰かに語り、あるいは自分に向けて語られる、言葉なのだ。だから、「育児を始めて間もない親が、安心してスタートを切れるよう必要な情報を提供し、人的ネットワークの形成を支援する」ような場というのは、子育ての支援において、本当に本当に大切なことなのだ。
デンマークでは、その役割を、公共図書館が担っているという。図書館が作り出す人と人との繋がり、あるいは、オルタナティブな共同体。そして、未来の世代。本好きとしては、なんとも心の躍る話である。
和気の紹介によれば、デンマークでの公共図書館のプログラムには、他にも「手工芸カフェ」「無料法律相談」「看護師と語る」「図書館での進路選択ガイダンス」「哲学カフェ」「郷土史デジタルアーカイブに書き込もう」等々、多種多様なものがあるという。
とりわけ「これはすごい……!」と驚き、感動したのが、デンマークの公共図書館が、難民や難民申請中の人々への支援を積極的に担ってきたという事実である。なかでも「アウトリーチ」、すなわち、
施設入所者、低所得者、非識字者、民族的少数者など、これまでの図書館サービスが及ばなかった人々に対して、サービスを広げていく活動
としての「出張市民サービス」には、目を見張らされた。その担当者である図書館員の言葉が、胸に刺さる。
「難民を対象とする場合、図書館で待っているだけでは、本当に支援を必要としている人にサービスを届けることは難しいのです」
さらに、難民として認定されるのを待っている難民認定前の人々を対象とした、「編み物カフェ」なるプログラムの素晴らしさには、本を読みながら、思わす「おお!」と声を上げてしまった。
図書館内の一角に集まり、他の参加者と会話しながら、図書館が所蔵する編み物のテキストを参考に編み物を楽しむというもので、デンマークの公共図書館でよく見られる長年人気のプログラムである。
どうだろうか。本というものが作り出す、国境や言語や民族や宗教を超えた、人と人との繋がり、あるいはコミュニティの創出。大袈裟ではなく、胸が熱くなる。そう感じられた方も、多いのではないだろうか。
ミツイパブリッシング
本書『デンマーク式 生涯学習社会の仕組み』には、上に紹介した和気尚美の論考以外にも、
坂口緑「デンマークの学校教育 回り道や寄り道を可能にする制度」
佐藤裕紀「すべての若者の移行支援と多層的な学びの場」
原田亜紀子「若者に影響力を ユースカウンシルで学ぶ政治教育」
原義彦「デンマークの成人教育制度」
が所収されている。いずれでも、学びや学校教育、そして生涯学習などに興味関心を持つ人にとっては、示唆に富む事例や実践などが多く報告されている。そしてこのような素敵な本を出版するのが、ミツイパブリッシングという出版社である。
北海道旭川市を拠点とする小さな出版社ミツイパブリッシング。「小さな声をカタチにします」をモットーに、編集者中野葉子とイラストレーター三井ヤスシの夫婦で地道に本を作っています。想いを込めた素敵な本を、北の大地からお届けします。
僕がこの出版社を知ったのは、森達也『フェイクニュースがあふれる世界に生きる君たちへ』という一冊がきっかけだった。

本書は元々他の出版社から『世界を信じるためのメソッド』というタイトルで刊行されていたのだが、生徒に薦めようと思って調べたら、既に新品は市場に出回っていない状況だった。とても良い本だったので残念で残念で仕方なかったのだが、とある方から、ミツイパブリッシングという出版社から増補改定された新版が刊行されていると聞いたのだ。それがこの、『フェイクニュースがあふれる世界に生きる君たちへ』である。本書の存在を知ったときの嬉しさと言ったら……!
さらに、ミツイパブリッシングは、同じ森達也の『ぼくらの時代の罪と罰』を刊行する。こちらも元は他の出版社から出されていたものの増補新版のようだが、元の方は、僕は未読だ。だが、あの『世界を信じるためのメソッド』を復刊してくれた出版社、そして同じ森達也の本、これは間違いないと思い、見つけて即購入する。やはり、間違いなかった。死刑というものについて議論や対話、熟考の場を開くための、正真正銘の名著である。小学生高学年から読めるし、無論、私たち大人が読んでも、十分すぎるほどの学びがある。むしろ、死刑制度の存在に馴れ、しかもそれを日常から不可視化してきた私たち大人こそが、読まねばいけない一冊と言えるかもしれない。

他にも、塾予備校という受験産業にどっぷり浸かってきた僕には耳の痛いところも多々あったが、内田樹/寺脇研/前川喜平『教育鼎談 子どもたちの未来のために』も、大いに考えさせられた一冊である。

まだ未読ではあるけれども他に気になっているタイトルに、
三井ヤスシ『福音ソフトボール 山梨ダルクの回復期』
安積遊歩/安積宇宙『多様性のレッスン 車いすに乗るピアカウンセラー母娘が答える47のQ&A』
ソフィア・ヤンベリ著/轡田いずみ訳『僕が小さなプライド・パレード 北欧スウェーデンのLGBT+』
わかな『わかな十五歳 中学生の瞳に映った3.11』
等々がある。良質な本をこつこつと刊行する、こうした出版社の存在が、一人の親として、市民として、あるいは出版文化の末席を汚す者として、どれほどに心強いか。
北海道は旭川の出版社、ミツイパブリッシング。
私のイチオシです。
皆さん、要チェックですぞ……!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
