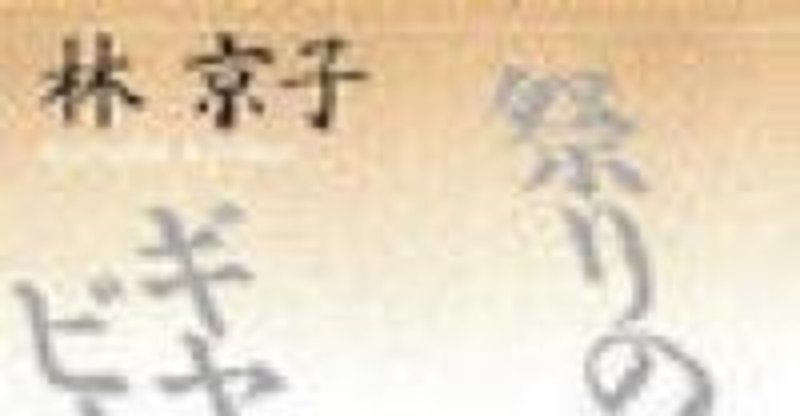
林京子『祭りの場・ギヤマン ビードロ』 (講談社文芸文庫)を読んで
林京子という作家がいます。
はやし‐きょうこ〔‐キヤウこ〕【林京子】
[1930〜2017]小説家。長崎の生まれ。本姓、宮崎。長崎での被爆体験に基づく「祭りの場」で芥川賞受賞。他に「上海」「三界の家」「やすらかに今はねむり給え」「長い時間をかけた人間の経験」など。
〜「デジタル大辞泉」より〜
文学の書き手にとって、書く出来事を実際に体験しているか否かは、あまり重要でないと考えられることもあります。なるほど、体験を第一義的なコードにしてしまうと、歴史やファンタジーの創作などナンセンスであるということになってしまいます。それに、文学者の文学者たる所以の一つは想像力。実際に経験しておらずとも、断片的な情報からあたかも実体験であるかのように描写する、というのは、それこそ作家の腕の見せどころと言えるでしょう。例えば太宰治は、師匠の井伏鱒二が火山の噴火について描写する際に太宰がちょっとだけ口にしたことをもとにリアルな叙述をつむいでいったとき、師の天才を感じた、というようなことを述べています。
けれども、ある種の作家や作品について、僕は、作家自身の経験というものが計り知れないほどに重きをなす、ということがあると考えています。その「ある種の」というのは、端的に言えば、戦争をモチーフとする、という意味です。今回紹介する林京子『祭りの場・ギヤマン ビードロ』(講談社文芸文庫)に所収される、芥川賞受賞作「祭りの場」から、いくつかの叙述を引用してみましょう。
広場で出陣の踊りを踊っていた学徒らは即死、火傷の重傷者は一、二時間生きた。爆圧でコンクリートに叩きつけられて腸が出た学徒がいた。若者だけにうめき声がすさまじかった。逃げる途中声を聞いた友人は、今でも話すとき両手で耳をおおう。
〜「祭りの場」より〜
原爆は即死が一番いい。なまじ一、二日生きのびたために苦しまぎれに自分の肉を引きちぎった工員がいた。
〜「祭りの場」より〜
一〇日朝浦上に入った稲富らは死体収容にあたった。白骨化した遺体は焼け跡にそのまま置き、黒こげ死体と全裸の火傷死体は焼跡に並べた。頭を中央にして車座に置く。探しにくる家族がすぐ見つけられる合理的な並べ方だ。一つ一つ見つけてあるく必要がない。
〜「祭りの場」より〜
実際に原爆を経験したことのない人間に、このような文章をつむぐことができるでしょうか。
もちろん、これが出来事としての客観的な事実を描写したものだと言うつもりはありません。小説はあくまでフィクションであり、たとえ経験や取材に基づいたものであっても、そこには必ず脚色が入ります。
しかし、どうでしょうか。
たとえ事実そのままでなかったとしても、書き手の林京子が実際に原爆を経験していなかったなら、このようなリアリティ、迫真性を持つ文章を描くことは、はたしてできたでしょうか。
原爆の投下直後の風景や様子だけではありません。同じく『祭りの場・ギヤマン ビードロ』に所収の「二人の墓標」という作品には、若い女性の、原爆を経験しなかったら絶対に思い描くことのできないような心理について、詳細に述べられています。以下は、燃え盛る炎のなか、死体につまずき、あるいは死体を踏みながら、必死に逃げていく場面からの引用になります。
そのうち、多すぎる人間の死に、こわさを感じなくなった。肉の柔らかさにも慣れた。
肉の柔らかさ加減で、男か女か、若いか年をとっているか、つま先で判断できるようにもなった。
肉から骨までの弾みが相当に厚く皮がやわらかい、若い女、一六人目。男、年より。骨が固く、肉が薄い、九人目。無意識に指を折って数えながら走っていく。同情は感じない。
どれほどに想像力が豊かであろうとも、原爆投下後の世界を自らの五感を通して熟知する人間でなければ、このような描写をすることは、きっと不可能でしょう。したがって、僕は、『祭りの場・ギヤマン ビードロ』に収められたすべての小説、つまりはフィクションについて、そこに疑いようのないリアルを確信するのです。要するに、この作品集は、証言=テスティモニーとして読まなければいけない、と。仮に虚構が散りばめられていたとしても、それは、実際に、どこかで誰かの経験として、ありえたはずの虚構、つまりはリアルとしての虚構なのだ、と。
最後にもう一箇所、「祭りの場」から引用しておきます。
被爆地に雑草をみつけた日の感動を、私は忘れない。登校の道すがらである。浦上駅のコンクリートのホームの割れ目に、一本の草をみつけた。ひょろひょろ伸びた草は白い、ゴマ粒のような花をつけていた。
六〇年間草一本生えない、と噂された被爆地である。雑草の生命は私たち被爆者の生命につながる。
私も生きられるのだ、と涙があふれた。
〜「祭りの場」より〜
林京子は、すでに他界しています。けれども、僕たちは、この証言としての作品を通じて、「私」の「涙」を受け取っています。そんな僕たちには、その「涙」を、次の世代、次の次の世代へと手渡していく義務がある。そう、強く思います。
この地球に、あらゆる核兵器のない世界を、いつか、必ず。
林京子『祭りの場・ギヤマン ビードロ』 (講談社文芸文庫)
https://a.co/6M0WZmk
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
