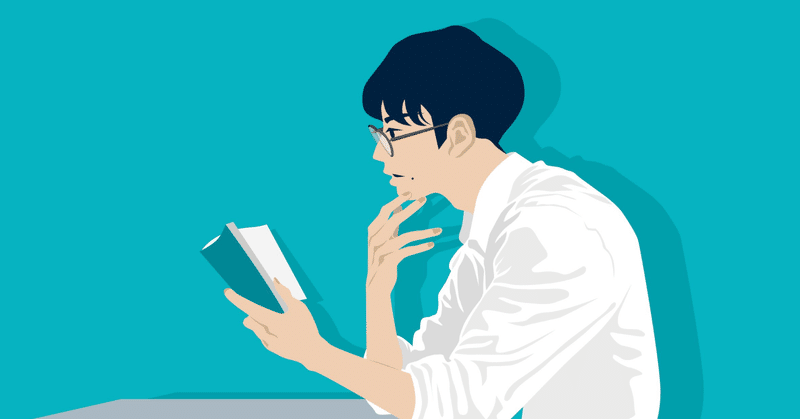
自分なりの文学の楽しみ方
先日、ふとしたきっかけで川端康成の『伊豆の踊子』を読み直した。
あらすじを確認したいだけだったのだが、改めて読んでみると、ところどころで見慣れない表現が目についた。
「峠の婆さんに煽り立てられた空想がぽきんと折れた」、「胸がほうと明るんだ」、「私は素早く寂しさを感じた」――。
恐らくどれも一般的な言い方ではないが、言葉はスッと入ってくる。
他にも、朝湯に入っていた主人公が、自分に向かって裸のまま無邪気に手を振る踊子を見つける有名なシーンでは、「ことこと笑った」、「朗らかな喜びでことことと笑い続けた」という描写がある。
これは初めて読んだ時から非常に印象的で、「ことこと」というのがどういう笑い方かは説明できないのだが、不思議とイメージは湧いてくる。
もちろんこのような言い方を会話や一般的な文章で使うと通じない、あるいは間違いだと指摘されるだろう。
だが、新しい言葉を自分の中に取り込んで言語感覚を養うことは、非常に大事ではないかと思う。
他人に伝える、伝わるかは別として、自分の感覚や感情を言語化する技術がが上がるからだ。
自分の感情や感覚をきれいに言語化できると気持ちがいい。
例えば、原因不明の体調不良に悩まされていた患者が、病院へ行ってはっきりと病名が診断されると、それがたとえ大病であっても今までの心のもやが晴れるような感じがして、かえって安心するといったケースをよく見聞きする。
これと似たような感じで、自分の喜怒哀楽のうち怒や哀といったネガティブな感情なら、それがどの程度なのか、どのような感覚なのか、何が原因なのかを自分なりに把握できると、ただ漠然と不安やイライラに悩まされるよりはるかに気持ちが落ち着く。
また、喜や楽といったポジティブな感情でも、同じように自分なりに明確に言語化できれば、単に嬉しい、楽しいというよりはるかに味わいが増す。
これはもしかしたら、あまり共感してもらえない感覚かもしれない。
だが、漠然と単純な言葉だけで処理するのは、私としては何だか落ち着かないのである。
そのせいか、文学を読んでいて印象に残るのは、感覚や心情の機微を見事に言語化していて、なおかつその言葉の選び方や使い方が自分のそれと共鳴するような作品が多い。
有名どころだと川端や三島や漱石なんかがそうだ。よくぞここまで言葉をあやつることができるものだと、いつも感動を覚える。
ストーリーや構成の巧みさよりも、そちらの方が印象に残るのだ。
私は定期的に文学に触れたくなるのだが、それは物語に感動や新鮮な体験を求めているのではなく、言葉では表現しきれない人間の感情や感覚を限界まで精密に言語化しようとする試みの極致を味わいたい、あるいは少しでもいいからそのレベルに近づきたいという願望の表れなのかもしれない。
残りの人生であとどれくらいたくさんの言葉に触れられるだろうか。
楽しみは尽きない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
