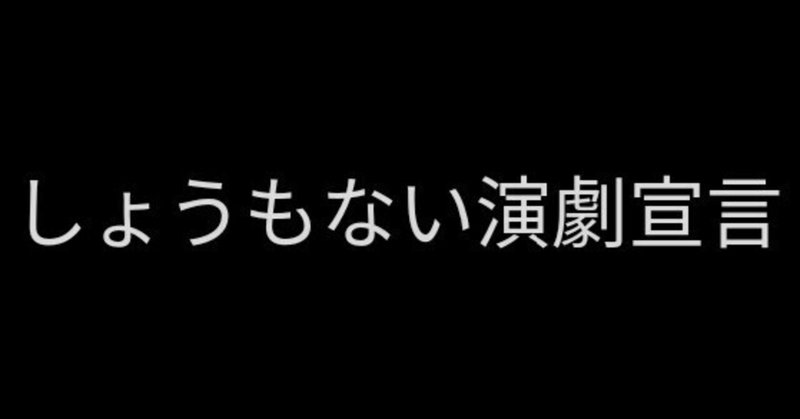
しょうもない演劇宣言(嘘の演劇ステートメント1)
※以下は、夜の知らない住宅街で私が拾った雑誌の切れ端に書かれていた演劇論です。演劇論の書かれたページのみが切り離され、ホッチキスで留められた状態で落ちていました。いや、落ちていたというのも実は違って、道の真ん中に不自然で小さな穴があり、そこに埋められていたというのが正確なところです。穴は浅くて、紙も地面の上に飛び出していたので簡単に取り出すことができました。私はふだん、落ちているものを拾うことはないのですが、あの時はなぜか拾ってしまいました。神のお告げのような出会いにもかかわらず、書かれていることは私になんの影響も及ぼしませんでした。読む前と後とで、私はなにも変化しませんでした。全く響かなかったのです。演劇をしていないのだから当然か。もしかしたら、演劇をしている人にとっては感じるところのある文章なのかもしれないので、試しにここに投稿してみることにしました。
「しょうもない演劇宣言」
ある演劇が、作者や劇を見る社会にとって切実であることは、その演劇がすばらしい作品であると評価される大きな要因になる。あるいは、必要条件とまで言っても差し支えないかもしれない。
切実なものは、現前する。現前性は、生身の身体をもって上演される演劇というメディアにとって、重要な性質である。現前を媒介に、演劇と切実とは固く結びついている。
現前を前提にされる演劇にとって、今この瞬間の社会と呼応する切実さは、嫌な言い方をしてしまえば、その出し物が演劇になるためのパスポートである。ある劇は、自らを通して演劇の中に、まだ気づかれていない切実さを入国させることができる。社会が社会の抱える問題に気がついてそれに社会問題として新たに取り組むのと同じだけ、演劇はその問題のパスポートを手に入れ、問題を入国させ、扱える内容を拡大することができる。この拡大により、無限地点においては社会と等号で結ばれることになるだろう。
常に現在の問題を持ち込んで悩み続けるのは、演劇のよい性質である。このことは、私たちを含めた演劇に携わる者ならば否定することはできない。遠い過去より現在まで、いかなる状況下においても演劇という面倒なメディアが滅びずに生きながらえているのは、その性質のおかげであることを感じているからだ。しかし——。しかし、である。切実さを取り込むほどに、私たちは社会の中で私たちがそうしているのと同じように、切実な状況を生み出してしまう社会に絶望してふさぎ込んでいってやしないだろうか? 私たちは、希望を現行社会の中の細い細い光の筋に見出すが、社会自体をぶん投げてしまえばもっと大きな光に包まれる可能性があることを忘れてしまってはいないだろうか? 実際の社会を瞬時に破壊することはできないが、社会に似ていると同時に嘘でもある演劇ならばそれが可能だということを、忘れてしまってはいないだろうか? 私たちは、持ち込んだ切実さを維持するために、それを生み出すよからぬ構造も捨てられなくなっていないだろうか?
切実なものは、現前する。現前は、あまりに「在る」ため、それを目の前にした時私たちは冷静な判断力を失う。切実なものははりぼてではありえないが、それが乗っかっている社会がはりぼてであることに私たちは気がつかない。我々は、グラスが積まれたテーブルのクロスを引き抜くように、切実さの乗っかったはりぼてを引き抜いて、ぶんぶん振り回しながら踊ってみよう。パニックになったふりをして、かつての地面を放り投げて、空中で笑い転げてみよう。それは私たちには、軽薄で虚無な、しょうもない行為にしか見えないかもしれない。しかし、切実さと同じ土俵に立つ私たちにはないものを、我々は手にするだろう——解放だ。
やめた! もういいや! 全部どうでもいい! ふおおおお! と叫ぶことで起こる解放感。これを我々は大切にすることにする。解放感は、爆発的なエネルギーである。爆発的なエネルギーは、切実さの衣服を剥ぎとって私たちの前に晒す。もちろんその時には、我々も全裸だ。なにもない更地で、引き入れた切実な心以外なにももたない我々は、新たに世界を創造する。かつて切実さが結びついていたはずの社会は既に焼き払われ、我々はそれがどんなだったかをすっかり忘れている。我々が新たに創る世界は今あるこの社会には似つかないものになるだろう。無限地点までいこうとも、社会と等号で結ばれることのない、次元を超越したニューフロンティアとなるのだ。一見大切なものを軽々と放り投げてしまうしょうもない演劇にこそ、その一連を可能にする起爆剤としての可能性が秘められているのだ。故に我々は、しょうもない演劇をここに宣言する。
しょうもない演劇を展開していこうにも、我々は、さっそく舞台も幕も客席も劇場も、すべてを失ってしまったかもしれない。それらは、一番はじめに我々が放り投げてしまったものだからだ。今、我々には漠然とした切実さだけが残されているが、それがどんな姿をしているのか輪郭を与えることができない。姿がわからなければ、パスポートを発行できず、この切実さを演劇に再び持ち込むことができない。
我々の前に広がるこの荒野は、まっさらな未来か、はたまた死後の無の世界か……。無限の荒野に放り出されたというのに、我々には元気が有り余っている。いったいこの巨大なエネルギーはどこから湧いてきているのだ? なにか大切なことを考えていた気がするのだが、どうにも思い出せない。思い出すべきか? この無限に思えるエネルギーはどこにぶつけたらいいんだ? 考えるべきか? いや! やめた! もういいや! 全部どうでもいい! ふおおおお!
気がつくと我々は、落下している。立っていた地面を引き抜いてしまったからだろう。突風が、我々の裸を激しくなでるように吹き上がっていく。この落下の解放的な気持ちよさを武器にすれば、私たちはいつか幸福を手に入れることができるのではないか! そう叫んではみたものの、大穴に滝のごとく落ちていく我々の声があなたに届くのか、わからない。わかるのは、穴の底にあなたが落ちてきたときだろう。一足先に我々が穴の底に着いたら、そこであなたに見てもらう演劇を作ってみようと思っている。どんな演劇になるだろうか。
劇団ナイアガラフォールズ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
