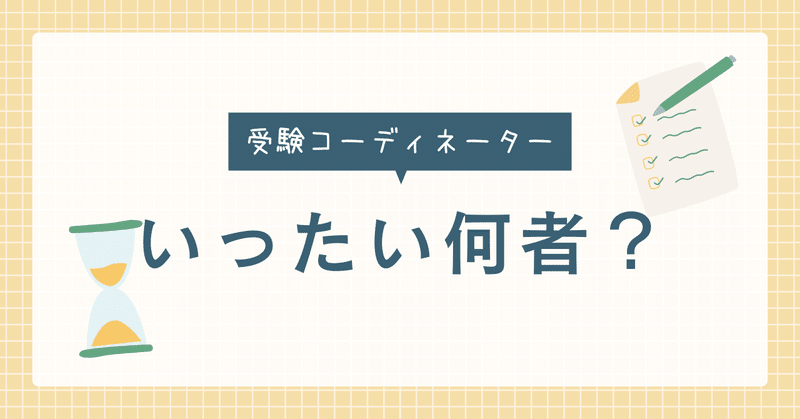
読書と計算で入試に挑むために
はじめに
19歳のころから、家庭教師をやり続け、学習意欲を失う生徒たちに、得点を取る気持ち良さを実感させながら受験に送り出すことを重ねています。
その経験から、いつ、何が必要なのかを自分なりに方向性を導きだし『受験コーディネーター』としてやってきたものを書いて行きたいと思います。
受験コーディネーターとは
不思議な肩書の説明が必要だと思います。37年前に知り合いの息子さんの学力補助を頼まれました。基礎学力が足りていなくて、その時点で、やっている教科書の単元は理解しにくいようだったので、少し戻って計算練習をしました。その回り道がちゃんと結果に結びつきました。
そこから、その生徒の保護者が、他の生徒の保護者に紹介いただいて、生徒が増えていくようになり、そのような紹介により家庭教師を続けてきました。
ただ教員免許を持っていない自分が『家庭教師』を名乗るのも憚れるので『受験コーディネーター』と名乗っております。
旅行でコーディネーターが計画をして案内をする印象があるので、受験までの勉強法はもちろん、この時期にこれをいつまでにやるとかの受験勉強のコーディネーターということで『受験コーディネーター』を名乗っています。
これを仕事とし、大手の家庭教師や塾と差別化するには、どうすれば良いのか?
生徒の学力を上げるには、自分にしか出来ないやり方があるのではないか?
そこで、徹底的に入試や定期テストの問題を解きまくりました。
途中10年ほど塾講師として、授業をしながら様々な試みを繰り返していました。
そして、小さな努力で大きな得点を取る方法の方向性が出来ました。
学校のワークを利用しながら、テストに出やすいものをテストで聞かれる形で、問題を解いていくことに慣れていく方法です。
定期テストでは聞かれるけど、入試では聞かれない部分や、入試では聞き方が違うものなどテストに合わせた授業をしていきました。
公立小学校中学校での現実
合わせて公立中学校の問題にも直面しました。
自治体によっての差が激しくなっていて、小さな町などでは学力が下がりがちになります。
学校の先生の異動システムがよって、一定期間で勤務する学校を異動しなくてはいけません。
その時に『異動願い』を書きますが、小さな自治体(中学校がひとつしか無いような自治体)では異動先は必ず他の自治体になります。
つまり自治体内で異動は出来ないわけです。
だから、優秀な先生もドンドン出ていってしまいます。そして、『希望異動先』にならないと、新人や他の自治体から放出された先生以外はほぼ来なくなります。
現在は、そこに先生不足も絡んでいます。もはや公立中学校での学力向上は、受験産業頼みとなっています。
勉強が得意な生徒だったのか
では筆者は勉強が出来たのかというところになります。
小学生の頃は、読書と友だちと遊ぶことに明け暮れていました。
読書は年間に800冊を越えた年もありました。とにかく片っ端から読みまくりました。本を読んだら、題名や作者、内容や感想を書きます。すると1冊に1枚シールが貰えて、それを教室の後ろの表に貼っていきます。そのシールを貼るのが気持ち良くて、さらに読書にのめり込みました。
下校すると、友だちと毎日遊んでいました。自転車で走り回ったり、球技をしたり、外で身体を使って遊んでいました。数字は元々好きでしたが、小学3年生のときに、算盤をならっていて計算の速かった友だちがいて、母に
「計算で友だちに負けたら、あなたも算盤を習えば?」と言われました。
今考えれば学校で計算の速さに負けても、母にはそれを知る手段は無かったのに、「負けたら算盤に行かなくてはならない」と思い込んでしまい、放課後は遊びたくて、それを邪魔する算盤に行きたくなかった自分は必死に計算能力を磨きました。
それが結果的に計算力を上げることになり、算数は苦手意識は全く持たずにすみました。
しかし、中学校へ進むとそれまでと同様でというわけにはいきませんでした。
毎日勉強しなければいけないところを、部活動で始めた野球に全力を注いでいました。そうです、全く勉強をしませんでしたので、成績はとんでもない状態でした。
細かく説明すると、国語は先生が隣の家の方で、授業はちゃんと聞いていましたし、小学生のころの読書が助けてくれて、平均点くらいはとれていました。
数学は前記した計算力はあったのと先生が、野球部のとなりのソフトボール部の監督だったので、大人しく授業を受けていまして、こちらも平均点はキープ、理科は担任の先生なので授業に集中、社会は全く聞いていませんでした。
さあ英語ですが、全くわかりませんでした。三学期のテストは12点、それも偶然記号が4つ当たっただけで、わかって答えたものはひとつもありませんでした。
そのまま2年生になり、1学期の三者面談で成績の酷さから、担任の先生からかなり酷いことを言われました。「なぜ、この人にここまで言われなければならない」となり、「だったら勉強くらいしてやるよ」と奮起しました。
ところが勉強をしていなかったので、何をしたら良いかわかりません。そこで考えました。『なぜ勉強するんだろう?』三者面談で言われた「高校へは行けません」が思い出されて『高校入試で合格すればよい』と考えて、高校入試問題をやりました。
もちろんほぼわかりません、それでも、そこにある6年分の問題を全部見ました。
そこであることに気付きました。6年間同じシステムで同じように問題が出来ていると。
だったら、『それに答えられるように覚えれば良いのではないか?』ということにたどり着きました。それには入試問題を解いていくのが良いはずだと、進研ゼミを始めました。
そこからは毎日勉強ばかりしていき、2年生の2学期にはクラスでも上位の成績が取れました。
今の自分から見れば、無駄な勉強をしていましたが、教えてくれる人が居なかったので、進研ゼミがあって良かったですね。勉強し続けることが大事ですからね。
ここから、『どうすれば得点をかせげるか』を究めて来ました。
長くなりましたので、次回につづきます。
最後までお読みいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
