
自己肯定感の高い社会を創りたい
いきなりですが、今回は掲題のテーマでnoteを綴ります。
<自己肯定感とは>
自己肯定感(じここうていかん)とは、自らの在り方を積極的に評価できる感情、自らの価値や存在意義を肯定できる感情などを意味する言葉であり、自尊心(英語: self-esteem)、自己存在感、自己効力感(英語: self-efficacy)、自尊感情などと類似概念であり同じ様な意味で用いられる言葉である。
~Wikipediaより引用~
とのことらしいです。
皆さんの自己肯定感はいかがですか?
そして、皆さんの周囲の方々の自己肯定感はいかがですか?
私の目には、自己肯定感が低い人がこの世の中には溢れかえっているように見えます。
ちなみに私は、自分が優れた人間とは微塵も思っていませんが、それでも自己肯定感は一定の水準以上だと思っています。
しかしながら私自身は、決して先天的に自己肯定感が高いわけではありません。これまでの様々な経験から自己肯定感を高めたほうが合理的に良いと考えるに至り、工夫と努力をコツコツ積み重ね、"後天的に自己肯定感を高めてきたタイプ"だと認識しています。
今回はそのコツを少しでも皆さんにお届けできれば嬉しいです。
まず、なぜ自己肯定感を高めたほうがいいのか。
それは自己肯定感が高いほうが日々幸せを感じながら生きれるからとかそういう話ではありません(最終的にはそういう話なのですが)。
一定の自己肯定感、もう少し分かりやすく別の表現にすると、一定の「自信」があったほうが、何事もうまくいくことが多いからです。
例えば皆さんも部活動とかで
「ふとしたミスが原因で、これまで出来たことも急に出来なくなる」
「ほんのわずかなきっかけで、色々なことがうまく出来るようになる」
こんな経験したことがありませんか?
私にはあります。急にパスが通らなくなったり、全然ゴールが決まらなくなったり、逆にどんなパスでも通るようになったり、難しいシュートもバンバン入るようになった経験が。
当然ですが、ある日を境に急激に能力が上がったり下がったりすることはありません。つまり「能力は変わっていないのにも関わらず、結果が大きく変わることがある」ということであり、その正体が今回言及している自信であり、自己肯定感だと私は考えています。
ちなみに日本は、先進国のなかでも「自己肯定感」が極めて低いというデータがあります。
内閣府の「令和元年版 子供・若者白書」によると、「自分自身に満足している」の調査項目で、自分自身に満足していないと回答した日本の子ども・若者の割合は55%で、諸外国の15%〜25%と比較してもダブルスコアを叩き出しています。

令和元年版 子供・若者白書
日本の若者意識の現状 ~国際比較からみえてくるもの~
https://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/r01honpen/pdf/b1_00toku1_01.pdf
これは日本古来の価値観とそこから形成された学校の教育政策、そして家庭内での教育が複雑に絡み合った結果であり、改善すべき喫緊的課題だとは思います。
とはいえ、当該課題を解決するには相当な時間と労力を要し即効性があるわけではないため、一旦今回のnoteでは割愛します。
前置きがだいぶ長くなってしまいましたが、自己肯定感を高めるために重要なことは以下の3つに集約されると私は考えています。
1、自信を持てる何かを持つこと
2、自信が醸成されるプロセスを経ていること
3、自分の哲学をもつこと
以下ではそれぞれに触れていきます。
1、自信を持てる何かを持つこと

自信を持てる何かを持っていることは「自己肯定感」という観点ではとても重要です。当然ですよね。
それは、見た目でも能力でも性格でも何でもいいと思います。もし何も思い浮かばないなら自信を持てる何かを今から創り出しましょう。
ただしその何かは「大多数の人が求めている何か」である必要はありません。
勿論マーケティング的なアプローチで「誰かが求めている何か」であってもそれはそれでいいと思います。
ただしそれは必要十分条件であり、絶対的に大切なのは「その何かをあなたが好きになれるか、誇れるか」ということだと思います。
尚、先程創り出すという言葉を用いましたが、新たな何かを創り出す必要すらないかもしれません。
あなたが今の自分には自信を持てるものがなにもない。そのように思ったのであれば、それは捉え方を変えれば解決出来る問題かもしれません。
自信を持てる何かは「大きな1つの何か」ではなく「小さな何かの掛け合わせ」でも全然良いのです。
小さな何かを掛け合わせていけば、自信が持てる何かを見つけ出せるかもしれません。
また自信を持てる何かを持つにあたって「他人と比較しない」ということも非常に大切です。
この世の中は広い。上には上がいます。比較してもキリがありません。
特定の分野で一番じゃないと自信をもってはいけないのか、勿論そんなことはありませんし、仮に特定の分野で一番の人と比較したとしても、そこに何らかを掛け合せればあなたのほうが優れているかもしれません。
そんなことに時間と精神を浪費するのは非常にもったいない。それよりもあなた自身が好きになれる何かを創り出す、見つけ出すことに集中しましょう。
2、自信が醸成されるプロセスを経ていること
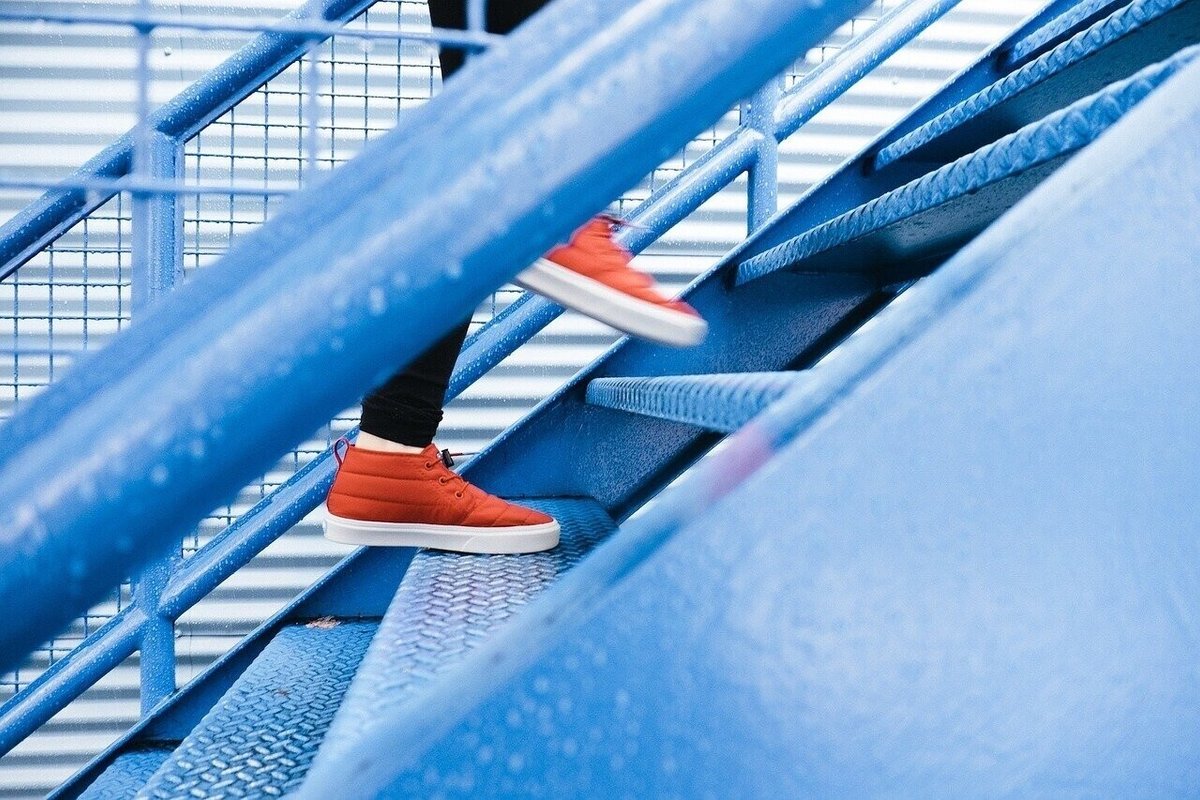
自己肯定感を持つためには、そのプロセスも非常に大切だと私は思います。
シンプルに言うと「何もせず頑張っていない自分を好きになれるか」ということです。
当然堕落してサボっている自分より、何かを頑張っている自分のほうが自身に肯定的になれますし、先天的にもったものよりも頑張ったことによって得たもののほうが誇らしい気持ちになれますよね。
しかしながら頑張り始めるのはともかく、頑張り続けることって非常に難しい。
元来人間は易きに流れる生き物。当然です。
そのため、頑張り続けたいのであればそのコツを理解し、実行することが大切だと思います。
これも色々な方法があるかと思いますが、「成功体験」が重要なキーワードになると私が考えています。
そしてそれにあたっては以下の2つが非常に大切です。
・適切な目標値を設定すること
・出来なかったことだけでなく、出来たことにも目を向けること
難攻不落の目標に燃える人もなかにはいますが、頑張っても頑張っても達成が見えないと、どこかで心折れる人のほうが当然多いです。
そのためいきなり高い目標を課すのではなく、まずは等身大+@程度の目標から始めて小さな成功体験を積み、徐々に徐々に高い目標を設定するようにしましょう。
いきなりフルマラソンを完走しようとするのではなく、1km→3km→5km→10km→20kmと成功体験を繰り返し、徐々に距離を伸ばすことが大切です。
また仮に途中で目標を達成出来ないときがあったとしても、出来なかったことだけでなく出来たことにも目を向けましょう。
10km走れずに8kmしか走れなかったとしても、目標に2km足らなかったではなく、8kmも走ることが出来た、前回から3kmも長く走ることが出来た。
そのように出来たことにも目を向けることが、頑張り続けるうえで凄く大切だと思います。
そうして頑張り続けていれば、自信を持てる何かを得ることが出来ると思いますし、その頑張り続けられている自分自身にも自信をもてるようになると思います。
3、自分の哲学を持つこと

最後は「自分の哲学を持つこと」です。
最後が一番抽象度が高く恐縮ですが、これが一番大切だと私は考えています。
誰しもが予測出来なかった天災の発生や、テクノロジーの革新により社会や経済の流動性が著しく高いこの現代において、何が正解かなんて誰にも分かりません。
そのような状況下においては、世の中で常識とされていることや他人の意見に惑わされて勝手に自身を不正解にするのではなく、自分の哲学、信念を持ち、自分で正解を決め、自分が決めたことを正解にすることが凄く大切だと思います。
そのためにも日々内省や自己分析を行ない、自分にとっては何が大切で何が大切ではないのか、振り返ることを心がけましょう。
そうすれば自ずとブレない確固たる自身の哲学が形成されるはずです。
以上、今回は「自己肯定感」をテーマに思うことをツラツラと綴らせていただきました。
誰かの何らか参考になったのであれば嬉しいです。
ちなみに最近はTwitterもアクティブに呟くようになったので、是非noteだけでなくこちらもフォローいただけると有り難いです。
https://twitter.com/fuuuuuujimon
最後に・・・
「みんなちがって、みんないい」
これはかの有名な金子みすゞさんが綴った詩の一部ですが、本当に本質的だと思います。100人いれば100通りの良さがそれぞれにはあり、みんな違ってみんな良いのです。(っていうか、多様性やダイバーシティなんて存在しなかった約100年前にこの作品が出来たって凄すぎません?)
「私と小鳥と鈴と」
作:金子みすゞ
私が両手をひろげても
お空はちっとも飛べないが
飛べる小鳥は私のやうに
地面を速くは走れない。
私がからだをゆすっても
きれいな音は出ないけど
あの鳴る鈴は私のやうに
たくさんな唄は知らないよ。
鈴と、小鳥と、それから私
みんなちがって、みんないい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
