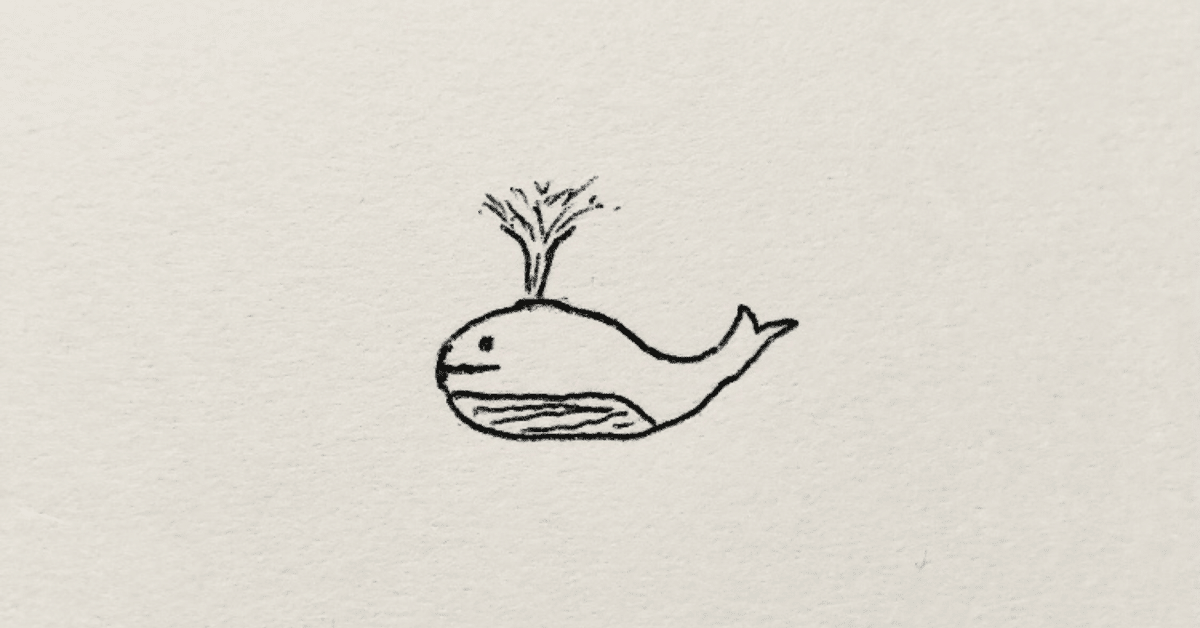
掌編小説(13)『辿り着くものたち』
自宅から逃げ出し、這う這うの体で近所の公園に駆け込んだ私は、蛸を模した巨大な滑り台にぽっかりとくり抜かれたトンネルの中に身を潜めた。
取るものもとりあえず家を出たので、靴は片方しか履いていない。街は不自然に静まりかえっていて、耳が痛いくらいだった。それに、昼過ぎだというのに、外の景色が薄衣越しに見る世界のように薄暗い。
少し離れたところにあるフェンスの向こう側では、そこらじゅうからあふれ出た怪異が我が物顔で道路を練り歩いていた。恐らくあれも、あたりの家々から現れたものなのだろう。
昨日から今日。今日から明日。
当たり前に繋がっていくはずの世界の撚り糸が、どこかでほつれてしまったようで、この日、命なきものに魂が宿り、命あるものの魂が、口溶けの良いラムネ菓子のようにきれいさっぱり消えてしまった。
私をひとり、置き去りにして。
自動車の背に乗った寸銅鍋が、なかなか閉まらない蓋に苦労しながらごとごと音を立てている。足といっしょにはみ出した、シミのついた白いエプロン。あれは近所のラーメン屋の主人のものに違いない。
私は蛸の足下から抜け出して、物陰を伝いながらこの行進についていくことにした。
「ふた月ほど前から地の脈が狂うとるのを感じとった。まっこと、粋なことをするもんじゃ。誰の取り計らいかは知らんがのう」
「かまやしないさ。こうもひっくり返ってしまっては、もう元には戻るまい。蝙蝠の命乞いさ。誰にも届きやしない。だあれにも」
せせら笑う声と、そぞろ歩く異形たち。みながそろって何かを口ずさんでいる。
もう明けぬ もう明けぬ
九十九の帳のその向こう
世も暮れぬ 世も暮れぬ
付喪の神の霧夜行
「ああ、これじゃあこれじゃあ。一度でいいからこれを弄うてみたかった」
アスファルトに転がった携帯端末を手に取ると、食器棚は中の茶碗どもと声を揃えてガチャガチャと歓声をあげた。操作方法など知る由もない彼らは、手に持った光る板を持て余して、ああでもないこうでもないと喚き立てる。
翅を広げた携帯端末が、握りしめる手を振りほどいてどこかに飛んでいく。食器棚が慌てたその拍子に、扉をすり抜けて外へと飛び出した皿が一枚、音を立てて割れた。それを見た茶碗の群れが「そら、あとに続け」とティーカップを囃し立てる。
不明瞭で不確かな光景の中で、地鳴りにも似た蠢きの立てる音だけが、人の世の終わりを確かに告げていた。それはまるで産声のようにも聞こえた。
背中に衝撃を感じて振り返ると、進路を妨害された衣装箪笥が、迷惑極まりないと抗議するかのようにシャツや肌着を撒き散らして、異形の列に加わっていった。
その列がさっとふたつに割れる。大きな影が薄暗い世界をより黒く塗り潰そうとこちらに迫り来る。
「掃かれて廃るも飽かれて哭くも、どれも終い。どれも終いよ」
公園にいた蛸が、お手玉をしながら目の前を通り過ぎていく。宙を舞う小さな体がみっつ。そのうちのひとつ。抜け殻となったかつての持ち主が、くるくるクルクル風を切る。
そうか、私は——。
ぽとりと落ちた運動靴を拾い上げる。ちょうど一足、一揃いしていたので、片方しかないビニール製の靴と交換することにした。膨らむようにして大きくなった私の足や体のせいで、これまで身につけていた装飾品はほとんどダメになってしまっていたから。
靴はなぜだか、私の足にぴったりだった。
諦めか、それとも安堵からか、私は深くため息をついた。
まあるい私の関節が、きりきりと悲しそうな音を立てて鳴いた。
赤黒く煤けた空の上では、汚れた月が嗤っていた。
***
このお話は、3月31日の『解放記念日(マルタ)』にちなんで、『解放』をテーマにして書きました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
