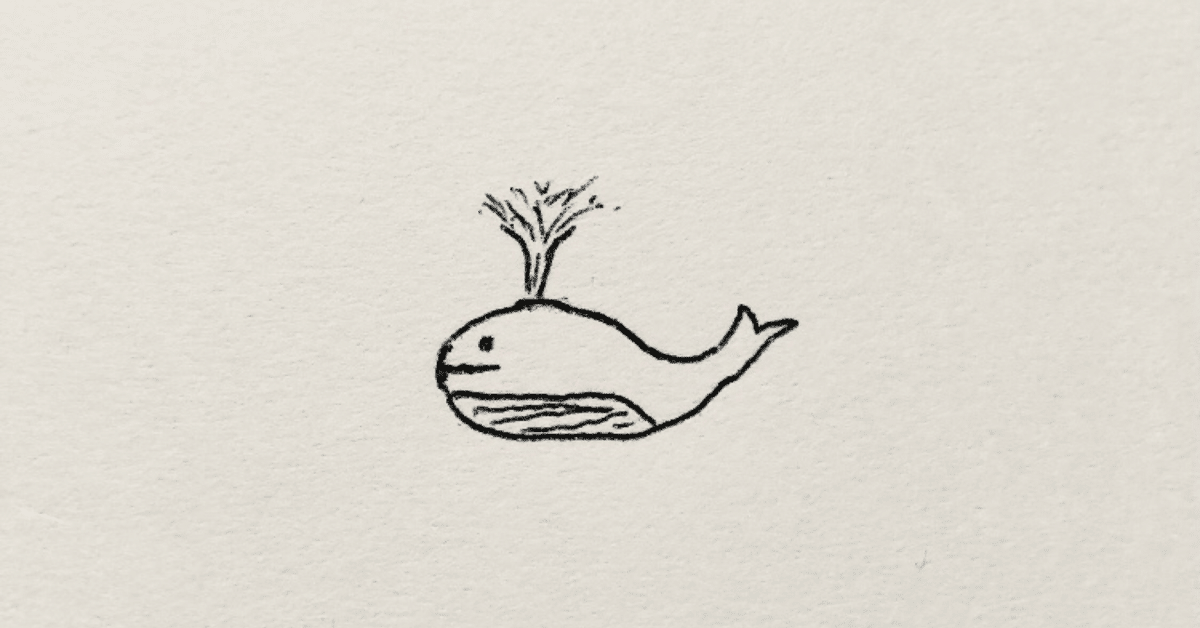
掌編小説(19)『風前の灯』
気持ちよく昼寝していた私を誰かが揺り起した。
夢の中でもちょうど誰かに呼び止められたところだったので、目が覚めたあと、現で私の肩をゆする呼び声の主が風の便りとわかるまで、少々の時間を有した。
「最近、妻の夢見が悪いようなんだ。見てやってくれないか」
澄み切った森の空気に似つかわしくない曇り顔をして、風の便りは私の手を引いた。
よほど気が急いているのか、風の便りは起き抜けの寝巻き姿のままだ。ズボンの裾は濡れ、枯れ葉や土で汚れている。洗濯する者の身にもなれよと嫌味を言おうとして、口をつぐんだ。彼の妻が一本の【夢渡しの木】となってひと月が経つ。
彼女はいま森の奥で、物言わず静かに佇んでいる。
「その洞を覗いてみてくれ。火花のようなものが見えるだろう?」
風の便りが急かすように私の背中を押して、ちょうど目線の高さにある洞を指さした。
私は彼の誘導するままに中を覗き込んだ。風の便りが言った通り、暗い洞の中に光が見える。
根のある下のほうから光の玉が飛び上がる。ひとつ、ふたつと、散発的に。やがて洞の中央あたりまで上昇した光源は、音も立てずに四方八方に分かれて散った。
「どうだ。やっぱり彼女は悪夢を見ているんだろう?」
「やっぱり?」
「いや——だってあんなものは見たことがない」
風の便りの言い方が少々気にかかったが、彼の言う通り、夢枕技師である私でもこのような物悲しい夢を見るのは初めてだった。こんなふうに、稀に夢の筋に陰りがさすこともある。そんなとき、夢見の調子を戻してやるのが私の仕事だった。
「ひとまず、今夜にでも詳しく見てみよう。直に君の細君と話すことができれば良いが」
「ああ、そうだな」
洞の中に視線を向けたまま、風の便りは力なく返事をかえした。
草木も虫も眠る頃、私は再び木のもとを訪れた。
足下を照らすカンテラの灯りを除いて、周囲は黒炭で塗りつぶしたような漆黒の闇に覆われている。
目を閉じて、木にそっと手のひらを当てる。名を呼び、両手を前方に押しやると、両開きのドアが開くようにして抵抗が弱まる。そうやって私は木の見る夢の中に入るのだ。
ゆっくりと瞼を開く。一瞬、元いた森の中に帰ってしまったかと思ったが、夢の中も外と変わらず夜のようで、目が慣れてくると、あたりの景色がじんわりと滲み出すように浮かび上がった。川原のようだ。
静かに流れる小川。そのほとりに一人の女を見つけた。風の便りの妻だ。いつだったか、こちらに迷い込んで帰り道を見失った彼女を、風の便りが妻として身請けしたと聞いた。
僧侶の着るような裾の長い着物。フードは無く、簡素なようにも見えるが、白い布のところどころに美しい紫の花の刺繍がほどこされている。現世の植物だろう。腰には幅の広い帯を巻いていて、背中側で器用に折り畳んでいる。
「お待ちしておりました」
「私の夢に現れたのはあなたですね?」
彼女は目を伏せ、頷いた。
「この川の向こうに渡りたいのです」
「この川を? どうして」
「こちらに迷い込んだあの日にも、川を渡ってきました。怖くなって、すぐに引き返そうとしたのです。あのひとは危ないと言って行かせてくれませんでしたが」
向こう岸に渡るには時を失い過ぎている。私がそう告げると、彼女は「そうですか」とだけ言って、あの光の球を川の中から掬い上げた。
彼女はそれを空に向かって静かに放り投げる。
「私の故郷では、お祭りでこれを打ち上げるんです。私はこれが大好きだったから」
音もなく、暗闇の中を光の玉が昇っていく。それはやがて散り散りになって消えた。
ほんの一瞬照らし出された彼女の横顔。その頬に涙の筋をみとめた。
彼女を置いて、私は夢から覚めることにした。
「どうだった」
いつの間にかそばに立っていた風の便りが、私の顔色を窺うように上目遣いで歩み寄る。
「君は……君は本当は彼女を元いたところに返すことができたんじゃないか?」
怒りを帯びた私の言葉に、風の便りは明らかに狼狽えた。
「君は彼女を手離したくなかったんだ。だから、彼女に嘘を教えて——」
「そんなつもりじゃ無かったんだ! ただ少しのあいだ、ともに暮らす誰かが欲しくて」
啜り泣く風の便り。
「彼女は故郷に帰りたかったんだ」
洞の中では青い灯が、繰り返し繰り返し打ち上がっては消えていった。
***
このお話は、5月28日の『花火の日』にちなんで、『花火』をモチーフにして書きました。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
