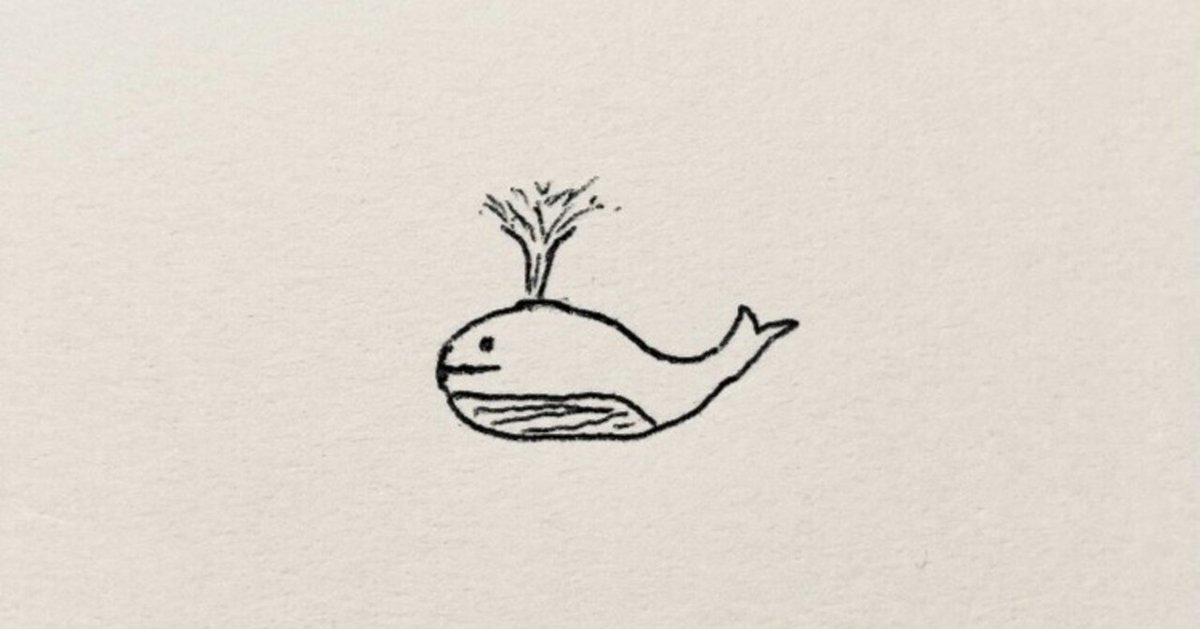
掌編小説『悔恨の靄』
私が異変に気付いたのは、夫の死体を運んでいるときだった。
月のない良い夜だった。
あたりは暗く、首から提げたペンダント式のライトが無ければ、まともに歩くこともできなかっただろう。十二月の夜気はどこまでも鋭く砥がれていて、夫の足首を掴む両手の感覚はとうに失われていた。
死体を引きずる私の進路上に現れたのは、青白く光る靄だった。ライトの光が届かない距離にもかかわらず、靄は神秘的な光を纏っていた。ちょうど人ひとりがすっぽりと収まるくらいの大きさだった。
私はしばらく見とれてから、我に返った。呆けている私の腕の付け根に、疲労による痛みがはしったせいだ。
木立に分け入ってから、すでに充分な距離を歩いたはずだ。埋めるならここにしようと、半ば直感的にそう思った。
そんな私に同意するように、靄がひっそりと近づいてきた。興味深そうにというのが正しいのかもしれない。
近くで見る靄はいやに艶めかしく、その揺らめきからは微かな粘度と質量を感じた。蜘蛛の巣が密度と体積を増せば、このような姿になるだろうなと考えた。
靄が夫の袖を引く。
既にこと切れている夫が抵抗するはずもなく、今は醜く肥えた身体は音もなく靄の中に飲み込まれていった。
私は見ていることしかできなかった。まるでそうなることが当然かのように、事の次第を見守った。
靄は楕円形の繭に姿を変えた。夫を包む繭からは、音もなく淡い燐光だけがこぼれていた。
「帰ろっかな」と、ため息混じりに私は言う。
別に靄に対して意思確認を行ったわけではないが、押し付けるように、手を引くように、光の繭にすべてを委ねることにした。
私は全てをあとにして、その場を立ち去った。
三時間かけて帰路に就き、歯を磨くこともせずベッドに倒れ込んだ。
私専用になって久しいセミダブルの寝台は、誰よりも優しく私の身体を受け止めた。
次の日の朝、九時間の眠りから目覚めた私はまず熱いシャワーを浴びることにした。
頬を叩く水滴と熱が、私をたちまち覚醒へと導く。
浴室を出て、体を拭き、髪を乾かす。
冷蔵庫から取り出したミルクをカップに注いだとき、ようやくテレビをつける決心がついた。
日曜日の午後は大して面白い番組がないと、いつか夫が言っていた。くだらないゴシップか、誰かの非業の死によってしか、メディアは茶の間の興味を満たせないというのが夫の持論だった。
自身が後者の「誰か」になったいま、茶の間の興味を満たす側になった境遇を彼はなんと評価するだろうか。
私の覚悟とは裏腹に、チャンネルを幾度か切り替えてみても、七十インチの画面の中に夫の姿は見つからなかった。
お代わりのミルクはレンジで温めることにした。
達成感と、小さじ二杯分の砂糖の甘さを噛み締めながら、私は昨夜見た靄について考えを巡らせていた。そのときだった。
玄関ドアのサムターンが回り、扉が開く音がした。誰かが家に入ってきたようだ。私は思わず立ち上がった。
廊下を歩く足音。その三歩目で、私は足音の主が誰かわかった。考えるより早く、体に染みついた不快感が動揺とともに全身を駆け巡る。
リビングの扉を開けて部屋に入ってきたのは、昨日殺したはずの夫だった。
「おう、お前か」
夫は狼狽える私に見向きもせず、服を脱ぎ散らかしながら家路に就くまでの経緯を説明した。彼も未だ混乱の中にあり、言葉として発することで状況整理をしていることが、鼻息の荒い口調から汲み取れた。
「でよお、気が付いたら山ン中だったんだよ。必死こいてバス停見っけてなんとかって駅まで行って、そっから電車乗ってよ。財布あって助かったわ」
財布を持たせたままにしたのは、へたに取り上げることで遺体発見時に不自然さが生まれないようにと配慮したからだ。
あくまでも事故に見せかけるための、ささやかな工作。それが裏目に出てしまった。だが、問題はそこではない。収まりつつある動揺の中で、私は冷静になろうと努力した。
「マジでわけわかんねえ。昨日、お前とメシ食ったとこまでは覚えてんだけどな。お前、なんか知らねえ?」
これは単なる勘に過ぎないが、恐らく夫は気付いている。私によって危害を加えられたことに薄々気が付いていて、疑念を確信にするために戻ってきたに違いない。
仮に密やかな後ろめたさも帰宅を決めた動機のひとつだとすれば、腹立たしさと虚しさを覚える。
靄状の不思議な気体が、生命活動を止めた肉体にどのような影響を与えたかはわからない。わかっているのは、間違いなくこの手で命を奪ったはずの夫が、こうして目の前で息をしているということだ。絶望と希望が混在した現象だった。
「お風呂、入ってきたら?」
弛緩する喉を制御して、私はどうにかひとこと言い終えた。
「ああ、そうするわ」
ジーンズを脱ぎながら、夫は上目遣いに言った。完全に警戒を解いたわけではないだろうが、今はそうするほかないと諦めているようにも見えた。
浴室から聞こえるシャワーの音を背中に、私は夫の携帯を手に取った。新婚旅行先で撮影した記念写真が表示される。
私たち二人の上に並んだ数字を、手袋ごしに八回タップする。
私のものでも、夫のものでもない生年月日で、携帯のロックは解除された。
メッセージアプリを立ち上げて、リボンを付けた可愛らしいキャラクターのアイコンを探す。彼女はとある星のプリンセスで、別惑星の王子と恋人という設定がある。ちなみに、夫のアイコンが件の王子であることは言うまでもない。
プリンセスのアイコン横には、未読を意味するマークが表示されていた。
私はアイコン横の簡易表示されたメッセージを長押しした。こうすれば、直前のやり取りを既読にすることなく確認ができた。きっと、同じような目的を持った誰かが適当な建前で搭載した機能に違いない。
—23:13 で、奥さんとの話ってなんだったん?
—23:15 ねえ、ちゃんと言ってくれたんだよね? 信じてるよ
—23:39 通話したいなー
—06:42 悪い あとで連絡するわ
—09:14 ずっと待ってて寝落ちした お肌荒れたらケイちゃんのせい
—10:18 ごめんって また明日家行くわ
震える指先でアプリを閉じて、携帯を元通りの位置に戻した。
想像していた通りの結果。にもかかわらず、二人のやり取りを見た私はそれなりにショックを受けていた。涙はとうに枯れていたが、動悸を鎮めるために、私は十分ほどトイレにこもるはめになった。
それから台所に行って、包丁を手に取り、浴室に向かい、目を見開く夫の腹に突き刺した。
夜が更けるのを待って、夫をトランクに詰め込んだ私は車で家を出た。
少し迷ったが、私は昨晩と同じ場所を行き先に選んだ。頭の中には例の靄の存在があった。
果たして靄は再び私の目の前に現れた。
私が再びここを訪れると予知していたかのように、靄は悠然と木立の中を漂っていた。
「またお願いしてもいいかな」
靄から返答はなかったが、私はその場に夫を置き去りにした。立ち去る途中で後ろを振り返ると、地面に滑り降りた靄が光の繭を象ったのが見えた。
私は期待と不安を胸に家路を急いだ。
月曜日の朝を迎えた。私は生まれて初めて、仮病で会社を休んだ。
ソファで時間を潰して待っていると、昨日より遅れて夫が帰宅した。
「おかえり。待ってたよ」
夫はやはり疲弊していて、前日と同じようなセリフを吐いたあと、シャワーに向かった。
それから前日と同じ表情で息絶えた。
—08:32 ねえ、ケイちゃん今日は会社お休み?
—08:33 奥さんとなんかあった? 今日、待ってていいんだよね?
—09:12 ごめん しばらく連絡ムリ
—12:34 不在着信
—12:46 不在着信
復活による効果の一つとして、夫にある特徴が現れた。
蘇るたびに、夫は私に従順になっていった。
家に戻ってくる時間は徐々に早くなり、女と交わすメッセージの数は激減していった。
四度目からは、私が迎えに行ってあげもした。
夫は運転席に座る私の姿を認めると、力なく微笑み、黙って助手席に身を沈めた。夜にはトランクに居場所を移して、やはり黙って付き従った。
八度目の帰宅時に夫は言った。
「なあ、もう許してくれないか」
「話ならあとで聞くから、先にシャワーでも浴びてきなよ」
夫は一瞬、今にも泣き出しそうな表情に顔を歪めてから、力ない足取りで浴室に向かった。
それでも私から悋気が失われることはなかった。
いつものように、深夜二時をめがけて私は山に向かった。夫は今日もトランクの中だ。
重量のある夫の巨体をトランクから引きずり降ろすことにも、もう慣れた。
「よし、今日も行こっか」
車の停車位置から木立に伸びる轍を辿る。
ネックライトはもういらない。行き先なら体が覚えている。
しかし、この日はいつまでたっても靄を見つけることができなかった。
地面の轍はとうに絶え、降り積もった枝葉で牽引に対する抵抗が増す。
しばらく森を彷徨ってから、私は茫然と立ち尽くした。途方に暮れるとはこのことだった。
靄は私を見放したのだろうか。それとも、私の後ろ暗い愉しみに気が付いて、手を差し伸べることをやめてしまったのだろうか。
明け方まで待ってみても、再び靄が姿を現すことはなかった。
あの靄がいったい何だったのかは私にはわからない。
私を諭していたのかもしれないし、試していたのかもしれない。いずれにせよ、十度目の死を最後にして、夫の生はようやく真の終わりを迎えた。
私は靄を待つことをやめた。
そして私は亡骸の重さを確かめるように、夫の足首を握り直した。
了
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
