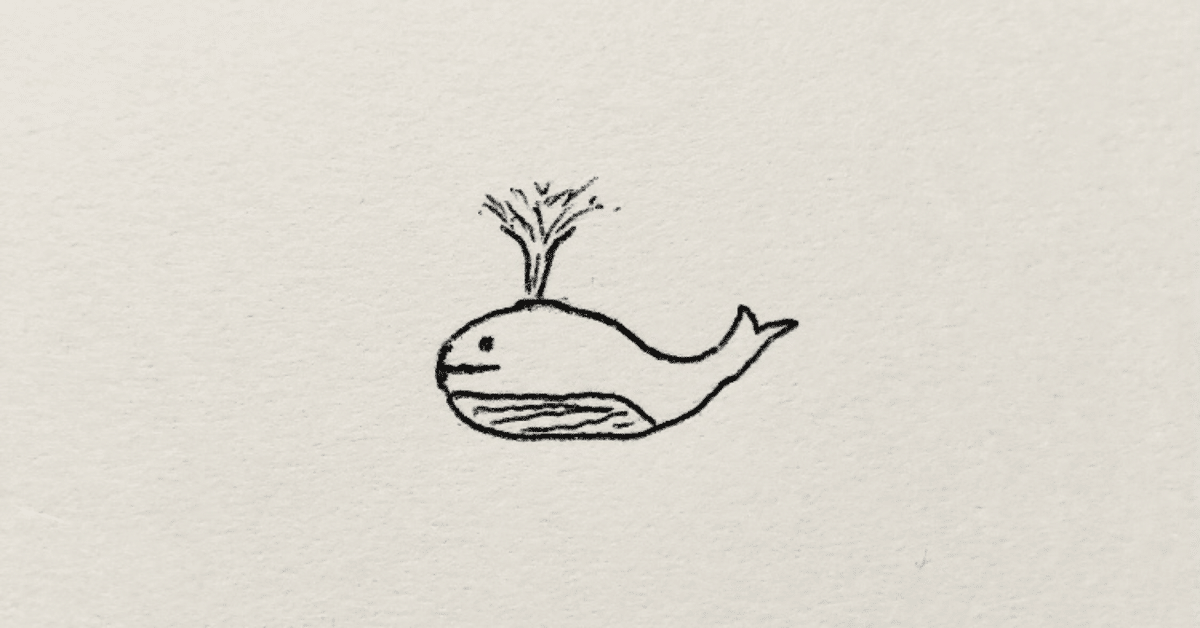
掌編小説(8)『読心エンヴェロープ』
私だって、最初に気がついたときには「こんなの偶然だ!」と、そう思った。それこそ偶然手に入れたこの封筒に、こんな不思議な力があるだなんて考えてもみなかった。
ある日。学校をサボった私はあてもなく住宅地をぶらぶらと彷徨っていた。
家の近くまで帰ったが、ご近所さんに見つかると親に告げ口されそうで、文字通り二の足を踏んだ私は路地裏を探検することにした。
途中、周りを家に囲まれた空き地のような場所を見つけた。なんというか、その土地に建っていた家か何かがすっかりどこかに消えてしまったような空っぽの空間だった。空き地を囲むすべての家が背をこちらに向けている。まるで世間から知らんぷりを決め込まれたようだ。
誰かに見られてやしないかと、空き地に面したいくつもの窓にさっと視線を走らせる。ガラス窓の向こうには人影はない。それでも、なんとなく落ち着かない気持ちのまま、私は空き地に足を踏み入れた。
「珍しいね。こんな場所に人が来るなんて」
急に声をかけられた私は慌てて口を塞いだ。悲鳴をあげそうになったというのもあるが、口から心臓が飛び出るんじゃないかと思ったからだ。振り返ると、着ている服がすべてパッチワークみたいな、ちぐはぐな格好をしたおばあさんがいた。首元は詰襟で袖は割烹着。右の裾は白衣で左はちゃんちゃんこだ。
「すいません。私、勝手に入っちゃって。すぐ出て行きます」
おばあさんは別にいいよとばかりに手を振って笑う。
「かまやしないよ。こようと思ってこれるもんでもなし。何か因果があるんだろうさ」
知らない場所で知らない誰かと二人きり。とても居心地が悪かったが、それと同時に何かの期待感というか、ふわふわと浮ついた感情が私の胸を満たしていった。
私の好奇心は、いつの間にか地面に敷かれたござの上で妖しげな魅力を放っている品々に向けられていた。
洗濯バサミや木のまな板。ところどころ染みのある古びた封筒に、欠けた茶碗。どう見てもガラクタにしか見えないのに、陳列されたその一つひとつからは生物の息づかいのような生々しい気配を感じる。
「どれだい?」
突然の問いかけに面食らいつつも、私は封筒を指さした。さっきからなぜか、この封筒から目が離せなくなっている。封筒を手に取る。
「じゃあ、お行き」
私は促されるままに、その場を後にした。
家に帰った私がまず最初にしたことは、手紙を書くことだった。机の引き出しから取り出した便箋に、今日、学校であったことやそのときに感じた気持ちを書き記した。
清塚くんが私を好きだというのは瑞稀の嘘だった。
本当は瑞稀も清塚くんを好きだったから、私の邪魔をしたらしい。
ふざけんなって思ったけど、私はなにも言えなかった。裏切られて悲しかったのもあるけど、瑞稀とは幼稚園からの親友だ。簡単には嫌いになれない。明日、どんな顔をして瑞稀に会えばいいのか。それを考えると吐きそう。
出す気もない便箋を封筒に入れて、その日は寝た。
その日見た夢の中で、細面の青年にこんこんと説教を食らった。
「いいかい? 辛いかも知れないが、逃げてちゃ何も解決などしない。友だちなんだろ? きちんと話をするべきだ」
それから何度か同じことを試したが、その度にあの青年は夢の中に現れては私に意見した。
彼は今まで出会った中で、誰よりも私のことを理解していた。私が見る夢なのだから当然かもしれない。私はこうして、最強の相談相手を手に入れた。
そんな生活の中で、私の中に予想だにしない想いが芽生えてしまった。思わず便箋にしたためてしまったが、こんなの、彼に見せるわけにはいかない。
何日も迷った結果、あの便箋はしばらく封筒に入れないことに決めた。
きっと向こうも困るだろうし、私だって、なんでも看破してくる封筒に対して、秘密のひとつくらい持ってみたい。
もう少し気持ちを整理してから、この便箋を封筒に入れようと思う。彼がどんな顔をするのかが、今の私のもっぱらの楽しみである。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
