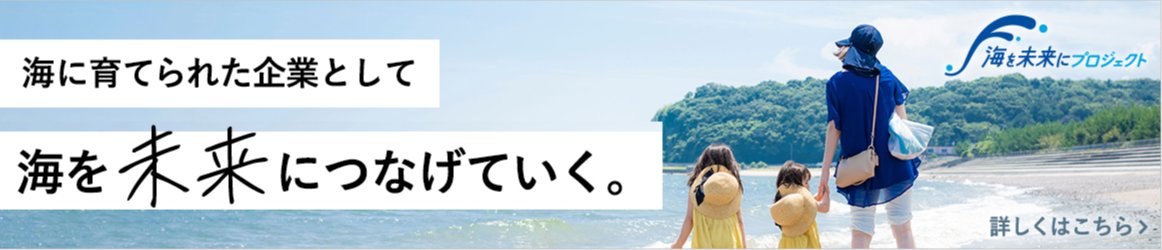渡り鳥調査の思い出・水ノ子島灯台/海辺の水彩画
絵・文 岡本幸雄
九州最東端へ突き出た鶴見半島。その先端の鶴見崎から北東約8㌔沖、豊後水道のど真ん中に「水ノ子島灯台」が立つ。
その昔、鶴見半島の松浦漁港を基地に、渡り鳥調査に参加したことがあった。NHK特集『渡り鳥・謎の夜間飛行』の取材協力である。

春と秋は渡りの季節。南方からやってくる鳥、北へ帰る鳥など、その習性は様々だ。生涯を日本で暮らす鳥に比べ、小さな体ではるかな洋上を休むことなく飛翔し続ける鳥たちは、とても愛おしい。
普通、小型の渡り鳥たちは群れをなして海面すれすれに飛ぶ。天敵から自らを守る手段でもある。そしてもうひとつ、鳥たちは危険をさけるため夜間にこっそりと移動する。ここに意外な事実が隠されている。渡りのルートに位置する水ノ子島灯台に鳥たちが衝突し墜落死するのだ。その現象は悪天候ほど多く、一夜明けた灯台周辺は鳥の死骸でいっぱいになるという。この不可解な出来事を解明するため、当時、FURUNOが漁船用として開発中だった「海鳥探知機」を使って実験を行ったのである。
南方からやってきた渡り鳥たちは、トカラ列島から九州へ上陸したあと、鶴見崎、豊後水道を経て四国へ渡る。水道のど真ん中に立つ水ノ子島灯台は、夜の渡りの道しるべとなる。水ノ子島灯台は、南北約70㍍、東西約30㍍、高さ約25㍍の岩礁島である水ノ子島に、明治33年から4年の歳月をかけて築かれた。高さ39㍍の石積み構造の灯台である。レーダービーコンが設置されており、漁船やボートほかの航海レーダーにも反応する。

水ノ子島灯台は、渡り鳥たちの目標であると同時に休憩の場でもある。しかし、灯台の光に目が眩んでしまうのか接近しすぎて衝突し墜落死するらしい。渡りのピーク時には一晩に150羽もの落鳥があるという。
調査班はSバンドレーダーの海鳥探知機を岩場に設置し連日、夕刻から22時頃まで観測を繰り返した。観測を始めて3日目。明るいうちは1羽の反応もなかったが、日が落ちた19時頃からレーダーに渡り鳥の反応が一つ二つと現れ始めた。やがて海鳥探知機には、無数の鳥の反応が現れ続ける。鳥・・鳥・・鳥の映像は、まるで満点の夜空の星を眺めているようだ。そのピークは20時から1時間ほど続いた。探知レンジは3マイル。画面に映っているのは15㌢ぐらいの小鳥で、すべて1羽鳥である。1羽鳥が間隔をあけながら飛び続けている。視認できたのは、ホオジロ、アカショービン、アカハラ、キビタキ、モズ、アオバズクなど。それはそれは感動的な光景であった。

画面中心が灯台の位置で船首線は南西を向いている。
点々はすべて1羽鳥で遠くに漁船が表示されている
Sバンドの海鳥探知機が誕生して30有余年。今日まであらゆる漁船で活用されてきた。そして2016年、Xバンドのバードレーダーが登場した。
本機は小型軽量のためプレジャーボート業界で注目され、スポーツフィッシングでの活用が始まろうとしている。水ノ子島灯台の渡り鳥調査に参加した当時は、想像もできなかったことである。

おかもと・ゆきお profile
1944年、姫路市生まれ。1967年古野電気入社。フルノ在籍時からマリンギアライターとしても活躍し、「須磨はじめ」のペンネームでフィッシング雑誌などに寄稿。著書に「魚探とソナーとGPSとレーダーと舶用電子機器の極意」、「魚探大研究」、「魚探・GPS 100%使いこなしブック」など多数。著書の挿絵から水彩画の世界へ。
本記事は2016年〜2022年までBoat Fishing誌にて連載されていた「海辺の水彩画(絵・文 岡本 幸雄)」を再編集したものです。
「渡り鳥調査の思い出・水ノ子島灯台」は2017年5月号に掲載された内容です。
当時の面影とともに水彩画の世界観をお楽しみください。