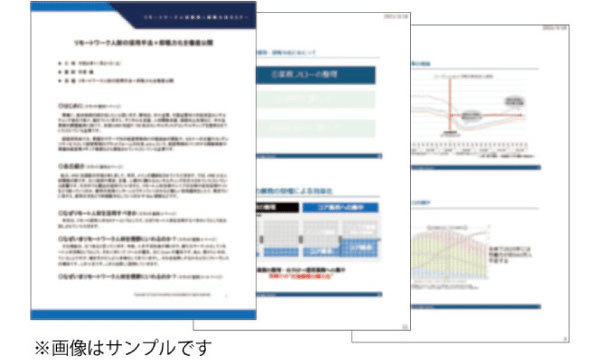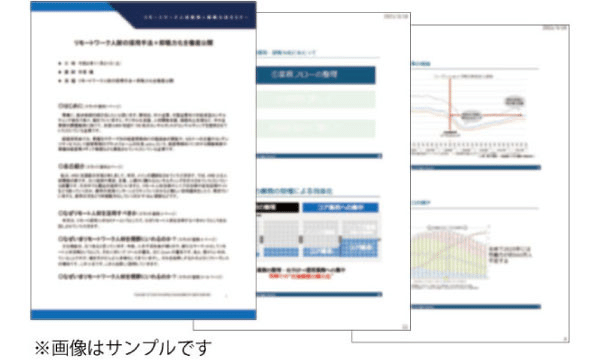中規模・中堅工事会社のDXとは「現場監督改革」 ~セミナー特選講演録~無料ダウンロード
セミナーの講演内容と当日使用したテキストを無料でダウンロードいただけます。平均10,000文字を超えるボリュームの講演文字起こしとノウハウの詰まったテキストをご覧ください。
◆開催日時:2021年5月25日
◆講師:船井総合研究所 釜谷 洋平
◆セミナー詳細:専門工事会社のデジタル戦略セミナー
最初に
もう一つ、最初にお伝えすべきことは、今日皆様と最後にこれを押えておきたいということです。本日のセミナーは「工事会社はDX化によって大きく成長することができる」です。どのように取り組んでいいのか、これは本当に意味があるのだろうか、流れ的にやらなければいけないのかなど思われる方もいるかと思いますが、断言します。DX化を取り組むことによって、成長路線へと一歩踏み出すことができるようになっていきます。
DX化によって得られることというのは、端的に三つ書いています。「営業利益額1.3倍の実現」することができます。「残業時間大幅削減」することができます。「若手監督活躍&脱人手不足」です。こういったことを実現させていくことを目的におきながらDX化に取り組んでいくということです。これを得ることによって、工事会社様におかれましては大きな成長の路線へと入っていくことができるということです。重ねてDXと言っていますが、工事会社がDX化するための正しい手法というのがあります。あるものを取って付けるというかたちではなく、正しいやり方や進め方、落とし込み方というものがあります。そちらを今日のセミナーで取り上げていければと思っています。
中規模・中堅工事会社のDXとは「現場監督改革」
それでは、早速ですが、第一講座に入りたいと思います。第一講座は、「中規模・中堅工事会社DXとは、現場監督改革」ということで引き続き私のほうからお伝えさせていただきたいと思います。
北陸地域年商15億円の設備工事会社の取り組み―2018年10月時点のA社
最初に皆様方と共有したいのは、このような話です。北陸地域の年商15億円の設備工事会社様の取り組みから始めたいと思います。
年商15億円、現場監督18名、工事職人12人、営業4人体制の工事会社様でした。この会社様も他社と同じく採用も進んでおらず、なかなか若手が入ってこないといったような状況が続いていました。したがって、平均年齢が年々上昇しているということが実際のところです。工事の受注といたしましては、ゼネコンさんからの下請け受注や公共工事の元受け受注が約6割です。それ以外は、製造工場様や施設様やオフィスのテナントの改修などの部分であるというような企業様になっています。もちろん小口のメンテ工事等も多く、保守契約を結んでいきながらお客様と関わりを持っているというような業績の構築です。仕事に対する魅力はあるものの働き方は旧態依然ということで、この会社の社長様は「どちらにしても厳しい業界だ。今の若い子達が入ってきてもなかなか続かない。その中で先輩社員や社長幹部層が、このお仕事の素晴らしさや魅力があることを伝えるしかないね」と言っており、そのようなことを伝えるために試行錯誤していることが事実です。
一方で、やはり、働き方自体は昔のままで、現場が終わって会社に帰ってきて、そこから事務作業をしていくというような状況が続いているという会社です。また、現場間の情報共有は限られていて、個人で協力会社、資材仕入れ業者等を決めているというのが実際の状況です。約15億円~25億円までなってくると、まだ個別の監督さんが協力会社さんの発注や資材の発注をされている企業さんも多いのではと思っています。私の経験上、60億~80億ぐらいになってくると購買担当がつくこともありますが、これくらいの規模になってくるとそこの部分の整備ができていなくて、現場監督単位で発注している企業さんも多いかと思います。
北陸地域年商15億円の設備工事会社の取り組み―取組事項①業務状況の把握
この会社様の取り組みは何から始めたのかといいますと、最初、業務棚卸からスタートしました。最初は社長のご要望としては、現場監督18名はそれぞれ現場を持っているのですが、現場の状況や結局監督は何をしているのか分からないというような部分からお声がけがスタートして、とりあえず見られるようになろうとスタートしたのがわれわれとの付き合いです。最初に取り組んだものが業務の棚卸しですが、どのような業務を実際やっているのか、監督の四つの管理業務です。工程、品質、安全、労務管理、資材管理などの部分についてしっかり見ていきました。合わせて工事事務の方々のサポートです。このようなサポートの方々の業務の状況を見ていきながら、どのような業務になっているのかというところまで一つ一つ見ていくというところからスタートしていきました。
北陸地域年商15億円の設備工事会社の取り組み―取組事項②組織の“あるべき論”&“現実論”の整理
次に、まず業務のあるべき論というところを作るところからスタートしていきました。やはり、今の業務をデジタルを使って効率化していこうとピンポイントでやっていっても、それが最終的に整合性あるのかどうなのかなかなか見えないのが事実です。そのため、最初に取り組んだのは業務のあるべき論です。
おそらく、本日参加の方々にもあるかと思います。例えば、図面からの拾い上げ、レベルが高い会社様であれば施工図や勾配の部分もやらせたい、安全書類などもそのあたりです。どちらが持っていて、どのように割り振りするのがベストなのかということを組織という観点から入っていったということです。それをやっていきながら現実論とあるべき論を対比していき、ギャップを認識していくということをしていったという状況です。ここに書いてあるのは協力会社の確保の仕方ですが、この会社さんも協力会社との関係性は、現場監督さんに寄っている部分が多かったです。監督さんごとに好意にしている協力会社さんがあり、いつもそこに発注がかかっていくということです。そこで、二つ分かったことがあります。一つは、監督さんによって仕事のムラがあって、協力会社の手が開くときがあったりするため、それは協力会社にとって不都合だという話とあとベテラン監督ほど良い協力会社を確保していますが、若手監督ほど良い協力会社さんと巡り合うこともないです。また年齢的にも合わないということもあり、若手ほど現場での協力会社さんとのやり取りに苦労していたという事実があったりしました。
先ほど話した各処理の考え方も含めてですが、組織のあるべき論と現実論を整理していくと社長の得たいという気持ちと、現実はなかなか難しいという話があります。
まず、原価意識という部分でいきます。監督に持たせたいという気持ちがある反面、それをやればやるほど監督に業務が帰属していくため、どこで割振りしていくのか、購買の在り方に関しても集中購買にしたほうが結局ロットが取れるので安くなります。また、部材の中でも在庫を持てるものも品番によってはあったりします。在庫を持つと突発的対応にも対応できまして、それが利益につながっているケースもあったりします。そして、積算や各種書類などの協力会社の確保の仕方です。このような話を諸々としていきました。本来はこうしたいという話とどこまで割り振るかということを1個1個詰めていくということをやっていきまして、まず組織図のあるべき論を作っていきました。
北陸地域年商15億円の設備工事会社の取り組み―取組事項③業務の再整理とデジタル化指針
次に、業務の再整理とデジタル指針というところを行いました。一つ見えてきたのは、やはり、現場監督ほど現場監督にしかできない仕事になっていくということです。
一方で、現場監督でなくても少しはできるのではないかというような仕事を別の人に寄せていくと、その人がその業務の専属マンであったり、業務量も溜まってきます。例えば、報告書業務や積算拾い上げにしても、あるべき組織図を作ったら現場監督以外の方に仕事が集まってきました。そこに対してデジタル化をしていこうという指針をしてみました。つまり、報告書専属マンや積算専属マンというような感じです。そのような業務を一つ作り、その人の報告書業務が圧倒的に速くなるような業務フロー、デジタルでできるものは切り替えていこう、それによりどれくらい時間が削減できるのかということを1個1個出していくということに取り組んでいきました。
北陸地域年商15億円の設備工事会社の取り組み―取組事項④定着へ向けたマイルストーンの整理
次に取り組んだことが、具体的にどのスピード感で進めていくかということです。まずは、KPIを何%を入力してみようやこれを取り組んでみようなどを一つ一つ決めていき、スケジュール立てをしていきました。
一気に進めると何が一番怖いかというと、もともとやっていたやり方をガラッと入れ替えてうまくいくかどうかというのは各会社さんによっても違います。これを入れ替えればオールオッケーというものはなく、各会社さんも業務の仕方があるため、一気にやってしまうと抜けや漏れがあり、結局業務もトラブルを起こしてしまうということもあります。小さく進めていきながら、どれぐらいの目標までいこうという小さいゴールを決めて定着を進めていくということが重要になってきます。
北陸地域年商15億円の設備工事会社の取り組み―取組事項⑤現場会議の実施全員で取組む業務改善
現場管理の実施、全員で取組む業務改善という点です。今まで18人ぐらいいると、
現場のミーティングなどもありますが、内容が薄いことが多かったりします。つまり、報告事項で時間が終わってしまうということです。本来の会議やこのような現場の皆さん方にやってほしいものは、いかに原価を下げるか、いかに若手が活躍させるかというような会議です。それやるためには相応な情報やデータがないといけませんが、それをしっかりと集まる素地を作っておくと会議が活性化します。
具体的にいうと、この会社さんにおいては現場監督1人1人における工事の進め方というところを全員が見られるようにしています。それも1人1人聞くと訳が分からなくなってしまうため、それがしっかり見えるようなデジタル化ツールを使っています。今木のほうでも紹介あるかと思いますが、現場管理クラウドというツールを使い、現場監督さんの工程情報をスマホやタブレットから常時共有をしていくという仕組みをやっていきます。そうすると、同じような公衆、現場、設備状況に対していろいろなアプローチの工事の進め方があって、結局どれがいいのかということを現場監督18人ぐらいで会議で話します。そうするとより効率的に工事を進める監督が出てきて、会社における工事の標準原価そのものが落ちてくるという具合になっていきます。そのような現場会議をしていくことが重要だということで取り組んでいきました。
この1~1番を急ぎすぎず、ゆっくりしすぎず進めていきました。
北陸地域年商15億円の設備工事会社の取り組み―訪れた変化①労務・工程管理のクラウド化
どのようなことが会社で起きたかとお話します。まず一つ目は、労務・工程管理のクラウド化を現場監督業務のうち工程管理と労務管理をクラウドツール用いて対応していきました。今まで工程管理や資材管理、原価管理の部分は監督さんの頭の中に入ってしまうことが多く、監督さんの報連相の質によって遅れている現場、進んでいる現場が見えないわけです。これは難しいところですが、やはり実行予算ベースでいきます。そのため、工事が早く終われば終わらせたいという気持ちもあるかと思います。しかし、予算がある限りはやってしまうという監督さんは実際にいます。しかし、現場データが見えるようにしていくクラウドツールを使って労務、工程、管理自体の対応をしていきました。これをやることによって、現場監督さんの現場での役割というのは品質と安全というところになっていきました。
北陸地域年商15億円の設備工事会社の取り組み―訪れた変化②安全おじさん誕生
次に何が起きたかといいますと・・・
セミナーの講演内容と当日使用したテキストを無料でダウンロードいただけます。平均10,000文字を超えるボリュームの講演文字起こしとノウハウの詰まったテキストをご覧ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?