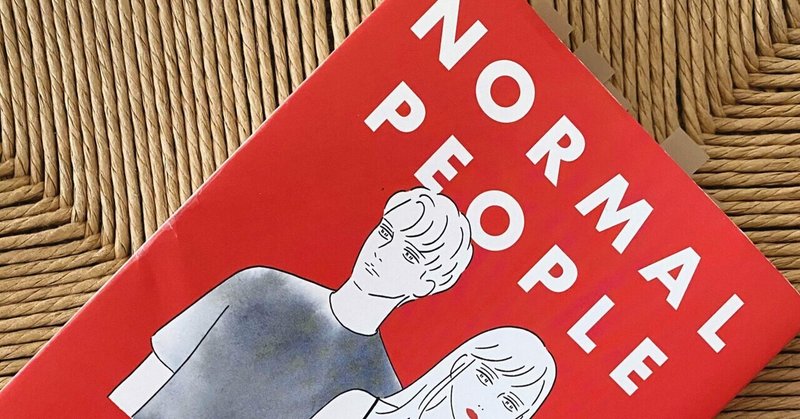
『ノーマル・ピープル』 サリー・ルーニー著 私の孤独を埋める唯一の存在
早く読み終わりたくてページを捲る手が止まらなくなる小説と、ずっと読み終わりたくなくて何度も同じページを咀嚼してしまうタイプの小説があると思う。どちらも傑作には違いないだろうが、サリールーニーの「ノーマル・ピープル」は、間違いなく後者だ。
この物語に、できることならばずっと浸っていたい。明日また最初から読み直してもう一度自分の感覚を確認したいと思うのだ。
私には10代の頃からの腐れ縁的な男性がいたわけではない。この物語の主人公の二人、コネルとマリアンのようには。それでも彼らと同じかつてティーンネイジャーだった、学校と家庭がこの世の全てだったあの頃の自分の感覚を、否応なしに思い出してしまっていた。
ほとんどの人たちはただ人生を生きていくのだ、彼女は思った。ここまで誰かと近しい気持ちになることもなしに。(ルーニー、2023、P49)
高校生の頃、初めてできた彼氏と親密になった頃に私も感じていた。自分一人で抱えなければならない人生の困難や喜びを、恋人という存在だけが分かち合えるのだと16歳の私は感覚的に知った。それが雷に打たれるぐらいに衝撃的だった。自宅で家族と話をしていても高校の授業中であっても、あの人のことを考えてしまうという経験を初めてした。「自分達だけが特別なのだ」と思っていた。中学まで仲が良かったあの子には絶対にわからないだろうなどと思い優越感に浸ってもいたのかもしれない。映画や小説では観ていた異性とのやりとりが、現実になり腑に落ちたと言ってもいいのかもしれない。このような感情がこの世の中に存在するのかという驚きがあったのだ。
私の場合は一瞬でそのような感情は終わってしまった。この小説の二人とは違って、それからほんの2−3年で恋愛する感覚というものにもすっかりと慣れきってしまっていた。熱されたものはいずれは冷めるものだった。
この物語はアイルランドの小さな田舎町で暮らす同級生のコネルとマリアンの、約4年間を時系列的に描かれていく。
二人は同じ学校に通う高校生で親密な関係だけれど、恋人ではない。「対」のようだけれど決して「一緒」であることがないのだ。それは例えば高校時代、コネルはサッカー部に所属していて社交的でハンサムで人気者だが、マリアンは彼女の性格や家柄の良さのせいで「お高くとまっている」とみられイジメの対象だ。マリアンの母は弁護士でいわゆる富裕層だが、コネルは何世代も前から労働者階級である。(彼の母親はシングルマザーで、マリアンの家で掃除婦として働いている。)
大学生になりダブリンの大学に進学すると、彼らのヒエラルキーは完全に逆転する。コネルは貧乏で地味で冴えない男性として周囲から認識される一方で、マリアンは自分と同じような階層の人が集まる大学では人気者になる。
このようなことは実際によくあることだ。経験的にピンとくる人も多いだろう。
どちらかがずっと幸福というわけでもないし、ずっと不幸というわけでもない。
社会階層や学校でのヒエラルキーが違うからといって、決してどちらかが特別に人生がイージーというわけではないところも面白いし現実味がある。まるでシーソーのように上がったり下がったり浮き沈みがあるのが人生だ。どちらが良くて悪いということがないのだ。
全く違う二人の唯一の共通点はなんだったのだろうか。
どちらも成績優秀であること。そして「どこにいても自分の居場所はここだ」と思える場所がないところであったかもしれない。
互いの孤独感を埋められる唯一の存在がお互いなのだ。それは物理的にも精神的にも言えることである。
「あの人だけが自分を理解してくれるはずだ」という安心感が時に傲慢さになってしまう。
その傲慢さが相手を傷つけてしまったり、時に関係を悪化させるものにさえなっていくのだが。
このような青春時代の繊細で複雑な男女の心理描写を中心としてながらも、決してそれだけに留まらない「社会と自分」という自己のアイデンティティの普遍的な物語でもあるのだと思う。
両親や兄弟など家族との関係性から、学校などの閉ざされた空間での友人との距離感、年齢を重ねるにつれ、次第にそれが社会へと開かれる。この世界で「自分にとって最も適した生き方は何なのか?」という課題へと変わっていく。それは現代を生きる我々の誰しもに共通するものだ。
同時に、この不条理などうしようもない人生の中でも、必ず喜びの瞬間があるのだとも感じさせられるシーンがいくつかある。
おそらく作家自身の思いなのではないか、と感じさせられ私はそれらの描写がとても好きである。
特に自分の生まれや社会階層には恵まれなかったけれど文学的才能に恵まれたコネルを通して描かれているように感じてもいる。
大学の文学系の人間達が基本的に、自分を文化的に見せる道具として本を読んでいるのは知っていた(中略)
それでもその夜コネルは家に戻ると、新しい短編のために書いてあったメモのいくつかを読み返して、サッカーの完璧なゴールのような、木漏れ日がキラキラと揺れ動くような、通り過ぎる車の窓から聞こえてきた曲のフレーズのように自分の中で脈打っているものを感じた。どんな状況であっても、人生はこんな喜びの瞬間を運んでくれる。(P278、279)
この小説は、ただ単純に主人公の二人の恋愛関係がどうなるのか追っていく、というものではない。
彼らの4年間を目撃し、二人の関係性と、個々の人生の最も重要な時期を見守っていくようでもある。
家族との仲、経済的な課題、メンタルヘルス、今後のキャリア。その中に驚くほど大切な一文や何度も繰り返し読んで考えたいテーマを含んだ一頁がいくつもありそこにマーカーをしておきたくなる。そういう類の作品だと思う。
2年ほど前にBBCのテレビシリーズを観て(これも傑作だ)、今回は原作を一度読んだけれど、「まだこの物語を味わいきれていない」と今の私は感じている。
これからの人生で何度かこの本を開くことになるだろう。彼らと同じような「若かりし時の自分」ではなく、「たった今現在の自分」にとっての好きなページを見つけてみたいのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
