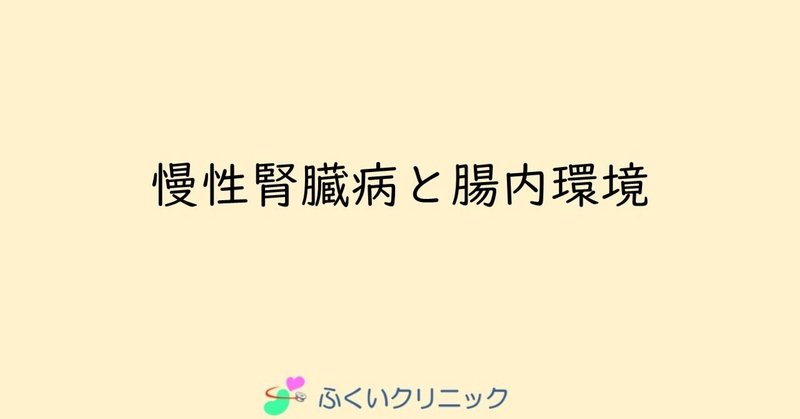
慢性腎臓病と腸内環境
慢性腎臓病(CKD)は成人の8人に1人に相当する約1330万人の患者がいると言われています。
高齢化に伴いこの数は今後増えていくと考えられています。
慢性腎臓病は生活習慣病などさまざまさ疾患により腎臓の機能が低下した状態です。
腎臓は背中と腰の中間あたりにある“そら豆”のような形をした臓器です。
腎臓の働きとしては一番大切なことは尿を作り老廃物を排泄することです。
この尿を作る過程で腎臓はとても複雑な働きをしています。
それが水と電解質の調整です。
我々は水を何も気にせず飲みますが、体が勝手に調節して、余分な水は尿として排泄してくれています。逆に体の水分が過剰に外に出てしまわないようにもしてくれています。
つまり体内の水分量をある程度一定に保ってくれているということです。
電解質とはナトリウムやカリウム、カルシウムなどのことを指します。
電解質は神経や筋肉が正常に働く上でとても重要であり、特にその濃度の調節が必要です。
例えばカリウムは高すぎると心臓の不整脈が出たり、筋肉が麻痺したりします。低すぎると意識障害や筋肉の脱力感や麻痺などが起こります。
その他、カルシウムやナトリウムも丁度いい塩梅があります。
これら電解質の調整を行ってくれているのもまた腎臓です。
その他にもたんぱく質を合成した後に出る、尿素やクレアチニンなどを排泄したり、体の酸性、アルカリ性の具合を調整する働きもあります。
またさまざまなホルモンを出して、各臓器に指令を出す役割もあります。その代表には、血を作るためのエリスロポエチンというホルモンや、血圧を調節するホルモンなどがあります。
慢性腎臓病ではこれらの機能が低下することにより、さまざまな症状がでます。
末期の腎不全になると体内でのコントロールができなくなるため、人工透析が行われます。
腎臓は一旦悪化すると元に戻すことは難しいため進行させないための予防が重要になります。
一般的には減塩などの食事療法や有酸素運動、筋トレなどの運動療法がありますが、最近では腸内環境の正常化がこの慢性腎臓病の治療として注目されています。
腎臓病と腸内環境の関連について簡単に解説します。
腸内には腸内細菌というさまざまな種類の菌が生息しています。
この菌の中には良い働きをする善玉菌、良くない働きをする悪玉菌、どちらでもない日和見菌が存在します。これらすべてを総称して腸内細菌叢といいます。
腸内細菌はビタミンやたんぱく質の合成、感染予防や免疫機能などコントロールしています。
この腸内細菌のバランスが崩れると毒素や発がん性物質の産生増加が起こったり、さまざまな疾患を引き起こすことがあります。
慢性腎臓病患者では健常人と比較して、この腸内細菌叢に変化が生じている可能性があるようです。
先ほど述べた善玉菌の減少などにより、腸の壁がバリア機能を失い、腸内から漏れ出た物質(毒素)が全身に慢性的な炎症を引き起こすことが知られています。
この毒素が蓄積することで腎機能を悪化させ、心臓血管疾患の合併や動脈硬化、筋肉量が減少するサルコペニアなどを発症する可能性があります。
これらの状態には酸化や炎症という現象が関わっています。酸化や炎症は体にとって好ましいものではありません。特に慢性の炎症は腎臓病だけでなく、糖尿病やその他の免疫疾患、感染症に対する抵抗力にも関わっています。
腸内細菌の乱れによる毒素の増加から毒素による体内の酸化や炎症の増加、それに伴う動脈硬化や心臓血管疾患の増加、心不全入院リスクの増加という悪い流れを断ち切るためには、上流である腸内細菌叢の改善が最も効果的かもしれません。
慢性腎臓病や透析患者では便秘の有病率が高いことが知られています。
そして腎臓病ではない人を対象にした研究では、便秘を合併している群は非便秘群と比較して、慢性腎臓病へと移行していく危険性が高いことも示されています。
このことからも腎臓病があるなしに関わらず、腸内環境を整えることは非常に重要であるということになります。
腸内環境を整えることで、毒素の産生が減るだけでなく、短鎖脂肪酸など、腎臓を保護するような役割のある物質の産生にも関わっています。
腸内環境を整える方法は別の記事で記載しているためここでは詳しく書きませんが、食物繊維の摂取、たんぱく質の適量摂取、ビタミンミネラル、腸内細菌を含むサプリメントの摂取、糖質や脂質の過剰摂取の是正などがあります。
他にも人工甘味料や添加物、加工食品、小麦や乳製品の過剰摂取も腸内環境を悪化させる要因です。
これらを念頭においた食事環境を整えることが、腸内環境を整える第一歩となります。
一見腎臓と関係ないように見える腸ですが、脳や腎臓、心臓との深い関わりがあります。
日々の生活で少しずつ改善し、健康維持を目指しましょう。
参考文献:日本腎臓リハビリテーション学会誌2022
