
ちびまる子ちゃんと帰国子女コンプレックス
さくらももこさんの『あのころ』というエッセイがとっても面白かった。きっとご存じの通り、さくらももこさんは国民的漫画・アニメの『ちびまる子ちゃん』の生みの親だ。このエッセイはそんな著者の少女時代についておもしろおかしく綴ったものだ。肩越しでぐずぐずと小言を漏らされているような語り口は独特な引力があり、ページをめくるたびにどんどん引き込まれていく。夏休みの宿題、遠足の思い出、ツチノコ騒動などなど。これらのエピソードはクスッと笑ってしまう一方、過ぎ去ってしまった子供時代に思いを馳せてどこか寂しさも感じさせるような。何はともあれ、とても味わい深い読み物だ。
マラソン大会の話
この本の中でぼくが群を抜いて面白いなと思ったのが「マラソン大会」という話だ。以下、ネタバレを含みます。
この話は小学校時代のマラソンがどれだけ嫌いだったかということから始まる。毎年二月上旬に行われていたマラソン大会に対して、十月ぐらいから心が重くなってしまうらしい。
大げさに言っているのではなく、マラソン大会の存在は、そんなにも私にとって負担だったのである。あの行事さえなかったら、私の子供時代はもっと軽やかな笑顔をふりまけたと強く感じている。
これだけでも結構おかしいのだが意外な展開が続く。
そんなに嫌いな事なのに、私はマラソンが得意であった。"好きこそ物の上手なれ"などという諺は腹が立って仕方がない気持ちでいっぱいだ。世界で一番嫌いな事なのに、かなり上手にこなしてしまう自分がうらめしくてたまらなかった。
実はめちゃめちゃ足が速かったらしい (笑)。ちびまる子ちゃんの初期のエピソードはさくらももこさんの実話を基にしているみたいだから、さくらももこさんの子供時代 = ちびまる子ちゃんと想像することはそんなに間違っていないはずだ。そう考えるとちびまる子ちゃんがめっさ足速いというのは何とも意外な気がする。嫌で嫌で仕方ないのに、毎年賞状をもらうレベルで突っ走ってしまうみたいだ (笑)。
それでも心の重さがピークに達したその年は、何とか風邪を引こうと画策する (それは例えば風邪を引いている友達のそばに寄ったり風呂上がりにあえて湯冷めしてみたり)。その甲斐も虚しく、さほど熱もあがらず仮病を使う手立てもないとわかったところで結局マラソン大会に参加することに。
過酷なレースの中をぜえぜえしながら「いやだなーいやだなー」と思いつつひたする走る。かなり苦しい。聞こえてくるのは呼吸の音と足音だけ。それでも足が速いので図らずも前方に出てしまう。ゴール二百メートル付近に立っているクラスの担任から、
さくら、あと一人抜けっ、そうすりゃ十位になるぞっ
とハッパをかけられる。どうやら十位までに入れば入賞ができるらしい。「ここまで頑張ったんだから」と渾身の力を振り絞ってゴールを駆け抜ける。
ただ、せっかく頑張ったのにオイルショックで紙が足りず五位までしか賞状がもらえないというまさかの展開に (笑)。
…が、小学校三年生の年はオイルショックの紙不足により、五位までしか症状がもらえないという情けない事態となった。全校生徒で六位から十位までの男女合計六十枚の賞状を、節約したからといってオイルショックに何の役に立つのか。
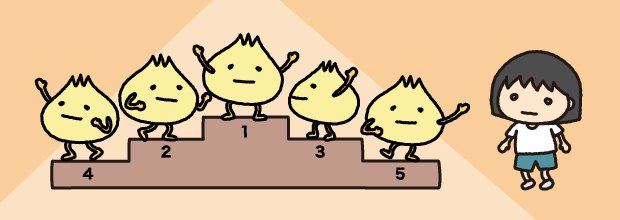
この話を読み切ったときにぼくはひとしきり爆笑した。ただ少し時間をおいてどこか物悲しい気分になった。一つのことを思い出して。
小学校時代というのは中庭でドッジボールをしたり、友達と家でゲームしたりするだけでもゲラゲラ笑いながら過ごせるものだったように思う。もちろんたくさんの例外があることは理解しているけれど、大枠はなんとなく理解してもらえるような気もする。
それでいて「どうしても嫌なこと」というのも同時にそこにはあったように思う。幼いからこそ有効な対処法をもたず、ただただ「いやだなー」と心が沈み込むことってあったんじゃないかなと。そしてそんな嫌な思い出は今でもイカリのように心の奥底で突き刺さったままなのだ。
帰国子女コンプレックス
ぼくにもそういった心につっかえていることがたくさんあるけれど、そのうちの一つが帰国子女コンプレックスによるものだった。こちらの記事にも書いたけど、ぼくはオーストラリアに3年半も住んだのに、英語も外人も大の苦手だった。ちょっとした日本人差別?みたいなものに遭い、白人も英語も勘弁してくれと心を閉ざしてしまったのだ。
オーストラリアでの残念な海外体験を経て、日本に戻ってきた。小学校3年生のときである (上記のマラソン大会のさくらももこさんと同じ年齢である)。
当時の小学校ではということになってしまうかもしれないけれど、転校生で「オーストラリアからはるばる日本に戻って来た」とでもなると学年ではちょっとしたニュースになるレベルだった。みんな口を揃えて「えーじゃあ英語しゃべれるの?すげー!!!」と言ってくるではないか。男の子にも女の子にも、物珍しさもあってか一様に高いテンションで絡まれたことを覚えている。ぼくの机を取り囲むボーイズアンドガールズの窮屈な質問に (ぼくにとってはということだけれども) 辟易していたように思う。
そんなある日である。クラスの担当先生 (キャピキャピした女性の方だったと記憶している) がこんなことを言うではないか。
みんな来週から国際交流の授業がはじまります!アメリカ人の先生がやってきてみんなと一緒に英語をお勉強するから、楽しみにしててね♪
まずい。「うわーついに来てしまった」と思った。先生の口から放たれた快活なアナウンスメントはぼくの心を奈落の底へと突き落とした。
国際交流の授業と言うからには英語を話さないといけないんだろう。「レッツ、英語でコミュニケーション♪」みたいなものだろうだから当然といえば当然だ。ただ問題なのは担任の先生もクラスのみんなもぼくが帰国子女ということを知っていることだ。なんとなく「福原たまねぎに英語話させようぜ!」という口合わせを周りにされているような気がする。今から考えれば被害妄想だと言えなくもないが。ただきっとその授業の中でぼくは皆の前で醜態を晒すんだろうな思うと暗澹たる気持ちになった。国際交流という、いかにもポジティブでポップな授業で「ヘイッ!」とか「ワッツアップ!」とかはしゃぐアメリカ人の先生を前に沈黙する自分がいとも簡単に想像できた。いやだよーもう学校に行きたくない。
「99%の不安は思い込みで現実化しない」みたいなポジティブな考え方があることは知っているが、この不安は残念なことに見事に現実化してしまった。
いよいよ国際交流の授業が始まる。いつもと異なる授業ということもあってか、クラスの担任もみんなもどこか忙しない感じでどこかキョロキョロしている。それはまるでクラスにお父さんお母さんがぞろぞろとやって来る授業参観のよう。
アメリカ人の先生が到着したようだ。
ミナサン、コンニッチッワ!ハジメマシテ!!
と勢いよく扉を開けてクラスに入ってきた。ツルツルのスキンヘッドと赤いシャツがパンパンになるほどの見事な筋肉が印象的な人だった。黒人のマッチョな男性、背丈は180cmぐらいだろうか?年は30前後といったところだろう。なんとなく今ならボビーって呼んであげたい人だった。
先生もみんなもなぜかキャーキャー叫んでいる。ビートルズが来たんじゃないんだから勘弁してくれよ。ぼくはもうその時点で気絶しそうになっていた。あのときに真っ直ぐ下を向いていたのは、きっとぼくだけだろう。
3分ほど先生のどうでもいい (と言ったら失礼だけれど) 自己紹介とちょっとしたスピーチが終わった後、今日のお題について話そうということになった。
お題は「冬休みなにする?」というものだった。まあ冬休み前だからそうなるだろうよとクラスのみんなもさして驚いてはいなかった。そこまではいいのだけど、担任の先生が余計なことを言ってしまう。
はーい、みんなは冬休みなにするかな!?英語で言える人いるかなー?
どういう意図かは分からないがそう言った。クラスには英会話を習っているというハイソな女子もいたから、もしかしたらぼくに向けたものではなかったのかもしれない。
それでもぼくは心臓バクバクだった。やばい、これおれに来るぞ。
案の定、冬でも半袖半パンのガキンチョたちがこう囃し立ててしまった。
「おい、福原たまねぎ!お前英語喋れんだろ?いけよー!」
うわーーー。やっぱそうなるよね。知ってたよ。
分かってはいたものの、いざ追い込まれるともうどうしようもない気分になった。その時点で1年分の汗をかいてシャツはぐしょぐしょである。
クラス中の視線がこちらに集まる。しばらくの沈黙を貫いたあと、「もう仕方ない」と白旗をあげたぼくは、物音立てずに静かに立ち上がった。それでそのとき思いついたことを言った。言うしかなかったのだ。
アイ…………アイ……。
アイ、アム…ウィンターバケーション!!!!!
力んでしまったせいか、大声でそう叫ぶ。いやもうそれは絶叫に近かったといえよう。「ぼくは冬休みです」と言い放った僕を見て、ボビー(アメリカ人の先生)は「え………?」みたいな顔をしていた。あまりに僕が思い切って言ったから何か深い意味があるんじゃないかと邪推しているようにすら見えた。
担任の先生もさっきまではしゃいでるギャルみたいだったのに「は‥……?」と冷たい視線をこちらに向けてくるではないか。半袖を着たガキンチョはよく分からなかったから「すげー」と言っているやつもいる。ここは今思い出してもなんでかは分からない (笑)。
そこから先のことはもう覚えていない。ぼくは真っ白な灰になって椅子にもたれかかっていたんだろう。

コンプレックスと生きていく
あの日のことはよく覚えている。ただ実はもっと辛かったのが、その後に英会話を習っているハイソな女子から「え、福原たまねぎ英語できないじゃん。ダサ〜!」とバカにされるようになったことだ。心ないことを言われるたびに返す言葉もなかったから、いつもキリキリと歯軋りをしながら拳を固く握りしめていたと思う。あのときの悔しさがその後にアメリカに移住する原動力のなっているんじゃなかろうか。冗談のようでいて、本当にそういう部分はあるかもしれない。
海外生活が長くても英語がしゃべれない、もしくは外人が苦手という話はよく聞く。逆にいえば海外に行って本当に現地に染まって生きているという人は少数派なんじゃないかなと思う。ぼくもまだまだそんな外人・英語コンプレックスとともに生きている一人です。

そんなところかな。今日はいい音しているバーをシアトルで見つけて上機嫌です。
それではどうも。お疲れたまねぎでした!
サポートとても励みになります!またなにか刺さったらコメントや他メディア(Xなど)で引用いただけると更に喜びます。よろしくお願いします!
