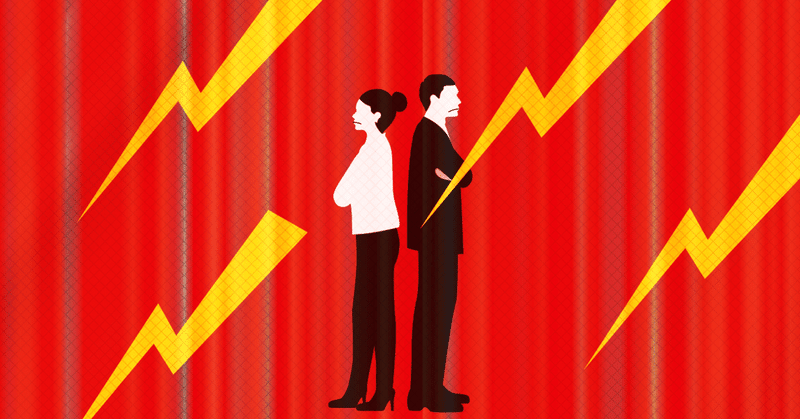
「あいつが悪い」の行き先。「わかりあえない」から、糸口が見えてくる。
「全社員の前で、社長が話しをするじゃないですか。会社の代表である、社長ですよ。普通、耳を傾けるじゃないですか?最近の若い子の傾向なんですかね、姿勢は前を向いているけど無表情で、まったく話が響いていないみたいで…」
*
こんな話を、少し前に製造業で役員を務める方から伺いました。トップに限らず、店舗、支社、リーダーの立場にある人は朝礼、総会、会議などあらゆる場面で会社の状況や方針をメンバーに向けて話す機会があると思いますが、同じように「伝わらない」「わかりあえない」ことへのもやもやを感じている人は、多いんじゃないでしょうか。
僕自身も「ああ…」とお腹が痛くなった苦い記憶がたくさんあります。
『新しい企画をチームで考えたい』『こんなイベント面白いと思うんだけど!』と会議の場で意気揚々と話し始めても、なんだか響いている実感が全然無くて。退屈なのかな?眠いのかな?って途中でジョークを交えたりしてもピクリともしない。(そもそも、おもしろい話が得意ではない)
むしろ僕が話す量が増えるたびに、会議室の空気はどんどん重たくなっていく。次第に、「自分」と「みんな」との間にクッキリとした溝が見えてくるんですよね。つらいなあ。
*
先の役員の方は、会議などの場で反応が無い状況を、「若い人の傾向」と捉えていました。「会社への帰属意識が薄い、最近の若者の特徴だ!」と。
伝わらない・わかりあえないって辛いですから、そう思いたくなるのも分かります…。
役員の方は続けてこう言っていました。
「みんな危機感がなさすぎる。このままでいいわけがない。もう少し厳しく、危機感を煽る必要があるのかもしれない」
極端に言ってしまえば、「若者(相手)側が悪い」という問題認識。
このまま危機感を煽り続けると、いったいどうなるでしょうか。伝わるかな。それとも、お互いの間にある溝が、さらに広がることになるでしょうか?
その後の展開を聞けていないのが心残りなんですが、相手がいる問題を解決するにあたって、「相手が悪い」「自分は悪くない」という前提に立つ時点で、問題の解決は難しくなってしまうように思います。
*
何事も問題を解決に導くには「問題自体の設定」がとても大切です。頭痛の原因が発熱によるものか、仕事のしすぎによる肩こりからか。問題が何かによって対処の仕方と、その後の結果は大きく変わります。
さきほどの「伝わらない」状況をみてみると、『伝える経営者が悪い』や『聞く若者が悪い』のように、どちらかが悪いと捉える時点でお互いに敵対関係も生まれかねず、問題解決は複雑さを増してしまいます。
別の見方をすると、どちらかが悪いのではなく、お互いの「間」がズレているだけ。例えば先の若手社員は、「表情を変えずにまっすぐ見つめること」が正しい話の聞き方だと思っていたかもしれない。「反応の仕方がわからない」と戸惑っていただけかもしれない。あるいは、「もっと自分たちの声を聞いて欲しい」と声にならないメッセージを発していたのかもしれない。
つまり、『お互いの前提、価値観、解釈のズレ』によって、生じている問題なんじゃないかな、ということです。
「他者と働くー」は、仕事がうまくいかなかったり、チーム内、部署間の連携がいまいちできていない...という悩む気持ちを軽くしてくれる本だったのですが、先の問題のようなお互いの間のズレや関係性によって生じる課題は『適応課題』と言われ、新しい予約システムを入れたら解決!」のように、既存の技術で解決できる『技術的問題』と対比して整理されています。
この『適応課題』の解決・解消に向かう方法として、「対話」が紹介されています。対話によってお互いのズレを確認し、認めあうことで、問題自体が「解消」されたり、解決の糸口が見つかっていくーーと。
相手が悪いと思った時点で解釈が固着して、『自分から見えている相手の姿』を疑うことができなくなあり、『お互いの間の溝に気づく』ことも難しくなってしまう。
まず対話の入口に立つことに、葛藤がつきまとうんじゃないかと思うんですが、分かってくれるだろう、分かって当然という前提を手放して、同じ組織でも、同じチームでも、「わかりあえない」という事実を前提にして考えていたほうが、精神的にも楽ですし、正しい処方箋を導きやすくなるんじゃないかなと思います。
同じ場所にいる人、近くにいる人に対してほど、少し距離を取って見つめることって難しいんですけどね。でも、無言の期待、相手に伝わっていない期待を勝手に抱いて、相手も同じ気持ちでないことにショックを受けたり、自分の思いと外れた行動にストレスを感じる。それは、自分で自分を疲れさせているようなものだなーーと、本書を通じて僕は思いました。
「あいつが悪い」と思ったとき。怒りや不満をある程度は発散(支障がないくらい)したあと、「わかりあえない」ということを思い出してみると、解決の糸口が見えてくるかもしれません。
いただいたサポートは書籍の購入代に充てさせていただきます!
