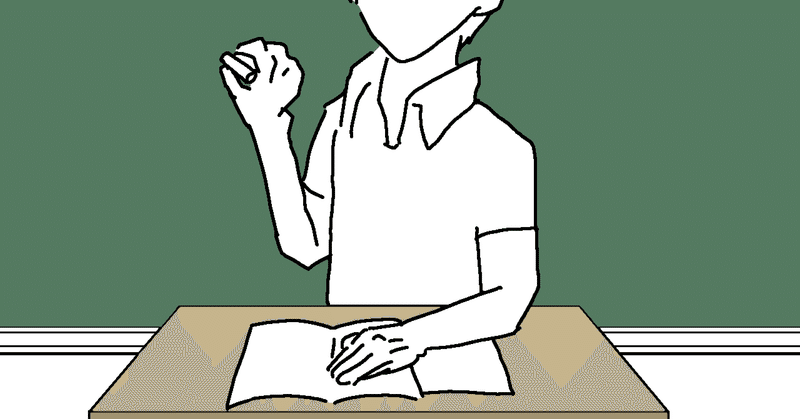
金融教育から考える本質的な学び
11月10日の日経新聞で、「金融教育を考える(上)貯蓄から投資、起点は学校 「知識に自信」米71%、日本12% リスク管理と両立促す」というタイトルの記事が掲載されました。金融教育の推進が、国を挙げての重要施策だというわけです。
同記事の一部を抜粋してみます。
政府は年内に資産所得倍増プランを策定する。個人マネーが現預金に滞留する現状を打開し、資産形成を後押しする。少額投資非課税制度(NISA)の抜本的拡充や恒久化と並んで金融教育も柱に据える。学校だけでなく、社会人も金融を学べる環境を整備する英米と比べると、日本の金融教育の取り組みは緒に就いたばかり。
金融広報中央委員会の調査によると、「金融知識に自信がある人」の割合は米国が71%なのに対し、日本は12%にすぎない。複利の計算問題の正答率では、日本は43%にとどまった。米国は72%だ。金融教育を学校などで受けた経験は日本が7%で、米国の20%に見劣りする。
金融の知識や判断力をさす金融リテラシーは英国やドイツ、フランスと比べても低い。例えば英国。カリキュラムは小学校に入学する前から組まれている。3歳から5歳ではポンドなどのお金の単位や価格、お店での支払い、銀行での貯金といった内容を学ぶ。5歳から7歳になると、銀行でのお金の使い方のほか、ニーズやウォンツといった心情についても教える。
9~11歳はクレジットカードなど日本では中学校で学ぶ内容が含まれ、さらに、経費、控除、損失、リスク、リターンなど日本の高校でも専門科目で学ぶ内容を取り扱う。貧困やギャンブルの問題についても触れる。
日本は学習指導要領を改訂し、中学生向けに2021年度から、高校生向けに22年度から金融教育をスタートした。教える教員側も人員不足で「投資は危ない」といった紋切り型のイメージを持つ教員も少なくない。社会人になっても金融を学ぶ機会はあまりない。
日本の投資比率は00年3月時点の15.7%から、20年以上経た22年3月も15.9%とほぼ横ばいで、現預金に個人マネーが滞留している。日本証券業協会によると、株や債券、投資信託に直接投資している20歳以上の日本人は成年人口の19.6%(21年10月時点)にとどまる。
「国全体として、中立的な立場から、金融経済教育の機会提供に向けた取り組みを推進するための体制を検討」。10月17日、官邸で開かれた第1回資産所得倍増分科会。資産所得倍増プランを実現させるための会議で、鈴木俊一金融相は金融教育を国家戦略に格上げするよう提言した。岸田文雄首相は鈴木金融相に対し「中立的で信頼できる助言者制度の創設」を指示した。
先日、経営の基本について学ぶ全10回シリーズの講座の中で、財務諸表をテーマにした回の講師役を担当する機会がありました。その際に改めて感じたのは、私たち働く人全般の傾向として、経営に関する他の諸テーマに比べて、財務とITのリテラシー(知識や知識の活用力)が極端に低いということです。
ITは技術の発展がすさまじく、どうしてもそれを専業や担当業務としている人とそうでない人の間で差がつきがちです。そのうえで、どんな立場の人であっても、自身の担当業務で求められる最低限のITリテラシーは高めようと、知識の習得やツールの使い方を覚えなければならないと自覚し、四苦八苦している人が大半だと思います。
一方の財務については、お金が私たちの生活に密着していて、その本質や使われ方が以前から大きく変わっているわけでもないながら、リテラシーが低いままとなっています。また、そのことについても多くの人が無自覚です。財務諸表の基本的な読み方は、それほど難しいものではありませんが、経営幹部も含めてほとんどの人が読むことができません。
お金のテーマと他のテーマでは、大きな違いがあります。それは、自分から意識的に学ばないとわかってこないということです。
・この商品を重点的に売るのが今期のテーマだと言われているが、売れ行きが悪い。お客さまのニーズからずれているのではないか。
・このチームを引っ張っていくにはどうしたらよいか。
・お客さまとのやりとりでうまくいかず、クレームを受けた。あの時どういえばよかっただろうのか。
・この目標設定は適切だったのだろうか。適切な目標設定のやり方について、目標管理の手引書に書いてあったような・・・
のように、経営戦略、マーケティング、組織、リーダーシップ、コミュニケーション、目標管理・・・経営を取り巻くテーマは様々ありますが、日常の仕事の活動の中で、自然に疑問を感じたり調べたりすることが多いものです。その過程の中で、商品開発のあり方や関係性のつくり方など、身についてくる部分も多いでしょう。
しかし、事業の投資収益性や、自社の現金での支払い能力など、お金に関することは理解を深めることにつながる自然な機会がなかなかないものです。お客さまの要望に応じて値引をするかどうか、かかった経費を精算する際に「これはお金かかりすぎかも」などのように表面的に考える機会はあります。そのうえで、それらの事象を超えて、体系的に捉えて考えることまではなかなか至らないと思います。
つまりは、自分からわざわざ学びにいかない限り、理解する機会が少ない領域、というわけです。
その観点から、義務教育の環境下でお金に関する理解を深め、成人した後にお金に関する実践力や自分からさらに学ぼうとする行動力の土台をつくっておくのは、意味があることではないかと考えます。
実際に、記事中の英米の例からは、金融に関する学びの経験の差が、意識やリテラシーの差となっているという関係性を想定することができます。
金融や投資にどのように向き合うべきなのか、次回以降続きを考えてみます。
<まとめ>
金融に関する学びの機会の有無が、金融リテラシーの差となる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
