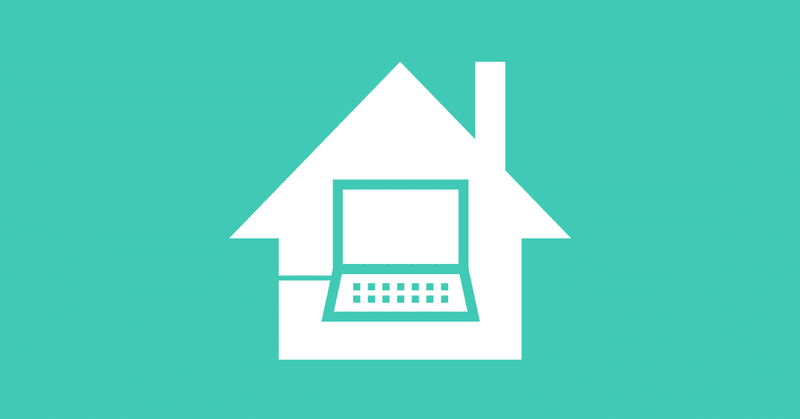
テレワークかオフィス勤務か
8月14日の日経新聞で、フィナンシャルタイムズの記事「在宅勤務、米国から再び拡大へ」が紹介されていました。テレワークは、コロナ禍で一気に広がった後に揺り戻して、オフィス勤務とテレワークのハイブリッドの中で各社が落ち着きどころを探していると言われていますが、そのことについて示唆する内容になっています。
同記事の一部を抜粋してみます。
米アマゾン・ドット・コムでは職場放棄。米スターバックスや米ウォルト・ディズニーでは要望書を提出――。これは新型コロナウイルス禍前なら耳を疑ったような会社の規定に対し、従業員が取った行動だ。その方針とは「週に最低3日は出社せよ」というもので、ディズニーは4日の出社を求めた。
柔軟に働ける新しい時代になったはずだが、筆者は企業がこれほど出社にこだわるとは思ってもみなかった。
オフィス以外で働いても必ずしも生産性が損なわれないことも分かってきた。完全なリモートワークは完全出社に比べて生産性が10%ほど低下する可能性があるものの、損失はオフィスの大幅な縮小などで穴埋めできそうだ。
在宅勤務が普及している国の特徴に関し、意外なことも見つかった。米スタンフォード大学のニコラス・ブルーム教授らは普及率を国際比較した。研究者は所得が上がるほど在宅勤務をする人の割合も増えるという傾向が世界規模で表れると予想していた。ところが所得水準ではなく言語によって大きな違いが出た。米国、英国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの英語圏では在宅勤務の普及率が平均を明らかに上回っていたのだ。非英語圏の日本やフランス、イタリアより在宅勤務の割合が高かった。
理由付けはいくつかできる。米国は住宅が広いため、北欧やアジアの狭い集合住宅より自宅で仕事をしやすいのかもしれない。中でも、米企業は従業員の働きぶりを測定・評価するのに優れているので在宅勤務を認めやすいという理由に筆者は納得した。米国の経営管理手法はまず英語圏に伝わり、それから非英語圏に広がっていくことが多い。ブルーム氏がリモートワークの割合は下がっても、次第にまた上がると考えるのはこのためだ。米スポーツ用品大手ナイキのロゴマーク「スウッシュ」のイメージだ。
同記事から3点考えてみます。ひとつは、完全なリモートワークは完全出社に比べて生産性が下がりそうだと示唆しているということです。
同記事では、完全リモートワークは生産性を10%低下させる可能性があるものの、オフィス縮小など(つまりは経費節減)でカバーできるとしていて、仕事で生み出す付加価値の量は減る可能性を暗示しています。アマゾンやディズニーなどは、そのことを経営として仮説立てているのかもしれません。
もちろん、リモートワークによって生産性が上がるかどうかは、仕事内容ややり方次第ですので、一概には言えません。そのうえで、個人の仕事のアウトプットを最終的には組織として束ね、顧客に届けるという組織活動全体で考えた時には、完全リモートワークという形態はメンバー間の協業や調整を難しくし、ロスを発生させるということなのかもしれません。
2つ目は、意外な要因(言語)が、リモートワークのやりやすさに影響を与えているということです。
日本でリモートワークのやりづらさを訴える人が、居住環境が不向きであることをやりづらさの理由に挙げることは以前から言われています。その他にも、各国の経営管理に大きな影響を与える米国の方法論が英語圏以外の言語圏には遅れて伝わってくるために、日本ではリモートワークのよりよい方法論が発展途上であることも、やりづらさの要因かもしれないというわけです。
パーパス経営、SDGs、DX、、、私たちを取り巻く経営課題としてクローズアップされる言葉やテーマは、米国に比べて周回遅れで日本へ入ってくるイメージがあります。しかし、そこには言語の壁が存在しているための必然的な結果でもあり、日本以外の非英語圏の国でも同じことが当てはまるということに、改めて気づかされます。
この点については、英語で直接情報を入手するなんらかの方法をつくる必要性を示唆しているようにも感じます。
3つ目は、完全オフィス型、完全リモート型、ハイブリッド型の場合はその割合について、ひとつの決まった答えはなさそうだということです。
仮に完全リモート型では生み出す付加価値の総量が下がるとしても、完全オフィス勤務型に戻すのが得策とは限りません。リモートワークという形態でも自身の仕事で対応可能な要素があると気づいた従業員が、完全に職場回帰を求められた場合、記事冒頭のように別のことで逆効果も想定されるためです。
今後ますます労総者数が不足していく社会環境下では、言うまでもなく多様な働き方を認め、介護や子育てなどの事情と仕事との両立を会社全体、あるいは社会全体で支援していく必要があります。
パーソル総合研究所の発表によると、2023年7月時点での正社員のテレワーク実施率は22.2%だということです。これは、コロナ禍の緊急事態宣言1回目が出た20年4月以降で最も低い値です。特に5類移行後にテレワークの減少傾向が鮮明になったということで、冒頭の米国事例の傾向は日本でも当てはまりそうです。
勤務形態に関してよりよい落としどころを見出していくことが、今後も引き続き必要となりそうです。
<まとめ>
リモートワークをテーマにした勤務形態のあり方は、各国の企業で試行錯誤中である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
