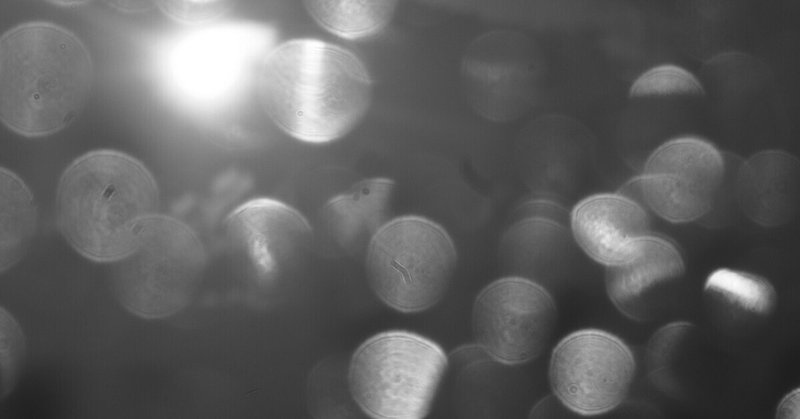
小説:イグニッションガール 【2000字ジャスト】
「低気圧ぶっころす」と、私は目が覚めると同時に呟いた。
パジャマにしているパーカーのフードで首のストレッチをしたが、頭は重いままだった。
たぶん今、頭が2トンくらいある。
私はベッドに寝たまま身体をずりずり移動し、テーブルの上のペットボトルに手を伸ばした。
しかし、あと少しのところでペットボトルは向こう側に倒れた。
私は天井を見つめたまま、「ミルクティーぶっころす」と呟いた。
空腹ではなかったけれど、頭痛薬を飲むためになにか食べようとキッチンに下りた。
「頭が痛いときはカフェインもいいんだよ」と、私の顔を見るなり母が言った。
「あたしコーヒー飲めない」
「カフェオレでもだめ?」
「1対9ぐらいなら」
「それはもはや飲まないほういいわね」
「なんか食べたい。頭痛薬飲みたい」
「ごはんにする?ライスにする?それともお・こ・め?」
「それ2万回くらい聞いた」
「ごはんにす」
「2万1回目言わないで。たらこあったっけ」
「あるよ。でもね」
「なに?」
「頭痛薬がない」
コンビニで頭痛薬を買おうと思ったが、なぜかどのコンビニでも見つからなかった。
4軒目でやっと見つけることができたので、私は自動ドアを出るなり飲んだ。
コンビニに入っていく人が私を怪訝な顔で見ていた。
そんなに変に見えたのだろうか。
ジャンキーっぽかっただろうか。
教室に入って席に着くと、今度は先生が私を怪訝な顔で見ていた。
先生がいる?
時計を見ると、すでに一時限目は始まっていた。
「あ、すいません、遅れました」
後ろでガタンと音がした。
振り返ると、笑いすぎたシオリが椅子から落ちていた。
頭痛薬を飲んで頭痛はすこし軽くなったが、今度は眠気と戦うはめになった。
いや、眠いと思うから眠いんだ。
私はまったく眠くない。ほら、こんなに起きている。春の熊みたいに起きている。私は春の熊だからあくびをひとつしたあとで木の実を探す。私は木漏れ日を浴びている木の実を見つける。つやつやした木の実はまるで宝石みたいに光を放っている。私はその皮を丁寧にはがして口に入れる。それはまるで山を食べているみたいな香りがする。そうして私は生きている。鹿が私にあいさつをする。私は鹿に木の実を剥いてあげる。鹿は嬉しそうにそれを食べる。鹿が私の名前を呼ぶ。鹿が私を起こそうとしている。
先生が私の名前を呼んでいた。
私は飛び起きて「鹿でした!」と叫んだ。
後ろでガタンと音がした。
とかくに人の世はあれだなと思う。
生きにくいだったか生きづらいだったか。
うまく世間と噛み合わないのはわかっている。
今に始まったことではない。
小さな頃からそうだったんだろうなと、今になって思う。
身長が伸びるのと比例するように、世の中との違和感も増していった。
私はときどき憂鬱になる。
生きづらいとわかったって、どうすればいいのかはわからない。
春の熊みたいにどんぐり食って寝ていたい。
昼休みになると私はどんぐりのかわりにサンドイッチを食べた。
いつものようにシオリのほうに向かって椅子に逆向きに座ると、シオリがカレーを食べていた。
「教室でカレーって、うっそだろ」
「と、思うじゃん」
「なにが?」
「いや、とくにない」
教室中がカレー臭になったので、皆はシオリにツッコミを入れた。
シオリはカレーがいかに素晴らしいかを演説した。
「ところでさぁ」とシオリが言った。
「なんであんたパーカーなの?」
「……ほんとだ」
どこかで犬が鳴いた。
帰り道で、私はシオリに言った。
「今がもうすでに生きにくいのに、あたしたちまだ子供らしいよ」
「でっけぇ子供だな」
「なんか、めんどくさいなぁ」
「生きにくいの?」
「なんか、あたしはちょっと変なのかもなって」
「あたしはあんたのこと好きだけどね」
「そう?」
「おもしろいし。たまに独特なこと言うし」
「じゃあ結婚する?」
「いいよ」
冗談のつもりだったのだけれど、私たちはどちらも黙り込んでしまった。
仕事から帰ってきた母は、私の作った唐揚げを食べながらビールを飲んだ。
「冷蔵庫に鶏肉漬けてあったから、絶対今日唐揚げだと思って」
「大人はなんでビール飲むんだろ」
「ただでさえ苦汁をなめてるのにね」
「くじゅうってなんだっけ」
「にがじると書いて、苦汁」
「ビールじゃん」
「苦汁うめー!」
母とご飯を食べたあと、私はソファーに寝ころびながら言った。
「あたし生きづらいんだ」
「そうかもね」
「知ってた?」
「小さい頃からそうだったわよ」
「完璧になりたかったけど、ぜんぜん逆の人間だ」
私がそう言うと、母は珍しく私の顔をじっと見つめた。
「あのね、たしかにあなたは完璧じゃないかもしれない」
私は頷いた。
「完璧じゃないかもしれないけど、最高なのよ。少なくとも私にとっては、あなたが産まれた瞬間からそう」
私は頭の中に光が走るのを感じた。
「わかった」と、私は言った。
私はその夜、眠る前にシオリに電話をした。
「ねぇ。今夜世界中に愛が降ってくるよ」
「そいつは最高だね」とシオリは言った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

