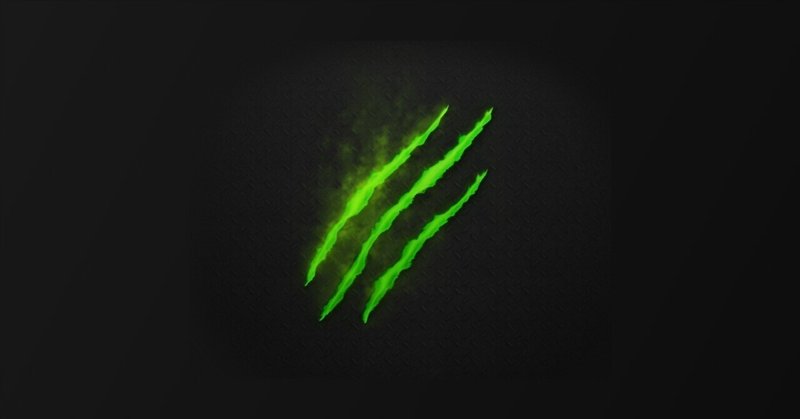
なぜ僕はその朝、モンスターを手に取ったのか。
フルスタックマーケティング株式会社の代表取締役CEO・清水優志(@fsm_shimizu)です。
企業のマーケティング活動を支援しています。
最近、十分に寝られずに朝を迎え、9時からのMTGに備えて気合を入れるか〜と思って、コンビニでモンスターエナジーを買いました。
コンビニの棚でモンスターを見つけ、手に取り、財布を出して会計しているそのとき、ふと思ったのです…。
俺、マーケティング、されてる?!
「モンスターを飲めば、元気のない朝でも乗り切れる」というのは、僕が日々の生活の中で勝手に得た認識です。
こういうのをマーケティング用語で「ブランドイメージ」と言います。
つまり、僕は「モンスター」のブランド戦略によって、元気のない朝にまんまと同商品を想起し、コンビニに立ち寄ってしまったのです。
これは、そんなモンスターを含めたエナジードリンク市場のマーケティングについて、マーケティングオタクの僕が饒舌に語るnoteです。
エナジードリンク市場はレッドブルと共に生まれた
1980年代の日本では、大正製薬の「リポビタンD」(1962年〜)と大塚製薬の「オロナミンC」(1965年〜)が、炭酸栄養ドリンクとしていずれも大ヒット商品となっていました。
来日時にその売れ行きを目の当たりにしたオーストリア人起業家のディートリヒ・マテシッツが「これは欧米でも大ヒットするのでは」と考え、1984年にタイの栄養ドリンクブランドの販売権を獲得。
改良の末、1987年に「レッドブル」として販売を始めました。

これが「エナジードリンク」の歴史のはじまりです。
そもそもエナジードリンクとは、栄養ドリンク(医薬品・医薬部外品)に含まれるような有効成分が入っていない清涼飲料水のことです。
要するに、栄養ドリンクは疲労回復や栄養補給を目的に飲むべきもの、エナジードリンクは「なんかいい感じの気分になりたいとき」に飲むもの、ってことですね。
当時は「エナジードリンク」という名称自体が存在せず、レッドブルがこの商品カテゴリを創出し、世界に広めました。
ディートリヒ・マテシッは後のインタビューで、日本でアイデアのタネを見つけたことを以下のように語っています。
きっかけは、日本の高額納税者のリストを見せてもらったことなんだ。そのなかの一人にミスター・タイショウがいた。大正製薬の上原(正吉。故人。元大正製薬会長)さんだ。その人がどういう人か友人に尋ねたら、製薬会社で、ドリンク剤『リポビタンD』をつくっているということだった。電気製品とか自動車会社のトップが高額納税者ならわかるけど、日本ではなぜドリンク剤で高額納税者リストのトップになれるか疑問に思い、リサーチした。そうしたら日本にはドリンク剤の巨大市場があることを発見した。
このように、栄養ドリンクから着想を得て生まれたエナジードリンクですが、すごい勢いで栄養ドリンクの市場を奪っています。

レッドブルという企業の特異性
実はレッドブル社は製造や流通は行わない、いわゆるファブレス企業です。
先ほど「タイの栄養ドリンクブランドの販売権を獲得」と書きましたが、工場を買収したわけではなく、あくまでも販売権を取得しただけです。
つまり、製造や流通は他の企業に委託することで、初期投資や経営リスクを下げているんですね。
(有名ファブレス企業の例)アップル / ナイキ / ユニクロ / 任天堂 / キーエンス / 無印良品 / 伊藤園 / ダイドードリンコ など
多くのファブレス企業では商品の企画・設計に強みを持つことが多いのですが、レッドブル社は創業からレッドブルのみを商品とし、そのマーケティングに多くのリソースを投じています。
創業期から現在まで、一貫して売上の3分の1を広告宣伝費に投資しているという話は有名です。だからこそ、強固なブランドイメージを形成し、それを維持し続けられるのです。
レッドブル社はスポーツイベントへの協賛など、創業間もない会社では異例のマーケティングを数多く展開し、オーストリア、ドイツ、イギリス、アメリカと次々に販路を広げ、2005年にはついに日本に上陸します。
若者にターゲットを絞ったお手本のようなマーケティング
日本のエナジードリンクの歴史も、レッドブルの上陸から始まります。
レッドブルは、類似商品であるリポDやオロCの「疲れを取る(マイナスをフラットに)」という価値ではなく、「気分を上げる(フラットをプラスに)」という価値にフォーカス。
ターゲットも「(疲れた)中高年のビジネスパーソン」ではなく「(気分を上げたい)10代後半〜20代前半の若者」としました。
このブランド戦略が功を奏し、結果的に「元気・活力を出したい」「気合を入れたい、テンションを上げたい」というシーンで、ビジネスパーソンにもよく飲まれるように。

レッドブル社はメインターゲットに商品を届けるために、大学周辺でいわゆる「レッドブルカー」を使ったサンプリングを展開しました。

特筆すべきは、レッドブル社が主要大学ごとに1名ずつ「SBM(Student Brand Manager)」という役職者を任命したこと。
彼らに販促やイベント企画・運営を任せることにより、日本の大学という狭いコミュニティにスムーズに入り込み、効率よく販促を行うことができたのです。
2000年代後半は、SNS黎明期。Mixi、Facebook、Twitterといった多くのSNSが日本で流行し始めたタイミングでもありました。
トレンドに敏感な大学生たちはこぞってSNSを使い始め、物珍しさから日常を気軽に投稿します。この波に乗るように、レッドブルのUGC(口コミ)は急増していきました。
徹夜明けの試験、6コマ連続の授業、長時間のサークル活動など、レッドブルを飲みたいシーンがたくさんある大学生にとって、レッドブルは「頑張っている自分」を発信するための言い訳にもなります。
それと同時に、自分の頑張りをサポートしてくれるパートナーのような存在ですから、UGCの質も非常に高いものでした。

2006年からはコンビニへの卸売も開始したのですが、「栄養ドリンク」ではなく「炭酸飲料」として棚取りをしたことで、目立つ場所に配架され多くの消費者の目に触れることに。
プロモーションに力を入れていたためによく売れ、サイズが小さく単価が高い「コンビニにとってぜひ取り扱いたい商品」の地位を確立し、一気に販路を拡大します。
2007年にはメインターゲットへの認知・宣伝も十分と判断したのか、マスマーケティングとして、かの有名な「翼を授ける」のテレビCMを放映開始。
そして2012年、レッドブルは171カ国以上で累計52億缶を販売し、世界で最も消費されたエナジードリンクとなりました。
モンスターという新参者の襲来
そんな2012年に日本にやってきたのが、黒船「モンスターエナジー」。
モンスターの強みは非常にシンプルで、大容量かつ低価格。
275円 / 250mlのレッドブルに対して、モンスターは200円 / 355mlで展開。
大容量のパッケージに目を引かれ、手の取りやすい価格に驚いた消費者も多いでしょう。
モンスターが非常に上手だったのが「なんかヤバいブランドがアメリカから来た」という空気づくり。
インパクト抜群のパッケージ、いかにもケミカルで体に悪そうなカラーリング、そしてレッドブル同様のラッピングカーを使ってのサンプリング。
サンプリングは365日、主要都市の大学の最寄り駅のどこかで必ずやっていたという徹底ぶりで、ターゲットに確実にリーチしていきました。

さらに、レッドブルがエクストリームスポーツのような、いわゆる「アーリーアダプター」と相性のよいスポンサードに集中していたのに対して、モンスターは音楽イベントなどのマス向けエンタメにも積極的に協賛。
レッドブルが創出した「エナジードリンク」という既存市場で、低価格・大容量を武器にして一気にマス層の認知を取り、パイを奪いました。
後発ブランドのお手本のようなポジショニングと販促活動です。
ちなみに、モンスターを日本に連れてきたのは、かのアサヒ飲料。
レッドブルの秀逸なマーケティングを踏襲しつつ、強力な販売網を駆使した販促活動が功を奏しました。
そして2019年には、エナジードリンク市場における1年間の国内販売箱数で首位を獲得。店頭には "No.1 BEST SELLING ENERGY DRINK IN JAPAN" の文字が踊りました。

今も、コンビニのエナジードリンクコーナーで幅を利かせているのはモンスターですね。
消えていった1,000以上のエナジードリンク
レッドブル・モンスターの2ブランドの急成長の裏で、数多くのエナジードリンクブランドが生まれては消えていきました。
2021年更新のブログ記事によると、少なくとも1082種類(バリエーション商品も含め)のエナジードリンクがこの世にあったそうです。

かのコカ・コーラ社も、かつて鳴り物入りで「burn」というエナジードリンクを発売しましたが、あえなく撤退。
この市場がどれだけ攻略困難だったかをうかがい知ることができます。
「burn」にも主要なエナジードリンクの要素をしっかり入れた。しかし、エナジードリンクの市場は非常に競争が激しく、1つのブランドを立てていくのに厳しい戦いを強いられたのも事実。
日本にはもともとドデカミン、デカビタC、リアルゴールド、ライフガードなどのエナジードリンクっぽい清涼飲料水も数多くありましたが、「エナジードリンク」としてのブランドイメージを獲得できている商品はなさそうです。
一方で、近年はサントリーの「ZONe」も新興エナジードリンクとして急激に人気を獲得しつつあります。
ゲームやVTuberなど、インドア趣味層をターゲットにしたマーケティングが成功しているようで、純国産エナジードリンクとしての今後に期待です。

こうして、モンスターは王座に君臨した
このように、レッドブルが開拓したエナジードリンクの市場で、後発であるモンスターは低価格・大容量を武器に急成長を遂げ、王座に君臨しました。
僕の高校時代・大学時代は、まさにレッドブルやモンスターといったエナジードリンクブームの真っ只中で、まわりにも愛飲者が多数いました。
僕はまったく関心がなく、最近になってハマり始めたレイトマジョリティなので、ブランドを選ぶ際には価格が最重要購買要因で、結果的にモンスターを手に取ります。
そんな僕の中にも「モンスターを飲めば、元気のない朝でも乗り切れる」というブランドイメージは強固に根付いています。
これは、レッドブルやモンスターの長年のマーケティング努力の賜物です。
マーケティングオタクはこんな感じで「自分はマーケティングされている…」と認識しつつも、素晴らしい商品は喜んで買います。これからもお世話になります、よろしくお願いします。
===============
もし清水に興味を持ってくださった方がいらっしゃったら、ぜひお気軽に以下のリンクより「ちょっと話してみたい」してください!案件の相談でも、キャリアの相談でも、コンテンツの書き方でも、なんでも大歓迎です!!
Twitterアカウントはこちら
https://twitter.com/fsm_shimizu
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
