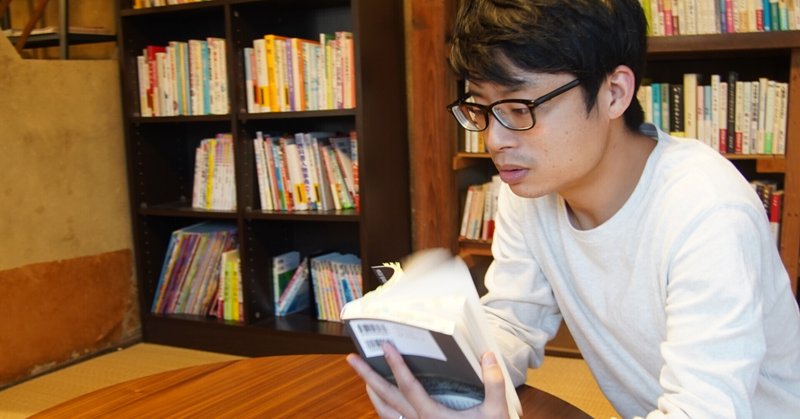
自力を鍛え、他者と生きる
TEXT BY MOMOKA YAMAGUCHI
※フリーペーパーSTAR*16号掲載記事より
学塾 誠和学舎では、成績の向上や受験勉強以外に、小中学生には生活教育や農業、社会見学などの体験活動を、中高生以上は多世代交流などのキャリア教育を通して「自ら人生を歩む力」を身に付けられるような多種多様な取り組みをしています。
今回は、教育者の視点から「自ら人生を歩む力」とはどこから生まれるのか。キャリア教育だけでない「生きる力」を向上させる塾、学塾 誠和学舎の塾長・高山和成さんにお話を伺いました。

出会いが生き方を変える
Q.誠和学舎の多様な取り組みが生まれたきっかけは何でしょうか
僕は、塾に通った経験、塾で働いた経験がなく、教育の世界に入っていくとは思っていませんでしたが、高校3年生のときに「師匠」と呼べる人と出会ったことで生き方への考えが変わっていきました。
それまでの僕は小中高と総社で人生を送り、「近いから」という理由で総社の大学を選びました。結果、自分のキャリアが狭まっていることに大学生になってから気づき、「なんとかなると思っていたけど、どうにもならないのでは」と未来へのモヤモヤとした不安を感じ始めました。
その時の師匠との出会いで得た学びは「出会いが生き方を変える」ということ、「学校教育では知ることができない多様な生き方があること」です。この多様な生き方の提案は、定義上学校教育の外じゃないと出来ないんです。生き方を模索できる場所があれば、高校生大学生になってからどのように社会に出ていくか悩む僕のような子が減るんじゃないかと思い、人生への考え方・生き方・学び方なども学べる塾を始めました。

誠和学舎の本棚には高山さんがこれまで読んできた幾つもの本が並んでいます。「学校でも読書教育はありましたが僕のために本を勧められることは無く、当時は師匠が読み初めに丁度良い本を勧めてくれました。」と高山さんは言います。
***
高校生の頃、「大学に行けばいつの間にか就職先が開け、社会人になるだろう」と思っていた高山さんに、師匠は一つ一つ疑問を投げ、本やお話を通して教えてくださったそうです。その経験は誠和学舎のコンセプト「生きる力」にも繋がると高山さんは話します。
***
自力を鍛え、他力を活かすこと
Q.「生きる力」とは何でしょうか
僕は「自力を鍛え、他力を活かすこと」だと思います。
今はお金を払い、アウトソーシングすれば自助努力なく生活できますが、そのままだと他者を鑑みず、自分勝手な考えになりがちです。「豊かに生きていく」ことを考えた時に、いかに他者と共存して生きるか。それは好きな人嫌いな人、自分のことを好きな人をぐるっと囲むでもなく、嫌いな人と線を引くでもなく、なんとなく共存するということなのだ、そういう仕組みを師匠から教わった気がします。囲んでしまうと角が立ち、線を引けば争いが生まれる…。優柔不断のどっちつかずとも言えますが、しっかり区切らないことを受け止める心持が大事なんだと思います。
また「自力を鍛えること」と「他力を活かすこと」は、両輪で考えないといけません。「自分でやる」ことも勿論大事ですが、その力を人の為に使うからこそ誰かが自分のために力を使ってくれるということがあるんじゃないかと思います。そうして一つの困難を乗り越えていけるというのがこれからの時代の共同モデル、問題解決法ではないでしょうか。
先生の役割は、子供たちにとってより良い「学びとの出会い」を演出すること
Q.自立性を持ちつつその力を誰かの為につかうことで、学びが社会に巡っていくということですね。次に、高山さんにとって「教育」とは何でしょうか。
「先人からの贈与」です。これはデジタルでもアナログでも変わりません。僕は学校の学びとは別に、師匠から生き方を教えてもらい、師匠も誰かから教えてもらっている。「先人からの贈与」は教えられた側が教える側に返す「交換」ではなく、送られてきたものを次の世代に流す「パス」です。なのでデジタルもアナログも結局「贈与」をスムーズにするための道具でしかなく、贈与するものの価値を高める為に多くの教育技術が開発され広まっていくのだと、educationの面では思います。
それとは別に子どもたちの育ちを表すgrowingの面では、メタ認知―自分の立ち位置や思考形態を知ることを伝えていきたいです。自分を俯瞰的に見る訓練をしていないと大学生になって、「自分は何者か」とすごく悩むことになりますが、自分を俯瞰して見られると自分の特性は何か、この力を他者にどうやって還元できるかと考えられるようになります。この考え方は前述の「生きる力」にも繋がってきます。だから自分は何者かという問いに苦しむ前に、自分を認知する思考法や問題解決の仕方を育てておきたいという考えがgrowingの中にはあります。
COVID-19以降デジタルによる学びの多様化は見えてきましたが、忘れてはいけないのは先生と生徒の関係性をどのように作るのかです。「先人からの贈与」は与えられる子どもからの信用がなければ成り立たず、学びの正体がまだ分かっていないという状況では、「この教えは自分のためにあるに違いない」と思ってもらわないと学びはスルーされてしまいます。この信頼は口で「信じて」と言っても駄目で、先生と生徒の関係性を子どもたちの特性に合わせて構築し、「この問題は自分の問題なんだ」と思ってもらわないと学びは始まりません。だからこそ学びとの出会い方はすごく大事で、それを演出してあげるのが先生の役割かなと思います。
***
PROFILE / KAZUNARI TAKAYAMA
高山和成
学塾 誠和学舎 塾長
6歳で総社に移住して以降、自称「総社を5日間以上離れたことがない男」として、総社市を拠点に精力的に活動。2013年から家庭教師をはじめ、2015年に学塾 誠和学舎を設立。非常勤で総社市内の小学校に勤務し、発達障がいを持つ児童や、不登校傾向の児童など、学校生活に困り感のある児童への対応も務める。その手法は、学校での教育の幅を超えた見識と発想で、多くの成果を残している。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
