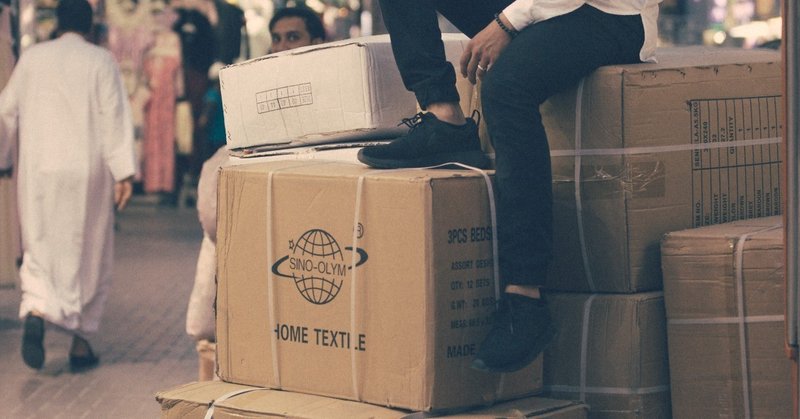
サイトリニューアルでのデータ移行作業は何をしているのか
こんにちは。TCAディビジョンの森田です。
サイトリニューアルの際、データ移行の作業を行っていたのですが、チームメンバーからすると「なぜそんなに苦戦しているのか?」という風に見えるようです。「なんとなくは理解しているけど、実際どういうところが大変なのか分からない」というのが本音のようなので、どんなことを行っているのか・何が大変なのかポイントを挙げていきます。
もし、サイトリニューアルの話があったら、参考にしていただければ幸いです。(移行作業で苦慮している方は、苦労を分かち合いましょうw)
[私について]
ブランドの持続的な成長のため、ブランドの中の人に寄り添ったセミナー・情報発信・コンサルティングを行っています。中の人のチカラこそブランドの原動力だと考えます。
私の得意なことは、今風に言うと「UXエンジニア」的なこと。モットーは「無理しないweb」、好きなものは「チョコレート(マニア)」
データ移行は、家の引越しぐらい時間や手間がかかる!

実際の家の引越しを想像してみてください。
大体どこのお家でもこんなことが起きているのではないでしょうか。
・梱包しようにも家の中でどこに何があるか把握していない
・全く同じ家具配置にしようと思っても、間取りが違うので、新しい間取りでどこに置こうか悩む
・引越し先の階段の天井が低すぎて、ベッドが階段に引っかかって運べず、廊下側からロープで釣り上げ(私の引越し実話です・・・)
とにかく時間と手間、イレギュラー対応に駆られますよね。
(ちなみに私は、引越し時にベッドが運べなかったので「数日後に釣り上げで対応しますね」と引越し業者の方に言われ、床で寝ていたりしました・・・段ボールを敷いて自宅難民していました・・・)
サイトリニューアルのデータ移行は引越しと同じようなイメージで、これを如何にスムーズに行うか、の活動をしていくことになります。
引越し先は別の家!

サイトリニューアルをする多くの場合は「システムの変更」になります。分かりやすい見た目にフォーカスしがちですが、システムが変わると何もかもが変わります。とても細かいところだと、会員登録の名前入力欄が姓・名に分かれているか一緒かなど。くっつければ良いのですが、そんなことが大量にあるので、一つ一つ丁寧に見ていく必要があります。
これも家に例えて考えるなら引越し先が全く同じ部屋はないので「前はガスだったのがIHになった」「前は4つあった電源が2つしかない」とか、何かしら変化があるはずです。
ベッドは置けるかしら?ここに置いたら朝日が眩しいかも?隣にサイドテーブルを置けるスペースあるかしら?といった、新しい生活をイメージした内容で、検証をしたり実測をすると思います。
システムにおいても、目に見えない細かな配慮や調査・検証を行っているので、時間がかかったり手間がかかったりするのです。
うまくデータ移行するために細かくチェック
旧サイトと現サイトのデータ構造を合わせていくことを「マッピング」といいます。実際のマッピングでは、例えばこんなことをチェックしています。
(ほんの一部です・・・)
・空の扱いはそもそもその項目をなしにするのか、空ですよと明示的にセットするのか
・途中から仕様を変えていたために、おかしなデータになっていないか
・id=1は北海道、と管理していたりしますが、システムによってはid=100が北海道となっていることも。このような場合、エクセル等で加工しなければならず、ものすごく時間がかかる
・csv(カンマ区切りのデータ形式)が一般的に使われますが、ダブルクオート、シングルクオート、半角カンマが混じっていると誤作動を引き起こす原因になるので、安全な状態にする
・旧システムでは商品番号をid=1,2,3・・・と扱っていて、新システムではa1,b2,c3・・・のような商品コードだったら、紐づけてやるためにひと工夫必要
・入力欄の文字数制限も異なっているので、オーバーしないか
・複数行入力できる入力欄:備考欄等があった場合、改行コードをどう扱っているかにも注意する(brタグに変換している場合もあるので)
・ダミーデータの作成、データ投入の所要時間検証
・新旧システムの入力チェックを考慮したデータレイアウト(必須、文字数、電番・メアド等の形式チェックなど)
データ移行は様々な領域のしわ寄せが集まるところ

・移行データは仕様書通りではない
・移行データも過去システムからの移行の寄せ集め
・現行システム担当者だってデータの実態わかってない
・新システムは設計真っ最中だから仕様は日々変わる
・よくわからなくたって移行の問題にされることがある
https://mhisaeda.com/archives/947
上記のように、未知の新システムと未知の現行システム(本当は知っているはずですが・・・)を相手にするため、様々な領域のしわ寄せが集まりやすく、調査・検証・検討といった作業が多くなります。
多くの場合、技術職が担当することになりがちですが、細かな作業に多少の知識差があるぐらいで、誰でも理解はできるはずです。実際業務に当たるメンバーと、同じチームメンバーで業務理解をして、チームとして対応するのが、成功する秘訣になるでしょう!
フラクタでは、ブランディングやEコマースに関する情報を発信しています。ぜひフォロー、スキをお願いいたします!!
