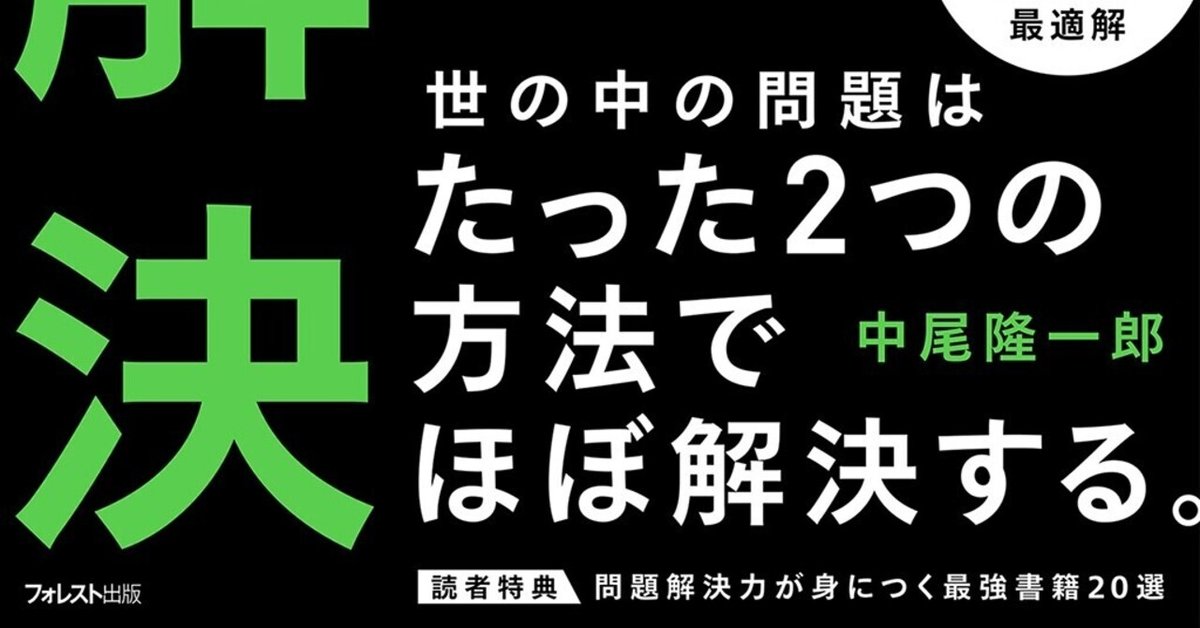
「問題」と「課題」の違いとは?
フォレスト出版編集部の寺崎です。
みなさんは「問題」と「課題」という言葉を使い分けているでしょうか?
私自身はかなりごっちゃになっていて、まったく使い分けられていません。
「○○に関しては”A”が問題だ」
「今回の企画の課題は”B”だ」
こういう言い方をする場合において、AとBには取り扱う上での厳密な違いはありません。
そこでまずは「問題」と「課題」について、国語辞書的な解釈を確認してみましょう。
問題(もんだい)
1 解答を求める問い。試験などの問い。「数学の―を解く」「入試―」
2 批判・論争・研究などの対象となる事柄。解決すべき事柄。課題。「そんな提案は―にならない」「経済―」「食糧―」
3 困った事柄。厄介な事件。「新たな―が起きる」
4 世間が関心をよせているもの。話題。「―の議員」
課題(かだい)
1 与える、または、与えられる題目や主題。「論文の―」「―図書」
2 解決しなければならない問題。果たすべき仕事。「公害対策は今日の大きな―である」「緊急―」
デジタル大辞泉(小学館)より
注目すべきは「課題」の「2 解決しなければならない問題」です。「課題」の中には「問題」が含まれているようです。つまり、「問題」に「課題」が内包されています。
そうなんです。
国語辞書的な意味レベルにおいても、「問題」と「課題」は別物だったのです。このことをビジネスのレイヤーで明確に規定しているのが、先週発売された中尾隆一郎さんの新刊『世界一シンプルな問題解決』です。以下、本書の解説を引用しつつ、問題と課題の違いについて考えてみたいと思います。
本当の「課題」を見つけるのが難しい理由
私は、戦国時代の武士にとっての刀や槍やりの腕前が、現代のビジネスパーソンにとっての「問題解決力」や「課題解決能力」にあたるのではないかと考えています。
ビジネスという戦場では「問題」があれば「解決」を求められます。まさに武士の合戦や一騎打ちのようなものです。一般的には「うまく問題解決ができる=仕事ができる」という等式が成立するので、腕に自信があるビジネスパーソンは、問題を見つけると、なんとかして解決したくなります。
それこそ、「腕の見せ所」です。
ところが、問題があるのに、それを放置した方がよい、つまり解決しない方がよいケースも少なくないのです。不思議ですね。
それはどのような場合でしょうか?
具体的な事例を紹介する前に、まずは「問題」と「課題」の違いについて整理をしたいと思います。
「問題」とは何で、「課題」とは何か。これには諸説があります。
問題解決、課題解決というように、同じ意味で使っているケースも多いのですが、大事な点は、この2つを明確に使い分けることです。
「問題解決ができる=デキるビジネスパーソン」という構図は、誰もが否定しないものではないかと普通は思います。自分自身もビジネスシーンにおけるあらゆる問題をばっさばさと解決していく人がすごいというイメージがあります。
ところが、「問題があるのに、それを放置した方がよい、つまり解決しない方がよいケースも少なくない」というのです。
いったいどういうことでしょうか?
「問題」と「課題」の決定的な違い
「問題」は、現在起きているよくないことや、気になること、もやもやしていることです。
一方の「課題」は、将来に到達したい「ゴール」や「あるべき姿= To Be」と、現状このまま進捗した場合にその将来に到達できるであろうポイントとのギャップです。
つまり、「問題」は現状の話です。
一方、「課題」は未来とのギャップと使い分けています。
私は、「問題」が発覚した際に、それが単なる「問題」なのか、未来にも影響がある「課題」なのか判断してから、解決するかどうかを判断する習慣を持っています。
それを「問題の課題化」と呼んでいます。
「課題」は解決すべきだけれども、「問題」は解決せずに放置していいのです。
ところが、この「問題の課題化」という整理の仕方を知らない人は、「問題」が起きると、次々に解決してしまいます。問題を片っぱしから解決して満足しているケースが多く見受けられます。
このことが、本来解決すべき「課題」を見つけるのを難しくしているのです。
なるほどです。問題は現在のことであり、課題は「あるべき目標」と「現状」とのギャップ。わかりやすく図で示すとこんな感じです。

本書ではこの「問題の課題化」について、次のような事例で具体的に解説されています。
この問題は「課題」となりえるのか?
これは私の失敗事例です。
10ほどの事業部がある企業でのことです。
当時、それぞれの事業部では個別にアルバイトの募集をしていました。事業部ごとに仕事の繁閑があるので、ある期間だけアルバイトを募集することが多かったのですが、そのタイミングは事業部ごとにまちまちでした。
各事業部でそれぞれアルバイト募集をし、該当期間が終了すると雇用契約を終了させていました。結果、ある部署でアルバイトを必要としているタイミングで、ほかの部署ではアルバイトの契約が終了するという事案が多数発生していたのです。
実際、他の部署で雇用契約を終了した人が、別の部署のアルバイトに再度応募するケースもありました。
■非効率な採用活動という「問題」を「課題化」すべきか?
私はこのような採用活動の非効率が「問題」だと考えました。
その都度かかる採用コストも教育コストももったいない。
問題解決策として、ある事業部で契約が終了するアルバイトの人たちに、新たに募集する事業部を紹介できればよいと考えたのです。
一度どこかの事業部で働いているので、組織文化や風土も分かっています。さらに求人コストや育成コストも削減できるはずです。
アルバイトする側にとっても、応募の手間が削減できるうえに、継続して就業できるので喜ばれるのではないかと考えました。
つまり、双方とも効率が上がるはずだという考えでした。具体的には、アルバイトの人たちのデータベース(DB)を作成して管理するというアイデアでした。
そして上司に意気揚々と提案したところ、こう言われたのです。
「おそらく、事業側も応募側もコストや手間が合わないと思う。1つの問題を解決すると、新たな問題が発生する。その解決コスト分が抜けているよ」
そこで、上司と一緒にその場でフェルミ推定(いくつかの手がかりを元に論理的に推論)したところ、マッチングに必要な情報をDBに取込み、それを更新・維持運営するコストが抜け落ちていました。それらを費用に加えると、確かにコストメリットはほぼありませんでした。
応募者にとっても、情報を登録し、更新する手間を考えるとメリットは限定的だと分かりました。まさに、目の前の問題(採用コスト・育成コスト削減)に目が行き過ぎて、他のコスト(DB作成・維持管理コストなど)が発生することが抜け落ちていたのです。
当然、実現には至りませんでした。目の前にある「問題」をすぐに解決するのではなく、もっと高い視点で、経営全体のコストという観点で「課題化」し、「この問題には対応しない」という判断をすべきなのです。
同様の事例は枚挙にいとまがありません。例えば、次のような事例です。
◎今期の目標達成のために、いたずらに顧客の見積もり金額を低くする。
◎決裁を取るために、見かけの投資対効果をよくする。
◎声の大きな人を説得するのが面倒なので、とりあえず対応する。
◎仕事を任された際に、全体像を把握せずに着手しやすいところから対応する。
◎値段の安さだけで、商品やサービスを選ぶ。
◎同業他社の値下げに追随して、条件反射的に値下げする。
前述したように、「問題」は現在起きているよくないことや、気になること、もやもやしていることです。
一方の「課題」は、将来に到達したい「ゴール」や「あるべき姿= To Be」と、現状このまま進捗した場合にその将来に到達できるであろうポイントとのギャップです。
目の前にある気になることが「これは単なる問題ではないか?」という視点を持つことが重要なのです。

いかがでしょうか。
目の前の「問題」をただ単に「問題だから今すぐ解決すべきだ」とするのではなく、まずはその「問題」が「解決すべき課題」なのかを吟味する。
ひとつの問題を解決したと思ったら、新たな問題が発生して、にっちもさっちもいかなくなったなんて経験は、誰しも心当たりがあるのではないでしょうか?
かといって、問題を先送りすればいいというわけではありません。
「解決してはいけない問題がある。たしかにそれは理解したけど、じゃあ、その解決すべき課題ってやつはどうやって特定するの?」
そうですよね。
本書『世界一シンプルな問題解決』(中尾隆一郎・著)はその部分の解説にかなりのページ数を割いています。なぜならば、「問題の課題化」のステップがあらゆる問題解決においてもっとも重要だからです。
その方法論についてはまた日を改めてご紹介したいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

