
【ドヤ顔】読む本は心が決める
どうも、主任やまもです。
幼稚園教諭をしたり、大学で講義をしたり、主任やまもの園内研修室を運営したりしています。
読みたい本があります。やりたいことがあります。
今日はそんなお話です。
積んである本はあるけれど
電子書籍kindleを使用しています。
kindle paperwhiteです。こちら。
セール中に買ったので1万円しなかったと思います。
まあ本体をおすすめしたい記事ではないんです。
kindleは日替わりセールがあり、いろいろな本が3冊ずつ紹介されます。
「お、読みたかったやつだ」なんてこともよくありますし、
「読んでみたくなっちゃった」なんてこともあります。
Amazonの思うつぼですね。
一方で、息子のこども園には園長の本棚があります。
定期的に入れ替えがあり、そこにも読みたい本がずらり。
そうなるとどうなるか。
そうです。本が山ほどになります。
「あれも読んでない。これも読んでない」となります。
ですが、山ほどの本に囲まれて気付くことがありました。
本当に読みたい本はとにかく読む。手が伸びるから。です。
意識では「あれも読みたい。これも読みたい」と手を出しますが、本当の本当に読みたい本は心が決めてくれます。
今週末に読むと決めた本
今週末はこの本を読む、と決めた本があります。
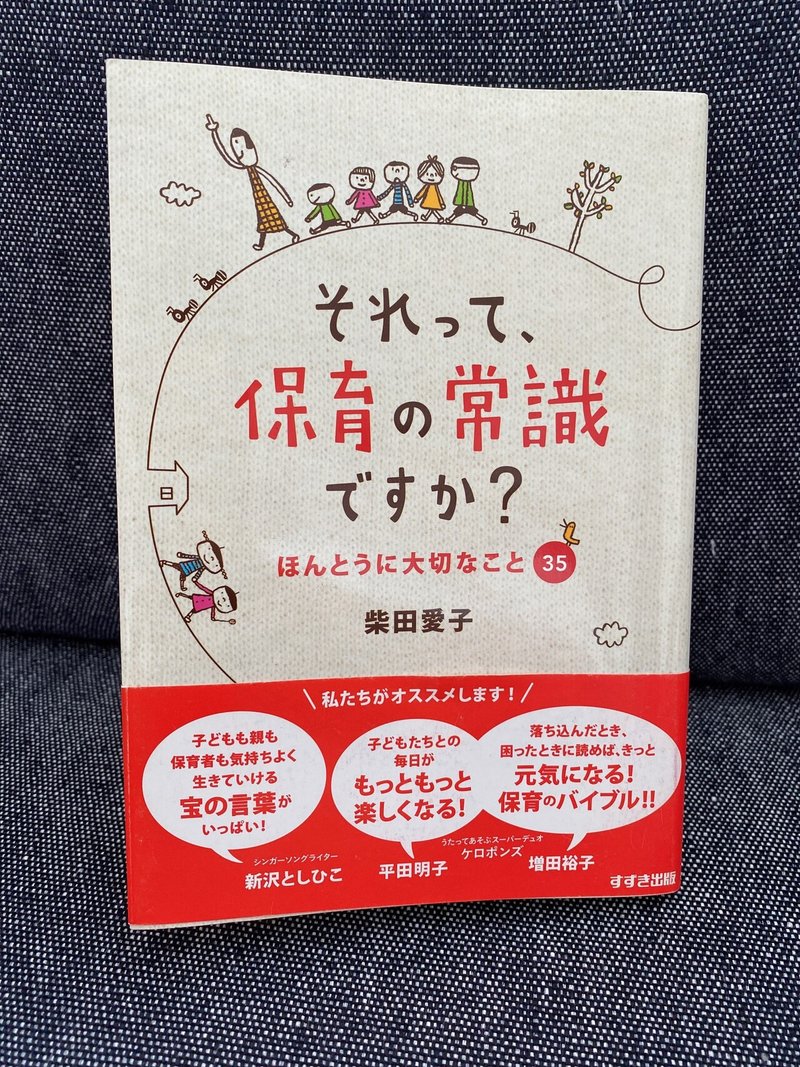
こちらです。
息子のこども園の園長先生の本です。
先日まで見ていた「りんごの木夏季セミナー」の講師であり、りんごの木の代表です。
柴田さんの子どもとの生活の中からのエピソードと気づきと考え方が書かれた本です。ハウツー本ではなく、考えされられる本です。
これを読みます。心が決めました。
というかもう半分読み終えたのです。
だから更新が遅れています。すみません。
内容としては、
「こういう事例ってあるよね。どう考えてどう対応している?私はね…」
といった感じです。
例えば、あめやおもちゃを園に持ってくる子ども。
「はいダメー」と即答する保育者は多いはずです。
が、子どもの心まで考えるとどう?ということです。
持ってくることを肯定するわけでも推奨するわけでもないです。
もっと素直に、その時の子どもは何を思っているかを考える。
こういうスタンスで子どもを語れる保育者に私は懐きます。
先輩でも後輩でも、とにかく懐きます。しつこく懐きます。
「とは言ってもね」「周りの子どもの手前、許すわけには」
という保育者には懐きません。言ってることは分かります。
最終的にはそこに話が行き着くこともあります。
ですが。子どもの理解の真髄は、その結論の前ですよね?
と私は思うわけです。
今日の夜か明日の朝にやること
話は変わり、保育雑誌を年間購読しています。
学研の「ほいくあっぷ」です。こちら。
保育者の中では「保育の質ってなんだろう?」と永遠のテーマみたいになっていますよね。
汐見先生は「保育の質ってなんだろう?私の保育はこれでいいのか?と思い続けることが保育の質」と話されているのをお聞きしました。
「そうだな」と思いますし、「も、もっと具体的に」とも思います。
そんな保育の質ですが、ほいくあっぷは「保育の質につながるワンテーマ・マガジン」と詠われています。やりますね。
たしかによくある保育雑誌のような「今月の壁面」みたいな製作のアイディアページはありません。運動遊びの紹介ページもありません。
現場の保育者にとっては「なら要らん!」と言われそうですが、私は保育雑誌のそこじゃないところが好きだったので、読んでいます。
それで、ほいくあっぷの紹介動画を作りたいんです。
とりあえず一本つくる。面白くなかったらやめる。です。
面白いかどうかは、私がです。
作って面白ければ視聴回数が一桁でもやります。
まずはやってみないと始まらない。
まとめ
というわけで、この週末も面白がって過ごしています。
妻が2回目のワクチンを打ったので、明日は家事で終わるかもしれないですが、それはそれで。
みなさんはいかがお過ごしですか?
素敵な週末をお過ごしください。
――――――――――――――――――――――――――――――――――
【平日更新】声のブログ(stand.FM)はこちら
【毎日更新】主任やまものTwitterはこちら
――――――――――――――――――――――――――――――――――
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
