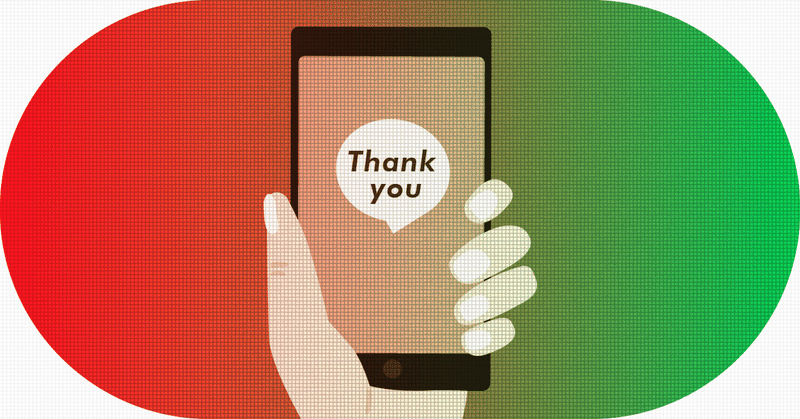
【勝手な提言】公教育と連携した子ども用のSNSを作ったらいい
こんにちは、飛び亀です。
インターネットが普及し始めてから二十余年。
ことSNSに関しては、大人よりも子どもたちの方が使いこなす日本社会となりました。
しかし、インターネット上で生の人間同士が関わることにより、多くの問題が日々引き起こされています。デマ・個人情報流出・いじめ・中傷・炎上・権利問題・詐欺・性被害・薬物・ゲーム依存 etc……
特に、子どもたちがこうした問題・犯罪の被害者・加害者になっていることが危惧されています。そのため、学校や家庭での情報教育(メディアリテラシー教育)と、逆に情報統制(年齢制限・ペアレンタルコントロール)の必要性が声高に叫ばれる世の中です。
これら教育の立場と統制の立場は、何かとぶつかり合ってしまいがちです。ただ僕は、双方の考え方が必要になってくると思います。
※以下小言
というか、教育において統制は必要です。原野に放り出されて一点の宝石を見つけられるような一握りの天才だけを育てることは教育とは呼びません。1平米の砂場に埋めた宝石を探させるのが教育です。勝手に育つ奴に任せるのではなく、全員が育つようにするのが教育です。つまり環境整備という統制が教育においては必要です。
インターネット上の問題を減らしていくためには、どうしたってユーザーのリテラシー教育が必要です。特に子どもたちを守るためには、子どもたち自身が学ばなければいけません。しかしそれには、机上の講義では足りません。実践=インターネット上で本物の他者とコミュニケーションをとる経験がいります。
でも、いきなりTwitterで炎上しながらリテラシーを学ぶのでは辛すぎます。だったら、統制された環境で教育を受けられたらいいじゃない。
そこで、思いついた理想があります。
公教育と連携した小中学生のためのSNS群を作るのです。
必要な制度・システム
1.日本じゅう全ての小中学生にアカウントを付与する
日本の公教育は批判の矢面に立つことが多いですが、大半の国民に影響を及ぼせるほどの安定したシステムをもっています。
(やはり世の中を変えるなら公教育に力を入れることが一番です。公教育は良くも悪くもそういうものです。)
つまり学校で全小中学生にIDとパスワードを配り、学校でオリエンテーションを行うSNSを作るのです。
というか、そうしないとTwitterやインスタに勝てません。
肝心の子どもたちが使わなければ、新しいSNSを作る意味がありません。
ああ、全小中学生と言いましたが、年齢は要検討ですね。
小さい子たちがスマホで遊んでいる現実を考えると、個人的には遅くとも小3,4から初めていいんじゃないかと思いますが……たいていこういうのって高学年からになるよね。
2.半匿名であること
まあ大抵の子は友達同士でアカウントを明かし合うことになるでしょうが、あくまでもシステムとしては半匿名がベストでしょう。
半匿名というのは、ここでは「ハンドルネーム+固定ID」での投稿を原則とするという意味です。
本名登録では「SNSでは覚悟なく個人情報を明かさないほうがいい」という最も大切なリテラシーを学ぶことができません。
一方、5ちゃんのように匿名性があまりに強すぎると発言への責任感が持ちづらく、自制も効きづらくなるでしょう(僕もそうだし)。かといって強制的な固定ハンドルネームでは自由度が低すぎるので、名前とは別の固定IDを付与・常時表示するのが良いかなと思います。
一応、情報保護の観点から、この固定IDとログインIDとは異なる方が良いでしょう。ログインIDは学校で最初に配られるものなので、たぶん紙に書いてあります。物理的に見られたログインIDから個人を同定されては、あまりに甘々セキュリティになので。
そうそう、最初のハンドルネームはオリエンテーションの中で、つまり学校で決めるとか、宿題として保護者と一緒に考えるとか、そういうのもありかもしれませんね。特に低学年から始めるなら、子どもに任せっきりじゃほぼ本名登録みたいになっちゃうでしょうし。
ともすれば、「あだ名禁止」みたいな謎校則も消せるかもしれませんね。
3.学校の管理下におかないこと・それなりに自由であること
これが非常に重要なことです。
公教育と連携、あるいは公教育主導となると、先生が管理するとか検閲するみたいな話になりかねません。ありえません。
そんなものはSNSでもインターネットでもありませんから、何のリテラシー教育にもなりません。というか先と同様、そんなSNSを学校に勧められても誰も使わなくなります。みんなインスタします。
学校が管理してはいけません。むしろ学校側は中を見てはいけません。
子どもたちが表現したいことを自由に表現できなくなります。
SNSとは何かを学ばせたいのですから、SNSらしくそれなりの自由がなければ意味がないのです。
ただ、これは確かに難しいところです。
当然野放しにしていいわけでもありません。野放しにするならホンモノのTwitterと変わりません。自由を尊重し、しかし毅然と管理できる第三者が必要になるのです。
この管理部分をどうするかという点において、いくつか重要なことがあります。
4.明確な投稿ルールがあること
まず、きっちり線引きされたルールを制定し、子どもたちにも分かりやすく明文化・視覚化することです。この部分は学校教育でオリエンテーションしても良いかもしれません。
このことによって、管理者側がルール違反に対してのみ明確な対応を取れるようになります。そしてもうひとつ、何より利用者=子どもたち自身の自治が利きます。
インターネット上において、「自治」はまた様々な問題を呼ぶことが多いですが、それも勉強ですし、一線を超えないための自浄作用にはなるでしょう。
そしてもう1つ、管理のしやすさと子どもたち側の使いやすさを両立する案が次項です。
5.ジャンルごとに板を分けたSNSにすること
Twitterとかインスタとかが非常に問題を大きくしやすい原因の1つには、世界に・世間に広がりすぎていることがあると思います。初心者にはオープン過ぎるのです。
インターネットの世界に足を踏み入れる当初は、もう少しクローズなコミュニティでの交流から始めるのが良いと僕は思っています。
(もちろんインターネット上である限り、そこは常に全世界に開かれています。しかし、近年はインターネット上でも「人の多い空間」と「人の少ない空間」という概念が成立するようになってきたと思います。)
そこで、5ちゃんのようなジャンルごとの板を作るのが良いと思います。
それぞれ別板の投稿は一切表示されない、それなりに閉じたコミュニティです。
これによって、ひとりひとりのユーザー(子どもたち)はまず興味関心のあるコミュニティに入ってコミュニケーションを始めることができます。タグ検索してフォローして話しかける「対個人」スタートが必要な現代のSNSよりもハードルは低いのではないでしょうか(現に僕はツイッター上で同じ趣味の人見つけても話しかけられないコミュ障です)。
それに、各板ごとに管理側の業務も分担できます。というか「管理人」制度なんて、そういう形じゃなきゃ成り立たないんじゃないでしょうかね。
ただ、疑似Twitter・疑似インスタなノージャンルオープン板も用意しておいて、中学生以上は利用可能とかもアリかもしれません。
6.年齢を決めて強制的に卒業させること
今回提案している「子どもたちのためのSNS」は、子どもたちが安全にリテラシーを学び、経験するためという目的のものです。
これは悩みどころですが、あくまで子どもにとって安全な場であるために、僕は「コミュニティから大人は排除する」しかないのでは、と思っています。今のところ。
15歳の3月末になったらアカウントが失効する。
ここは強制的なシステムが必要かと思いました。
優しい大人をたくさん見てきましたが、子どもを餌にするような大人がいることもまた事実なのです。
投稿可能な唯一の大人として管理者がいればいいのかな、と思っています。
7.オフ会は専用板で
最後に、僕は人見知りなので本当に一度も参加したことがないオフ会について。
ネット上の他者との出会いにおいて、オフ会に大きな意義があることは間違いないです。そして同時に、大きなリスクを抱えていることも間違いない。
オンライン上の友人に現実で会いに行くのは危険だから禁止。
厳しくすればそんなルールになるでしょうが、せっかく学びのSNSなのにそれはもったいない気がします。
そういうわけで折衷案としては、オフ会専門の板を作って、それなりに厳しい管理の目とか保護者通知とかを必須とするシステムの中で話すようにするのがいいんじゃないかと思います。
やっぱり禁止にされたことって、裏で行われるようになるんですよ。それが一番怖い。ちゃんと表で堂々とできるようにした方がいい。
一人で勝手に誰にも知られずオフ会に行かないとか、そういうことさえ守ればOKにする。そういうシステムにする。これが子どもたちの安全を守るということだと思います。
その代わり、他の板でオフ会の予定を詰めたりすることは禁止です。
提案の背景
以上が、「子ども用SNS」について思いついたことをまとめた備忘録です。穴だらけなのでいずれ追記するかもしれません。
何にせよ理想も理想だし、大変な金と人を動かさねば決してできない制度・システムです。でも、これが本当に実現できれば、子どもたちを取り巻くネット・SNS環境は大幅に改善されるはずだと思っています。
ところで、今回の僕の提案が何をもとにして生まれてきたか分かるでしょうか。それは、僕が初めてインターネットに接続した時代の思い出です。
当時はSNSという言葉も聞かれず、ネット上で他者と関わるのは主にBBS=電子掲示板やチャットツール、メッセンジャーツールでした。
様々なジャンルの個人サイトがあり、そこに設置されたBBSやチャットで趣味を同じくする人たちと会話する時代。「はじめまして」とスレッドを立てれば、そのBBSの住人(常連さん)から暖かく迎え入れられる。自分勝手な発言もあるし、荒らしもいるけれど、それは管理人さんを中心に対処され、平和が戻る。
あの時代のインターネット・コミュニティは非常にクローズであって、また距離感も自分で調節しやすいものでした。大人たちは優しく小坊や中坊の書き込みを見守ってくれることが多かったのではないかと勝手に思っています。
そして、互いに守るべきルールとマナーの共有ができていたように思います。というか、いわゆるネチケットというやつが色々なところで明文化されていました。もちろん守らない人が多数いたからこそ生まれたネチケットではありますが、当時は誰しも何らかのネチケット・ネットマナーサイトを読んだのではないでしょうか。
今のSNS時代において、こういうまとまったマナーサイトに一度は目を通しておこうみたいな習慣残ってるんでしょうか。
まあ当時もマナーやルールには賛否両論ありましたし、Twitterだけ見ても色んなマナーが乱立していますから、何を信ずればいいのか分からないでしょうね。
↑自記事
そういうわけで、ルールは分かりやすく明文化したほうが良いということを先述したのでした。ちゃんと書いてあれば小中学生の8割は守るよ。
とにかく、あの個人サイト時代にインターネットデビューできたことを、僕は幸せだと思っています(当時中学生)。そして今の難易度の高いSNS時代にデビューしていく子どもたちを、正直ちょっと可哀想だと思っています。
子どもたちには、もうちょっと安心できて簡単で小さなステップからインターネット体験を始めてほしい。
そういう意図の記事でございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
