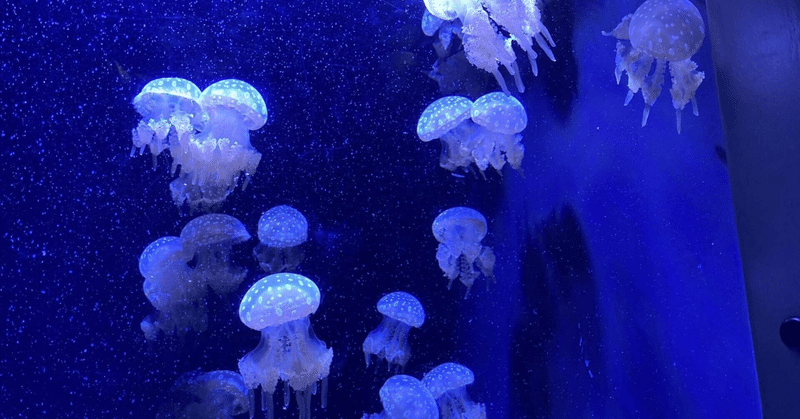
モノクロームの、さがしもの等。
見上げると、木製のレリーフが天井にアーチのように張り巡らされていた。それに、洞窟。
白い砂壁がくりぬかれたようで、わたしは、ここにいるとき、一度だって、行ったこともない異国の地をおもって、隣で発券を終えて順番をまっている恋人同士の他愛もない会話を、耳で変換して、聞いていた。スペイン語とか、ドイツ語とか。
リュックは、でかくて、荷物をいれると四角くかくばりふくらむ。
バイトから帰るときに、狭い通路を通るとき、グラスや酒のストックや、ガスコンロ、壊れやすいものばかりが並んでいるから、前に抱えるように持っていたら、「おっきな赤ちゃん抱えて、どこいくのーお疲れさん」と、見送られたから、でた瞬間、ぼんぼりみたいに満開で密集した桜の花が商店街に満開で、来るときもあったのに、ずっと咲いて、少しずつ散っていったのに、わたしは、一度も気に留めようとしていなかったことに気が付く。
まったく。ただの、ぼんぼり桜。ピンク色の、春のぼんぼり。
せっかく、なんて言うと、興ざめる、でも、わたしは言いたい。
昨日は、家族ででかけるめずらしい一日だったのに、やっぱ、朝から小石も清掃されているはずなのに、躓く、出かける時間が、遅延し、皮膚科の予定がリスケになり、怪訝な時間と表情がすぎて、幸せが膝こぞに、はさまったり、リンパに乗って流れたり、ときどき、誰かが悲しそうに、うつむいた。
それでも、わたしたちは、目的の場所まで、キャリーケースをひいた。旅に出る理由がないから、ここに押しとどめられているというのに。
買ったばかりの、白いキャリーケースを現地学習の友達みたいにひいて、地下鉄にのり、おりて、なお歩く。
風が強い。
札幌では有名なレストランのバイキングを予約していたので、時間前につき、そのころには少しだけ華やいだ家族の顔に、わたしは頭痛を誤魔化しながら、笑った。
最近、思想とかはなく体調体質の関係で肉を食べないようにしているんだけど、家族は目の前で焼いてくれるタイプのサーロインステーキに何回も並んでいた。
そのあと、些細なことで、また、朝の時間がさかさにかき回されたから、静かに帰宅する。
急いで用意など進めて、すぐにバイトの時間。
鼓舞するものも、持ち合わせないまま、そもそも、駒が留守だった――外に飛び出す。風は収まっている。
目的のために、外出することしかないから、歯車の上で、遊んでるみたい。
死ぬほど緊張して、それでも死なないで、致命傷も追わないで、生きながらえて、酒を混ぜて、ビールの泡の量を叱られたり、目配せされたり、業務を終える。土曜なのに、混雑はなく、わたしの容量のなさ、要領の悪さだけが、離脱して、わたしの表面を覆う。どうして、うまくいかないことをこんなに嘆き、かわすことができないんだろう。居酒屋なんだから、明るく、ほがらかに接客する。わたしは、うわずっているだろうか。糞まじめで、不適合な人材だろうか。なんて、ずっと考えて、腹の中にみずから錐をつきたて、ねじこむ。
カウンターの内側にたつ。
風が強い。また、ぶり返しだ。
外に、わたしが、せいのびして、六時にだしたくすんだ赤い暖簾が、風になびいて、まるで、少女の足が、走って逃げだしているようなループに見えた。
透かしガラスの向こうに、桜の木の影が揺れた。ほんとうに、癪だ。美しいだけでもてはやされる、咲いただけなのに。今日だって、桜のアイスがあったけど、桜の味なんてしなかったのに。
花びらが、時々散る。雪、雪のようにも見えた。冷たくもないだろう、しっとりと、薄くて、やぶれやすいだろう。
ほんとうは、こっから見える景色なんて、桜からしたら、わたしの荒んだ表情なんて、ぼうっと光る薄暗い店内のわたしになんて、あきれるくらい、興味もない。
走って、日記を書くために、避難する。いつものファミレスで、コーヒーを飲む。土曜の喧噪のなか、番号札を引く。
文章に救われたかった。
後ろの席に、信じられないことに、深夜のファミレスに、小学生くらいの家族連れが座っていた。ブロッコリーが嫌いだから、よけようとする子供に、『ブロッコリー戦争はもういい加減にやめてよ』と、母親らしき声が叫ぶ。
わたしは、よい母親なのだろうか。コーヒを飲み込む。
うちに、帰らなきゃ、そう、ばねみたいに。結わえつけられているから、帰らなきゃならない。
それなのに、体は動かない。ここに、ずっと、座って、おもいつくまま、言葉をつづりたい。安心して眠りたい。わたしは、よい母親なのか、母親になってよかったのか。
満ち足りるように、歌って、眠るように踊って、黙るように愛して、傷つけるように、沈黙したい。錯覚しながら、生き延びたい。
いったい、あんたは、なんなんだ。
なんのために、生まれてきたんだ。
文章を書くことで、心の平静を保っている、だろう、そうだろう?でなければ、わたしは、とっくに狂っていて、喪失の当事者になっているだろう。
走って、戻る。
中央分離帯を越えて。車は、びたいちもん、通ってない。
血の気のない、夜の道路、記憶の瘡蓋とか、夢とか、水分とか、失って、寝入りばな、蛍光灯で明るい、居間の光をたよりに、寝床にあった、ハン・ガンの“すべての、白いものたちの”を、恐る恐る開いた。
書き出しは、こうやってはじまる。
白いものについて書こうと決めた。春。そのとき私が最初にやったのは
、目録を作ることだった。
見当違いでもなかった。おおむね、わたしのこの作品に対する、向き合い方は、なんて思って、薄目で、読んだ。
はくし。
目録のなかに、でてくる言葉だった。
白紙。
それは、まさに、わたしの小説の中で、考えていた言葉そのもので、老いていくのを、白紙に戻ろうとする、と結び付けて表現したかったものだ。
鼻をすすりながら、数ページ読んで、眠った。
白紙に、もどろう。
そう思って、眠った、今では、きっと、わたしも、白紙で、ぜんぶ、白紙で。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
