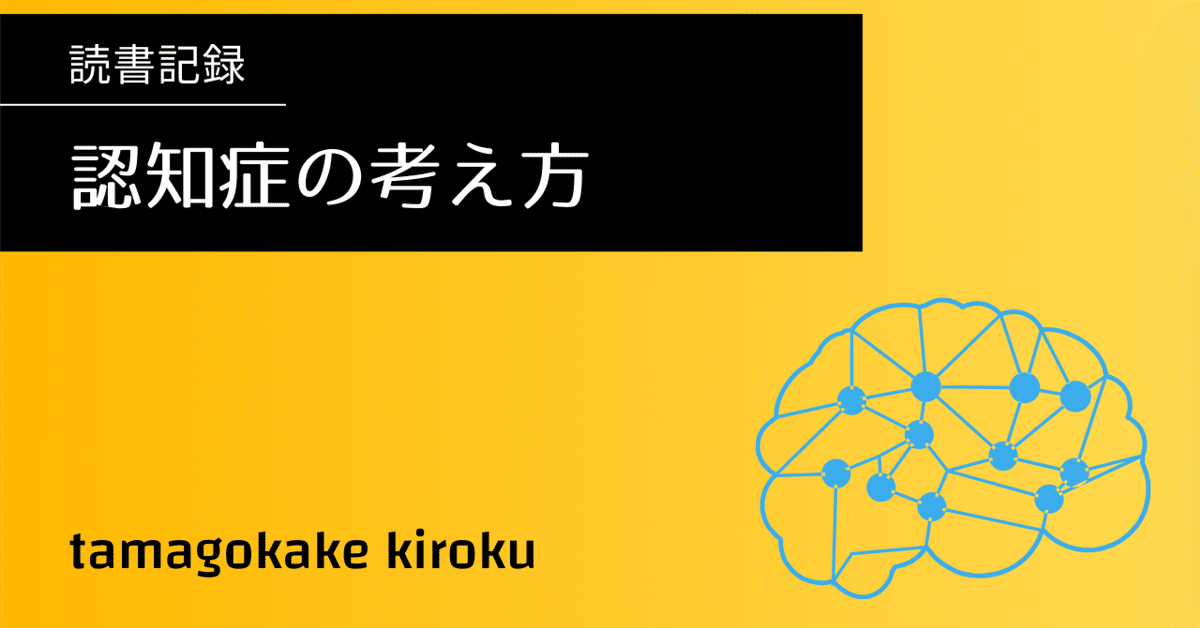
認知症との共生:リハビリテーションの重要性
こんにちは!!久しぶりの投稿です。
少しずつフォロワーの人数も増えてきて嬉しい限りです!!
世の中のためになれるように少しずつ歩みを進めております。
さて,本日は認知症との共生についてリハビリテーションの重要性の観点
から考えていきたいと思います。
内容については,ビックテーマであるため,薬物療法と非薬物療法に絞って
お伝えできればと考えています。
認知症とは??
このような当たり前の見出しをつけたことには、理由があります。この記事を読んで頂いている皆さんは認知症とは??と尋ねられたら答えることができますか??認知症や軽度認知障害(MCI)に対する作業療法を専門的に取り扱っているtamagokakegohanも自信をもって確定的な定義をつけることは難しいです。
一般的に認知症の定義は、「成年期以降に,記憶や言語,知覚,思考などに関する脳機能の低下が起こり、日常生活に支障をきたすようになった状態」と指すといわれています。つまり正常な老化とは逸脱した認知機能の低下が生じている状態とも解釈ができます。でもね,世の中には認知機能が低下していても認知症と診断を受けている高齢者は意外にも少なく,地域社会の中で「あの人認知症があるのかな?」程度で認知症は世の中が作り出した病気とも言われているんですよね。詳しくは以下↓の本に記載があります。
認知症の病理と薬物療法:危険性
認知症の治療には、認知症の進行を遅らせる薬物療法が代表的です。認知症が進行する脳の過程が少しずつ明らかになってきていることもあり、「アリセプト」、「レミニール」、「イクセロンパッチ」、「メマリー」と呼ばれる薬物治療が一定の有効性を担保している。しかし、これらの薬物は、認知症の根治療法にはならず、あくまでも症状を抑制するに留まっている。つまり、認知症の進行過程は我々が認識しているよりも複雑かつすべてを解釈するのは不可能であると思う(全容を解明してという願望はあるが・・・)。
この薬物療法に焦点が置かれすぎると認知症の進行過程の全容が明らかでない世の中では,予想もしない副作用に犯される可能性もあることから,近年は非薬物療法のエビデンスを高めることが喫緊の課題だ。
認知症との共生:非薬物療法で認知機能低下を予防かつ改善する
tamagokakegohanは、認知症になったわけでもなく、当然その当事者ではないことから、軽はずみな発言はできないけれど、作業療法士になって9年間変わらない思いがある。「認知症の人やMCIの人が存在しているのは、地域社会が作り出した病気であるからだ」、「地域社会がこのような高齢者を支えることができる世の中になれば、病気が病気でなくなる可能性を秘めているのではないか」。つまり、このような高齢者が地域社会に溶け込んで自分の大切なことができるようになれば、少なくとも「認知症の人」という認識はなくなるはずだ。このような社会にしていかなければならないと作業療法士としての想いを募らせていた。前回、MCIと考えられた高齢者が編み物を老健の中でできるようになった記事を掲載したが、あの高齢者も老健だけでなく地域の文化祭に展示するといった地域社会への参加目的があったからこそ認知機能が健常人といわれる点数まで改善した。まだ読んでいない方は、リンクを張り付けているのでぜひ読んでいただきたい。
このような事例からtamagokakegohanは、やはり地域社会には無限の可能性があると感じた。次回は、これまでの流れから、地域社会とMCI高齢者の認知機能との関連を考えていきたいと思う。
今後もたくさんのフォローとコメント、スキをお待ちしています!!
追記
tamagokakegohanは、今後も記事を作成していきますが、マガジン機能を活用して、よりエビデンスの高い学術関係の情報を掲載していく予定です!
データを活用した情報でもあることから、100円程度の有料販売になりますが、興味を持っていただけた方はぜひ読んでいって下さい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
