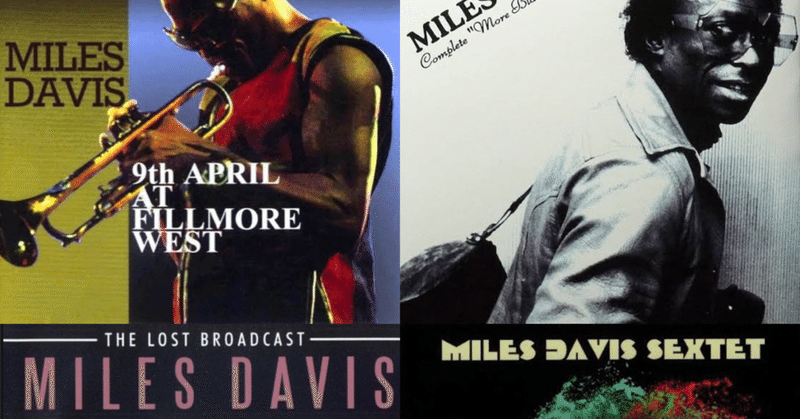
1970年4月9日フィルモア・ウェストのマイルスを聴く
personnel
Miles Davis (trumpet)
Steve Grossman (soprano sax)
Dave Holland (electric bass,bass)
Jack De Johnette (drums)
Chick Corea (electric piano)
Airto Moreira (percussion)
1970年4月、マイルスたちはロックの殿堂、フィルモア・ウェストへの出演を果たす。「果たす」という表現が、この当時すでに大御所であったマイルスに相応しい物であるかどうかは置いておくとして、畑違いの(それもヒッピー目線からすれば黴の生えたジャズの!)巨匠が態々俗界に身を窶しに来たというのだから驚きだったであろう。
もっともこれは当時コロンビアの社長を務めていたクライヴ・デイビスの狙い。ロックと比べても熱気の点では全く見劣りしないマイルスの音楽を、もっと広い世代に(もっと言えば同年3月に発売されたばかりの『Bitches Brew』を)宣伝する企図があったのだ。この試みは先んじること一か月前、3月6日と7日にニューヨークのフィルモア・イーストにて幕を開けている。
当日の模様を新聞紙などで伺う限り、観衆は単純な賛嘆というより驚きと「何が何だか分からんがスゲェ!」的な反応をもって迎え入れたらしい。半世紀以上経過する現代においても、電化マイルスをこんな風に受容するリスナーは意想外に多いのではないか。
それにしてもこの二日間のヘッドライナーを務めたのがスティーブ・ミラーとニール・ヤングだったというのだから、観衆も温度差で思わず風邪をひきそうになったことだろう。対して4月のウェスト出演でヘッドライナーを務めたのはグレイトフル・デッドである。こちらの方は音楽性のジャズっぽさ、ジャンキーっぽさという点でマイルスのグループの雰囲気とマッチしていたと思わないでもない。
さて、「激動の1970年」は世界史においても、マイルスにおいても同様であった。まず第二期クインテット時代から6年にわたり在籍していたウェイン・ショーターが3月のフィルモア・イーストを最後に退団。空いた席を埋めたのが当時期待の新星として注目を集めていたスティーブ・グロスマンである。アイアート・モレイラを除く、基本的な人事はロスト・クインテットのままであるが、サウンド面での違いは一目瞭然だ。それらについてはここで語りつくしてしまうのは惜しいので、続く10日、11日、12日の中で追々綴っていこうと思う。
① Directions
演奏の開始を告げるのは例によってこの曲、《Directions》である。時代が進むごとに換骨奪胎の具合が凄まじいことになる楽曲であるが、はてさて70年4月の時点ではどうだったのだろうか。まずチックのエレピとホランドの怪しげなフレーズから始まるが、これは3月のイースト、いやもっと言えば1969年のフォーマットと同じである。
しかし一番の違いは”フリーキー“ではないこと。3月の段階においてはジャックのドラムがやかましいぐらいにドシャメシャと暴れていたが、4月に入るとスネア主体に変わってシャープな印象を受ける。確かにフリーな状態に突入する瞬間はいくつもある。5分前後に始まるチックのソロ、後にも先にもこんな過激なフレーズを弾いた事があろうか!この音、鉄棒を思うがままにぶっ叩いているかのような音である。
そして短い。チックのソロが終わると早々にマイルスは次の曲のフレーズを吹く。ただいま文章を書いている最中にも四回程度ループしたかというぐらい短いのである。僕が単に遅筆であることもあるが、それにしたってもっと焦らしてもいいのではないかと思わせる。
しかしそれがいい。盛り上がるだけ盛り上がったら次に移行する、マイルスが如何に「過去を見ない男」であるか、ここ7分間に凝縮されているとは言えないだろうか(考えすぎ?)。
② Miles Runs the Voodoo Down
ムムムっ!短めな《Directions》に《Miles Runs the Voodoo Down》……この展開は大名盤『1969 Miles』と同じではないか!と過激なマイルス信者は喜びを隠せない。もっとも、10日『Black Beauty』、11日共に同じメドレーであるので、《Directions》からの《Miles Runs the Voodoo Down》はある程度決まった流れだったのかもしれない。
8分頃、マイルスの小刻みなフレーズの連続に反応するチックの電気攻撃が堪らないったらない。同じ電子ピアノを弾かせても、自由自在に飛び回り跳ね回るのがキース、あくまで周りの音に耳を澄まし、暴れすぎないのがチックの特徴。マイルスとチック、お互いに演奏家として最も攻撃的であった時代に邂逅したものだから、最強のコンビネーションを実現させている。
グロスマンのフリーキーだがワンパターンなソロを終えると、とたんチックの独断場。ロスト・クインテットによるローマ公演の二曲目、《This》でも聴き覚えのあるアバンギャルドな世界に陥る。最初から影の薄かったアイアートも何やらガラガラガラと幼児の玩具のような音を立てながら遊んでいる。ホランドもアコースティックに持ち替え、さながら一気にフィルモアのロックステージからフリージャズのロフトステージに先祖返りといった様。そうか、妙に聴き覚えがあるかと思えば、チックがその後結成する”Circle“的な展開なのだ。と、思ったか思わないかのところで次の曲へと展開を譲る。
う~ん何につけてもチック様様である。
③ This
ここでも現れた!チック作曲の未発表フリージャズナンバー《This》である。さすがはフリージャズ、演奏は中々盛り上がりを見せるも、やはり前曲に引き続きここでも先祖返り的な展開。始まって早々、ビシバシドンドンとロック風にキマっていたジャックのドラムは、ジャンジャンドシャメシャとロストクインテット時代のそれと近いものに戻っている。何かと持ち替えたがるホランドもここではアコースティックをキープ。しまいにはウォーキングベースなんかを刻んでしまっている。
それを察知してかマイルスも長めに尺を取らず、早々に次の曲のフレーズを吹く。このテイク、時間にしてなんと4分58秒(!)セッションデータを見る限り、元来本作が10分以上演奏されることは稀だったようだが、それにしたって短い。69年から70年まで、音源が見つかっているうち最短クラスである。
さらに言えばこのライブ、《This》が最後に登場したコンサートとなったことが分かっている。これら事実から鑑みるに、恐らくではあるが、《This》がセットリストから切り捨てられた理由は「古臭さ」が原因ではないか。確かにパーソネルは全員イケイケのジャズメンたち、演奏されるたびに盛り上がりは見せるものの、恐らくこの当時マイルスが求めていた熱気とは性格が違った。マイルスが求めていた熱気は知性に拠るものではない、それと比べればもっと単純な、身体から弾け散る熱気である。おおよそ4月の段階では未だ前者の熱気の方が強い。マイルスが後者の熱気を獲得するに至るのは、マイケル・ヘンダーソンが加入して以降。この段階ではまだ思索段階にも入っていなかったのだろうが、当時既に彼の脳裏に「フリージャズとは違うことをしたい」というビジョンがあったことをビンビンに感じさせるものとなっている。
④ It's About That Time
マイルスの一吹きをきっかけに、フリー・ジャズの世界からエレックトリック・ジャズの世界に再び様変わり。元々がシンプルな曲であるだけに、いっそうマイルス、ジャック、チック、ホランドの四つ巴の乱戦が楽しめる。マイルスのフレーズ一つ一つにチックのエレピが強力に反応し、ジャックのドラムも激しく過激に盛り立てる。ホランドの単調極まりないエレベもここばかりは愛おしい。
対して場外でただただ見守るしかないのがグロスマンとアイアート。27分頃、グロスマンはソロを取るも3分程度しか隙を与えてくれない。通りで中山康樹氏が「サックスは箸休め」と言う訳だと強く頷く。アイアートに至っては録音ボリュームの問題か、果たしてそこに居るのかすら分からない始末。
そうだ、69年から行動を共にしてきたあの四人の間に割って入る真似など誰にもできっこないのだ。この四つ巴関係は三位一体ならぬ四位一体。一人一人の音に機敏に反応し、また相手がどんな手に出るのか、とうに予想がついている。相手の反応と思考を必死に読み解こうとする黎明期の不安定さはそれはそれで魅力的だが、各々が一心同体として結び付いた状態は、往々にして時間と経験のみが産出してくれるものである。一人が頭脳を果たし、もう一人が手を果たし、またもう一人が足を果たし、これまた一人が視聴覚を果たす、各人揃って一人の人間を成す状態、これはまことに貴重な状態だと言えないか。
⑤ I Fall in Love Too Easily ~
⑥ Sanctuary
ひとしきり盛り上がった後は恒例のスロー・バラードパート。基本的な展開はロスト・クインテット時代とは変容がない。唯一の変更点であるホランドがエレクトリックベースを弾いている点も、3月のフィルモアから変わりがないようだ。
⑦ Spanish Key
お馴染みのフレーズと共に《Spanish Key》が幕を開ける。ヴーンヴーンヴーンといつも以上に強力にうねり絡み合うのはホランドのエレベ。まるで自分がダブルベースを弾いている気にでもなっているのではないか。
過激なのはチックのエレピである。フロントの動きに逐一対抗する様にグワシグワワンと隙あらばノイジーサウンドを繰り出す。さらに独断場になると全然違うアプローチで魅せるのはどういう訳か。45分以降、舞台に立って音を出すのは、ジャックとホランドとチックの三人のみ。超絶強力なトリオ、オマケに三人中二人は電子楽器を持っているという素晴らしさ。この油断できない緊迫状態はマイルスが再び登場する50分後半まで継続する。1970年4月9日のフィルモア・ウェスト、全曲にして1時間5分程度、例によって様々な展開が見られるが、ここ5分間のために存在しているといっても過言ではない。それだけの気迫がある。
⑧ Bitches Brew ~ Theme
お次はまたしても『Bitches Brew』からこの曲。展開的にやや冗長(そこが良いのだが)であり、時間的に制約があった3月のフィルモアでは《Spanish Key》と共に選ばれていなかった。それだけに4月のフィルモアでは14分と大いに焦らす。
導入部分のマイルスによるソロを最高点として、グロスマンのソロ、チックのソロと盛り上がりは徐々に下降線をたどっていく。もっとも、それは地道なやり合いにシフトしたというような言い方もできるだろう。互いの顔をよく見合うジャズ的な展開はこんな場面でこそ活きてくる。
61分辺りのチックのソロは余りにもフリーキー。細かな点では違っているものの、やはり肝心なところはロスト・クインテット時代を引き継いでいたことがここでもよく分かると思う。
64分、そんなフリー然としたソロの合間にマイルスも割り込んで参入する。これまた強力なぶつかり合いで残る1分間、果たして無事に着地するのかと思うか思わないかのところで、《Theme》のフレーズをマイルスが吹く。うーん強引な幕引き。しかしそれに即座に反応できるチックも他メンバーも凄い。今さらな感想であるが、やっぱりこの6人は凄い。
総評
入門度 ★★★☆☆
音質とパフォーマンスの質は比較的高いので入門には適している。ただし、これは4月のフィルモア自体の特徴でもあるのだが、他の日程と比べると若干こじんまりとした雰囲気があることも否めない。
テンション ★★★☆☆
盛り上がりどころはあるが、場面によっての差がある。10日『Black Beauty』と大きな差はない(確かにこちらの方がテンション高めではあるが)。
音質 ★★★★☆
サウンドボード音源はとあってかなりよく録れている。しかし若干籠り気味であるので、オフィシャルレベルとまでは行かない。
パーソネル ★★★☆☆
ロスト・クインテット時代からのメンバーは更に練度が上がっていて、それでいて69年時とは異なるアプローチも見られる。ただしアイアートなど個性が伸びきっていない面も。
レア度 ★★☆☆☆
グロスマン時代の音源は一応『Black Beauty』にて公式化されているので貴重ではない。しかし《This》のラストテイクなど、過渡期の模様を捉えた音源ではあるのでその点は貴重。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
